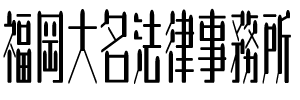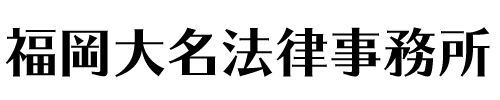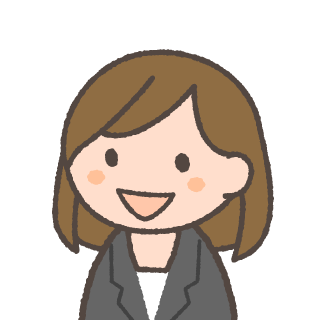

法律は、15歳に達した者のみが遺言ができるとしており、14歳の少年が遺言をしても、単純に無効になります。
現実問題として遺言をしたい14歳はあまりいないので、直接に問題になることは少ない決まりです。ただ、「遺言をするためにはどの程度の判断能力が残存している必要があるか」という問題を論じる時に、引き合いに出されたりします。
このコラムでは、遺言に必要な能力や方式などについて、まとめて説明していきたいと思います。
遺言能力について
遺言能力を要する時期
遺言をする時(民法963条)です。
では、認知症の母が遺言をした場合、効力はあるのでしょうか?
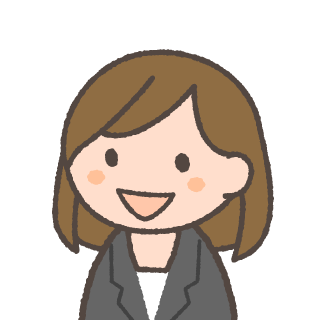

まず、法定の後見制度を利用している方の場合は、以下のようになります。
成年被後見人の遺言
事理弁識する能力を一時回復した時は、医師2人以上の立ち会いがあれば、遺言をすることができます(民法973条)。
被保佐人の遺言
被保佐人であることを理由に遺言能力を制限されることはなく、単独で遺言ができます。
ただし、遺言時の事理弁識能力の有無は別途問題となりえます。
被補助人の遺言
被保佐人の場合と同様です。
上のような制度は利用していないのですが…
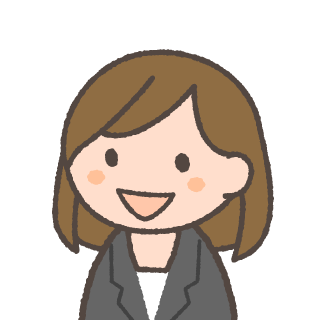

その場合、事理弁識能力(意思能力)があれば遺言ができます。
意思能力
重度の認知症である場合など、遺言のときに遺言の内容を理解し、判断しうる能力(意思能力)がなかった場合には、遺言は無効になります。
ただし、遺言によって不利益を受けた相続人などが、意思能力の欠如による遺言の無効を主張する場合、通常、医療記録その他「能力がなかったこと」を示す証拠が必要になります。公正証書遺言の場合には、ハードルはさらに高くなります(不可能というわけではなく、無効を認めた判例もあります)。

この判断にあたっては、周囲との意思疎通の可否、遺言までの経緯、遺言時の状況、遺言の内容の複雑性や、結果の重大性などが考慮材料になります。
遺言の方式について
上記のような能力を有していても、遺言には厳格な方式が法で定められており、方式を欠けば無効になってしまいます。
通常使われる遺言には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。ここではこの2つの遺言について説明します。
自筆証書遺言の方式
自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは、読んで字のごとく、自筆で書いた遺言のことです。この遺言は、遺言者が「全文」「日付」「氏名」を自署し、さらに印を押さなければならないとされています。
「全文」を自筆で書くことが必要ですので、本文をワープロで書いて、署名押印部分だけ自筆というわけにはいきません。法律上の規定を満たしていないものは、遺言としては無効になります。
また、加除変更の方法についても厳格に法定されています。
※2019年1月追記:平成30年相続法改正により、自筆証書遺言の方式は大きく緩和されました(施行期日は2019年1月13日とされています)。くわしくは別途記事を作成しています。
なお、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認の手続も必要になります。
公正証書遺言とは?自筆証書遺言とどう違う?
公証人が作成する「公正証書」による遺言を、公正証書遺言といいます。
自筆証書遺言の場合、紛失されたり、その方式の適正さに疑義が出たり、偽造や変造の疑いがあると言われたり、強要されて作成されたものだと主張されたり、さまざまな争いが起こりがちです。
公正証書遺言の場合、中立・専門の第三者である公証人が立ち会い、公証役場に遺言の原本を保管するため、100%ではありませんが、そうした争いを相当程度にまで抑制できます。また、家庭裁判所での検認の手続も不要です。
一方で、作成に費用がかかるというデメリットもあります。

公証人とは?
国の事務である「公証」をおこなう公的機関です。「公証役場」で仕事をしています。
公正証書遺言の作成についてのご相談も承っておりますので、詳しくはご相談ください。