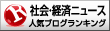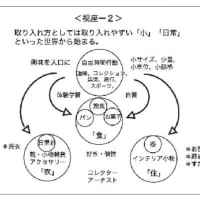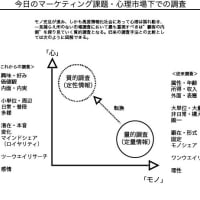ヒット商品応援団日記No765(毎週更新) 2020.5.10.

「正しく、恐る」
その原点に立ち返る
4月7日緊急事態宣言が発令され、街も、生活も、働き方も一変した。その根幹にあるのは「移動」の制限であり、それはウイルスは人によって運ばれるということからであった。既に、2月11日のブログで「移動抑制が消費を直接低下させる 」というテーマで、しかも昨年12月からの季節性インフルエンザの流行は予測を大きく下回る感染であることが報告されているとも。これは1月後半からの新型コロナウイルスに対する自己防衛によるところが大きいと分析する医師も多いと書いた。つまり、海外から持ち込まれるウイルスの防疫強化以前に既に生活者の「自己防衛」は1月末から始まっているという指摘であった。そして、実はのちにわかったことだが、感染のピーク4月1日はちょうど新型コロナウイルスによって急死した志村けんさんと同じ時期であった。その間感染の拡大に対し、政府も専門家会議も感染対策は遅れに遅れたと指摘されてもやむおえないであろう。既に1月23日には中国の武漢は封鎖されていた。

また、最近の研究などから専門家会議によって行われた多くのシュミレーション、「このままであれば42万人が死亡する」といった恫喝・脅しとも取れる発表に対し、その数理モデル計算式が誤りではないかとの他の専門家からの指摘も出てきた。現実はシュミレーションとは大きく異なり、感染者数も死亡者数もある意味世界でも不思議であると注目されているほど少ない。一時期、専門家会議メンバーは「米国NYのようになる、地獄になる」と発言し恐怖を増幅させていたが、これもそんな現実は起こっていないことは周知の通りである。この専門家会議のシュミレーションを鵜呑みにした感染症の大学教授が盛んにTV番組で煽り立てる発言をしていたが、現実は全く異なる展開となっている。専門家会議や鵜呑みにした某大学教授の責任を問う声もあるが、未来塾はその任にはない。
それではその「現実」はどうであるのか、緊急事態宣言後1ヶ月半ほど経ち5月25日全面解除となった。その後新たに分かったことが数多く出てきている。例えば、マスクの効用についてWHOは否定的であったが、その後の動物実験ではうつさないだけでなくうつされない効果が得られたとの研究結果も出てきた。今回は専門家会議が提言した新型コロナとの付き合い方、その生活様式をどのように受け止めたら良いのかを考えてみた。
公衆衛生の始まり
ところで少し前に「不確かな時代の不安」をテーマにブログを書いたことがあった。それは江戸時代の台風・水害などの災害対策についてであったが、次のようにも書いた。
『江戸時代における最大の不安は疾病や病気であった。周知のように最初に隅田川の川開きに打ち上げられた花火は京保18年が最初であった。この年の前年には100万人もの餓死者が出るほどの大凶作で、しかも江戸市内でころり(コレラ)が流行し多くの死者が出た年であった。八代将軍吉宗は多くの死者の魂を供養するために水神祭が開かれ、その時に打ち上げられた花火が今日まで続いている。弔いの花火であったが、ひと時華やかな打ち上げ花火を観て不安を打ち消すというこれも江戸の知恵であった。』
このコレラが日本にもたらされたのは文政5(1822)年で中国(清)経由で沖縄、九州に上陸したと考えられている。しかし、この時には江戸には本格的な感染拡大はしなかったと言われている。当時の花火大会も一種の「お祓い」の意味もあり、それまでの疫病に対しては全て祈禱によって行われていた。
このコレラが猛威をふるったのは江戸から明治へと移行する開国の時期であった。安政5(1858)年。感染源はペリー艦隊に属していた米国艦船ミシシッピー号で、中国を経由して長崎に入った際、乗員にコレラ患者が出たと言われている。そして、江戸の死者数は約10万人とも、28万人や30万人に及んだとも言われている。
日本に衛生観念を植え付けたコレラ
実はコレラの流行まで、日本国内に医学的な感染症対策はほとんどなかった。加持祈禱(かじきとう)に頼り、疫病退散のお札を戸口に貼って家に閉じこもったり、病気を追い払おうと太鼓や鐘を打ち鳴らしたりしたという非科学的なものであった。例えば、今も続いているのが、おばあちゃんの聖地、巣鴨とげぬき地蔵尊のある高岩寺は本尊の姿を刷った御影(おみかげ)に祈願・またはその札を水などと共に飲むなどして、病気平癒に効験があるとされている。
医師緒方洪庵や長崎のオランダ医師ポンペの治療法が一定の効果をみせたこともあり、江戸幕府は文久2年に洋書調所に命じて『疫毒預防説(えきどくよぼうせつ)』を刊行させている。オランダ医師のフロインコプスが記した『衛生全書』の抄訳本で、「身体と衣服を清潔に保つ」「室内の空気循環をよくする」「適度な運動と節度ある食生活」などを推奨している。今日の感染症対策にも通じるものであることがわかる。幕末の1858(安政5)年、安政の五カ国条約が調印されたこの年にコレラの乱が起きる。海外からもたらされた病であることから、当時の攘夷思想に拍車をかけたといえよう。また、コレラは感染すると、激しい嘔吐、下痢が突然始まり、全身痙攣をきたす病であった。瞬 く間に死に至るため、幕末から明治にかけて「三日コロリ」「虎列刺」「虎狼痢」「暴瀉 病 」と よばれた。
清潔な町江戸はエコシステムによってつくられた
120万人という世界で類を見ない都市であった江戸では、その高度技術の象徴として流れる上水道を取り上げたことがあったが、下水道もまた衛生管理されたものであった。例えば、トイレの糞尿は河川に流すことなど禁止されており、定期的に糞尿は汲み取られ近隣の田畑の肥料として使われていた。それら糞尿は農家に売られ町の財源となり道路の補修などに使われていた。他にもゴミ捨ては禁止され汚水をつくらない対策が講じられていた。これが江戸社会が極めて優れたエコシステムであることの一つの例となっている。ちなみに、ゴミの不法投棄を一掃するため、明暦元年(1655年)に「全てのゴミは隅田川の河口の永代島(えいたいじま)に捨てる」というルールを発布している。
面白いことに、江戸の街は東京湾の埋め立てによってつくられたものだが、ゴミの分別もきちんとなされ、埋め立て用のゴミ、燃料用のゴミ、堆肥用のゴミ、に分けられゴミひとつない清潔な町が造られていた。当時の大都市ロンドンなどと比較した資料を見てもわかるように、糞尿に塗れたロンドンとは大違いであった。
銭湯という清潔習慣
日本は火山列島であり、至る所で温泉があり、日本書紀にも記述されている。その効用は泉質により多様であるが、治療をはじめ広く健康のための入浴が行われてきた。
江戸時代には市内で広く銭湯として日常のライフスタイルの重要な一つとなっていた。上水道の水は飲料の他に銭湯にも使われていた。当時の江戸の町は土埃の多い町であったことから、仕事前に朝風呂、仕事終わりに夕風呂と少なくとも2回は入ったようで、1日に何回も銭湯を使っていた。入浴料金は大人8文(約120円)、子ども6文(約90円)とそば1杯の値段の半分とリーズナブルな料金であった。さらにお風呂好きにはうれしいことに「羽書(はがき)」というフリーパスもあり、1ヶ月148文(約2200円)で何度でも入浴することができる仕組みさえ出来ていた。
江戸市民のライフスタイル上、欠かせない習慣となり、町も身体も清潔なものとなっていた。
ところで、感染症の歴史であるが、明治17(1884)年、結核菌の発見でも知られるドイツのコッホによって、コレラがコレラ菌による伝染病であることが突き止められ、その後、パンデミックなどの大流行が見られることはなくなりました。
ペニシリンをはじめとした治療薬が次々と発見され、原因や対処法が判明してきた現在でも、コレラは全滅したわけではない。人類はウイルスや細菌との戦いの歴史だと言われてきたが、ウイルスや細菌と共存した歴史でもあるということである。
昭和から平成の時代へ
江戸時代からいきなり昭和の時代に移ってしまうが、戦後の荒廃した時代の生活は「雑菌」と「ウイルス」の中の生活、今で言うところの雑菌やウイルスとの「共生」であった。食べ物すらも衛生的とは言えない環境にあって、生きるとはそうした共生そのものであった。今、テーマとなっている「免疫」をテーマとした研究者、いや私にとっては作家である多田富雄さんの著書「免疫の意味論」を読んだ記憶がある。覚えているのは免疫の科学的知見ではなく、生活するうえで”ああそんなことなのか”と経験に即した意味論であった。戦後の不潔な環境ではそれなりに打ち勝つために免疫が自然と高まるという理解であった。
というのも1990年代当時問題となっていた過剰な「清潔」「無菌社会」に対する一つの警鐘となった記憶であった。清潔の考えが極端に振れた社会で、同じように「健康」がダイエットにとってかわり、必要カロリーに満たないという現象が起きた。共に、豊かであるが故の奇妙な変換が起きた時代であった。そうした変換のキーワードは何かといえば、「過剰」ということになる。こうした豊かさを背景に、一部生活者はタクシーがわりの救急車を使ったり、病院の待合室がサロン化するといった現象も見られるようになる。こうした意識は今回の新型コロナウイルスのような「未知」に対しても過剰に反応することとなる。その過剰さの先が「恐怖」である。
そして、一方では2003年の重症急性呼吸器症候群(SARS)、09年には新型インフルエンザが流行したが、パンデミックのような大きな流行が起こらなかったことから、リスク対策が行われず今回の新型コロナウイルスを迎えることになる。特に、受け入れる病院、あるいは保健所もそうであるが、行革の対象となり、医療現場は削減したまま今回のコロナ禍を迎えることとなった。医療危機が叫ばれているが、その背景はこうした経緯がある。ただ問題なのは行革は単なる施設や人員の削減だけではなく、ITなどを駆使したシステムでなくてはならない。しかし、特別給付金のマイナンバーカードによる給付に見られたように、ITによるシステムがいかに遅れているかが露呈した。自宅での就労、リモートワークはまだまだ一部であり、学校の休校に伴うオンライン授業も同様である。それは大学においても同様で授業を始めた途端サーバーがダウンしてしまう、そんなITとは名ばかりの実情が次々と社会の面へと出てきた。
新型コロナウイルスの迎え方
ところで1月末にはいち早く生活者は認識いていたと書いた。その背景であるが、周知のように季節インフルエンザは例年より早く昨年11月ごろから流行り始めていた。昨年の12月にはマスク姿の人たちが街中に多く見られるようになった。しかも、グラフを見てもわかるように、季節インフルエンザの罹患者は例年より極めて少なくなっている。(東京都)

赤い線が今年の罹患者のグラフである。多くの人は今年のインフルエンザは軽かったなというのが印象であったと思う。ちなみに全国ののインフル患者数は昨年は1210万人であったのに対し、今年は729万人と減少している。
何故、季節性インフルエンザは減少したのか。季節性インフルエンザに代わるように新型コロナウイルスの感染が始まるのだが、その際、生活者のマスク着用や手洗い・うがいといった日常の感染対策は新型コロナウイルス感染を防御し得たのかどうか、実はこうした疑問点について専門家会議も明確な答えられてはいない。極論を言えば、「疫学」という専門研究の世界だけの知見であって、生活者のライフスタイルをどう変えて行ったら良いのかという視点が決定的に欠けている。つまり、専門家会議の提案する「生活様式」が素直に受け止められないのはこうしたことに起因している。

こうした季節性インフルエンザの実態を踏まえ、多くの感染症研究者は単なる季節性インフルエンザの延長線上で新型コロナウイルスを受け止めていた。しかし、冒頭に書いたように既に中国の感染実態に触れ、勿論一部の研究者や医師の間では感染対策をどうすべきかと言った声は1月には上がっていた。
コロナの正体が少しづつわかってきた
新型コロナウイルスの対策を始めその情報のほとんどは政府専門家会議(現在は諮問委員会)のメンバーによるものであった。しかし、海外の情報を始め感染症以外の科学者からの発言が多く見られるようになった。そうした発言の中で、新型コロナウイルスと戦っている現場の医療従事者を始め、多くの国民の支持を得てきたのがあのiPS細胞研究所の山中伸弥教授である。ノーベル賞の受賞研究者ではあるが、多くの国民にとっては難病患者のために努力し続けている誠実で真摯な人物であると理解している。情報の時代、つまり過剰な新型コロナウイルス情報に対し、科学者の目で冷静に「今」わかっている新型コロナウイルスの正体を「証拠(エビデンス)の強さによる情報分類」したうえで、「5つの提言」をHPを通じて投げかけてくれている。
国民が求めていることは新型コロナウイルスとは何かという本質である

山中伸弥教授の発言によって、新型コロナウイルスの姿が少しづつわかってきた。これは政府専門家会議による広報では得られない多面的、多様な情報である。それは本来「正しく、恐る」という理解であるはずの理解を促すべきところを、「恐怖」によって移動の自粛を行う戦略を採ったことへの疑義であると私は受け止めている。山中教授は異なるコロナ理解、つまり冷静に理性的に確認できる「事実」を「正しく」伝えることが重要で、その姿勢が多くの国民の理解を得つつある。
専門家会議によるコロナ対策、クラスターという小集団対策、ある意味もぐらたたき戦略は、一方でコロナの「恐怖」を提示することによってある時までは成立してきた。それはもぐらたたきが可能であった時期までである。既に3月に入り欧米に観光で出かけた観光客が帰国した頃から、主に都市における市中感染が始まっている。これは専門家会議も認めていることだが、PCR検査体制を抑制したこともあり、この感染の防疫の対策を持ち得なかった。残ったのは「恐怖」だけであった。それも何による恐怖なのかという具体性のない、漠たる恐怖であった。
現段階で分かったこと、その証拠が正しい可能性が高いかどうかを冷静に整理してくれている。ここには理性を持って新型コロナウイルスに向き合う態度がある。マスメディア、特に「刺激」ばかりを追い求めてきたTVメディアの態度とは真逆である。こうした「証拠」に基づいた提言こそが必要であり、恐怖による行動変容は一時期的に表面的な自粛が行われても、同時に人と人との間に憎しみや争いを生むことになる。
恐怖による行動変容
ところで社会心理学を持ち出すまでもなく、行動の変容を促すには恐怖と強制が効果的であると言われている。そして、恐怖は憎悪を産み、分断・差別を促す。憎むべきウイルスは次第にルールを逸脱する人間へと変わっていく。少し前になるが、ゼミやサークルの懇親会で新型コロナウイルスのクラスター(感染者集団)が発生した京都産業大の学生に対し、抗議や意見の電話やメールが数百件寄せられているとの報道があった。抗議どころかあるTV番組のコメンテーターはウイルスを撒き散らした学生にはまともな治療を受けさせるなと暴言を吐く始末である。
あるいは同じ番組であるが、今度は外出の自粛要請の休日に禁止されている区域に潮干狩りをしているとの報道を踏まえてと思うが、感染症学の教授が「二週間後はニューヨークになってる。地獄になってる」と発言したのには驚きを越えてこの人物は大学教授なのか、教育者としての知性・人間性を疑ってしまった。ニューヨークのようになってはならないと発言するのであればわかるが、それにしても「地獄」などといった言葉は間違っても使ってはならない。つまり、恐怖心をただ煽っただけで、しかも専門分野の教授の発言であるからだ、
「自粛」を促すには恐怖と強制が常套手段であると書いたが、「2週間後にはニュ-ヨークになる」「地獄になってる」といった恐怖を煽るようなTVコメンテーターの発言も現実・事実がそのように推移しなくなったことから、その刺激的な発言もトーンダウンしてきた。一方私権を制限することが法的にもできない日本においては「強制」できない現実から「自粛警察」といったキーワードが流行る嫌な現象が生まれている。『自粛警察』とは、例えばクラスター感染のシンボリックな場所・施設となったライブハウスへの中傷で、東京高円寺の街では休業中の店舗などに休業を促す張り紙をしたり、張り紙に文言を書き込んだりすることを指すとされる。他にも居酒屋など休業要請を指定されてはいない店舗への嫌がらせも出てくる状況が生まれている。私に言わせれば、「正義」の仮面をかぶった一種の嫌がらせであるが、憎むべき敵であるコロナウイルスが休業していない店舗にすり替えられての行為が至る所で見られるようになった。「恐怖」はこうした中傷をはじめとした差別を連れてきている。その象徴が『自粛警察』である。また、カラオケについてもあたかも密=クラスターの発生源であるかのような発言をするコメンテーターもいて、勝手なイメージが一人歩きする。
ロックダウンではなく、セルフダウン
東日本大震災の時もそうであったが、「現場」で新しい新型コロナウイルスとの戦いが始まっている。医療現場もそうであるが、マスクや医療用具の製造などメーカーは自主的に動き始めている。助け合いの精神が具体的行動となって社会の表面に出てきたということである。「できること」から始めてみようということである。その良き事例としてあのサッカーのレジェンド「キングカズ」はHP上で「都市封鎖をしなくたって、被害を小さく食い止められた。やはり日本人は素晴らしい」。そう記憶されるように。力を発揮するなら今、そうとらえて僕はできることをする。ロックダウンでなく「セルフ・ダウン」でいくよ、と発信している。そして、「自分たちを信じる。僕たちのモラル、秩序と連帯、日本のアイデンティティーで乗り切ってみせる。そんな見本を示せたらいいね。」とも。恐怖と強制による行動変容ではなく、キングカズが発言しているように、今からできることから始めるということに尽きる。人との接触を80%無くすとは、一律ではなく、一人一人異なっていいじゃないかということである。どんな結果が待っているかはわからない。しかし、それが今の日本を映し出しているということだ。
東日本大震災の時に生まれたのが「絆」であった。今回の新型コロナウイルス災害では「連帯」がコミュニティのキーワードとなって欲しいものである。
大阪らしい戦い方
一足先にコロナ禍からの出口戦略に組み出した大阪は知事を中心に大阪らしい戦い方を見せてくれている。それはコロナ禍が始まって以降大阪が行ってきた対策はどこよりも的確でスピードのあるものであった。中国観光客のバスガイドが感染したことを踏まえ、徹底的にその行動履歴を明らかにして感染拡大を防ぐ行動をとった。その後、周知の和歌山県で起きた院内集団感染拡大に対しても、和歌県の要請を受けてPCR検査を肩代わりする、つまり近隣県とのネットワークも果たしている。更に、ライブハウスで感染クラスターが明らかになったときもライブハウス参加者に呼びかけ、つまりここでも情報公開を行ってきている。更には早い段階で軽症感染者や重症感染者など症状に応じた「トリアージ」の考え方を取り入れ、病院崩壊を防ぐ対策をとってきている。また、病床確保にも動いており、十三にはコロナ専門病院も用意している。・・・・・・・こうした情報公開と準備を踏まえたうえでの「出口」の提示であるということである。大阪府民が支持するのも当然であろう。少なくともPCR検査を含め東京都とは違いデータの収集分析はシステマチックになされている。勿論、他県も同様であるが、東京が正確なデータで「出口」を示せないのに対し、大阪はかなり先へ進んでいる。東京の場合、ロードマップという工程表を提示しているが、4段階のうち、第一段階は進めたとしても、第二段階、第三段階などどんな「目標・数値」が達成できれば次の段階へ進めると言ったことが明確になっていないこと。つまり、数字での判断ではなく、「成り行きまかせ」で、いつになったら「出口」となるのか各業種ごと不明であるという点が大阪と大きな違いとなっている。


こうした対策に呼応するように府民も戦っていることがわかる。それは商売の街・大阪の戦い方によく出ている。東京が休業協力金を出すことができるという財政に余裕があるのに対し、大阪の場合余裕はない。当然戦い方も異なり、府民の「協力」しか武器はないということである。その武器は何か、大阪らしさ、大阪のアイデンティティに依拠した戦い方である。
そのキャッチフレーズは「負けへんで」。臨時休業の告知だけではつまらない、「どうせ耐えるなら楽しく」やろうじゃないかということだ。きっかけはお好み焼きのチェーン店「千房」で、「負けへんで 絶対ひっくり返したる」と書かれたポスターである。お好み焼きのコテにひっかけた、ウイットのある大阪らしい表現である。今やギンザセブンにも出店している串カツの「だるま」は、ソースの二度ずけ禁止」にかけ「負けへんで コロナの流行は禁止やで」と。そして、「二度ずけ禁止」という大阪文化は少しの間お預けして、かけるボトルソースを用意し、少しでも感染予防になればと工夫が凝らされている。
この「負けへんで」死rーずの延長線上に営業再開のポスターが作られている。大阪の友人にお願いしてその大阪らしい「心意気」、商人文化を撮ってもらっtあ一部である。(後半へ続く)

コロナ禍から学ぶ(1)
「正しく、恐る」
その原点に立ち返る
ファクターXと言う仮説、
恐怖後遺症の行方。
恐怖後遺症の行方。
4月7日緊急事態宣言が発令され、街も、生活も、働き方も一変した。その根幹にあるのは「移動」の制限であり、それはウイルスは人によって運ばれるということからであった。既に、2月11日のブログで「移動抑制が消費を直接低下させる 」というテーマで、しかも昨年12月からの季節性インフルエンザの流行は予測を大きく下回る感染であることが報告されているとも。これは1月後半からの新型コロナウイルスに対する自己防衛によるところが大きいと分析する医師も多いと書いた。つまり、海外から持ち込まれるウイルスの防疫強化以前に既に生活者の「自己防衛」は1月末から始まっているという指摘であった。そして、実はのちにわかったことだが、感染のピーク4月1日はちょうど新型コロナウイルスによって急死した志村けんさんと同じ時期であった。その間感染の拡大に対し、政府も専門家会議も感染対策は遅れに遅れたと指摘されてもやむおえないであろう。既に1月23日には中国の武漢は封鎖されていた。

また、最近の研究などから専門家会議によって行われた多くのシュミレーション、「このままであれば42万人が死亡する」といった恫喝・脅しとも取れる発表に対し、その数理モデル計算式が誤りではないかとの他の専門家からの指摘も出てきた。現実はシュミレーションとは大きく異なり、感染者数も死亡者数もある意味世界でも不思議であると注目されているほど少ない。一時期、専門家会議メンバーは「米国NYのようになる、地獄になる」と発言し恐怖を増幅させていたが、これもそんな現実は起こっていないことは周知の通りである。この専門家会議のシュミレーションを鵜呑みにした感染症の大学教授が盛んにTV番組で煽り立てる発言をしていたが、現実は全く異なる展開となっている。専門家会議や鵜呑みにした某大学教授の責任を問う声もあるが、未来塾はその任にはない。
それではその「現実」はどうであるのか、緊急事態宣言後1ヶ月半ほど経ち5月25日全面解除となった。その後新たに分かったことが数多く出てきている。例えば、マスクの効用についてWHOは否定的であったが、その後の動物実験ではうつさないだけでなくうつされない効果が得られたとの研究結果も出てきた。今回は専門家会議が提言した新型コロナとの付き合い方、その生活様式をどのように受け止めたら良いのかを考えてみた。
公衆衛生の始まり
ところで少し前に「不確かな時代の不安」をテーマにブログを書いたことがあった。それは江戸時代の台風・水害などの災害対策についてであったが、次のようにも書いた。
『江戸時代における最大の不安は疾病や病気であった。周知のように最初に隅田川の川開きに打ち上げられた花火は京保18年が最初であった。この年の前年には100万人もの餓死者が出るほどの大凶作で、しかも江戸市内でころり(コレラ)が流行し多くの死者が出た年であった。八代将軍吉宗は多くの死者の魂を供養するために水神祭が開かれ、その時に打ち上げられた花火が今日まで続いている。弔いの花火であったが、ひと時華やかな打ち上げ花火を観て不安を打ち消すというこれも江戸の知恵であった。』
このコレラが日本にもたらされたのは文政5(1822)年で中国(清)経由で沖縄、九州に上陸したと考えられている。しかし、この時には江戸には本格的な感染拡大はしなかったと言われている。当時の花火大会も一種の「お祓い」の意味もあり、それまでの疫病に対しては全て祈禱によって行われていた。
このコレラが猛威をふるったのは江戸から明治へと移行する開国の時期であった。安政5(1858)年。感染源はペリー艦隊に属していた米国艦船ミシシッピー号で、中国を経由して長崎に入った際、乗員にコレラ患者が出たと言われている。そして、江戸の死者数は約10万人とも、28万人や30万人に及んだとも言われている。
日本に衛生観念を植え付けたコレラ
実はコレラの流行まで、日本国内に医学的な感染症対策はほとんどなかった。加持祈禱(かじきとう)に頼り、疫病退散のお札を戸口に貼って家に閉じこもったり、病気を追い払おうと太鼓や鐘を打ち鳴らしたりしたという非科学的なものであった。例えば、今も続いているのが、おばあちゃんの聖地、巣鴨とげぬき地蔵尊のある高岩寺は本尊の姿を刷った御影(おみかげ)に祈願・またはその札を水などと共に飲むなどして、病気平癒に効験があるとされている。
医師緒方洪庵や長崎のオランダ医師ポンペの治療法が一定の効果をみせたこともあり、江戸幕府は文久2年に洋書調所に命じて『疫毒預防説(えきどくよぼうせつ)』を刊行させている。オランダ医師のフロインコプスが記した『衛生全書』の抄訳本で、「身体と衣服を清潔に保つ」「室内の空気循環をよくする」「適度な運動と節度ある食生活」などを推奨している。今日の感染症対策にも通じるものであることがわかる。幕末の1858(安政5)年、安政の五カ国条約が調印されたこの年にコレラの乱が起きる。海外からもたらされた病であることから、当時の攘夷思想に拍車をかけたといえよう。また、コレラは感染すると、激しい嘔吐、下痢が突然始まり、全身痙攣をきたす病であった。瞬 く間に死に至るため、幕末から明治にかけて「三日コロリ」「虎列刺」「虎狼痢」「暴瀉 病 」と よばれた。
清潔な町江戸はエコシステムによってつくられた
120万人という世界で類を見ない都市であった江戸では、その高度技術の象徴として流れる上水道を取り上げたことがあったが、下水道もまた衛生管理されたものであった。例えば、トイレの糞尿は河川に流すことなど禁止されており、定期的に糞尿は汲み取られ近隣の田畑の肥料として使われていた。それら糞尿は農家に売られ町の財源となり道路の補修などに使われていた。他にもゴミ捨ては禁止され汚水をつくらない対策が講じられていた。これが江戸社会が極めて優れたエコシステムであることの一つの例となっている。ちなみに、ゴミの不法投棄を一掃するため、明暦元年(1655年)に「全てのゴミは隅田川の河口の永代島(えいたいじま)に捨てる」というルールを発布している。
面白いことに、江戸の街は東京湾の埋め立てによってつくられたものだが、ゴミの分別もきちんとなされ、埋め立て用のゴミ、燃料用のゴミ、堆肥用のゴミ、に分けられゴミひとつない清潔な町が造られていた。当時の大都市ロンドンなどと比較した資料を見てもわかるように、糞尿に塗れたロンドンとは大違いであった。
銭湯という清潔習慣
日本は火山列島であり、至る所で温泉があり、日本書紀にも記述されている。その効用は泉質により多様であるが、治療をはじめ広く健康のための入浴が行われてきた。
江戸時代には市内で広く銭湯として日常のライフスタイルの重要な一つとなっていた。上水道の水は飲料の他に銭湯にも使われていた。当時の江戸の町は土埃の多い町であったことから、仕事前に朝風呂、仕事終わりに夕風呂と少なくとも2回は入ったようで、1日に何回も銭湯を使っていた。入浴料金は大人8文(約120円)、子ども6文(約90円)とそば1杯の値段の半分とリーズナブルな料金であった。さらにお風呂好きにはうれしいことに「羽書(はがき)」というフリーパスもあり、1ヶ月148文(約2200円)で何度でも入浴することができる仕組みさえ出来ていた。
江戸市民のライフスタイル上、欠かせない習慣となり、町も身体も清潔なものとなっていた。
ところで、感染症の歴史であるが、明治17(1884)年、結核菌の発見でも知られるドイツのコッホによって、コレラがコレラ菌による伝染病であることが突き止められ、その後、パンデミックなどの大流行が見られることはなくなりました。
ペニシリンをはじめとした治療薬が次々と発見され、原因や対処法が判明してきた現在でも、コレラは全滅したわけではない。人類はウイルスや細菌との戦いの歴史だと言われてきたが、ウイルスや細菌と共存した歴史でもあるということである。
昭和から平成の時代へ
江戸時代からいきなり昭和の時代に移ってしまうが、戦後の荒廃した時代の生活は「雑菌」と「ウイルス」の中の生活、今で言うところの雑菌やウイルスとの「共生」であった。食べ物すらも衛生的とは言えない環境にあって、生きるとはそうした共生そのものであった。今、テーマとなっている「免疫」をテーマとした研究者、いや私にとっては作家である多田富雄さんの著書「免疫の意味論」を読んだ記憶がある。覚えているのは免疫の科学的知見ではなく、生活するうえで”ああそんなことなのか”と経験に即した意味論であった。戦後の不潔な環境ではそれなりに打ち勝つために免疫が自然と高まるという理解であった。
というのも1990年代当時問題となっていた過剰な「清潔」「無菌社会」に対する一つの警鐘となった記憶であった。清潔の考えが極端に振れた社会で、同じように「健康」がダイエットにとってかわり、必要カロリーに満たないという現象が起きた。共に、豊かであるが故の奇妙な変換が起きた時代であった。そうした変換のキーワードは何かといえば、「過剰」ということになる。こうした豊かさを背景に、一部生活者はタクシーがわりの救急車を使ったり、病院の待合室がサロン化するといった現象も見られるようになる。こうした意識は今回の新型コロナウイルスのような「未知」に対しても過剰に反応することとなる。その過剰さの先が「恐怖」である。
そして、一方では2003年の重症急性呼吸器症候群(SARS)、09年には新型インフルエンザが流行したが、パンデミックのような大きな流行が起こらなかったことから、リスク対策が行われず今回の新型コロナウイルスを迎えることになる。特に、受け入れる病院、あるいは保健所もそうであるが、行革の対象となり、医療現場は削減したまま今回のコロナ禍を迎えることとなった。医療危機が叫ばれているが、その背景はこうした経緯がある。ただ問題なのは行革は単なる施設や人員の削減だけではなく、ITなどを駆使したシステムでなくてはならない。しかし、特別給付金のマイナンバーカードによる給付に見られたように、ITによるシステムがいかに遅れているかが露呈した。自宅での就労、リモートワークはまだまだ一部であり、学校の休校に伴うオンライン授業も同様である。それは大学においても同様で授業を始めた途端サーバーがダウンしてしまう、そんなITとは名ばかりの実情が次々と社会の面へと出てきた。
新型コロナウイルスの迎え方
ところで1月末にはいち早く生活者は認識いていたと書いた。その背景であるが、周知のように季節インフルエンザは例年より早く昨年11月ごろから流行り始めていた。昨年の12月にはマスク姿の人たちが街中に多く見られるようになった。しかも、グラフを見てもわかるように、季節インフルエンザの罹患者は例年より極めて少なくなっている。(東京都)

赤い線が今年の罹患者のグラフである。多くの人は今年のインフルエンザは軽かったなというのが印象であったと思う。ちなみに全国ののインフル患者数は昨年は1210万人であったのに対し、今年は729万人と減少している。
何故、季節性インフルエンザは減少したのか。季節性インフルエンザに代わるように新型コロナウイルスの感染が始まるのだが、その際、生活者のマスク着用や手洗い・うがいといった日常の感染対策は新型コロナウイルス感染を防御し得たのかどうか、実はこうした疑問点について専門家会議も明確な答えられてはいない。極論を言えば、「疫学」という専門研究の世界だけの知見であって、生活者のライフスタイルをどう変えて行ったら良いのかという視点が決定的に欠けている。つまり、専門家会議の提案する「生活様式」が素直に受け止められないのはこうしたことに起因している。

こうした季節性インフルエンザの実態を踏まえ、多くの感染症研究者は単なる季節性インフルエンザの延長線上で新型コロナウイルスを受け止めていた。しかし、冒頭に書いたように既に中国の感染実態に触れ、勿論一部の研究者や医師の間では感染対策をどうすべきかと言った声は1月には上がっていた。
コロナの正体が少しづつわかってきた
新型コロナウイルスの対策を始めその情報のほとんどは政府専門家会議(現在は諮問委員会)のメンバーによるものであった。しかし、海外の情報を始め感染症以外の科学者からの発言が多く見られるようになった。そうした発言の中で、新型コロナウイルスと戦っている現場の医療従事者を始め、多くの国民の支持を得てきたのがあのiPS細胞研究所の山中伸弥教授である。ノーベル賞の受賞研究者ではあるが、多くの国民にとっては難病患者のために努力し続けている誠実で真摯な人物であると理解している。情報の時代、つまり過剰な新型コロナウイルス情報に対し、科学者の目で冷静に「今」わかっている新型コロナウイルスの正体を「証拠(エビデンス)の強さによる情報分類」したうえで、「5つの提言」をHPを通じて投げかけてくれている。
国民が求めていることは新型コロナウイルスとは何かという本質である

山中伸弥教授の発言によって、新型コロナウイルスの姿が少しづつわかってきた。これは政府専門家会議による広報では得られない多面的、多様な情報である。それは本来「正しく、恐る」という理解であるはずの理解を促すべきところを、「恐怖」によって移動の自粛を行う戦略を採ったことへの疑義であると私は受け止めている。山中教授は異なるコロナ理解、つまり冷静に理性的に確認できる「事実」を「正しく」伝えることが重要で、その姿勢が多くの国民の理解を得つつある。
専門家会議によるコロナ対策、クラスターという小集団対策、ある意味もぐらたたき戦略は、一方でコロナの「恐怖」を提示することによってある時までは成立してきた。それはもぐらたたきが可能であった時期までである。既に3月に入り欧米に観光で出かけた観光客が帰国した頃から、主に都市における市中感染が始まっている。これは専門家会議も認めていることだが、PCR検査体制を抑制したこともあり、この感染の防疫の対策を持ち得なかった。残ったのは「恐怖」だけであった。それも何による恐怖なのかという具体性のない、漠たる恐怖であった。
現段階で分かったこと、その証拠が正しい可能性が高いかどうかを冷静に整理してくれている。ここには理性を持って新型コロナウイルスに向き合う態度がある。マスメディア、特に「刺激」ばかりを追い求めてきたTVメディアの態度とは真逆である。こうした「証拠」に基づいた提言こそが必要であり、恐怖による行動変容は一時期的に表面的な自粛が行われても、同時に人と人との間に憎しみや争いを生むことになる。
恐怖による行動変容
ところで社会心理学を持ち出すまでもなく、行動の変容を促すには恐怖と強制が効果的であると言われている。そして、恐怖は憎悪を産み、分断・差別を促す。憎むべきウイルスは次第にルールを逸脱する人間へと変わっていく。少し前になるが、ゼミやサークルの懇親会で新型コロナウイルスのクラスター(感染者集団)が発生した京都産業大の学生に対し、抗議や意見の電話やメールが数百件寄せられているとの報道があった。抗議どころかあるTV番組のコメンテーターはウイルスを撒き散らした学生にはまともな治療を受けさせるなと暴言を吐く始末である。
あるいは同じ番組であるが、今度は外出の自粛要請の休日に禁止されている区域に潮干狩りをしているとの報道を踏まえてと思うが、感染症学の教授が「二週間後はニューヨークになってる。地獄になってる」と発言したのには驚きを越えてこの人物は大学教授なのか、教育者としての知性・人間性を疑ってしまった。ニューヨークのようになってはならないと発言するのであればわかるが、それにしても「地獄」などといった言葉は間違っても使ってはならない。つまり、恐怖心をただ煽っただけで、しかも専門分野の教授の発言であるからだ、
「自粛」を促すには恐怖と強制が常套手段であると書いたが、「2週間後にはニュ-ヨークになる」「地獄になってる」といった恐怖を煽るようなTVコメンテーターの発言も現実・事実がそのように推移しなくなったことから、その刺激的な発言もトーンダウンしてきた。一方私権を制限することが法的にもできない日本においては「強制」できない現実から「自粛警察」といったキーワードが流行る嫌な現象が生まれている。『自粛警察』とは、例えばクラスター感染のシンボリックな場所・施設となったライブハウスへの中傷で、東京高円寺の街では休業中の店舗などに休業を促す張り紙をしたり、張り紙に文言を書き込んだりすることを指すとされる。他にも居酒屋など休業要請を指定されてはいない店舗への嫌がらせも出てくる状況が生まれている。私に言わせれば、「正義」の仮面をかぶった一種の嫌がらせであるが、憎むべき敵であるコロナウイルスが休業していない店舗にすり替えられての行為が至る所で見られるようになった。「恐怖」はこうした中傷をはじめとした差別を連れてきている。その象徴が『自粛警察』である。また、カラオケについてもあたかも密=クラスターの発生源であるかのような発言をするコメンテーターもいて、勝手なイメージが一人歩きする。
ロックダウンではなく、セルフダウン
東日本大震災の時もそうであったが、「現場」で新しい新型コロナウイルスとの戦いが始まっている。医療現場もそうであるが、マスクや医療用具の製造などメーカーは自主的に動き始めている。助け合いの精神が具体的行動となって社会の表面に出てきたということである。「できること」から始めてみようということである。その良き事例としてあのサッカーのレジェンド「キングカズ」はHP上で「都市封鎖をしなくたって、被害を小さく食い止められた。やはり日本人は素晴らしい」。そう記憶されるように。力を発揮するなら今、そうとらえて僕はできることをする。ロックダウンでなく「セルフ・ダウン」でいくよ、と発信している。そして、「自分たちを信じる。僕たちのモラル、秩序と連帯、日本のアイデンティティーで乗り切ってみせる。そんな見本を示せたらいいね。」とも。恐怖と強制による行動変容ではなく、キングカズが発言しているように、今からできることから始めるということに尽きる。人との接触を80%無くすとは、一律ではなく、一人一人異なっていいじゃないかということである。どんな結果が待っているかはわからない。しかし、それが今の日本を映し出しているということだ。
東日本大震災の時に生まれたのが「絆」であった。今回の新型コロナウイルス災害では「連帯」がコミュニティのキーワードとなって欲しいものである。
大阪らしい戦い方
一足先にコロナ禍からの出口戦略に組み出した大阪は知事を中心に大阪らしい戦い方を見せてくれている。それはコロナ禍が始まって以降大阪が行ってきた対策はどこよりも的確でスピードのあるものであった。中国観光客のバスガイドが感染したことを踏まえ、徹底的にその行動履歴を明らかにして感染拡大を防ぐ行動をとった。その後、周知の和歌山県で起きた院内集団感染拡大に対しても、和歌県の要請を受けてPCR検査を肩代わりする、つまり近隣県とのネットワークも果たしている。更に、ライブハウスで感染クラスターが明らかになったときもライブハウス参加者に呼びかけ、つまりここでも情報公開を行ってきている。更には早い段階で軽症感染者や重症感染者など症状に応じた「トリアージ」の考え方を取り入れ、病院崩壊を防ぐ対策をとってきている。また、病床確保にも動いており、十三にはコロナ専門病院も用意している。・・・・・・・こうした情報公開と準備を踏まえたうえでの「出口」の提示であるということである。大阪府民が支持するのも当然であろう。少なくともPCR検査を含め東京都とは違いデータの収集分析はシステマチックになされている。勿論、他県も同様であるが、東京が正確なデータで「出口」を示せないのに対し、大阪はかなり先へ進んでいる。東京の場合、ロードマップという工程表を提示しているが、4段階のうち、第一段階は進めたとしても、第二段階、第三段階などどんな「目標・数値」が達成できれば次の段階へ進めると言ったことが明確になっていないこと。つまり、数字での判断ではなく、「成り行きまかせ」で、いつになったら「出口」となるのか各業種ごと不明であるという点が大阪と大きな違いとなっている。


こうした対策に呼応するように府民も戦っていることがわかる。それは商売の街・大阪の戦い方によく出ている。東京が休業協力金を出すことができるという財政に余裕があるのに対し、大阪の場合余裕はない。当然戦い方も異なり、府民の「協力」しか武器はないということである。その武器は何か、大阪らしさ、大阪のアイデンティティに依拠した戦い方である。
そのキャッチフレーズは「負けへんで」。臨時休業の告知だけではつまらない、「どうせ耐えるなら楽しく」やろうじゃないかということだ。きっかけはお好み焼きのチェーン店「千房」で、「負けへんで 絶対ひっくり返したる」と書かれたポスターである。お好み焼きのコテにひっかけた、ウイットのある大阪らしい表現である。今やギンザセブンにも出店している串カツの「だるま」は、ソースの二度ずけ禁止」にかけ「負けへんで コロナの流行は禁止やで」と。そして、「二度ずけ禁止」という大阪文化は少しの間お預けして、かけるボトルソースを用意し、少しでも感染予防になればと工夫が凝らされている。
この「負けへんで」死rーずの延長線上に営業再開のポスターが作られている。大阪の友人にお願いしてその大阪らしい「心意気」、商人文化を撮ってもらっtあ一部である。(後半へ続く)