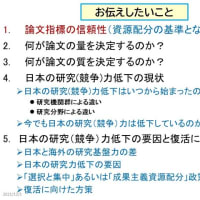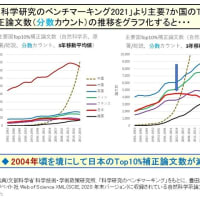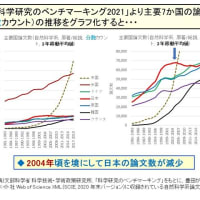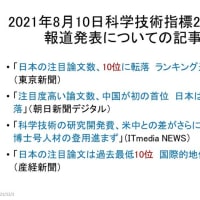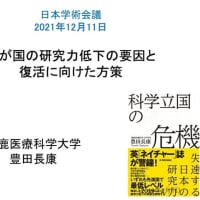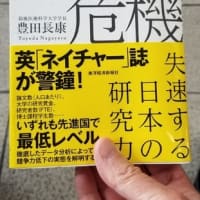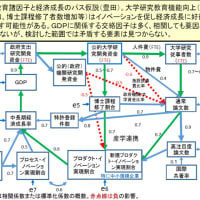前回のブログで、大学院生の使い捨て問題について、沖縄科学技術大学院大学(OIST)では大学院生を少数に絞って、人財育成に重きを置いていることが伺われること、ただし、潤沢な研究資金が投入されていることをお話ししたところ、彦朗さんからまた、コメントをいただきました。
彦朗
19/01/11 19:22
>大学院生を労働力として使い捨てにしない研究環境を整えるには、政府が大学への研究資金を他の先進国並みに
これはちょっと頂けません。まるで学生を人質に取っているように読めてしまいます。研究資金がどうであろうと、学生を使い捨てにしてはいけません。
また、大学院生の労働問題は2000年頃から盛んに叫ばれていますが、その頃は予算も比較的潤沢だったのではないでしょうか?
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Labo/5828/index.html
彦朗さんは、以前(20年ほど前?)に、基礎生物系の大学院生としてずいぶんと辛い目に遇われたようですね。彦朗さんのサイトを読ませていただき、その当時の状況がやっとわかりました。
僕自身の研究者のキャリアーとしては、研究指導者の面では良い先生ばかりで、幸いでした。一方、当時僕が見聞きした範囲においても、研究費をけっこう獲得できている先生で、若手を労働力としか見ていないと思われる先生がおられましたね。超一流の研究者についても、今だったらアカハラで訴えられていたかも、という声が聞こえてくることがありますね。
彦朗さんのおっしゃるように、この問題は、指導者の資質も大きく関係していますね。研究費が少なくても、良い指導者の元で研究ができたら、大学院生としてはかけがえのない経験が積めるかも知れません。
僕も、前回の彦朗さんへの説明の中で、ロジックの基本である「逆必ずしも真ならず」をうっかりと無視してしまいましたね。
「大学院生を使い捨てにしていないOIST ⇒ 研究資金が潤沢に投入されている。」
の逆の
「研究資金を潤沢に投入すれば ⇒ 大学院生を使い捨てにしない。」
とは、必ずしも言えないということですね。なぜなら、大学院生を使い捨てにする要因としては、僕が考えた「研究資金の不足のために大学院生を労働力として使わざるを得ないプアな研究環境」ということ以外にも、「大学院生を労働力としてしか見ることができない研究指導者の資質」もあるからですね。ひょっとしてこれらの他にも要因が考えられるかもしれません。
今回の僕の「科学立国の危機ー失速する日本の研究力」においては、指導者の資質の問題については、残念ながら言及できていません。彦朗さんのようなケースを防止するための方策については今後の課題とさせていただきたいと思います。
ただ、僕の著書では、若手研究者の意見を一部ですが紹介しています。これは、文科省の科学技術・学術政策研究所の「科学技術の状況に係わる意識調査」(NISTEP定点調査)の自由記載(ネットで見れます)から引用しています。
この自由記載欄を読むと最近の若手研究者や若手教員の大変な状況や不満が、よく伝わってきます。無能なシニア教員に対して早く辞めて欲しいという意見もありますが、国立大の運営費交付金削減等による教員ポスト減少によって昇任チャンスが減ったことに対する不満や、生計の不安定なポスドクを脱してやっと助教になっても、任期制教員ポストが増えており、生計の不安定さが延々と続くことに対する不満が多いです。そして、このような若手研究者のキャリア環境の厳しさが、博士課程に進学する学生数の減少に結び付いているという意見もあります。
政府は、シニア教員を早く転職させるようにしむけて、その分若手研究者を早期に教員に採用するように求めているようです。そして若手教員比率(40歳未満)を高めることを国立大学の評価の共通指標として評価し、運営費交付金を傾斜配分(メリハリ)しようとしているようです。
僕も若手研究者のキャリア環境は、なんとか改善する方向で検討していただきたいと思います。ただし、「若手教員比率」という指標を各大学の評価の共通指標とすることについては反対です。
その理由の一つが、今回僕もうっかりして陥ってしまったわけですが、先ほどの「逆必ずしも真ならず」というロジックの基本を無視してしまうことになるからです。
「研究生産性を向上させ若手研究者のキュアリア環境を改善させると想像される一つの案 ➡ 若手教員比率上昇」
の逆の
「若手教員比率を高めれば ➡ 研究生産性が向上し、若手研究者のキャリア環境が改善する」
ということは必ずしも言えないからです。
若手教員比率を上下させる要因はたくさんあります。たとえば、教員の定年の低年齢化(高年齢化)、また、教員(助教)採用年齢の低年齢化(高年齢化)があります。教員ポスト(定員)の削減(増)は一時的に若手教員比率を低下(上昇)させます。ただし、若手はそのうちシニアになりますから、中期的には若手教員比率は元にもどります。つまりポスト(定員)の増減は若手教員比率には中立的です。
テニュアトラック制は、若手研究者に自立した研究をさせて、研究能力を評価した上で教員に採用する方式ですが、教員採用年齢が高めになるので、若手教員比率を下げる要因となります。そんなことをせずに、もっと若い研究者を早く助教にした方が若手教員比率は高まります。外部の優秀な教員を准教授や教授で採用することは、若手教員比率を低める方向に働きます。内部昇格で助教を准教授や教授にすれば、助教のポストが空くので、若手研究者を教員にすることができますが、外部から准教授や教授を採用した場合には、助教のポストが必ずしも空くとは限らないからです。
国立大学が法人化された2004年に三重大学の学長になった僕は、さっそく、定年後の特任教員制度を始めました。彼らに大学からは給与を支給しませんが、つまり無給ですが、教育・研究・産学連携活動に尽力していただき、外部資金も獲得していただけます。大学にとってはこれほどありがたい存在はないと思うのですが、若手教員比率を低めることになりますから、若手教員比率が共通指標に設定されると、こういう生産性の高い人事もできなくなります。
実は日本のメジャーな学術分野で唯一臨床医学論文数だけは増えているのですが、この原因は、大学病院の経営改善によって医師数が増えたことにあります。そして、若手教員が減ったわけではなく、シニア教員が増えたために、若手教員比率が急速に低下しています。臨床医学においては、若手教員比率が低下したにも関わらず、ある意味での研究生産性は高まったのです。
職階のヒエラルキーを激しくする、つまり、助教の数に対する教授・准教授の比率を小さくすれば、若手教員比率を高める方向にプラスになります。若手教員比率を高める最も確実な方法は、職階のヒエラルキーを激しくした上で、助教を全員任期制にして、シニア(40歳)になる前に、辞めさせることです。しかし、これではせっかく優秀な助教が見つかった時に、准教授や教授に抜擢することもほとんど出来ませんね。そして、このようなキャリア環境を若手研究者が希望しているわけではないと思います。
「若手教員比率」を国立大学の評価の共通指標とすることは、全国立大学にそうすることを求める訳ですから、40歳未満で辞めざるを得ない助教や、あるいは早期退職をするシニア教員が他の国立大学の准教授や教授、あるいは特任教員に採用されるチャンスは、彼らがいくら優秀であっても極めて小さくなります。そして教員の流動化という面ではマイナスに働きます。これは一種の「合成の誤謬」という現象が起こることになりますね。
さらに、日本の大学の若手教員比率が低下していることが問題視されているのですが、スイスや韓国など、日本よりも若手教員比率が低いけれども、研究生産性の高い国がいくつかあります。また、OISTは日本の中で、最もインパクトの高い論文を産生している研究機関の一つですが、若手教員比率は他の国立大学よりも低いと想定されます。また、2016年にScienceという有名な学術誌に発表された論文では、Random Impact Ruleが提唱されています。これは、一流の研究者の生涯のうちで最もインパクトの強かった研究は、年齢によらずランダムに生じていることを示したものです。2002年にノーベル化学賞を受賞したジョン・B・フェン博士はエール大学を退職させられてからの研究で受賞したとのことです。
このようなことを考えると
「若手教員比率を高めれば ⇒ 研究生産性が高まり、若手研究者のキャリア環境が改善する」
とは、到底言えないことがわかります。
蛇足ですが「若手教員比率」を高める超裏技をご紹介しましょう。それはポスドク等の若手研究員に対して、給与等の条件はいっさい変えずに、「特任助教」という称号だけを与えることです。そして、彼らが40歳に達したら、元の研究員の称号に戻します。これで、ポスドクが多く存在する旧帝大クラスの大学では「若手教員比率は」一気に高まります。ただし、研究生産性が今よりも高まることもないし、若手のキャリア環境の改善もなされるわけではありませんね。
「逆必ずしも真ならず」に注意することの他に、「若手教員比率」の上昇が最終的な目的・目標の達成に、いったいどの程度寄与するのか、という観点も重要です。例えば「若手教員比率」を法人化前の値に引き上げた場合に、いったい研究生産性が何パーセント上がると期待されるのでしょうか?僕は上がったとしてもごくわずかであると想定します。そして、研究従事者数を増やして論文数を増やした先進諸国との研究競争力の差は、ほとんど縮まりませんね。つまり、最も大切な目的である、研究面での国際競争力を高めることには、ほとんど寄与しない指標であると考えられます。
このように「若手教員比率」というのは、一見単純そうに見えますが、たいへん複雑で難しい指標であり、落とし穴がたくさんあります。
なお、「若手研究者比率」という指標は、「若手教員比率」とは、似て非なる指標です。先ほどお話ししましたようにOISTの「若手教員比率」は低いと想定されますが、「若手研究者比率」は高いと想定されます。ただし、「若手研究者比率」を大学評価の共通指標にすることにも、大きな問題があります。
今、行政は国も地方もKGI,KPIブームで数値目標で溢れかえっています。しかし、数値目標の設定は、特に評価指標として資源の配分の根拠として用いる場合には、慎重にも慎重を期す必要があると思います。不適切な数値目標を設定してしまうと、効果があるどころか、弊害が生じてマイナスになることもありえます。1990年代に日本の企業が欧米の成果主義評価を導入した際、皮相な結果主義評価となって業績が下がり、総合評価に修正を余儀なくされた轍を踏まないようにお願いしたいと思います。










![科学立国の危機失速する日本の学術研究力[豊田長康]](https://tshop.r10s.jp/book/cabinet/3895/9784492223895.jpg?fitin=200:300&composite-to=*,*|200:300)