底抜けもててもてて(1961)
The Ladies Man
監督:ジェリー・ルイス
出演:ジェリー・ルイス、ヘレン・トローベル、パット・スタンリー、キャスリーン・フリーマンetc
評価:95点
おはようございます、チェ・ブンブンです。
さて、ジェリー・ルイスである。
1950年代から、ノーマン・タウログ、フランク・タシュリン、そしてコメディ役者であるジェリー・ルイス自身もメガホンをとって量産されたドタバタコメディ《底抜け》シリーズは日本でもクレージーキャッツやザ・ドリフターズの破天荒なギャグに影響が与えたアメリカンコメディである。アメリカ本国でもエディ・マーフィーの『ナッティ・プロフェッサー クランプ教授の場合』でリメイクされ、黒人映画の文脈で継承されている。そして、何よりも堅物映画雑誌カイエ・デュ・シネマでは、このアメリカンコメディシリーズがカルト的人気を博し、何度か年間ベストに選出されているのだ。本作を観ると、映画から音がなくなる場面や、ダンスのシーンがゴダールの『はなればなれ』に影響与えていることに気づくでしょう。それだけ、映画史的に重要なものをもっているのだ。
そんな、《底抜け》シリーズ。ジェリー・ルイスが《女嫌いの男の悪夢》という非常に際どいテーマを、ウェス・アンダーソン的巨大な家を真っ二つに切った世界のなかで描くのだから面白くないわけがない。しかし、何故本作が面白いのか?何故、《底抜け》シリーズが凄いのかを分析している記事は少ない。そこで稚拙ながら、ブンブンが分析してみようと思う。
『底抜けもててもてて』あらすじ
アメリカの西部に近いここミルタウンにハービー君(ジェリー・ルイス)という青年がいた。大学卒業式の日、幼い頃から憧れていた女に振られた彼は、町を去って仕事に打ち込もうとあちこち当たってみるが、うまくゆかない。みんな美しい女たちのせいだ。やむなくハリウッドのある寮のボーイになったが、男に飢えた女でいっぱい。早速、逃げようとすると、寮長のヘレン(ヘレン・トローベル)がなだめすかして引き止めた。寮の女たちは、かれがイカれていると思い込む。フェイ(パット・スタンリー)だけは好意をよせ、彼もまた親切にしてやる。ある日、もとプリマドンナのヘレンにテレビ局からインタビューにきたが、ハービー君が録音機とカメラをこわしたので、リンチをくわえられる。海岸へピクニックに出かけた日、同行の女たちにちょっかいをかける16人の猛者連中を出しぬいたことで、ハービー君はいささか威信を挽回。他事多難な彼の生活に、2人の有名人が顔を出した。それはジョージ・ラフトとハリー・ジェームズである。そんな毎日の中で、わがハービー君はやっと女性恐怖症から開放されそうになると、こんどは犬だ。ベイビイと呼ばれるこの犬は、餌を与えようとして戸を開けるか開けないうちに、すごい声で吠えつくのである。たまりかねて脱出をくわだてる彼を、なんと寮長以下全員の女たちが通せんぼするではないか!「みんなあなたにいて貰いたいのよ」とフェイにいわれ、ハービー君は思わずスーツケースを抛り出して彼女を抱きしめた。寮にとどまる気になったのはいうまでもない。
※MovieWalkerより引用
ドールハウスで女嫌いマン死す
カイエ派を驚かせた《底抜け》シリーズ、ないし1950~60年代のアメリカドタバタコメディはコントを映画言語に翻訳したことに注目することが重要だ。アンドレ・バザンによれば、かつてのフランス映画界では演劇の安易な映画化が多く、批評家をうんざりとさせていたのだそう。演劇をそのままカメラで捉えてもそれは《映画》ではないのだ。それ故に、カイエ派の批評家はロケや即興演出中心の自由な作風を試行錯誤し、ヌーヴェルヴァーグが巻き起こった。その際に、カイエ派が注目したのは、アメリカ映画であった。低予算でB級であっても、自由で、カメラの動きを意識した映画的画面作りに熱狂したのであった。
そんなカイエ派にとって、演劇的な《底抜け》シリーズ、またはその流れをゆく作品群は驚愕の代物であった。『底抜け大学教授』や『ロック・ハンターはそれを我慢できるか?』を観ると分かる通り、ドリフのコントである。大掛かりなセットの中で役者が饒舌な口調でしゃべくり、破壊的なギャグを畳み込む。しかし、映画は演劇的固定された空間を否定し、例えば、『底抜け大学教授』におけるスクリーンを意識した強烈な色彩、『ロック・ハンターはそれを我慢できるか?』における大量の女に追いかけられる男の3次元的な動かし方や画面を変幻させることで生み出されるギャグといった形で映画言語に翻訳していった。
閑話休題、『底抜けもててもてて』における、映画言語の翻訳は凄まじい。それこそ、冒頭、犬や男が飛び出して、大量の人が隊列を組み、自転車は車に轢かれそうになって、よろけて電柱にぶつかり、電柱にいる人がずり落ちで尻に尖ったものが刺さるピタゴラスイッチたるギャグの釣瓶打ちの鮮やかさはお茶の子さいさいな演出だ。ジェリー・ルイス演じるハービーは失恋して以降、女恐怖症になってしっまう。大学を卒業するも、仕事が上手くいかず現在休職中だ。ベンチに座って求人案内を探すのだが、よく観ると、彼の座っている空間には膨大な広告が立ち並んでいる。食料品から、店の宣伝、ベンチには金貸しの広告があるのだが、彼は目もくれず四六時中、求人の書類をぶちまけながら仕事を探す。しかし、カットが切り替わり彼の目線の先が映し出されると、そこには広告は1つだけ。
「未婚者のボーイ募集中」
彼は仕事に飛びついた!
住み込みで寮のボーイとなった彼。しかし、彼は知らなかった。ここは女子寮だったのだ。
ここで、軽いジョブがてらベッドの概念破壊を魅せる。2段ベッドで一休みしようとハービーが飛び乗ると、ベッドは粉砕してしまう。仕方がないので下のベッドで寝ようとすると、ベッドは沈み込む。ベッド=寝るものという概念が溶解していく視覚的にユニークな笑いを提供し、悪夢の日々へシフトしていく。ドールハウスのように、整然とした空間に膨大な女が鎮座し、ハービーを出迎え、オペラサウンドで女が歌う。そこに女嫌いから見た恐怖が説得力持った形で提示される。
そして、舞台的構図を映画的動きに翻訳しながら破壊的なエピソードが所狭しと並べられていく。
画面空間的面白さの面で2つ紹介しよう。
女性寮の生活を説明する場面。寮は真っ二つにぶった切られているので、横移動で女性の生活が絵巻のように描かれるのだが、化粧している女性を魅力的に映すため、鏡はフレームだけ残して、女性は画面に向かって化粧しているように見せている。また、部屋の仕切りは役者の判断に任されているので、妙なところにある扉の影にハービーが入っていき、彼が悲鳴をあげながら扉を開けると、女性がこんにちわするといったネタがある。映画の持つフレームを、扉や目に見えない壁で分断していき、それを自由自在にカメラが移動していく。この動きこそが演劇から映画への翻訳と言えよう。
そして、かつてスクリューボール・コメディで描かれた、それこそ『赤ちゃん教育』で描かれた破壊的なまでに自由な女という役割を逆転させ、映画における男女関係を鋭く考察していく。ハービーは、寮のボーイであるにもかかわらず、常時何かを破壊している。水は噴射され、標本を開ければ蝶が逃げてしまう。ガラスの置物は粉砕され、絵画には口から出血の落書きがされてしまう。これはまさしく、『赤ちゃん教育』でヒロインがやっていたことそのものである。そして終盤になると、このセットから女が消えはじめ、膨大な映画スタッフがハービーを撮り収めるようになる。映画業界ないしテレビ業界が男社会で、男によって女が撮られる構図の中にハービーという存在を置くことで、そんな男社会を皮肉ってみせているのだ。
こうも考えると中学時代に観て、あまりにヒロインの破天荒さにげんなりしオールタイムワーストに入れている『赤ちゃん教育』に対する印象が変わってくる。ドタバタコメディは大味で俗ではあるが、その表現の自由さが奇跡的に演劇から映画へ跳躍する瞬間を捉えていたりするので侮れないなと感じた。
『死ぬまでに観たい映画1001本』に掲載されているアメリカンドタバタコメディ『画家とモデル』も早いところ観たいところです。
 ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!
ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう! ブロトピ:映画ブログ更新
ブロトピ:映画ブログ更新














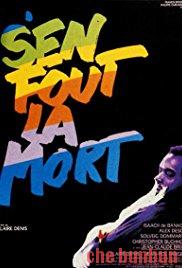
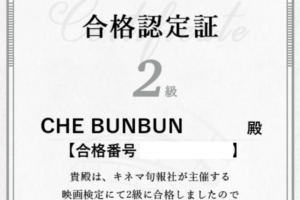







コメントを残す