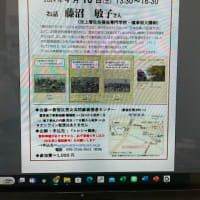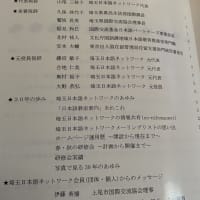拙著『あの戦争さえなかったら 62人の中国残留孤児たち(上)(下)』に、推薦の言葉を書いてくださった法政大学の高柳俊男先生のインタビュー記事が、大正大学『地域人』第60号に掲載されました。留学生のフィールドワークの様子を知ることができます。その中に、私の本の「推薦の言葉」に書かれていた三六災害の『濁流の子』碓田栄一氏のことも、郷土史の文脈の中で紹介されていましたので、全体像を探ることができました。感想を寄せてくださった多くの方が、高柳先生の「推薦の言葉」に感動したと記していますので、ここに一緒に紹介することにします。



《推薦の言葉》
藤沼敏子著『あの戦争さえなかったら 62人の中国残留孤児たち』に寄せて
「不条理な過去を未来へとつなぐために」
法政大学教授 高柳俊男
藤沼敏子さんとの出会い
私が藤沼敏子さんという人物を知ったのは、いまから四年前の2016年だった。その春、私は前年に歌集『伊那の谷びと』を自費出版した小林勝人さんをお招きして、歌に込めた想いなどを伺うイベントを、長野県阿智村の満蒙開拓平和記念館で開いた。というのは、私の所属学部では2012年度以来、伊那谷を舞台に夏休みの学生研修を実施しており、私がその担当者を拝命している。満蒙開拓や中国人強制連行をはじめ、かつて生業だった養蚕や近年の過疎化など、小林さんの詠んだ短歌を媒介に、伊那谷の経てきた近現代史の歩みや精神史のようなものを、ともに考える場が設けられないかと思ってのことだ。
イベントの終了後、ネットを見ていて、藤沼敏子さんという方が自身のブログでこの件を詳しく紹介しているのを知った。そこにはこのブログで以前、小林さんの歌集を紹介したことに続けて、「小林さんは目立たない地味な仕事を労を惜しまずなさっていらした」「お二人は、かつて旧満洲を訪ねる旅で同行して以来の交流仲間とのこと。高柳先生は、小林さんの地道な努力を研究者として高く評価してきたと言い、先生からこの対談企画を申し出たという。嬉しい!」などと、きわめて好意的に綴られていた。そこで、ブログ宛てにお礼を書き送ったり、藤沼さんがどんな方かを小林さんに尋ねたりするなかで、初めて交流が実現した。同年夏、同趣旨のイベントを東京でも開催した際には、藤沼さんも足を運んでくださって、お目にかかることもできた。
それ以来、約四年間。ご本人は1953年、栃木県生まれの由だが、私も栃木県が郷里で生年が1956年なので、奇遇に感じる(ついでに名前の読みも?)。立教大学で教え、小さな民の発想で歴史を学ぶ意義を説いた故・森弘之先生(インドネシア史)を、藤沼さんは「尊敬する恩師」と書いているが、私も台東区谷中のお寺の住職でもあった森先生に学部時代以来お世話になってきたので、その意味でも身近な存在に思う。
その割には、いまも藤沼さん個人の経歴については知るところが少ないのだが、ここで何よりも強調すべきは、彼女がかつて満州(中国東北部)で暮らした体験者を全国に訪ね歩き、二百人前後から聞き取りを行い、その映像を自身のホームページ「アーカイブス 中国残留孤児・残留婦人の証言」(https://kikokusya.wixsite.com/kikokusya)上にアップするという、地道な作業を永年にわたって続けてきたことである。そのことを知り、実際に映像のいくつかを見るに及んで、私は正直圧倒された。研究機関に籍を置く恵まれた立場の研究者でもないのに、どうしてここまでできるのだろうか? もちろん、こうした作業を可能にする前提として、時間的な余裕や一定の経済的な裏付けは必要かもしれない。しかし、日本の満州政策の下で過酷な人生を送らざるを得なかった人々の声に耳を傾け、それを聞き書きとして残さねばという強い意思、さらには一種の使命感のようなものがなければ、そもそも不可能な営みなのではないか?
それ以来、私にとって藤沼さんは、一目も二目も置く人物であり、脱帽の対象であり続けている。
前著『不条理を生き貫いて:34人の中国残留婦人たち』刊行をめぐって
藤沼さんが、ネット上に映像をアップした聞き書き記録を文字化する作業を進めていることは、本人からしばしば耳にしていた。そして、全四部作を見込んだ最初の一冊『不条理を生き貫いて:34人の中国残留婦人たち』が、昨年刊行された。その際、これまでの不断の努力が少しでも報いられるよう、私も何かお力添えできないかと考えた。
幸い、私の本来の専門である朝鮮関係でその頃たまたま知り合った人に、「東京新聞」記者の五味洋治さんがいる。出身は長野県の茅野市で、満蒙開拓にも大いに関心があるという。彼に相談を持ちかけたところ直ちに快諾、藤沼さんの居住地を担当する同社の中里宏記者に話を回してくれ、大きめの紹介記事が年末の同紙(二〇一九年十二月二二日付)に掲載された。ここでは、本書が「貴重な口述の歴史資料」だとしたうえで、藤沼さんが日本語ボランティア講座のコーディネーターとして活動する中で日本に帰国した中国残留婦人と親しくなり、インタビュー調査が始まった旨を記している。末尾には、本書がオンライン書店のアマゾンで販売中とも付記されていた。
この記事掲載で、藤沼さんにこれまでのご恩返しが多小なりともできたかと、いったんは胸をなでおろした。ところが、全国の大学図書館などの蔵書が一度に検索できるCinii Booksで調べると、現時点で所蔵が確認できる大学はわずか五校しかない。しかも「東京新聞」配布の中心エリアと思われる東京都内では、私がこの記事を添えてリクエストした法政大学のみである。もっと宣伝して、藤沼さんの仕事を幅広く知ってもらわねばとあらためて思う。
ちなみに、都内の公共図書館の所蔵を横断検索できるサイトによれば、区立ないし市立の図書館でヒットしたのはあいにく品川区のみ。都立図書館所蔵本が貸出中で、予約も三件入っていたのがせめてもの救いだった。
前著『不条理を生き貫いて:34人の中国残留婦人たち』の内容から
では、前著についてごく簡単に紹介してみよう。本書は、いわゆる中国残留婦人(国の定義だと終戦時に一三歳以上の女性)からの聞き書き集で、五五〇頁以上におよぶ大冊である。章立ては、第Ⅰ部が満蒙開拓団(各開拓団ごと)、第Ⅱ部が農業以外の自由移民、そして第Ⅲ部 サハリン残留邦人(例外的に男性からの聞き書きを含む)、第Ⅳ部 大陸の花嫁、第Ⅴ部 日本に帰らない選択をした残留婦人、と続く。残留婦人等とされる計三四人の、満州渡航の経緯、現地での生活、ソ連軍侵攻後の逃避行、死と隣り合わせの収容所生活、新中国での暮らし、日本に帰国してからの日々などが項目別に記されている。ソ連軍による婦女暴行や中国での人身売買をはじめ、結婚・出産・育児など、女性ゆえの証言がとりわけ重たく響く。「生きて虜囚の辱めを受けず」という戦前の価値観が、現地の中国人に嫁ぐに至った女性たちを苦しめたことも、男性とは異なる点である。それぞれの聞き書きには、本人の語った特徴的な言葉がタイトルとして付され、差異化が図られている。
基本的には、ネット上に音声で載っている証言を文字化したものだが、こうした作業が必要な大きな理由として、インタビューに応じてくれた方々が高齢で、インターネットにアクセスできないためと説明されている。
一般的に言って、他者からの聞き書きは思うほど楽な作業ではない。私も自分の研究の必要上、特定の体験をもつ個人からお話を聞かせていただいたことが多々あるし、大学史委員会の業務として、学徒出陣を体験した卒業生からの聞き取り作業に、同僚たちと数年間、これがラストチャンスになろうとの予測のもと従事してきた。私が考える聞き書きの最大の難しさは、「こちらの器の大きさに応じてしか話を聞けない」こと、つまり自分の体験していない世界の話を聞くので、聞き手側に知性の点でも感性の点でも十分な備えがないと、相手の話を最大限に引き出すことができない、という点である。そして、一定の人間関係、つまり相手からの信頼がないと、奥深いところまで語ってくれはしないという問題もある。時間の経過による忘却・記憶違いや、意識的・無意識的な自己弁護もあり得る証言内容をどう整理し、いかに事実を確定するかも含めて、神経を使う作業の連続である。本書の場合も、証言者を探し出し、連絡を入れて取材のアポを取り、現地まで出かけることから始まって、全過程に費やされた時間や労力は想像を絶する。
私が本書で特徴的だと思う点を三点挙げると、まずはある個人の証言が、一つには本書における文字資料として、もう一つはその表情や語り口もわかるネット上の映像により、二つの媒体で確認できることである。これは、両者それぞれの長所を活かし、短所を補完するという意味で、なかなかユニークな試みだと思う。場合によっては、固有名詞の間違いなど、著者の作業の不備が露呈してしまうことにもつながるが、そのことを厭わず、むしろそうした検証の機会を読者に提供している態度を公明正大に思う。
第二の特徴は、一つもしくは関連する複数の証言のあとに「証言の背景」という文章を入れ、語られた内容をより理解しやすくするための解説を丹念に加えていることである。たとえば、「第Ⅳ部 大陸の花嫁」では、満州に移民した青年男性が「屯墾病」(一種のホームシックのような疾患)に罹らず現地に定着できるよう、未婚の女性を一定の訓練を施したうえで大陸に送る「大陸の花嫁」と呼ばれる政策があったことが、各種の資料から説明される、といった具合である。
そして、第三の特徴として挙げるべきは、戦前戦中の満州での日常や、死の逃避行の話以上に、戦後の人民中国や帰国後の日本での人生に多くの分量が割かれていることだと言えよう。新中国の荒波を、養父母の人間愛に支えられ、またときにはスパイ視されるなどの理不尽な扱いを受けながらも命を繋いできた行動力や、帰国後の「祖国」での悲喜こもごもの想いなどに焦点が据えられている。
記録を残すということ―過去を未来へとつなぐ
冒頭で、学部で実施する伊那谷研修の担当者だと書いたが、研修の引率だけでなく、週一回の事前学習授業も担当している。そこで毎年扱う項目の一つに、伊那谷を梅雨末期の集中豪雨が襲(おそ)い百人以上の犠牲者を出した、一九六一(昭和三六)年の三六災害がある。自然災害の事実だけでなく、そこからの復興の過程や、とくにその記憶や記録を後世にどう残し教訓化しようとしているかに重点を置いて講義している。
その際、恐怖の三六災害を経験した子どもたちの作文を集め、ガリ版刷りで記録集『濁流の子』を作成した、箕輪町の碓田栄一氏についても触れている。行政や学校関係者ではなく、一個人がこうした作業を黙々とこなしたことに驚くが、実は本人は当時まだ高校を終えて大学に入ったばかりの、十代末の若者だったのである。記録を残し、過去を未来に活かそうとしたこうした孤独な営み、無償の行為こそ、私たちが真に記憶にとどめるべき事柄であり、まさに森弘之先生のいう「小さな民」の歴史ではないだろうか。碓田氏はその後、寄せてくれたものの当時は収録できなかった作文を、続編や補遺として世に出している。こうした行為がようやく認められて、いまでは信州大学などが三六災害関連資料を集めてつくるデータベースが、「語りつぐ“濁流の子”アーカイブス」(http://lore.shinshu-u.ac.jp/)と命名されている。
年齢の違いはともかく、藤沼さんの場合もこれに等しい営みだと言えよう。満州移民関係の本は、開拓団のいわば正史や体験者個人による回想録から、外部のルポライターないし研究者がまとめたものまで、実に膨大にある。とはいえ、公の機関ではなく、専門の研究者でもない立場から、これだけ多くの場所を訪ね、これほど大勢の聞き書きを残すのはきわめて異例と言えよう。しかも、苦難の人生を生き抜いてきた一人ひとりの生に寄り添おうという姿勢が、ひしひしと感じられる。それら多くの証言を通して、日本の庶民にとって満蒙開拓とは何だったのか、先の大戦とは何だったのか、その真相を明らかにしたいという切情に溢れている。彼女たちが、語りにくい話も含めて自分に語ってくださったことへの感謝の気持ちが、聞き書き活動のエネルギーの源泉になっているかもしれないとも思う。
藤沼さんの仕事は、これからもまだまだ続けられる。読者は、満蒙開拓という「被害」と「加害」の入り混じった歴史の重さ、今も残る課題の大きさ、そしてこの聞き書き集の分量の膨大さの前に、一瞬たじろぐこともあり得よう。ただし、まずは一編でもいいので、証言者の生の声に耳を傾けてみてほしい。そこから何か新しい認識や発見が生まれるかもしれないし、時代や環境こそ違え、同じ人間としての喜怒哀楽や、辛酸を乗り越えてきた個々人の生き様から、心に沁みるメッセージが届けられるかもしれない。「若い人にも読んでいただきたい」(前著の「はじめに」)という筆者の希望が、少しでも達せられることを願いたい。
この小文を書きながら、いまの聞き書き集の仕事が一段落したら、藤沼敏子さんの自分史もぜひ読んでみたい思いに駆(か)られた。そのことで、彼女がこれほどまで精力を注いで中国帰国者の聞き取りをする深い背景、藤森成吉を借用すれば「何が彼女をそうさせたか?」がわかり、この聞き書き集がより立体的に理解できるのではないかと思うからである。