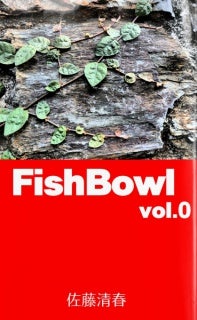前屈みになって、僕は手を組みあわせた。どういうわけか非常に落ち着いた気分になっていた。風の音はあいかわらずだったけど、僕たちはそれから遠ざけられていた。でも、そういう守られてる状態からくるのとは違う安心感があった。
「まあね」と僕は言った。
「みんな、あたしたちのことああいうふうに見てんのかな?」
「みんなじゃないよ。きちんとわかってくれる人もいる。そんなにたくさんはいないかもしれないけど、探そうとすればひとりくらいはいる。それに、そんな人間はひとりくらいがちょうどいいんだ。周りからどんなふうに思われてたって知っていてくれる人間はいるさ」
そう言いながら、僕は淳平を思い浮かべていた。こんなふうに考えるとは自分でも思わなかったけど、口に出してみると、まさしく僕には知っていてくれる人間がいるのだとわかった。温佳はすこし驚いたような顔をしていた。もしかしたら僕が長くしゃべれることに驚いたのかもしれなかった。
「あんたは強いのよ。だから、そんなふうに思えるの」
「強くなんかないよ。まったく強くない」
「嘘よ」と温佳は言った。
「あんたもあたしと違うんだわ。あたしは怖いの」
「なにが?」
「わからない。でも、すごく怖いの。どこにいたって、なにしてたって怖いの。ずっとそうだった。お父さんがいなくなってから、ずっとそうだった」
温佳は突然泣きだした。はじめは大きな瞳から涙が幾筋か流れただけだったけど、それはとどまることなく大きな流れになった。温佳は顔をくしゃくしゃにして声をあげて泣いた。
僕は立ちあがって、それからまた椅子にかけた。どうすればいいかわからなかったのだ。泣けばいいのにと思ったこともあったけど、実際にこうまで泣かれると狼狽するしかなかった。
温佳は脚をたぐり寄せ、膝に顔を押しあて、わんわん泣いた。パンツが見えていたけど、それはこの際どうでもいいことだった。僕は温佳の隣に座った。そうすればパンツに気を取られることもないし、この事態にきちんと対応できると考えたのだ。僕が隣に座ったのがわかると、温佳はさらに大きな声をあげて泣いた。でも、それからはしくしくと静かに泣きつづけた。
↓押していただけると、非常に、嬉しいです。
![]()
にほんブログ村
《佐藤清春渾身の超大作『FishBowl』です。
どうぞ(いえ、どうか)お読みください》