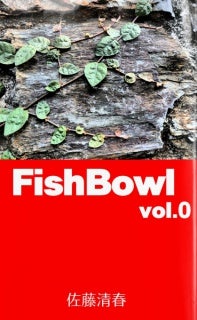僕は非常に忙しくなった。
部活と、温佳たちを母さんから遠ざけるのと、図書館通いを同時進行的につづけていたからだ。学園の方も土曜の午後に強制的な課外活動というのがつけ加えられていた。周辺の清掃やら、老人ホームへの慰問やら、小学校で勉強を教えるやら――だ。
それは、ふたたび理事会に参画するようになった真昼ちゃんの指示によるものだった。ほとぼりがさめたというのもあった。しかし、それだけではなかった。敏光くんの理事長振りを見るにつけ、もっと強力なリーダーシップを持つ人間が必要ということになったのだ。
それに、大きな影響力を持っていた理事たち(真昼ちゃんを遠ざけた者たちだ)は既に引退したか死んでいたので、そういう枷がなくなったというのもあった。真昼ちゃんは【外部理事】という肩書きを持つようにもなった。そして、学園改革のひとつとして課外活動をさせることにしたのだ。
これ以降の真昼ちゃんはごく穏やかに学園の運営に関わるようになった。
母親が理事長だったときと比べて、より迎えいれる態勢ができていたのだ。それには美樹さんの根回しが効いてもいた。美樹さんからしても、夫が理事長の職責をひとりで全うできるか疑問だったのだろう。また、昔から櫻井家を知ってる老人からすると、敏光くんはあくまでも愛人との間に生まれた子という肚もあった。たとえ途中でその性別を変えたにせよ、理事長職を継ぐべきは真昼ちゃん(というか、直系の息子)と考えていたわけだ。長く櫻井家の番頭をしてきた老人にとってそれは公理だった。
「馬鹿げた考えよ。ほんとにそう思ってたとしたらね」
真昼ちゃんはそう言っていた。
「でも、そのぶん前のときと比べれば楽だったわ。私も肩肘張らずにやってたしね。まあ、敏光をなんとか一人前にしなくちゃならなかったし、すくなくともそう見えるようにしなきゃならないでしょ? 美樹ちゃんはそっちの仕事で大変だったのよ。だから、私がご老体たちの相手を一手に引きうけることになってたの。でも、好きなようにやらせてもらってたわ。あの人たちには学園をどうするとか、教育とはどのようなものであるべきとか、そういう思想がまったく無いの。ただ定期的に集まって、数字の報告を受け、お茶を飲んで終わりなの。なんの変化も生まないし、そんなの望んでもいないのよ。前はそういうのがすごく腹立たしかったわ。でも、腹たてたってなにも変わらないからね」
運動部は清掃活動に従事していた。授業が終わるとユニホームに着替え、ゴミ袋を片手に学園周辺をうろつきまわるのだ。ひとつの集団につき、教員がひとり監督者としてついた。監督の仕方はまちまちで、生徒と一緒に清掃する者もいれば、はじめと終わりにだけあらわれる者もいた。僕としては一緒にしてくれる教員の方がありがたかった。向こうもとくに率先してやりたい仕事ではなかっただろうけど、それはこっちだって同じなのだ。であるなら、人手の多いに越したことはない。
しかし、生徒たちの人気は一緒に働く教員へより多く傾いていたわけではなかった。
一番人気があったのは上杉という、三十代の、引き締まった身体にいつもこざっぱりしたスーツを着た、冬場でも日に灼けた数学教員だった。一番人気がなかったのは市川という、これまた三十代の、スマートな、しかし、いつもよれよれの上着にちょっと汚れた眼鏡の美術教員だった。
市川さんは黙々と吸い殻やらパンの袋やらを拾いまわっていた。僕も彼が監督者のときは比較的真面目にゴミ拾いした。上杉の方は指示をして、それからしばらくどこかへ消え、終わった頃を見計らって戻ってきた。僕はその日には学園周辺の散策だと自らに言い聞かせ、無駄に思える時間をやり過ごした。
ただ、上杉が戻ってくると生徒たちには熱狂のようなものが起こった。それは主として女子からのものだったけど、彼が冗談を言いながら狎れ狎れしく近寄ってくると男子生徒だってまんざらでもない表情を浮かべた。人はその仕事で評価を受けるのではなく、見た目で評価される――まあ、完全にそういえなくても、そういった部分は厳然としてあるというのを僕はこの二人を見て学ぶことができた。
↓押していただけると、非常に、嬉しいです。
![]()
にほんブログ村
《佐藤清春渾身の超大作『FishBowl』です。
どうぞ(いえ、どうか)お読みください》