16.雪原と春風
ノア、という人は、素性のわからないわたしにもとてもよくしてくれる。それはもう、泣きそうになるくらい、優しくしてくれる。
それはたぶん、普通に生きていれば、当たり前とも言えてしまうようなささやかな優しさだ。
だけどわたしはそれを知らない。
だから嬉しい。
だから泣きたくなる。
わたしは、そんな優しさなどないところで生きてきたのだとわかるから。
「お早うリリー」
「おはよう、ございます」
朝、起床して、キッチンへ行くと、ノアの友人だというシリルが朝食を作り、ノアがコーヒーを淹れてくれる空間がある。とてもしあわせな場所が。しあわせな朝がある。
挨拶をすれば挨拶が返ってきて、あたたかいホットサンドとスープが並び、わたしはまるで彼らの一員のように、朝食を食べることができる。
今日で、ノアのもとでお世話になり始めて一週間になってしまった。
わたしはお金を持っていないし、お金になりそうなものもない。あるのはこの身一つだけ。
そんなわたしにノアが求めたのは、『お店を手伝ってほしい』という、とても健全な申し出だった。
ノアはわたしを傷つけない。ノアはわたしに痛くしない。
ノアはわたしをリリーと呼んでくれる。
冬の雪原のように雪が降り積もり、ひたすらに静かだったわたしの心に春風が吹き込んで、雪が舞い上がり、隠れていた色とりどりの花々が顔を出す。
そんな風を運んだノアという人物に、わたしは、たまらなく、泣き出したくなっている。
どうしてだろう。どうしてだろう? どうしてわたしは彼に対して『ごめんなさい』と思っているんだろう。『ありがとう』よりも『申し訳ない』が先に立つのだろう。
無一文なのに彼のお世話になっているから?
本当にそれだけだろうか?
今すぐここを飛び出したい。それが彼のため。そんなふうに強く思っているのは、本当に、それだけの理由?
悩みながら、考えながら、わたしは、喫茶店ドラゴンを離れることができずにいる。
(だって。ここは、とても、あたたかいから)
本当に。しあわせすぎて。泣きたくなるくらいに。あたたかいから。
冬に閉ざされた心は春を知ってしまった。あたたかさを知ってしまった。風のやわらかさを。咲き誇る花々を。
この場所から、白くて寒いあの世界には、もう戻れそうもない。

わたしの一日は、窓から差し込む朝陽から始まる。
眩しさに抵抗するように、最初は毛布を被って顔を隠す。
それから、耳をすませばわたし以外の誰かの出す音がして、わたしも起きなければ、と思えて、毛布から抜け出し、古いソファを立つ。
借りっぱなしのノアの服から、スーパーで買ってもらった白いシャツと黒いパンツスタイルに着替えてカーディガンを羽織る。
キッチンでノアとシリルにおはようございますをして、洗面所で顔を洗って戻ると、その頃にはテーブルに朝食が並んでいる。
チーズとハムと野菜のサンドイッチに、あたたかいスープとコーヒー。それだけでも、わたしにはとても贅沢でありがたい朝食だ。
眉間に皺を寄せて今日もタブレットを睨んでいるシリルと、寝ぐせが少し直っていないノアと朝食をとる。
それから、お店を手伝って箒を手に表に出たり、テーブルとチェアをアルコール消毒してキレイに拭いたり。
営業時間になったら、お客さんがすぐに来なくても、黒いエプロンをつけて、わたしは店に立つ。
今日は午前中、女性が四人で来店した。一度に四人もなんて、この喫茶店ではとても珍しいことだ。
四人組は、シリル曰く、ホームページの紹介を見て来たらしい。
最近シリルがタブレットに向かって作業を続けていたのは見ていたから知っているけれど、そんなに効果があるものとは、知らなかった。
シリルは普段は欠片も浮かべない(ああいうのを愛想笑いと言うのだろう)笑顔で女性四人に接客していたけれど、一人がコーヒーを淹れているノアを見て小声で「え、コーヒーってアジア人が…?」とこぼした、その小さな声に、シリルは一瞬真顔になった。それから、わたしでもわかる、薄っぺらい笑顔を浮かべて「店長はイギリス生まれですよ」と静かな声で訂正をしていた。
それが気に入らなかったのか、ノアのことをアジア人だと言った女性は、むっと不機嫌な顔になり、コーヒーには最後まで口をつけようとしなかった。
「なんだよ、もったいねぇ」
四人が退店したあと、シリルはいつもの難しい顔になると、口のつけられなかったコーヒーのカップを持ち上げた。
外からは甲高い、女性の声がする。「アジア人が淹れたコーヒー飲むとかありえないって!」きっとあの人だ。ノアのことをアジア人だと言った人。まだ店の辺りにいるのだ。「ちょっと…聞こえるよ。それにアンタさ、ちょっと過剰すぎ。イギリス英語のできる人だったじゃん。ほら、イケメンも、イギリス生まれだって言ってたよ」「それにおいしかったよ? コーヒー」「そうそう。どんなコーヒーがいいかって訊いてくれた。好みを出してくれるところ、評価できると思うけどなー」他の声は、ノアのことを非難していない。そのせいか、一人の声だけが甲高く、制御をなくして響いている。
「でもさ、どう見たってアジア人の平たい顔だった! アジア人なんて今じゃ奴隷同然じゃない! 奴隷の淹れたコーヒー飲むとか、白人としてどうかと思う!」
奴隷。
シリルのこめかみがピリッと引きつったのがわたしにもわかった。
それから、わたしも、全身の体毛がざわっとした。全身の血が騒いでいる気もする。
うまく言えないのだけど…これが、怒る、ってことなのかもしれない。
体が熱を持っている。この熱を発散して逃がしたいと考えている。その矛先を、切っ先を、ノアのことを悪く言っている人に向けたいと、そう思ってしまう。
だけど、ノアはカップやケーキがのっていたプレートを片付けながら、やんわりと笑って「大丈夫。慣れてるよ」と言う。奴隷と言われることを、ただ見た目で避難されることを慣れていると笑う。
彼が、笑う。大丈夫だと。
そうやって言われると、わたしの感じた怒りかもしれない感情がとたんに鋭さをなくしてしまい、中途半端に膨らんだまま、ふわふわと辺りを漂うしかない。
シリルは、感じた感情に、どう決着をつけたのか。彼は深く溜息を吐くと、手のつけられていないコーヒーの入ったカップをシンクに運んだ。そして、独り言のように声を落とした。
「今のオレなら、報いも、償いも、受けさせることができる」
静かな、感情のこもった言葉……だったと思う。
それがどういう意味なのか、わたしにはわからなかった。ノアにもきっとよくわからなかったに違いない。彼の表情は戸惑っていた。
……空気が、どこか、重い。
音がしない。古いテレビのザラついたノイズ混じりの音がしない。外でまだ騒がしいはずのあの女性の声もしない。世界から音がしない。ただ濃密な、ミシ、ミシ、と音を立てる何か大きなモノの気配が、シリルから、カフェというこのアンティークな空間を伝播してわたしたちにまで届こうとしている……。
「僕は、シリルと、リリーがいれば、それでもう充分だよ。
二人が普通に接してくれるだけで、僕は充分、報われている。だから、誰かを呪う必要はないよ」
この異変に、軋みに、ノアは気付いているのか、いないのか。
不機嫌を通り越して無表情になっているシリルをなだめるように彼はそう言った。今で充分だ、と。
リリー。リリーは、わたし。
(わたし?)
シリルはわかる。彼はノアのお友達だ。付き合いも長いという。彼はノアの支えになっているに違いない。
でも、わたしは。出会ってたったの一週間しかたっていないわたしが、あなたの中に、いるの?
「呪いは、悲しいだけだ」
この話はもう終わり。さ、片付けをしよう。
ノアの言葉で、わたしたちを圧迫していた重い空気がフッと消えた。
ザラザラとしたノイズ混じりの古いテレビの音と、陶器の食器がキレイに洗われていく音と、窓から射し込む光のキラキラとした欠片だけが店内に満ちていく。静かで奇跡的な景色が当たり前のように存在する世界に戻っていく。
きっと、これはただの断片。
彼が受けてきたいわれのない罰のほんの一場面。
わたしは、ノアを非難していた女性が座っていた席をじっと見つめた。
頭の中にはシリルの言葉がある。
(報いを。償いを。受けさせることができる………)
気付くと、わたしは自分の指を噛んでいた。噛む、というより、皮膚を噛み切って、血を滴らせていた。「…?」無意識だった。どうしてそんなことをしたのか、自分でもよくわからない。
だから、血を止めるために指をくわえたままのわたしを見たノアが「リリー? どうかした?」と訊くから………わたしは、自分の謎めいた行動をぎこちない笑みで誤魔化した。「ちょっと、切ってしまったみたいで。洗って、絆創膏、貼ります」ノアに傷口を見られる前にそそくさと洗面所に向かい、自分で噛み切った指を水道水につける。
(わたし、指を噛んで…何をしようとしていたの?)
記憶のない、わたし。
思い出そうとすると常に痛みが伴う、わたしという人の過去。
わたしはリリー。自分のことはそれしか知らない。
わたしは、リリー。それすら危うい認識だ。
ノアがリリーと呼んでくれるから、かろうじて、今のわたしはわたしでいられる…。
16話め!
間違って記事の公開ボタンを押していたため、急遽整えました💦
この時点でのリリーは記憶喪失みたいな感じとなっています
応援! にポチッとしてもらえると励みになります❤(ӦvӦ。)
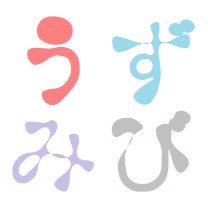






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません