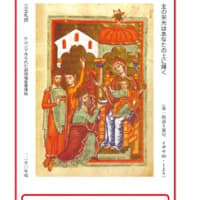明日にも緊急事態宣言が発令されるかもしれないという時にバルト論でもないが、だからこそと思わなくもない。
Ⅳ エキュメニカルな相互理解
ルターによれば、教会は信仰箇条によって発展もするし、衰退もする。教会は信仰箇条によって立つ。宗教改革とトリエント公会議(対抗宗教改革)の時代以来、カトリックとプロテスタントとの相互理解にとって根本的な障害物と見なされてきたのが、「義認の教説」(義化論・成義論)だ。ここでなにか意見の一致が見られれば、教会分裂の克服が可能になる。
キュンクの著書『義認』( Rechtfertigung 1957 )(1)はそれを意図したものだという。義認に関するバルトの教説とカトリック教会の教説の間には基本的な一致があり、義認論はもはやプロテスタントとカトリックとの教会分裂の理由にはならないと主張しているという。
キュンクはこの本についてバルトから送られた礼状「著者への手紙」をー誇らしげにー紹介している。バルトからキュンクへの私信で、キュンクの説への慎重な、しかし好意的な返答である。長文なので引用できないが、極めて興味深い内容の手紙だ。
このキュンクの著書は、当時としては過激な主張をしていたにもかかわらず、ローマによって「禁書目録」に入れられることはなかったという。1958年にヨハネ23世が教皇となり、カトリック教会は第二バチカン公会議にむけて新しい方向に歩み始めていたからである。
やがて、1971年に地中海のマルタ島で、ルター派世界連盟とローマ・カトリック教会の合同研究委員会による「マルタ文書」なるものが発表され、ルター派とカトリックとの間で次のような合意が確認されたという。
「カトリックの神学者たちも、義認の問題について、信仰者に対する神の救いの賜物はいかなる人間的条件にも拘束されないことを強調する・・・義認の使信は、福音の中心も最も重要な説明であると、繰り返し新しく表明し直されなくてはならない」(301頁)。この合意文書はローマからも確認がなされたが、このときすでにバルトはこの世の人ではなかったという。
(宗教改革500年記念 ルーテル教会との共同礼拝 中央がフランシスコ教皇)

バルトは、教義学は単に「自由な」学問なのではなく、教会という場所でのみ可能で、意味豊かな学問になり得るという主張をしていた。バルトのこういう主張は、あまりにカトリックとスコラ神学に接近しすぎているという批判が当時のプロテスタント側からあり、かれは最初の『キリスト教教義学』(1927)という本のタイトルを『教会教義学』に変更したのだという。キュンクはバルトのこの主張を、「福音へ集中した、カトリック的な、そして真にエキュメニカルな教会論である」と評価している。
だが、エキュメニカルな理解が双方で難しくなるのは、議論が、神学ではなく、「教会の組織構造や
教会政治の実際」が話題になる時だ。バルトは、教皇職がもつエキュメニカルな可能性に魅了されてはいたが、個別の歴代教皇については反発していたという。バルトは、「私はこのペテロの座から、よき羊飼いの声を聞いたことがない」と言っていたようだが、ピウス12世の時代(1939-58)のことらしい(2)。
Ⅴ 第二ヴァチカン公会議
5年間しかなかったが画期的だったヨハネ23世の教皇時代(1958-63)に、第二ヴァチカン公会議が開かれ(1962-65)、「二重のパラダイム転換」(宗教改革のパラダイムと現代的パラダイムが教会と神学に統合されること)が起こった。カトリックの「現代化」である。バルトは深く感銘を受け、ヨハネ23世についてためらうことなく述べたという。「今、私はよき牧者の声を聞くことができる」。
(ヨハネ23世 第二バチカン公会議)


キュンクも公会議に関わっていく。バルトに刺激されて宗教改革のスローガン「常に改革されるべき教会 Ecclesia semper reformanda 」を掲げて、公会議に改革プログラムを提出していく。公会議は非常にプロテスタント的に見える恒常的改革の必要性を「教会憲章」のなかに受け入れていった。それは、一方では宗教改革者たちの関心事(聖書と宣教の重視・信徒の重視・典礼における各国語の使用)を受け入れることであり、他方では、現代的問題(信仰・良心・宗教の自由、寛容とエキュメニカルな相互理解、ユダヤ教や世界の諸宗教との対話、世俗世界への対応など)への新しい態度・姿勢を受け入れることであった。
このカトリック世界の大変化と霊的波瀾は、当時のプロテスタント世界が陥っていた広範囲にわたる停滞状況と対照的だった。だが、それでもバルトはカトリックにはならなかった。キュンクはバルトを公会議に招待したが、健康上の理由で断ったという。1966年にかれはローマに旅行に出かける。バルトはパウロ6世(1963-78)を尊敬に値する愛すべき人を思ったようだが、すでに改革をとどめようとする教皇庁の妨害に出会っていると知ったようである。
キュンクは、バルトがその後の後継者(ヨハネ・パウロ1世と2世)についてどんな印象を持ったかはわからないと言っている(3)。事実この時点ではバルトは『教会教義学』の執筆を打ち切っていた。トマス・アクィナスが『神学大全』を突然打ち切ったように、バルトも突然仕事を中断した。それは「未完成交響楽」にとどまったのだという。バルトは最後の未完成の講演原稿のなかにルカ20・38を引用して82歳の生涯を閉じたという。
「神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。すべての人は、神によって生きるからである」(協会共同訳)
注
1 邦訳があるかどうかわからない。
2 ピオ12世またはピウス12世(Pius PP. XII、1876年 - 1958年)は第260代ローマ教皇(在位:1939年 - 1958年)。本名はエウジェニオ・マリア・ジュゼッペ・ジョヴァンニ・パチェッリ(Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli)。第二次世界大戦をはさんで20年間カトリック教会を導く。死後75年で関係書類の公開がなされるとの規程に伴い、先般、デジタル化された書類が公開され始まったという。ピオ12世のナチへの対応姿勢を巡っては毀誉褒貶が激しく、まだ評価が定まっていないようだが、研究が進むことだろう。われわれや少し上の世代には、ヨハネ23世と並んで身近な名前である。
(ピオ12世)
3 ヨハネ・パウロ2世の保守的な傾向が明らかになるにつれて、キュンクはヨハネ・パウロ2世批判を強めていく。
(ヨハネ・パウロ二世)