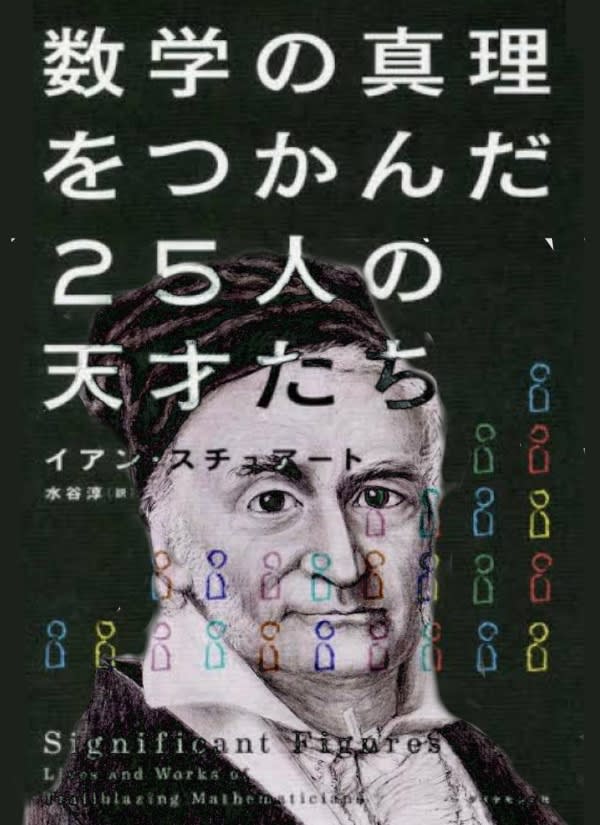
前回の”その2”ではガウスの数論と合同算術、それに平方剰余について述べましたが、やはり代数系はホント難しいですね。書いててチンプンカンプンです。
そこで今日は数学から離れ、ガウスのもう一つの顔である天文学に関する偉業を紹介したいと思います。
前回でも述べたんですが、ガウスは平方剰余相互法則の第一補充法則の発見と同時に、高次冪剰余の理論における基本定理(高次剰余相互法則)の存在を感知し探索を続けます。
その過程で、”数論の舞台を複素数域にまで拡張すべきだ”と認識します。これまた長い探索と格闘の末に、a=a+b√(−1)、但しa、bは有理数、という形のガウス整数域にて、4次剰余の基本定理の発見に成功し、「4次剰余の理論」という2篇の論文を書いた。
第一論文は1828年に、第二論文は1832年に、証明は敢えて記さなかったが、ディリクレやクンマーらの後進の研究を誘い、”類体論”の建設へと続く代数的数論の端緒を開く。
この様に、早くから虚数への偏見から逃れてたガウスは、複素数の領域に深く分け入った。
まず、1797年から始まる楕円関数の最初の研究とレムニスケート関数の発見はとても重要ですね。そして1800年にはとうとう一般楕円関数を発見し、その理論を展開した。
ここで、楕円関数論に関しては次回に回すとして、ガウスの天文学のお話に移ります。
天文学者としてのガウス
一方で、学者の間ではガウスの名声が天を付くほどに高まり、公爵からの支援が近い内になくなる恐れはなくなったが、有給の終身職に就ければもっと将来は確実になる。
その為には一般大衆からも評判が得られればいい。ガウスはそう考えた。
因みに、ガウスは数学がそれほど世の中の役に立つとは考えていなかった。
元々、職業数学者というポストが成立したのは大学制度が出来てからで、それ以前は貴族王侯の名誉を支える一種の芸人として、或いは自然科学や産業上の研究と不可分な形で、または個人の名誉の探求行為としてのみ存在したに過ぎなかった。その為、彼自身は天文学者になる事を願う様になってたのだ。
これも珍しい話だが、ガウスは数学の教授になった事はなく、教師となる事も嫌ったが、弟子のディリクレやリーマンやデデキントが偉大な数学者になった事は誰もが知りうる所ではある。また、ガウスの僚友でユダヤ人初の正教授となったモーリツ•アブラハム•スターンも才能を引き出され、彼らが偉大な数学者となった事を付け加えておく。
1801年、24歳のガウスに天文学を研究するチャンスが訪れた。この年の元旦、天文学者のジュゼッペ•ピアッツィ(伊)が”新惑星”ケレスを発見し、大きな話題を呼んだ。
火星と木星の間を公転する小惑星こそが未知の”新天体”とされていた。
その時の6月にかけて、ガウスの友人であるフランツ•フォン•ツァッハ男爵がケレスの観測結果を何度か発表していた。しかし、ピアッツィはこの新天体を短い区間でしか観察できなかった。ケレスが太陽の陰に隠れると2度と見つけられないのでは?との大きな懸念が広まったのだ。
そこでガウスは、精度の高くない少ない観測結果からケレスの精確な軌道を割り出したのだ。12月、ツァッハ男爵がケレスを再発見すると、その位置はガウスが予測したのとほぼ一致していた。
この偉業により”数学の巨匠”としてのガウスの名声は不動のものになったのだ。
その功績でガウスは、1807年にゲッティンゲン天文台の台長に就任し、以後40年間同職につく。
30歳になったガウスは、測定用機材の開発(ガウス式レンズの設計)や楕円関数の惑星の摂動運動への応用、力学における最小作用の法則の一つ「ガウスの最小拘束の原理」など、数々の発見を成し遂げた。
因みにガウスは1801年、この軌道近似法を自らの「数学日誌」に”天体の軌道に関する簡単で最も新しい方法(近似法)”として記していた。
フェーリクス•クラインはガウスが用いた手法を”最小二乗法”と見て、”ガウスはこの目的の為に自ら創造した応用力の広い近似法を用いた。更に4回目の不完全な観測に基づいて軌道計算を行い、両者で得られた結果を最小二乗法でまとめ上げた。この最小二乗法はこの時点ではまだ発表されてなかったが、ガウスの証言によると1795年に既に自分のものにしていた”と、語っている。
最愛の妻と息子の死を乗り越えて
1809年にガウスは「天体運行論」の中で、”この最小二乗法は、現在の科学ではほぼ全ての分野で観測等の誤差を含むデータから推定値を求める際の計算法として用いらてる。
また、誤差の分布に対してある程度の仮定を設ける事で正規分布が導かれる事や<正規分布に基づき最小二乗法による推定の良さが導かれる>事なども証明した”と記している。
これについては、1805年にルジャンドルが発表していたが、上述の様にガウスはこの理論に1795年には到達してた。
但し、これがルジャンドルとの先取権を巡るいざこざの原因となり、面倒を嫌うガウスの秘密主義を招いたとも言われる。
ガウスは1805年に、ヨハンナ•オスホトフと結婚し、非常に幸せな生活を送ってた。
しかし、1809年に3人目の息子を出産した後に最愛の妻は命を落とし、続いて、産んだばかりの2男のルイスをも失う。
ガウスは悲しみに打ちひしがれたが、数学の研究だけは続けた。それは単に気を紛らわせてただけなのかも知れない。
しかし失意中のガウスは、前述のケレスの研究を拡張し、構成や惑星や衛星の運動を扱う天体力学の一般理論を打ち立てた。
そして、1809年に前述の「円錐曲線に従う天体公転運動の理論」(=「天体運行論」)を出版した。
リーマンと同じで、苦境に立った時のガウスの躍動は狂気にも似たものがありますね。
ガウスは、最愛のヨハンナの死から1年もせずに、親友のフリーデリカ•ヴァルデミック(愛称ミンナ)と再婚。しかし、この結婚から得られた幸せは希薄だった様で、ガウスはヨハンナの面影が忘れられず、再婚相手のミンナにもその事を告げる始末だった。そのミンナも1831年に長い病気の末に他界し、その後は娘のテレーズが身の回りの世話をした。
因みに、ガウスの子供は2人の妻に3人ずつ、計6人。ヨハンナとの間の子供は、ヨゼフ(1806−1873)、ヴィルヘルミーナ(1808−1846)、ルイス(1809−1810)。
中でもヴィルヘルミーナの才能はガウスに近かったとされるが、残念ながら若くして亡くなった。一方でミンナとの間の子供は、オイゲネ(1811−1896)、ヴィルヘルム(1813−1879)、テレーズ(1816−1864)。
オイゲネとヴィルヘルムはアメリカへ移住しますが、ヴィルヘルムは靴のビジネスで成功を収めます。
追記〜最小二乗法とは?
ここで共分散を変数xの分散で割り、回帰直線の傾きa=y/xを得る。故に、2変数x,yの平均値X,Yと傾きaから回帰直線のy切片bを得て、回帰直線を導くが、b=Y−aXという公式を使う。
これを関数で表せば、回帰直線をy=ax+bとすると、a=∑ᵢ(1,n)(xᵢ−X)(yᵢ−Y)/∑ᵢ(1,n)(xᵢ−X)²となる。
少し短いですが、今日はここまでです。次回の”その4”では、人生後半のガウスの躍動と幅広い研究について紹介します。










そこでガウスはシューマッハーにアーベルの死を悼む手紙を返信します。
”お手紙によってアーベルの逝去を知りました。実に学問会の一大損失であります。この異常なる英才の経歴に関して何か書いたものが御手に入りましたならば早速御知らせください。もしも肖像があるならば見たいものです”「近世数学史談」
1829年5月の事ですから、ガウスが52歳の時、再婚の妻が他界する2年前の事です。
ガウスしか知る余地のない意味の深い言葉です。
やはりガウスはアーベルの偉大さを見抜いてたんですね。一つ一つの言葉が非常に重いです。
そのガウスも順風満帆という生涯でもなく、結構苦労してんですね。当時は医療技術が遅れてたから、病気すると簡単に死んだ時代です。そんな時代に稀有の天才が数多く生まれたのも皮肉ですね。
貴重なコメント有難うです。
n=2の時は平方剰余(2次の冪剰余)ですが、若い時からガウスは4次の相互法則を確信し苦心を重ねます。
a+bi(ガウス整数)という複素数の数域に移る時、十全な形の4次剰余相互法則が見つかるとガウスは洞察しました。
4次剰余相互法則は虚数を導入して初めて理解できる数学的現象で虚数の実在感の強力な支えです。
つまりガウス整数とは複素数を一般的な視点から捉えようとする試みと4次剰余相互法則を理解する為の工夫でもありました。
ガウスは彼自身の特異な視点と一般的な視点とを交互に比較しながら理論を進めていったんでしょうか。我ら凡人には理解できそうにもない。
ガウスの数論が複素数を基盤にしてた事はリーマンの学士論文にも強く引き継がれてますね。
一見冷たいように見えるガウスも中身は情熱の塊だったんです。
貴重なコメント有難うです。
一般にその近似関数をf(x)とすると、∑(i=1,n){yi−f(x)}²が最小となる様なf(x)を求める事です。
例えば、近似関数を回帰直線(2変数の一次直線)とする場合、最小二乗法による回帰直線の求め方は、先ずデータ(変数)の平均値を求め、変数の偏差(数値-平均値)を求めます。次に変数xの分散(偏差の2乗平均)を求め、共分散(偏差の積の平均)を求め、共分散を変数xの分散で割り、回帰直線の傾きa=y/xを得ます。故に、2変数x,yの平均X,Yと傾きaから回帰直線のy切片bを得るんですが。b=Y−aXという公式を使います。
つまりデータの平均値⇒偏差⇒分散⇒共分散⇒回帰直線の傾きと切片という流れですが、誤差の二乗の和が最小になるとは偏差⇒分散⇒共分散の流れから来てるのですかね。
受験に必須な偏差値の概念もガウスが起源になったんですね。
貴重な補足どうも有難うです。
一昨年インドの旅で、ゼロの発見は
彼の地で為された事を初めて知った
この程度の自分は永遠の0かも
それにしても、コロナ感染は
等比級数的拡大の兆しを見せてる
ゼロの定義を明確に確立するまでに千年以上掛かったらしいです。
まさに永遠のゼロですね。