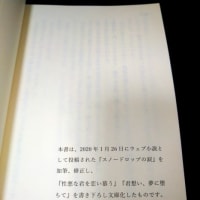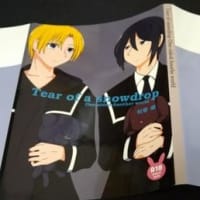1
「白音」
ベッドに横たわる黒髪の少女の名を呼ぶ琥珀の黒い髪と瞳は、今にも部屋の隅の影に消えそうな雰囲気を醸し出していた。
「パパ。だいじょうぶ?」
「ん? 別に、俺は元気だぞ」
「シオンね、パパのことだいすきだよ…おやすみのぎゅーってして」
「…俺も、好きだよ。おやすみ白音」
そう言って琥珀は、歩み寄り抱くと部屋を後にした。抱かれた時の暖かさと廊下の光に照らされ、はっきりと彼の姿を見て白音は、安心し布団にもぐりゆっくりと眠りに落ちていった。
白音の部屋を後にし、琥珀は、寝室に向かう。
「白音は? 寝たのか?」
少しして、友人のサンが部屋を訪れた。
「…寝たよ。それよりノックもせずに入るなと言っただろう」
カーテンが閉め切られ明りもない部屋は暗闇そのもので、正直なところサンは、部屋の雰囲気が苦手だった。「暗すぎて目が悪くなる」そう言ってみるが、彼の過去を考えるとそれ以上何も言えないでいた。琥珀の過去、それは五年前、白音の命が生れ落ちそれと入れ替わるように最愛の妻、緋音の命の灯が消えた日の事だ。琥珀は、彼女の強さに惚れ、精神的支柱であった緋音が死ぬなど考えてもいなかった。それからしばらく琥珀は、まるで彼も死んだかのような目で白音の育児をしていた。ふらふらと動く姿は、まるで歩く死人の様だった。
白音の為にも良くない状況だと判断したサンは、「必要ない」と拒否をする琥珀の感情を押しのけ、勝手に手伝いをするようになっていた。
はじめの数年は、実家とラングレン家を行き来していたが、気が付くと私物はこちらに置かれ、空き部屋に住み着くようになった。白音がサンを気に入って歓迎していたのと、琥珀自身、言わなかったがサンの手助けに感謝し頼りにしていたところもあり、小言を口にしながらも追い出しはしなかった。
「俺も、もう寝るわ」
「そうか…おやすみ」
「おやすみ」
ふと、サンは琥珀が袖で目のあたりを拭うのを見た気がした。
「…」
「…なんだ? さっさと閉めて部屋に戻ったらどうだ」
「あ、ああ」
泣いていた?
実のところ、緋音が死んだ時、それ以降も琥珀が泣いている姿を見たことが無かった。悲しんでいないわけでは無い。昔から一度も泣かず、涙腺はあるのか? と思う事もあった。泣く方法、それは生理現象で自然にできる事、だが琥珀にはそれが出来ないのだと考えていた。
しかし、そうでもなかったようだ。
(あいつも…泣くんだな)
サンは、しみじみ思いながら自室に向かい、乱雑なベッドに身を落とし眠りについた。
2
「…いてっ」
翌日、サンは整備中に気が緩み、機械に腕を引っ掻けてしまい、傷を負った。かなり深く切ったようで、ポタポタと血のしずくを床に流している。
「あぁ、盛大にやったねぇ…。医務室行ってきなよ」
サンの上司である第四武装団の団長、梨羽依織は、見慣れた光景だと特に驚くこともなく、へらへら笑いながらサンに手を振った。抜けているわけでは無いが、サンはどうにも注意力が散漫になる時がよくあった。それで、怪我をすることが日常になっていた。つい琥珀の顔を思い浮かべ、タオルで腕を抑えながら医務塔には向かわず、第一武装団歩兵隊舎に足を進めた。なんとなく今日は琥珀に治療してもらいたい気分だった。
昨日、夜に見た琥珀が気になっていたのもある。なぜか分からないが、あの表情を思い出すと胃か鳩尾の当たりに押さえつけられるような重みを感じた。隊舎に到着すると若い女が、血の滲むタオルを見て驚いた様子でサンに駆け寄ってきた。サンは、「大丈夫」そう言い、団長室に行き、ノックをした。
「はい」
「よう…」
いるはずのないサンがここにいる。怪訝そうな顔で彼に目を向け、腕を抑えていることに気が付き大きくため息を吐いた。
「…またか? いい加減お前は、まぁいい…それより何故ここにいる?」
「なんとなく、お前の顔が見たかったんだよ」
「その為に怪我したのか? 馬鹿か?」
「いや、怪我は別にたまたまだ」
呆れた、言葉にはしないが目はそう言う。琥珀は、サンを窓際にあるソファーに座らせタオルを受け取る。ずいぶんと深い傷だった。
傷に右手を翳す。魔力の影響なのか暖かく感じ、その後元の形に戻るように傷口が閉じていった。ものの数分で治療は終わった。琥珀だからこのスピードで治すことが出来るのだ。しかし、傷は治るが、痛みは消えることがないので、見た目と感覚の違和感にいつも悩まされていた。
「終わった」
「ありがとうな…しかし、痛いのはどうにかなんねぇかな」
「だったら簡単だ。怪我をしなければいい」
それはそうだ、サンは笑いながらタオルを受け取る。立ち上がろうと思ったが、サンはその場で琥珀を見つめた。
「なんだ?」
「いや、お前昨日どうしたんだ?」
琥珀は、分かりやすく眉間に皺を寄せ不機嫌そうな表情をし、なんのことだ? と誤魔化す。泣いていただろう、サンは間髪入れずに言った。
「お前が泣くなんて思ってなかったから、心配で」
「忘れろ。俺は泣いてなんかいない」
「琥珀…別に泣くのは、悪いことじゃないだろ」
「煩い」
それ以上何も言うなと琥珀の目が鋭く睨みつける。普通彼にそんな目を向けられれば、恐怖を覚えるのだろうが、サンは苛立ちを覚える。
無意識に、琥珀の腕を掴みそのまま壁に押さえつけていた。先に仕掛けたのはサンの方なので半ば逆ギレ状態に思われた。
「おい! っ」
「別に強がることないだろ」
「強がっているわけではない…俺は、白音を守らなきゃいけないんだ。だから、泣かない。弱さは俺に必要ない」
「強がりだろ」
「お前に何がわかる?」
琥珀は息を荒げ押さえつけられていた腕に力を入れ、押し返そうとする。そうはさせまいとサンは更に力を入れた。戦闘力で言えば琥珀に軍配が上がる。純粋な力だけで言えばサンはいつの間にか琥珀を超えていた。
「そうだな…俺は、愛した人間を失ったことなんてないからな、お前の気持ちなんか一生分からねぇよ」
愛した。琥珀はその言葉を呟き、視線を落とす。そしてほんの一瞬だけ体の力を緩めた(と言うより抜けたに近かった)。か細く「だったら口を挟むな」と口にしながら、睨むように顔を上げた琥珀の瞳は、今にも目尻から零れそうなほどの涙が滲んでいた。まただ、サンは胃、みぞおち辺りに重く、締め付けるような違和感を覚え、琥珀の見たこともない表情に、思わず体を抱き寄せた。
「なっ、なにをしている…っ」
「弱いとか、そんな風に思わないから、辛いなら泣け。一人で抱えるなよ」
「これは、俺の問題でお前には関係ない。…離せ、暑苦しい。心配してくれなくて結構だ。早く仕事に戻れ」
「緋音は、お前を愛してた。今でもお前の事を愛してる」
琥珀は、サンの体を押し退け、後ろに下がった。
「俺も、緋音を…愛していた。…愛している…今でも…分かるか? こんなに…こんなにも、彼女を思って…ても…もう、届かない…緋音は、緋音が居ないんだ……っ」
そう言って立ち尽くす、琥珀の苦痛に歪んだ顔に、ついに零れた涙が頬に流れる。悪い事をした。サンは、ようやく諦めたようで、謝りタオルを差し出す。「血塗れのタオルなんかいらない」と琥珀は、受け取らず袖で涙を拭う。それはそうだろう、サンはタオルを畳んで手に収める。
「今あったことは忘れろ」
琥珀のいつになく感情的な声に、返答できず、気まずい沈黙が二人の間に生まれた。すぐにそれを破ったのは、ノック音だった。
「はい」
琥珀が返事をすると、部下の男が申し訳なさそうに顔を見せる。どうやら、追加の書類仕事を持ってきたようで、このままでは、業務時間内に終わらない。だから申し訳なさそうに入ってきたのか。琥珀自身、残業は問題なかったが白音の迎えに行く時間へ間に合わないという問題があった。仕事量を見るに一時間程度の残業で済みそうと判断し、託児施設に延長の連絡を入れてほしいと部下に頼む。
「俺が迎えに行ってやるよ」
「…まぁ、待たせるよりもその方がいいだろう。という事だ、サンが迎えに行くと伝えておいてほしい」
「了解しました」
部下が一礼し、部屋を去り、サンも続いて出ていった。廊下に出ると部下の青年が、サンに「団長の怒っている顔を、初めて見ましたよ」と。どうやら、琥珀の声(内容は聞こえていなかった)が、外まで聞こえていたようで、部屋に入りづらかったと青年は言う。
「覚悟決めて入ってみたら、もう…一瞬、あんな寒気のする目…よく平気ですね」
「そうか、あいつ怒っていたんだな」
「どう考えても怒ってましたよ…でも、俺、奥さんを亡くす前の団長を知らなかったから、ちゃんと感情があるのかって思って」
「はは、一応アイツも人間だからな。昔は笑っていた時もあったけどな」
「そうなのですね…とりあえず、団長は怒らせないようにしてくださいよ」
「別に怒らせたくて怒らせたわけじゃないんだけどな…」
ため息交じりに、サンは言う。青年は、疑うように笑って二人は別れた。
「忘れろ…って言われてもなぁ。はぁ、休憩してから戻るか…」
今の今まで休憩していたようなものだというのに、休憩所に向かって足を進めた。
3
「サン!」
「よう、白音、いい子にしていたか?」
「うん!」
軍の敷地からそれほど遠くない位置にある託児所で、黒い髪を左右で束ねた少女が、サンの姿を見るや否や、駆け出し彼の足にしがみついて、笑顔で出迎えた。
仕事を終えすぐに迎えに来たが、結局最後だったようで、教室の奥から、赤い髪を揺らし施設長のバルバラ・ルベルが、姿を見せた。
「お兄さんが迎えに来てくれたようだな」
赤い瞳に笑みを浮かべ嫌味のようにお兄さんと口にする。それを彼は、鼻で笑って返す。
仲が悪いわけでは無い。むしろ、サンは、彼女に恋心を抱いていた時期もあった。いや、今でもそうなのかもしれない。一方のバルバラも彼に好意を持っていたが、結局二人の思いが通じることはなかった。
お互いがお互いに抱えている秘密や思いが大きな壁になり、直属ではなかったが、上司と部下(バルバラは、元々第三騎士団医療班の団長をしていた)、もしくは、友人。今ではこの関係のままでよかったのではないか? と考えるまでだ。周りの状況が変わり困難に苛まれている者達を見ると、変わらない、それが心地よかったのだ。
ふと、サンは白音が身軽な事に気が付いた。
「白音。荷物は?」
「あ、わすれてた! ちょっとまってて!」
パタパタと靴を鳴らし教室に戻って、壁に並んだ棚からリュックを引っ張り出す白音を見る。「また白音が最後だな」サンの問いかけに、バルバラはそうだなと同意の言葉を返した。
「お前も琥珀も忙しいのだから仕方がないだろう」
「そうだけどな…」確かに二人とも、立場上(サンも一応部隊長を任されていた)、どうしても人より仕事量が多くなり、遅くまで帰ることが出来ないでいた。一応、白音の事もあるので事前に分かっていれば、サンが迎えに行くなどして都合を合わせて時間を延ばしてもらいつつ預けていた。バルバラは、そういった軍人の為にも、と退役後、軍地区近くに施設を建てたので、使い方としては正しいのだと思っているが、サンも同じように考えているのだろう、最後まで一人残される子供の気持ちはどうなのだ? と。しかし、二人の悩みなど杞憂に感じる程、彼女は明るかった。走って戻ってきた白音は、笑顔でリュックを突き出す。
「リュックあった」
白音は、リュックを背負おうとしたとこで、急に荷物を落とし、外の門へ走り出した。「白音!」突然のことに驚きサンとバルバラは、慌てて白音の向かった先を見るとそこには、いるはずのない人影があった。
「パパだ!」飛び掛かるように琥珀へ抱きつく。
「間に合ってよかった」
「お仕事、もうおわったの?」
琥珀は頷くと両手を広げ「だっこ」と甘える白音を抱きかかえた。白音に捨てられたウサギのリュックを片手に、サンが二人の前に向かい呆れた顔で「白音、荷物を捨てるな」と。当の白音は、怒られているにも関わらず、幸せそうに笑う。
「ウサギさん!」
「サンにありがとうって言わないとダメだろ」
「ありがとう!」
琥珀の腕の中でお辞儀をする白音の頭を撫でる。
「なんだ? 残業せずにすんだのか?」
「ああ、終わらせてきた」
白音は、満足したのか「降ろして」と。そっと降ろし、彼女はリュックを背負い直し、琥珀とサンの間で二人の手を握る。
「じゃあ、帰ろう。白音、先生にさようならしなさい」
「バイバイせんせー、また明日!」両手を上げて手を振る(繋いでいるので必然的に琥珀とサンも手を振ることになった)と、先導するように二人の手を引いて立ち去った。バルバラは、そんな三人の背を微笑ましく見送った。
白音は、来ないと思っていた琥珀が迎えに来たことが嬉しかったようで、ラジオの子供向け番組で流れる軽快な曲を口ずさみながら、跳ねるように歩いていた。そんな白音を間に、二人は昼の事を気にしているのか、どことなく気まずい空気が流れていた。誤魔化すように「施設は楽しいか?」と、サンは白音に問いかける。
悩む事無く白音は楽しいと答えた。そしてまた白音の歌う声だけが道に響く。
「…」
「…」
「パパとサンはケンカしてるの?」
謎の沈黙を悟ったのか白音はそういった。別に喧嘩はしていない。二人の声が重なる。お互いの声に驚き二人はお互いの顔を見合う。
「そっか! よかった!」
白音に気を遣わせていたことに気が付き、恥ずかしさを覚えた。琥珀は、白音を見る。「晩御飯、何が食べたい?」「シオンが決めていいの?」偏らないよう月に二日だけ、白音が食べたいモノを決めていい、というルールがあった。今日はその日ではなかったが、琥珀の気まぐれではなく、気を遣わせた事へ謝罪の意味で、特別にと彼は言った。
「やったー、うーん…どうしようかなぁ?」
ぴょんぴょんと、跳ねる白音に合わせてリュックに飾りでついていたウサギの耳が彼女の肩に当たる。
「あ、ウサギさん!」
「え?」
「ウサギさんが食べたいです!」
琥珀は一瞬固まる。サンがどうかしたのか?と覗き込むとはっとしてから、ああ、と頷いた。
きっと緋音と重ねていたのだろうとサンは思う。
緋音と白音は瞳の色だけでなく、行動が似ていた。気になるものを見つけると一目散に駆け出してしまい、機嫌がいいと歌を口ずさみ、食べたいものを聞かれると必ずウサギの肉と言う。
忘れたくても、白音をみるとイヤでも彼女を思い出してしまうのだろう。しかし別の視点で見るに、そっくりなおかげで彼は、白音の父親で居られるのだろう、と。緋音の事だけを思う。今に始まったことではない。サンは複雑な心境に顔を歪める。
「食材はあるから買い物の必要はないか」琥珀が晩御飯について考えていると、白音が彼の腕をぐっと引く。なんだ? と目を向ける。
「…ねぇねぇ、パパ?」
白音は、真剣な顔を琥珀に向けた。
「ママに会いに行きたい」
4
「白音、走るなよ」
サンの言葉に、はーい、と元気に手を上げて駆け足をやめ白音が歩く。街はずれの静かな墓地に三人はいた。夏が過ぎようとしていたが、それにしてもここはいつも肌寒く感じる。カラスの鳴く声が、夕日に照らされた空を響く。
琥珀とサンは、黙って白音の背中を見ながら並んで歩いていた。
足を止めた白音が、二人に向かって「早く来て!」そう声を上げる。
彼女の前には、緋音・ラングレンの文字と五年前、白音の誕生日と同じ日付が掘られた綺麗な墓石があった。他の墓石に比べて汚れも目立たず、供えられた綺麗な花は、つい最近のモノだと見受けられた。
琥珀が定期的に来ては掃除をしていたからだ。三日に一度。出来れば毎日ここに会いに来たいと、琥珀は思っているのだろう。実際彼女が死んで二年ほどは、毎日彼の姿がここにあった。休日は何時間も立っていたのを管理人が見ていたようで、心配して声をかけた。丁度そのころ、歩くようになった白音と遊ぶ時間を作れ、そうサンに注意されたこともあって彼がここに姿を見せるのは、それ以来、三日に一度、になった。
「ママ」
「白音、手を」
琥珀は、白音の横に並ぶと、静かに手を合わせる。白音とサンも同じように手を合わせた。
「シオンもパパもサンもみんなげんきです…」
小さく最近の出来事を報告するように呟く。一通り話し終えた白音は、満足そうに目を開ける。が、隣に並ぶ琥珀とサンは未だに手を合わせていた。琥珀が長い間、こうして手を合わせていることはよくあったが、サンまで、珍しい。白音は、大人しく二人が目を開けるのを待っていたが一向に辞める気配がなく、サンのズボンの裾を引いた。
「ん?…ああ、白音?」
「ママとお話おわった?」
「…ああ、終わったよ」
そういったサンの顔に何処か寂しそうな雰囲気を感じた白音はそっと足に抱き着いた。琥珀が目を開けると白音がサンの足に抱きついている奇妙な光景を目の当たりにし「白音、なにをしているんだ? 」と聞くも、琥珀の声に白音は、「なんでもないよ」しがみついたままでくぐもった声がそう返した。
何をしたんだ?とサンを見るが、彼にも理由は分からないようで。さぁと肩を竦めて見せた。
「暗くなる前に帰ろう」
「うん…」
琥珀の手を取り(本当は先ほどのように二人の手を取り間に居たかったが通路が狭く叶わなかった)墓地を後にしようと歩き始める。白音の足取りがふわふわしていることに気付き琥珀が、彼女の顔を見ると、目がボーとして、そして空いている手で瞼を擦っていた。
「白音、眠たいのか?」
「ううん…だいじょうぶ…」
大丈夫には聞こえない。琥珀は、手を離すと白音を抱き抱えた。
「パパ?」
寝てなさい、彼の言葉に白音は、素直に頷くと体を預け小さく寝息を立て始めた。
カラスの鳴く声はいつの間にか消えていた。
墓地の門で、サンは足を止めた。
「なんだ?」
「悪い、俺ちょっと春のところ行くわ」
「それは構わないが、晩御飯は?」
「いい」
春。その名前を聞いて寝言のように白音が「ハルくんのところ…シオンも…行きたい」と呟く。「また今度連れて行ってやるから」サンは、そっと白音の頭を撫でる。
「多分日が変わる前には帰るけど」
「気を付けて」
「ん。白音、おやすみ」
「おや、すみなさ…」
睡魔に負け、言い終える前に白音は眠りについた。ついさっきまで元気にはしゃいでいたと言うのに、サンは、もう一度彼女の頭を撫でると、ゆっくり足を街の方へ向けた。琥珀は、心做しか気落ちして見えるサンの姿を、怪訝そうに見つめ見送る。夕日は半分以上落ちた夜の時間。暗くなった墓地を後に、琥珀は白音と家路についた。
「白音」
ベッドに横たわる黒髪の少女の名を呼ぶ琥珀の黒い髪と瞳は、今にも部屋の隅の影に消えそうな雰囲気を醸し出していた。
「パパ。だいじょうぶ?」
「ん? 別に、俺は元気だぞ」
「シオンね、パパのことだいすきだよ…おやすみのぎゅーってして」
「…俺も、好きだよ。おやすみ白音」
そう言って琥珀は、歩み寄り抱くと部屋を後にした。抱かれた時の暖かさと廊下の光に照らされ、はっきりと彼の姿を見て白音は、安心し布団にもぐりゆっくりと眠りに落ちていった。
白音の部屋を後にし、琥珀は、寝室に向かう。
「白音は? 寝たのか?」
少しして、友人のサンが部屋を訪れた。
「…寝たよ。それよりノックもせずに入るなと言っただろう」
カーテンが閉め切られ明りもない部屋は暗闇そのもので、正直なところサンは、部屋の雰囲気が苦手だった。「暗すぎて目が悪くなる」そう言ってみるが、彼の過去を考えるとそれ以上何も言えないでいた。琥珀の過去、それは五年前、白音の命が生れ落ちそれと入れ替わるように最愛の妻、緋音の命の灯が消えた日の事だ。琥珀は、彼女の強さに惚れ、精神的支柱であった緋音が死ぬなど考えてもいなかった。それからしばらく琥珀は、まるで彼も死んだかのような目で白音の育児をしていた。ふらふらと動く姿は、まるで歩く死人の様だった。
白音の為にも良くない状況だと判断したサンは、「必要ない」と拒否をする琥珀の感情を押しのけ、勝手に手伝いをするようになっていた。
はじめの数年は、実家とラングレン家を行き来していたが、気が付くと私物はこちらに置かれ、空き部屋に住み着くようになった。白音がサンを気に入って歓迎していたのと、琥珀自身、言わなかったがサンの手助けに感謝し頼りにしていたところもあり、小言を口にしながらも追い出しはしなかった。
「俺も、もう寝るわ」
「そうか…おやすみ」
「おやすみ」
ふと、サンは琥珀が袖で目のあたりを拭うのを見た気がした。
「…」
「…なんだ? さっさと閉めて部屋に戻ったらどうだ」
「あ、ああ」
泣いていた?
実のところ、緋音が死んだ時、それ以降も琥珀が泣いている姿を見たことが無かった。悲しんでいないわけでは無い。昔から一度も泣かず、涙腺はあるのか? と思う事もあった。泣く方法、それは生理現象で自然にできる事、だが琥珀にはそれが出来ないのだと考えていた。
しかし、そうでもなかったようだ。
(あいつも…泣くんだな)
サンは、しみじみ思いながら自室に向かい、乱雑なベッドに身を落とし眠りについた。
2
「…いてっ」
翌日、サンは整備中に気が緩み、機械に腕を引っ掻けてしまい、傷を負った。かなり深く切ったようで、ポタポタと血のしずくを床に流している。
「あぁ、盛大にやったねぇ…。医務室行ってきなよ」
サンの上司である第四武装団の団長、梨羽依織は、見慣れた光景だと特に驚くこともなく、へらへら笑いながらサンに手を振った。抜けているわけでは無いが、サンはどうにも注意力が散漫になる時がよくあった。それで、怪我をすることが日常になっていた。つい琥珀の顔を思い浮かべ、タオルで腕を抑えながら医務塔には向かわず、第一武装団歩兵隊舎に足を進めた。なんとなく今日は琥珀に治療してもらいたい気分だった。
昨日、夜に見た琥珀が気になっていたのもある。なぜか分からないが、あの表情を思い出すと胃か鳩尾の当たりに押さえつけられるような重みを感じた。隊舎に到着すると若い女が、血の滲むタオルを見て驚いた様子でサンに駆け寄ってきた。サンは、「大丈夫」そう言い、団長室に行き、ノックをした。
「はい」
「よう…」
いるはずのないサンがここにいる。怪訝そうな顔で彼に目を向け、腕を抑えていることに気が付き大きくため息を吐いた。
「…またか? いい加減お前は、まぁいい…それより何故ここにいる?」
「なんとなく、お前の顔が見たかったんだよ」
「その為に怪我したのか? 馬鹿か?」
「いや、怪我は別にたまたまだ」
呆れた、言葉にはしないが目はそう言う。琥珀は、サンを窓際にあるソファーに座らせタオルを受け取る。ずいぶんと深い傷だった。
傷に右手を翳す。魔力の影響なのか暖かく感じ、その後元の形に戻るように傷口が閉じていった。ものの数分で治療は終わった。琥珀だからこのスピードで治すことが出来るのだ。しかし、傷は治るが、痛みは消えることがないので、見た目と感覚の違和感にいつも悩まされていた。
「終わった」
「ありがとうな…しかし、痛いのはどうにかなんねぇかな」
「だったら簡単だ。怪我をしなければいい」
それはそうだ、サンは笑いながらタオルを受け取る。立ち上がろうと思ったが、サンはその場で琥珀を見つめた。
「なんだ?」
「いや、お前昨日どうしたんだ?」
琥珀は、分かりやすく眉間に皺を寄せ不機嫌そうな表情をし、なんのことだ? と誤魔化す。泣いていただろう、サンは間髪入れずに言った。
「お前が泣くなんて思ってなかったから、心配で」
「忘れろ。俺は泣いてなんかいない」
「琥珀…別に泣くのは、悪いことじゃないだろ」
「煩い」
それ以上何も言うなと琥珀の目が鋭く睨みつける。普通彼にそんな目を向けられれば、恐怖を覚えるのだろうが、サンは苛立ちを覚える。
無意識に、琥珀の腕を掴みそのまま壁に押さえつけていた。先に仕掛けたのはサンの方なので半ば逆ギレ状態に思われた。
「おい! っ」
「別に強がることないだろ」
「強がっているわけではない…俺は、白音を守らなきゃいけないんだ。だから、泣かない。弱さは俺に必要ない」
「強がりだろ」
「お前に何がわかる?」
琥珀は息を荒げ押さえつけられていた腕に力を入れ、押し返そうとする。そうはさせまいとサンは更に力を入れた。戦闘力で言えば琥珀に軍配が上がる。純粋な力だけで言えばサンはいつの間にか琥珀を超えていた。
「そうだな…俺は、愛した人間を失ったことなんてないからな、お前の気持ちなんか一生分からねぇよ」
愛した。琥珀はその言葉を呟き、視線を落とす。そしてほんの一瞬だけ体の力を緩めた(と言うより抜けたに近かった)。か細く「だったら口を挟むな」と口にしながら、睨むように顔を上げた琥珀の瞳は、今にも目尻から零れそうなほどの涙が滲んでいた。まただ、サンは胃、みぞおち辺りに重く、締め付けるような違和感を覚え、琥珀の見たこともない表情に、思わず体を抱き寄せた。
「なっ、なにをしている…っ」
「弱いとか、そんな風に思わないから、辛いなら泣け。一人で抱えるなよ」
「これは、俺の問題でお前には関係ない。…離せ、暑苦しい。心配してくれなくて結構だ。早く仕事に戻れ」
「緋音は、お前を愛してた。今でもお前の事を愛してる」
琥珀は、サンの体を押し退け、後ろに下がった。
「俺も、緋音を…愛していた。…愛している…今でも…分かるか? こんなに…こんなにも、彼女を思って…ても…もう、届かない…緋音は、緋音が居ないんだ……っ」
そう言って立ち尽くす、琥珀の苦痛に歪んだ顔に、ついに零れた涙が頬に流れる。悪い事をした。サンは、ようやく諦めたようで、謝りタオルを差し出す。「血塗れのタオルなんかいらない」と琥珀は、受け取らず袖で涙を拭う。それはそうだろう、サンはタオルを畳んで手に収める。
「今あったことは忘れろ」
琥珀のいつになく感情的な声に、返答できず、気まずい沈黙が二人の間に生まれた。すぐにそれを破ったのは、ノック音だった。
「はい」
琥珀が返事をすると、部下の男が申し訳なさそうに顔を見せる。どうやら、追加の書類仕事を持ってきたようで、このままでは、業務時間内に終わらない。だから申し訳なさそうに入ってきたのか。琥珀自身、残業は問題なかったが白音の迎えに行く時間へ間に合わないという問題があった。仕事量を見るに一時間程度の残業で済みそうと判断し、託児施設に延長の連絡を入れてほしいと部下に頼む。
「俺が迎えに行ってやるよ」
「…まぁ、待たせるよりもその方がいいだろう。という事だ、サンが迎えに行くと伝えておいてほしい」
「了解しました」
部下が一礼し、部屋を去り、サンも続いて出ていった。廊下に出ると部下の青年が、サンに「団長の怒っている顔を、初めて見ましたよ」と。どうやら、琥珀の声(内容は聞こえていなかった)が、外まで聞こえていたようで、部屋に入りづらかったと青年は言う。
「覚悟決めて入ってみたら、もう…一瞬、あんな寒気のする目…よく平気ですね」
「そうか、あいつ怒っていたんだな」
「どう考えても怒ってましたよ…でも、俺、奥さんを亡くす前の団長を知らなかったから、ちゃんと感情があるのかって思って」
「はは、一応アイツも人間だからな。昔は笑っていた時もあったけどな」
「そうなのですね…とりあえず、団長は怒らせないようにしてくださいよ」
「別に怒らせたくて怒らせたわけじゃないんだけどな…」
ため息交じりに、サンは言う。青年は、疑うように笑って二人は別れた。
「忘れろ…って言われてもなぁ。はぁ、休憩してから戻るか…」
今の今まで休憩していたようなものだというのに、休憩所に向かって足を進めた。
3
「サン!」
「よう、白音、いい子にしていたか?」
「うん!」
軍の敷地からそれほど遠くない位置にある託児所で、黒い髪を左右で束ねた少女が、サンの姿を見るや否や、駆け出し彼の足にしがみついて、笑顔で出迎えた。
仕事を終えすぐに迎えに来たが、結局最後だったようで、教室の奥から、赤い髪を揺らし施設長のバルバラ・ルベルが、姿を見せた。
「お兄さんが迎えに来てくれたようだな」
赤い瞳に笑みを浮かべ嫌味のようにお兄さんと口にする。それを彼は、鼻で笑って返す。
仲が悪いわけでは無い。むしろ、サンは、彼女に恋心を抱いていた時期もあった。いや、今でもそうなのかもしれない。一方のバルバラも彼に好意を持っていたが、結局二人の思いが通じることはなかった。
お互いがお互いに抱えている秘密や思いが大きな壁になり、直属ではなかったが、上司と部下(バルバラは、元々第三騎士団医療班の団長をしていた)、もしくは、友人。今ではこの関係のままでよかったのではないか? と考えるまでだ。周りの状況が変わり困難に苛まれている者達を見ると、変わらない、それが心地よかったのだ。
ふと、サンは白音が身軽な事に気が付いた。
「白音。荷物は?」
「あ、わすれてた! ちょっとまってて!」
パタパタと靴を鳴らし教室に戻って、壁に並んだ棚からリュックを引っ張り出す白音を見る。「また白音が最後だな」サンの問いかけに、バルバラはそうだなと同意の言葉を返した。
「お前も琥珀も忙しいのだから仕方がないだろう」
「そうだけどな…」確かに二人とも、立場上(サンも一応部隊長を任されていた)、どうしても人より仕事量が多くなり、遅くまで帰ることが出来ないでいた。一応、白音の事もあるので事前に分かっていれば、サンが迎えに行くなどして都合を合わせて時間を延ばしてもらいつつ預けていた。バルバラは、そういった軍人の為にも、と退役後、軍地区近くに施設を建てたので、使い方としては正しいのだと思っているが、サンも同じように考えているのだろう、最後まで一人残される子供の気持ちはどうなのだ? と。しかし、二人の悩みなど杞憂に感じる程、彼女は明るかった。走って戻ってきた白音は、笑顔でリュックを突き出す。
「リュックあった」
白音は、リュックを背負おうとしたとこで、急に荷物を落とし、外の門へ走り出した。「白音!」突然のことに驚きサンとバルバラは、慌てて白音の向かった先を見るとそこには、いるはずのない人影があった。
「パパだ!」飛び掛かるように琥珀へ抱きつく。
「間に合ってよかった」
「お仕事、もうおわったの?」
琥珀は頷くと両手を広げ「だっこ」と甘える白音を抱きかかえた。白音に捨てられたウサギのリュックを片手に、サンが二人の前に向かい呆れた顔で「白音、荷物を捨てるな」と。当の白音は、怒られているにも関わらず、幸せそうに笑う。
「ウサギさん!」
「サンにありがとうって言わないとダメだろ」
「ありがとう!」
琥珀の腕の中でお辞儀をする白音の頭を撫でる。
「なんだ? 残業せずにすんだのか?」
「ああ、終わらせてきた」
白音は、満足したのか「降ろして」と。そっと降ろし、彼女はリュックを背負い直し、琥珀とサンの間で二人の手を握る。
「じゃあ、帰ろう。白音、先生にさようならしなさい」
「バイバイせんせー、また明日!」両手を上げて手を振る(繋いでいるので必然的に琥珀とサンも手を振ることになった)と、先導するように二人の手を引いて立ち去った。バルバラは、そんな三人の背を微笑ましく見送った。
白音は、来ないと思っていた琥珀が迎えに来たことが嬉しかったようで、ラジオの子供向け番組で流れる軽快な曲を口ずさみながら、跳ねるように歩いていた。そんな白音を間に、二人は昼の事を気にしているのか、どことなく気まずい空気が流れていた。誤魔化すように「施設は楽しいか?」と、サンは白音に問いかける。
悩む事無く白音は楽しいと答えた。そしてまた白音の歌う声だけが道に響く。
「…」
「…」
「パパとサンはケンカしてるの?」
謎の沈黙を悟ったのか白音はそういった。別に喧嘩はしていない。二人の声が重なる。お互いの声に驚き二人はお互いの顔を見合う。
「そっか! よかった!」
白音に気を遣わせていたことに気が付き、恥ずかしさを覚えた。琥珀は、白音を見る。「晩御飯、何が食べたい?」「シオンが決めていいの?」偏らないよう月に二日だけ、白音が食べたいモノを決めていい、というルールがあった。今日はその日ではなかったが、琥珀の気まぐれではなく、気を遣わせた事へ謝罪の意味で、特別にと彼は言った。
「やったー、うーん…どうしようかなぁ?」
ぴょんぴょんと、跳ねる白音に合わせてリュックに飾りでついていたウサギの耳が彼女の肩に当たる。
「あ、ウサギさん!」
「え?」
「ウサギさんが食べたいです!」
琥珀は一瞬固まる。サンがどうかしたのか?と覗き込むとはっとしてから、ああ、と頷いた。
きっと緋音と重ねていたのだろうとサンは思う。
緋音と白音は瞳の色だけでなく、行動が似ていた。気になるものを見つけると一目散に駆け出してしまい、機嫌がいいと歌を口ずさみ、食べたいものを聞かれると必ずウサギの肉と言う。
忘れたくても、白音をみるとイヤでも彼女を思い出してしまうのだろう。しかし別の視点で見るに、そっくりなおかげで彼は、白音の父親で居られるのだろう、と。緋音の事だけを思う。今に始まったことではない。サンは複雑な心境に顔を歪める。
「食材はあるから買い物の必要はないか」琥珀が晩御飯について考えていると、白音が彼の腕をぐっと引く。なんだ? と目を向ける。
「…ねぇねぇ、パパ?」
白音は、真剣な顔を琥珀に向けた。
「ママに会いに行きたい」
4
「白音、走るなよ」
サンの言葉に、はーい、と元気に手を上げて駆け足をやめ白音が歩く。街はずれの静かな墓地に三人はいた。夏が過ぎようとしていたが、それにしてもここはいつも肌寒く感じる。カラスの鳴く声が、夕日に照らされた空を響く。
琥珀とサンは、黙って白音の背中を見ながら並んで歩いていた。
足を止めた白音が、二人に向かって「早く来て!」そう声を上げる。
彼女の前には、緋音・ラングレンの文字と五年前、白音の誕生日と同じ日付が掘られた綺麗な墓石があった。他の墓石に比べて汚れも目立たず、供えられた綺麗な花は、つい最近のモノだと見受けられた。
琥珀が定期的に来ては掃除をしていたからだ。三日に一度。出来れば毎日ここに会いに来たいと、琥珀は思っているのだろう。実際彼女が死んで二年ほどは、毎日彼の姿がここにあった。休日は何時間も立っていたのを管理人が見ていたようで、心配して声をかけた。丁度そのころ、歩くようになった白音と遊ぶ時間を作れ、そうサンに注意されたこともあって彼がここに姿を見せるのは、それ以来、三日に一度、になった。
「ママ」
「白音、手を」
琥珀は、白音の横に並ぶと、静かに手を合わせる。白音とサンも同じように手を合わせた。
「シオンもパパもサンもみんなげんきです…」
小さく最近の出来事を報告するように呟く。一通り話し終えた白音は、満足そうに目を開ける。が、隣に並ぶ琥珀とサンは未だに手を合わせていた。琥珀が長い間、こうして手を合わせていることはよくあったが、サンまで、珍しい。白音は、大人しく二人が目を開けるのを待っていたが一向に辞める気配がなく、サンのズボンの裾を引いた。
「ん?…ああ、白音?」
「ママとお話おわった?」
「…ああ、終わったよ」
そういったサンの顔に何処か寂しそうな雰囲気を感じた白音はそっと足に抱き着いた。琥珀が目を開けると白音がサンの足に抱きついている奇妙な光景を目の当たりにし「白音、なにをしているんだ? 」と聞くも、琥珀の声に白音は、「なんでもないよ」しがみついたままでくぐもった声がそう返した。
何をしたんだ?とサンを見るが、彼にも理由は分からないようで。さぁと肩を竦めて見せた。
「暗くなる前に帰ろう」
「うん…」
琥珀の手を取り(本当は先ほどのように二人の手を取り間に居たかったが通路が狭く叶わなかった)墓地を後にしようと歩き始める。白音の足取りがふわふわしていることに気付き琥珀が、彼女の顔を見ると、目がボーとして、そして空いている手で瞼を擦っていた。
「白音、眠たいのか?」
「ううん…だいじょうぶ…」
大丈夫には聞こえない。琥珀は、手を離すと白音を抱き抱えた。
「パパ?」
寝てなさい、彼の言葉に白音は、素直に頷くと体を預け小さく寝息を立て始めた。
カラスの鳴く声はいつの間にか消えていた。
墓地の門で、サンは足を止めた。
「なんだ?」
「悪い、俺ちょっと春のところ行くわ」
「それは構わないが、晩御飯は?」
「いい」
春。その名前を聞いて寝言のように白音が「ハルくんのところ…シオンも…行きたい」と呟く。「また今度連れて行ってやるから」サンは、そっと白音の頭を撫でる。
「多分日が変わる前には帰るけど」
「気を付けて」
「ん。白音、おやすみ」
「おや、すみなさ…」
睡魔に負け、言い終える前に白音は眠りについた。ついさっきまで元気にはしゃいでいたと言うのに、サンは、もう一度彼女の頭を撫でると、ゆっくり足を街の方へ向けた。琥珀は、心做しか気落ちして見えるサンの姿を、怪訝そうに見つめ見送る。夕日は半分以上落ちた夜の時間。暗くなった墓地を後に、琥珀は白音と家路についた。