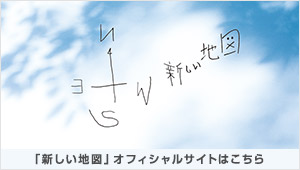昭和59年2月。
喜美子は、大崎から骨髄検査の結果は残念ながら一致しなかったと告げられた。もともと親子でも一致する確率は1%にも満たないことは説明を受けていたが、実際にそうなると衝撃は大きい。ソレをごまかすため待合室でおかしな体操を始めた喜美子に大崎は、患者の会を紹介する。
退院した武志はアルバイトに戻り、フカ先生から貰った絵葉書にインスピレーションを感じて新たな作陶に取り掛かる。一方で照子や信作の提案で武志を救うための支援の輪も広がっていく。その中には武志自身が自らの病気を打ち明けた友人たちや石井真奈もいた。しかし一致する人は現れず、喜美子や武志は落胆しつつも感謝を忘れない。アルバイト先の店長まで時間を減らそうと言い出し、周りに気を使わせているのが心苦しい武志は真奈に対してもどこかよそよそしくなっている。ある晩、真奈は川原家を訪ね、喜美子に武志への思いを打ち明けると工房へ。武志は困惑し、「病気だからや」という理由で追い返そうとする。ショックを受けた真奈は「病気やからうちと会うのを避けるのは納得できひん」と言い返して帰っていく。
ある日、喜美子は京都へ出かけることになり、代わりに八郎が武志に付き添うことになった。だが、武志は作陶しながら八郎と話している時に少し熱を出していた。病気とはいえ二十歳過ぎている息子の発熱にオタオタする八郎に、電話を受けた大崎は解熱剤を飲んで休むように指示する。部屋で寝ろという八郎を遮り、武志が居間の縁側に近いところで横になっているとにわか雨が降ってきた。雨が止んだ後、喜美子が物干し竿に掛けていったビニール傘が風に揺れ、その雫が手水鉢に滴り落ちた。その様子を見た武志はスケッチブックを手に取った。喜美子が帰宅すると大崎が武志の様子を見に来ていた。武志は「新しいイメージができた」と嬉しそうにスケッチブックを見せる。水が生きている=波紋だ。大崎は、やりたいことがあるというのは武志の支えになっているので、病状が落ち着いている限りは陶芸を続けても構わないと太鼓判を押した。しかし武志は髪の毛が抜け始めるなど少しずつ病状は進行していて…。
そんな時、武志と同室で武志より重い症状の智也が、智也の母のために作ったチューリップ柄の皿を届けに来た喜美子の前で容態が急変、大崎の必死の手当てもむなしく息を引き取った。喜美子はお通夜に行くつもりだったが、そこにかつて喜美子が女中として働いていた荒木荘のオーナー荒木さだと住人で喜美子の初恋の相手だった酒田圭介が川原家にやってくる。髪の毛が真っ白になっても口の達者なさだと無口な圭介だが、実は2人もちや子から武志の病気やドナー探しで苦労していることを聞き、駆け付けてくれたのだ。小児科医である圭介は懸命に2人を励ます。さだたちが帰ると2人は工房の武志に智也が亡くなったことを伝えた。春が過ぎて夏が過ぎるが、相変わらずドナーは見つからない。しかし、喜美子は懸命に探し回ってくれる武志の友人たちに感謝していた。武志は遂にアルバイトを辞めることになった。店長は元気になってまた戻っておいで、と労いの言葉を掛ける。
八郎は、武志の父方の伯母(つまり自分の姉)にもドナーの協力を求めていた。八郎にとって姉は親代わりで、怖いが有り難い存在でもあり、その姉のために茶碗を作っているところだった。友人たちは気分転換に八郎を大阪へ連れ出す。入れ違いに直子がスッポンを持って帰ってきた。真奈も加わり、その夜は久々にスッポン鍋を囲んで賑やかな川原家となる。直子は3人が帰ると武志に真奈と付き合うように勧めてきた。三姉妹の中でもズケズケ言うタイプの直子は、こういう時、喜美子以上にお節介なおばさんになっている。やがて武志の作った皿が焼きあがった。武志は、水が生きている皿を見て笑みを浮かべ、喜美子も笑顔を見せる。