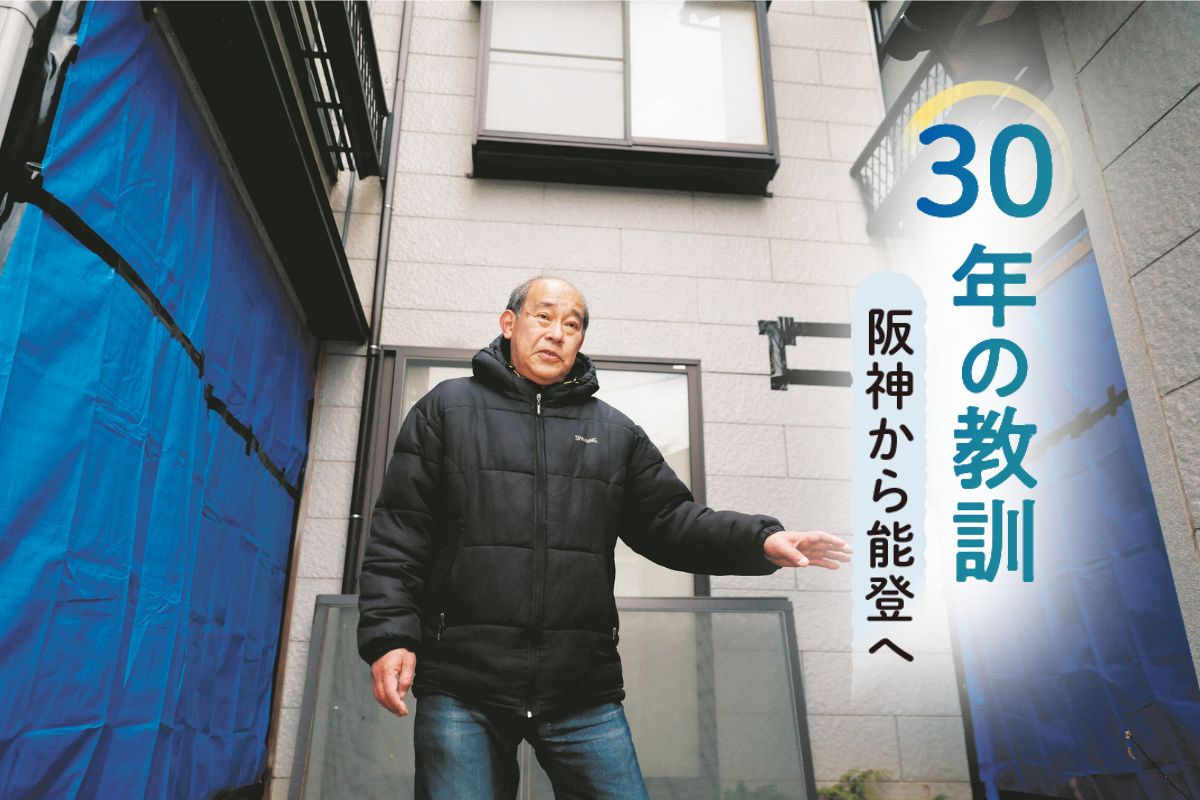タイトルに掲げた小田さんの本は阪神大震災から3か月ほど(1995年4月)で刊行されたものだが,避難所生活など当時の状況を読むと,昨年1月に起こった能登半島地震の状況と重なってくる。初期対応の遅れや避難所の劣悪な環境など,阪神大震災から30年経っても,この国や地方自治体の防災・災害対策というのはほとんど変わっていないのだな,というのが本書を読んだ率直な感想である。
小田さんは,大地震自体は天災だが,その地震に伴うさまざまな災害を見ると,これは人災ではないかと疑問を投げかける。この問題提起は能登半島地震にも当てはまるような気がする。
いろいろな人が,多くの人が事後の対策のまずさを指摘しています。どうしてもう少し早く人命救助しなかったのか,あるいは,今もってたくさんの被災者が避難所の小学校の体育館でくらしているのに,仮設住宅の建設は遅々として進まないとか,どうして消火活動ができなかったのとか,事後の対策はひどいもので,まったくこれは人災というほかにないものですが,ここで今私があらためて考えたいのは,そもそものはじめからこれはどうも人災ではないか,ということです。大地震のなかでたくさんの人が死んだ。しかも死ななくてもいいような命を失った,このこと全体を今少し深いところで考えてみたらどうかという気持ちが,私には非常に強いのです。
(小田実『「殺すな」と「共生」』岩波ジュニア新書p.85~p.86)
小田さんが住んでいた,人口40万人の西宮市では当時,1525億円の年間予算のうち災害対策費はたったの4500万円で,しかも非常用の備蓄食料はゼロだったという。こういう市民無視・軽視の非人間的な地方行政は,「土建屋の経済」「土建屋の政治」「政・官・財の癒着」が進めてきた「乱開発」の結果だ,と小田さんは手厳しい評価を下す。阪神大震災はこうした開発優先主義がもたらした「人災」だとする小田さんの告発はその通りというほかないし,2025年大阪万博の誘致・開催に見られるように,住民の安全・福祉は二の次にして開発を優先する土建屋の政治・経済・癒着構造はいまだに何も変わっていない。
阪神大震災の起こった1995年は「戦後50年」にあたり,村山談話が出されるなど「戦後50年」をめぐってさまざまな論議が活発になされた年であった。小田さんは,阪神大震災を受けて,本書で「戦後50年」をこう振り返っている。私が本書を読んで最も印象に残った一節である。
戦前の歴史の総決算としてあった空襲の火焔が燃えさかるなかで,水がないままに消防車は放水できず,まったく無力でした。いや,消防車自体が燃え上がっていました。しかし,「戦後50年」のあと,神戸の長田という大災害の現場で,同じように火焔が燃え上がるなか,水がないままに消防車は放水できず,あまたの家,建物は燃え上がりました。そのさまは,私の眼にはまるで,「戦後五〇年」の歴史がそのまま燃え上がっているように見えました。(同書p.173)
「戦後50年」が燃え上がっているとはどういうことか――。
たしかに,私たちは「戦後」,「経済大国」をつくり出すことに全力をつくして来ました。・・・結果として,超高層建築があまた建ち,高速道路があちこちにできた。しかし,それは,大災害にさいして,消防車に水がなく,非常備蓄用の食糧がゼロという「棄民」の現実をつくり出したことではなかったでしょうか。そして,その現実は五五〇〇人余りの「難死」をも生み出しました。この「戦後五〇年」と「戦前」の歴史の総体を通して共通して存在した事実がまちがいなくひとつありました。それは,どちらもが,「軍事大国」「経済大国」をつくり出しながら,ついに人間が安心して生きられる「人間の国」をつくり出さなかったことです。(同書p.174)
阪神大震災から30年経った今年は「戦後80年」にあたるわけだが,今,能登の現実を見れば,「戦後80年」の歴史が引き続き燃え上がっているように思えてならない。しかも,この30年は国として経済の再生にも失敗して多くの「経済棄民」=貧困層をつくり出した上に,「人間が安心して生きられる『人間の国』」もつくり出せなかった。その意味で,「戦前」は「戦後50年」を経て「戦後80年」まで地続きでつながっている。いまだに私たちは小田さんの提起した課題を解決できていないし,そもそも小田さんの問題提起そのものの大切さをよく理解していないように思う。小田さんのため息が聞こえてくるようだ。
ところで,本書は中高生向けの新書として書かれたものだが,小田さんの思想や行動を見る上で本書は非常に重要な位置を占めており,大学生以上の一般読者にも十分読み応えのある著作になっている。というのも,阪神大震災を当事者=被災者として体験したことで市民社会や民主主義に対する小田さんの見方がさらに深まり重層的となっていて,本書で小田さんの《市民思想》が完成の域に近づいたように思えるからである。特に重要なポイントは,本書において戦中の空襲体験と阪神大震災での被災体験が,「難死」の概念によって結びつけられたことである。もちろん,これは阪神大震災以前の著作や運動の中にはなかった視点である。
「難死」とは,ただ災難に遭って死んだとしか考えようのない「無意味な死」として小田さんが若い頃に定義づけた概念で,それは小田さんの空襲体験に裏打ちされた言葉だった。阪神大震災でも多くの人が「難死」をとげた。つまり死ななくてもいい人たちが戦争や震災であまた亡くなったのだ。殺されたと言ってもいい。そのような死を小田さんは「難死」と呼んだ。そして,「難死」においては,その難死を強いる側,つまり殺す側にはよく実態が見えていないが,難死を強いられる側,つまり「殺される側にこそ,いろんなものが見えて来る。」(本書p.32)
空襲体験と被災体験という二重の体験の上に「難死」の思想を鍛え直した小田さんは,人間が安心して暮らしていける場所は,「防災都市」でも「防災国家」でもないと主張する。今の小池都知事が掲げる「首都防衛」や石破首相が設置を目指す「防災庁」などについて,小田さんなら,土建屋だけが儲かる公共事業システムなど必要ないと一刀両断するだろう。目指すべきは,「防災大国」などではなくて,「難死」を強いられずに「人間が安心して生きられる国」である。
私たちが求めるものが「防災大国」などではなくて「人間の国」であることは,もうはっきりしていると思います。この「人間の国」の基本の原理は「殺すな」と「共生」。…この二つの「人間の国」の基本を政治的に実現するために「民主主義」がある。(同書p.180)
この「人間の国」をつくるに際して,小田さんは個々の市民の力に信頼を寄せる。
「人間の国」は誰がつくるのか。答えは今や,はっきりしています。政府も市役所も政党も頼りにならないとすれば,市民が自分でつくり出して行くほかはない。このことが事実として明らかに示されたのが,今度の大地震,大災害でした。(同書p.181)
大地震は手ひどい被害を神戸その他の被災地の「市民」にもたらしましたが,「市民」がおたがい助け合い,おたがい同士のあいだで「市民奉仕活動」をすることで「市民社会」をつくり出し維持するという「人間の国」の根幹になる「市民社会」の原型が示されたのも,今度の大地震,大災害のなかでのことでした。(同書p.182)
実際に阪神大震災後,小田さんらを中心に被災者市民が立ち上がって,被災者を公費助成で直接救済するための法律案を作り,それを基に議員立法の形で1998年「被災者生活再建支援法」ができた。これは「市民社会」が機能した画期的な事例であり,「人間が安心して生活できる国」づくりの第一歩であったと言えよう。
だが,市民=議員立法で作られたこの支援法が,能登において行政・権力側によって被災者を切り棄てる基準として運用(=悪用)されていることが,下の記事で報じられている。能登において行政側は被災者を救うための支援法を逆手にとって,被災者を切り棄て,「難死」を強いる道具として利用しているのだ。何たることか!と怒りが湧く。弱者を切り棄て「棄民」とし,ついには「難死」を強制してきた戦前の歴史は,「戦後50年」でも変わらず,「戦後80年」となってもいまだに変わっていないのである。「戦後80年」とは一体何だったのか。小田さんが生きていたら,能登の惨状を見て何と言うだろうか。「『戦後80年』の歴史がそのまま燃え上がっているように見える」と改めて感想を漏らすかもしれない。その意味では日本は今なお「戦後ゼロ年」だ。
本書を読んで,今更ながら小田さんの「難死」の思想の重要性に気づいた。戦前~戦後80年の間,為政者は弱い市民に「難死」を強いてきた。その歴史に終止符を打ち,「被災者生活再建支援法」のように市民自らが「難死」を極小化する仕組みを作っていくしかない,と市民の一人として強く思う。「難死」を拒絶して生き延びる権利は,市民の最も基本的な権利だ。それを主張することは,小田さんの言う民主主義に直接つながるはずだ。
小田実はいつも私たちの前を走っているような気がする。それは,小田さんが説く市民社会や民主主義に私たちが追いついていないことを意味するだろう。「私たち」というより,小田さんにならって「われ=われ」といった方が良いかもしれない。一人の市民=個人である「われ」が他の「われ」と結びつき,さらに「われ=われ=われ=われ…」と外へ広がっていくのが,小田さんの言う市民社会であり,一人ひとりの異なった価値を認め合う共生社会の基礎をなすものだ。「私たち」や「われら」に収斂されることなく,「われ=われ」として,「棄民」や「難死」を強いる今の行政府や権力者に抵抗しよう!それが小田さんの言う民主主義だ…