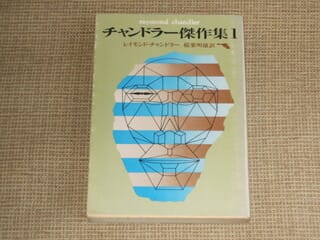E.ケストナー/小松太郎訳 一九九〇年 ちくま文庫版
これは去年12月に街の古本屋でたまたま見つけた文庫。
知らない書名だったので、ケストナーってあのケストナーだよなと、表紙めくってカバーそでんところの著者紹介みて、『エミールと探偵たち』を書いたケストナーだとたしかめた。
あとは裏表紙のほうめくってみて、鉛筆書きの値段たしかめたら、即買い決めた。(なんか最近、(特に外国文学の?)文庫本でもおどろくような値段のときあるんで。(この店はそうでもないけど。))
1931年の作品で、副題が「あるモラリストの物語」となってるけど、モラリストってなんだあと私なんかはわかってないわけで。
主人公ファービアンはタバコの広告をつくる仕事をしてる30男で、ベルリンで下宿してるとこへ心配してる母親から手紙が来たりする。
時代はナチス党が勢力を伸ばしてるころで、世間はなにかと騒がしいが、なんかあやしそうなクラブとかカフェとかも活況のようで、失業は多いかもしれないけど、そんな暗いってばかりでもなさそう。
ファービアンは、だんないるのに男をひっぱりこむ女と関わりあいになったり、友人の新聞編集者が紙面を埋めるためにウソの記事をさらっと書くのを見たりして、なんか嫌だ厭だと思う毎日のようで。
>「ぼくが資本家でない、っていう意味はだね、全然金をもうけようっていう気がないんだ。何のために金を儲けるんだ。金を儲けてどうするんだ。腹一杯喰うためなら何も出世する必要はない。(略)とにかくぼくは資本家じゃないよ! ぼくなんか利子も欲しいと思わないし、剰余価値も欲しいと思わないよ:
>ラブーデは頭をゆすぶった。「きみは呑気だな。金がもうかって、その金が要らなきゃ、権力と交換することができるんだよ」
>「権力があったからって何になるんだい。きみが権力を欲しがってるのは分ってるよ。だけれどぼくはそんなものは欲しくないんだ。欲しくないのに、権力を得たって何になるんだ。利欲と権勢欲とは姉妹だよ。しかしぼくとは血がつながっていないんだ」(p.75)
なんて友人とのやりとりから、なんとなく性格がわかるような気がする。
風変わりな若い娘たちと出会ったときには、
>「昔は女が男に身をまかせると、男はそれを贈物として大切にしたものだけど、いまの男はお金を払ってくれて、あとはもうお金を払って使ってしまった商品みたいに、いつか女を捨ててしまうのよ。現金払いの方が安上りだと思ってるのねえ」
>「昔は贈物と商品とは全然別なものでした。今日では贈物は金のかからない商品なんです。あんまり安いもんだから、買手は信用が置けないんです。きっといい加減なまやかしものだろうと思っちゃうんです。まあ、たいていはそれが本当の場合が多いんですがね。なぜかっていうと、たいがい女は後になって請求書を出しますからね。突然男はその贈物の道徳的な値段を払い戻さなきゃならないんです。精神的な為替相場で、終身年金として払わされるんですからね」(p.129-130)
なんてやりとりがあるけど、このへんは個人の気質ってよりは、時代の風俗を語ってんだろうなという気がする。
そんなこんなでダラダラしてるだけかと思いきや、新しいガールフレンドができたとたんに、会社をクビになったりして、その後も不幸な出来事が続発。
田舎の親元へ帰ったところで、
>「どうするかまだ分りません」と、ファービアンはいった。「ここで暮すようになるかもしれません。ぼくは仕事がしたいんです。働きたいんです。もうそろそろ目の前に一つの目的を持ちたいんです。見つからなきゃ発明しますよ。もうこうやっちゃいられません」(p.308)
なんて、やる気を見せるんだけど、ハッピーエンドにはならない。
ファービアンは、「その反対が明白に証明されないかぎり、ひとを見たら気違いと思え」(p.142)って、人間と付き合う場合に役立つ仮説をもってるけど、母親のほうは「人間は習慣の動物なり」(p.308)なんていうのが口ぐせらしい、なんかおもしろい、エミールとおかあさんみたい。
章立ては以下のとおり。最後の「ファービアンと道学者先生たち」は著者があとがきのつもりにしていたが削除されたもの。「盲腸のない紳士」は1931年初版のとき出版社の意向で収録を拒否されたもので、本来は第11章の前に入るものらしい。
第一章 カフェのボーイが神託を告げる それでも相手は出かける 「精神的ちかづき」の会
第二章 世の中にはおそろしく厚かましい淑女がいること 弁護士に異存はないこと 乞食は品性を堕落させること
第三章 カルカッタに十四名の死者が出たこと 嘘をつくのは正当なこと かたつむりが環になって這うこと
第四章 ケルンの大寺院のように大きなシガレットのこと ホールフェルト夫人の好奇心のこと 間借人がデカルトを読むこと
第五章 ダンスホールでまじめな会話 こっそり剃っているパウラ嬢 モル夫人がコップを投げること
第六章 メルキッシェス・ムゼーウムでの決闘 次の戦争はいつ起こるか 医者は診断を誤らぬこと
第七章 舞台の上の狂人のこと パウル・ミュラーの大冒険 浴槽の工場主
第八章 大学生が政治に没頭すること 父親のラブーデがこの世に惚れていること 外アルスターでの平手打ち
第九章 風変りな若い娘たちのこと 死ぬはずの男がぴんぴんしていること 「従妹」と呼ばれるクラブのこと
第十章 不道徳の局所解剖学 男女の道は尽きることなし ちょっとの違いが大きな違いのこと
第十一章 工場で寝耳に水 クロイツベルクの奇人 貧乏は一つの悪い習慣であること
第十二章 戸棚の中の発明家 働かないのは恥であること 母親が登場すること
第十三章 百貨店とショーペンハウアーのこと 逆の女郎屋 二枚の二十マルク紙幣
第十四章 ドアのない路のこと ゼロフ嬢の舌のこと 掏摸のいる階段
第十五章 模範的な青年のこと 駅の意義 コルネリアが一通の手紙をしたためること
第十六章 冒険を求めて ヴェディングの銃声 ペレスおじさんの遊楽園
第十七章 犢の肝臓、ただし筋のないところ ファービアンが意見を述べること セールスマンが堪忍袋の緒を切らすこと
第十八章 がっかりして家に帰る 警察はどうしようというのか 惨憺たる光景
第十九章 ファービアンが友だちのために弁護をすること レッシングの肖像が真二つに割れること ハーレンゼーでの孤独
第二十章 自家用車のなかのコルネリア 寝耳に水の教授 ラブーデ夫人が失神すること
第二十一章 法律家が映画スターになること 昔の知人 母親が軟石鹸を売ること
第二十二章 子供の兵舎を訪れる グラウンドの九柱戯 過去が街角を曲ってくれる
第二十三章 ピルゼン・ビールと愛国心のこと トルコ式ビーダーマイヤーのこと ファービアンがロハでもてなされること
第二十四章 クノル氏に魚の目があること 日刊新聞は有能の士を必要とすること 泳ぎは習っておくべきこと
ファービアンと道学者先生たち
盲腸のない紳士

これは去年12月に街の古本屋でたまたま見つけた文庫。
知らない書名だったので、ケストナーってあのケストナーだよなと、表紙めくってカバーそでんところの著者紹介みて、『エミールと探偵たち』を書いたケストナーだとたしかめた。
あとは裏表紙のほうめくってみて、鉛筆書きの値段たしかめたら、即買い決めた。(なんか最近、(特に外国文学の?)文庫本でもおどろくような値段のときあるんで。(この店はそうでもないけど。))
1931年の作品で、副題が「あるモラリストの物語」となってるけど、モラリストってなんだあと私なんかはわかってないわけで。
主人公ファービアンはタバコの広告をつくる仕事をしてる30男で、ベルリンで下宿してるとこへ心配してる母親から手紙が来たりする。
時代はナチス党が勢力を伸ばしてるころで、世間はなにかと騒がしいが、なんかあやしそうなクラブとかカフェとかも活況のようで、失業は多いかもしれないけど、そんな暗いってばかりでもなさそう。
ファービアンは、だんないるのに男をひっぱりこむ女と関わりあいになったり、友人の新聞編集者が紙面を埋めるためにウソの記事をさらっと書くのを見たりして、なんか嫌だ厭だと思う毎日のようで。
>「ぼくが資本家でない、っていう意味はだね、全然金をもうけようっていう気がないんだ。何のために金を儲けるんだ。金を儲けてどうするんだ。腹一杯喰うためなら何も出世する必要はない。(略)とにかくぼくは資本家じゃないよ! ぼくなんか利子も欲しいと思わないし、剰余価値も欲しいと思わないよ:
>ラブーデは頭をゆすぶった。「きみは呑気だな。金がもうかって、その金が要らなきゃ、権力と交換することができるんだよ」
>「権力があったからって何になるんだい。きみが権力を欲しがってるのは分ってるよ。だけれどぼくはそんなものは欲しくないんだ。欲しくないのに、権力を得たって何になるんだ。利欲と権勢欲とは姉妹だよ。しかしぼくとは血がつながっていないんだ」(p.75)
なんて友人とのやりとりから、なんとなく性格がわかるような気がする。
風変わりな若い娘たちと出会ったときには、
>「昔は女が男に身をまかせると、男はそれを贈物として大切にしたものだけど、いまの男はお金を払ってくれて、あとはもうお金を払って使ってしまった商品みたいに、いつか女を捨ててしまうのよ。現金払いの方が安上りだと思ってるのねえ」
>「昔は贈物と商品とは全然別なものでした。今日では贈物は金のかからない商品なんです。あんまり安いもんだから、買手は信用が置けないんです。きっといい加減なまやかしものだろうと思っちゃうんです。まあ、たいていはそれが本当の場合が多いんですがね。なぜかっていうと、たいがい女は後になって請求書を出しますからね。突然男はその贈物の道徳的な値段を払い戻さなきゃならないんです。精神的な為替相場で、終身年金として払わされるんですからね」(p.129-130)
なんてやりとりがあるけど、このへんは個人の気質ってよりは、時代の風俗を語ってんだろうなという気がする。
そんなこんなでダラダラしてるだけかと思いきや、新しいガールフレンドができたとたんに、会社をクビになったりして、その後も不幸な出来事が続発。
田舎の親元へ帰ったところで、
>「どうするかまだ分りません」と、ファービアンはいった。「ここで暮すようになるかもしれません。ぼくは仕事がしたいんです。働きたいんです。もうそろそろ目の前に一つの目的を持ちたいんです。見つからなきゃ発明しますよ。もうこうやっちゃいられません」(p.308)
なんて、やる気を見せるんだけど、ハッピーエンドにはならない。
ファービアンは、「その反対が明白に証明されないかぎり、ひとを見たら気違いと思え」(p.142)って、人間と付き合う場合に役立つ仮説をもってるけど、母親のほうは「人間は習慣の動物なり」(p.308)なんていうのが口ぐせらしい、なんかおもしろい、エミールとおかあさんみたい。
章立ては以下のとおり。最後の「ファービアンと道学者先生たち」は著者があとがきのつもりにしていたが削除されたもの。「盲腸のない紳士」は1931年初版のとき出版社の意向で収録を拒否されたもので、本来は第11章の前に入るものらしい。
第一章 カフェのボーイが神託を告げる それでも相手は出かける 「精神的ちかづき」の会
第二章 世の中にはおそろしく厚かましい淑女がいること 弁護士に異存はないこと 乞食は品性を堕落させること
第三章 カルカッタに十四名の死者が出たこと 嘘をつくのは正当なこと かたつむりが環になって這うこと
第四章 ケルンの大寺院のように大きなシガレットのこと ホールフェルト夫人の好奇心のこと 間借人がデカルトを読むこと
第五章 ダンスホールでまじめな会話 こっそり剃っているパウラ嬢 モル夫人がコップを投げること
第六章 メルキッシェス・ムゼーウムでの決闘 次の戦争はいつ起こるか 医者は診断を誤らぬこと
第七章 舞台の上の狂人のこと パウル・ミュラーの大冒険 浴槽の工場主
第八章 大学生が政治に没頭すること 父親のラブーデがこの世に惚れていること 外アルスターでの平手打ち
第九章 風変りな若い娘たちのこと 死ぬはずの男がぴんぴんしていること 「従妹」と呼ばれるクラブのこと
第十章 不道徳の局所解剖学 男女の道は尽きることなし ちょっとの違いが大きな違いのこと
第十一章 工場で寝耳に水 クロイツベルクの奇人 貧乏は一つの悪い習慣であること
第十二章 戸棚の中の発明家 働かないのは恥であること 母親が登場すること
第十三章 百貨店とショーペンハウアーのこと 逆の女郎屋 二枚の二十マルク紙幣
第十四章 ドアのない路のこと ゼロフ嬢の舌のこと 掏摸のいる階段
第十五章 模範的な青年のこと 駅の意義 コルネリアが一通の手紙をしたためること
第十六章 冒険を求めて ヴェディングの銃声 ペレスおじさんの遊楽園
第十七章 犢の肝臓、ただし筋のないところ ファービアンが意見を述べること セールスマンが堪忍袋の緒を切らすこと
第十八章 がっかりして家に帰る 警察はどうしようというのか 惨憺たる光景
第十九章 ファービアンが友だちのために弁護をすること レッシングの肖像が真二つに割れること ハーレンゼーでの孤独
第二十章 自家用車のなかのコルネリア 寝耳に水の教授 ラブーデ夫人が失神すること
第二十一章 法律家が映画スターになること 昔の知人 母親が軟石鹸を売ること
第二十二章 子供の兵舎を訪れる グラウンドの九柱戯 過去が街角を曲ってくれる
第二十三章 ピルゼン・ビールと愛国心のこと トルコ式ビーダーマイヤーのこと ファービアンがロハでもてなされること
第二十四章 クノル氏に魚の目があること 日刊新聞は有能の士を必要とすること 泳ぎは習っておくべきこと
ファービアンと道学者先生たち
盲腸のない紳士