読売日響・第611回定期演奏会
鵠沼のサロンでクラシカル・フルートとフォルテピアノを堪能した翌日、古楽は真逆の現代オーケストラ作品をサントリーの大ホールで聴いてきました。
読響の9月定期、以下のプログラムです。
ゴリホフ/チェロ協奏曲「アズール」(日本初演)
~休憩~
ストラヴィンスキー/管楽器のための交響曲
ショスタコーヴィチ/交響曲第9番
指揮/井上道義
チェロ/宮田大
アコーディオン/太田智美
パーカッション/海沼正利、萱谷亮一
音響/有馬純寿
コンサートマスター/林悠介
発表されていた指揮のイラン・ヴォルコフが政府の入国制限により来日出来ず、わが井上道義に交替した演奏会。目玉はこれが日本初演となるゴリホフ作品でしょうが、予定の指揮者が振れなくなってもピンチヒッターを引き受けてくれるマエストロがいる日本、改めて日本の指揮者陣の層の厚さが実感できるコンサートでもありました。
当初は冒頭にストラヴィンスキー、続いてチェロ協奏曲が演奏されることになっていましたが、直前になって指揮者の意向ということで曲順が入れ替わりました。しかしこれは正解じゃないでしょうか。ゴリホフ作品には特殊楽器がズラリと並び、通常楽器の配置も普通とは違います。舞台転換が大変なわけで、これなら開演前にセッティングしておけるし、休憩時間を使って転換もスムーズ。音楽的にも前半で協奏曲を、後半は同じロシアに生まれながら共産主義とは距離を置いたストラヴィンスキーと、ソ連に留まって作品を書き続けたショスタコーヴィチを並べて聴けるという利点もありましょう。寧ろ何故最初からこの演奏順にしなかったのか不思議に思えるほどに自然な変更だったと思います。
ホールに入ると、指揮台の周りに見たこともないような楽器が並んでいるのが目に入ります。プログラムを開けるとゴートネイル、スプリング、カシ―シ、シェーカー等々。なんじゃそれ。作曲家の指示に従い、一部アンプ(音響機器)を使用しています、とも。
上記演奏者リストに紹介したチェロ・ソロ以外のアコーディオン、パーカッション、音響は全てゴリホフ作品で登場するもの。因みにブージー・アンド・ホークス社のオンライン・スコアで楽譜を閲覧してみると、アコーディオンはマイケル・ヴァルド=ヴェルゲマン考案のハイパー・アコーディオンが使われることになっていますが、今回はスコアにもあるように普通のアコーディオンで演奏されたようですね。
他にもこのスコアには特殊打楽器が写真入りで紹介されていて、羊の蹄で作られたガラガラであるゴートネイルなどの珍しい打楽器も確認することが出来ます。ブージーのオンライン・スコアはメールアドレスとパスワードの自由登録だけで誰でも無料で見ることが出来ますから、興味ある方は試してみてください。
さてゴリホフ。ウクライナとルーマニアのユダヤ系移民の子孫で、アルゼンチン生まれ。その音楽にはタンゴやクレズマー(東欧ユダヤ民族)、ロマや中東、もちろん西洋音楽の要素も含まれ、些か雑食的な傾向があります。日本では日生劇場で上演されたオペラ「アイナダマール」や、パシフィカとエクが合奏したラスト・ラウンド、ボローメオ・クァルテットが晴海で紹介したテネブレなどで既にお馴染み。特にテネブレはゴリホフがイスラエルで体験した暴力事件に触発されて書いた音楽で、今回のアズールでも引用され、絶大な効果を挙げていました。
題名のアズール Azul とは、スペイン語で「青」の意味。ゴリホフの述懐では、郷愁を誘うタングルウッドの夕暮れの空や、宇宙から撮影した青い地球のイメージとも重なる由。ボストン交響楽団の委嘱、ヨーヨー・マのために書かれた作品であることにも繋がるのでしょう。
日本初演で聴くアズール、これは録音などで「聴く」ものではなく、実際にホールでライブ演奏を「見て感ずる」音楽だ、というのが第一印象。4楽章構成、最後に2種類のコーダが続きますが、全体は切れ目なく演奏されます。正に宇宙から響いてくる音楽、というか音響。
第1楽章「硫黄の平和」は、発想の原点でもあるパブロ・ネルーダの詩や自然そのものとも関係の深い開始部。独奏チェロとアコーディオン、二人の打楽器が模索するような第2楽章「沈黙」。第3楽章「推移」は独奏者4人によるカデンツァで、今回は舞台照明が落とされ、指揮の井上道義も指揮台に座り込んでカデンツァに耳を傾けます。もちろんポーズという側面もあるでしょうが、指揮者がその場で仁王立ちになっていては、席によっては4人が演奏する姿の邪魔になる。これは作曲者の指示ではなく、マエストロの配慮なのだろうと思われます。ところでこのカデンツァ、見よう聴きようによってはバッハのチェロ・ソナタを、アコーディオンと二人の打楽器奏者が通奏低音として支えている姿と取れなくもない。現代風バロック音楽。
やおら井上が立ち上がる所からが、第4楽章「エルサレム」。冒頭では判別し難かったテネブレのテーマが、トロンボーンに明瞭に聴き取れます。
傑作なのは、「パルサー Pulsar」と「流れ星 Shooting Stars」と題された連続して演奏される二つのコーダ。先ずパルサーでは13小節の夫々に楽器の指定があるソロ的な箇所で、続く流れ星も同じく13小節に亘ってグリッサンドを連発しながら最強音まで大きなクレッシェンドを描くのです。そして突然音楽は最弱音に静まり、ここも13小節に亘ってディミニュエンドしながら無の中に消えてゆくのでした。13という数字にも意味が隠されているのではないでしょうか。
コーダの演奏に付いて、ゴリホフは「ルイ・アームストロングが天馬に跨る感じ」と指示したのだそうです。
コーダの最後、消え行く13小節では次第にホールの照明が落とされ、遂には真の暗黒に。このような演出は私が探した限りではスコアの指示に見当たりませんでしたから、あるいは井上道義のアイデアかも知れません。以前に井上が読響定期で取り上げたスクリャービンのプロメテウスでの演出効果を思い出してしまいました。
井上の指揮は、水を得た魚のよう。しなやかに、そして時に大きなアクションを伴って自らの表現意図を伝えてゆく。これほど井上の感性、音楽性に適した音楽は無いのではないかと思えるほどに嵌っていました。
禁止されているので歓声こそ上がりませんでしたが、客席の反応が熱狂的だったことは、拍手の熱量からして明らかです。
大盛り上がりの前半が終わり、慌ただしい舞台転換を終えて後半のロシア・プログラム。今年が没後50年に当たるストラヴィンスキーは、1920年の原典版ではなく、1947年改訂版での演奏。舞台奥に並んだ名手揃いの読響管楽器メンバーを、椅子を寄せて広くした舞台で指揮台なしでのタクト。
続くショスタコーヴィチは、井上道義の十八番。これまで数々の名演を繰り広げてきたレパートリーだけに、道義のショスタコーヴィチを聴きに集合したファンも多かったのじゃないでしょうか。第4楽章、吉田将首席のファゴット・ソロに聴き惚れます。
大成功裡に終えた久々の井上道義による読響定期。カーテンコールに応えて颯爽と、ある時はさも疲れた、もう歳だ、とでも言わんばかりのポーズで拍手に応えるミッチー。最後は指揮台前でバレーで鍛えた回転を披露し、客席の笑いも誘っていました。
読響さん、これからも度々井上道義を指揮台に読んでください。次の機会には盛大な “ブラヴォ~” がホールに響き渡りますように。
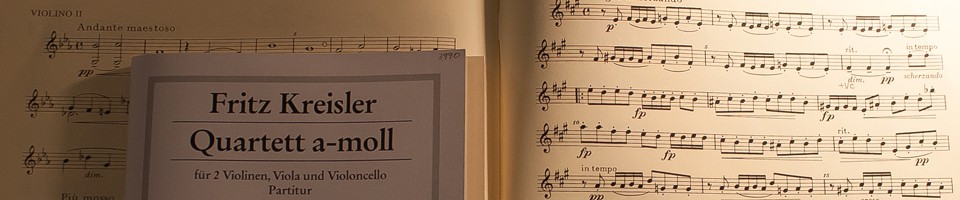
最近のコメント