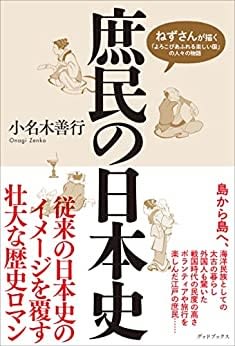
庶民の日本史 ねずさんが描く「よろこびあふれる楽しい国」の人々の物語 - 小名木 善行
■1.庶民の一部だった武士がなぜ武士道を形成したのか?
国史啓蒙家・「ねずさん」こと小名木善行氏の新著『庶民の日本史』が刊行されました。かねがね私は、我が国は皇室から「大御宝(おおみたから)」として大事にされてきた庶民が、その皇恩に応えて国の維持発展に尽くしてきたことが、国史の背骨だと考えていたので、このタイトルを見て「なるほど」と膝を打ちました。
早速、本を読んでみると、なんと旧石器時代から、日本の庶民がどう暮らしていたか、豊富な逸話と共に絵巻物のように語られています。本号では、その中でも私自身が特に共感した点をご紹介しましょう。
それは武士に関しての一節です。ねずさんは、まず武士が庶民の一種だったということを、次のように説明します。
・・・武士は、奈良時代以降の開墾百姓、つまり庶民です。新しく土地を開墾し、田んぼや畑を開いてそこを私有地にした人たちを祖とします。そして自警団として彼ら自身が武装し、武士団を形成するようになったとされます。その武士団は、源平を戦い、また鎌倉時代に元寇を倒すことで、国内に敢然とした力を発揮するようになりました。[小名木、p142]
庶民の一種だった武士たちが、なぜ「武士道」という独特の哲学を持つようになったのでしょうか?
よく言われるのは、武士は中国渡来の四書五経や儒教を学ぶことで、武士道を形成したということです。けれど、それはちょっとおかしな議論です。なぜなら儒教も四書五経も中国で生まれ、科挙の試験科目にもなり、また朝鮮半島においても学ばれた書です。それなのに、どうして中国や半鳥で武士道が形成されず、日本だけに武士道か生まれたのでしょうか。[小名木、p142]
■2.権力者にも、弱い者の気持ちを察するやさしさが必要
その答えは「お能」だった、とねずさんは指摘します。武士はお能を見ることで、武士道を身に付けた。それをお能の定番の二つの演目で、説明します。
最初の演目は「熊野(ゆや)」です。ねずさんは、その筋をこう解説します。
遠州(静岡県)出身の美しい女性である熊野は、京の都で平宗盛(たいらのむねもり)に仕えているのですが、母が病気だと連絡が入る。そこで宗盛様にお暇をいただいて故郷(くに)に帰りたいのだけれど、宗盛はちょうど清水寺の大花見大会を計画しており、美しい熊野は、是非とも連れていきたい女性であるだけに、熊野自身もそうした宗盛の気持ちを察して言い出せない。
いよいよ花見の日、酒宴のときに衆生を守護する熊野権現(くまのごんげん)がにわか雨を降らして、花を散らせてしまいます。そして熊野が、
いかにせん 都の春も惜しけれど 馴(な)れし東(あずま)の花や散るらん
と母を慕う和歌をしたためると、これを読んだ宗盛が、熊野の帰郷を許すわけです。そして熊野は急いで故郷に旅立っていく。[小名木、p144]
熊野権現が、熊野の気持ちを察して、にわか雨を降らし花を散らせてしまう、ということから、この物語は神々のご意思はどこまでも衆生の幸せの上にあることを明かし、そのご意思に従って時の権力者・宗盛がか弱い一人の女性の気持ちを察して、帰郷を許すのです。ねずさんは、この物語から、こう指摘します。
武士であれば、当然、武力をもつし、武力を用いるための訓練も受けています。つまり一般の民よりも強く、そして権力をもつ存在です。けれど強いからこそ、武力や官位や権力以上に、弱い者の気持を些細なことから察する。そういう人としてのやさしさか大切であることを、このお能の演目は教えているわけです。[小名木、p145]
■3.いのちを奪った相手を回向して、成仏させてやらねばならない
もう一つの演目が「鵺(ぬえ)」です。
鵺は、頭が猿、尾が蛇、手足が虎という恐ろしい妖怪で、その昔、源頼政によって退治されたのですが、退治されただけで、その魂魄(こんぱく)がいまだこの世にさまよっていました。たまたまその鵺の魂と出会った旅僧の回向(えこう)によって、鵺の魂魄はおさまり、成仏してこの世を去っていくというのがこの物語です。[小名木、p146]
戦いで相手の命を奪うことは武士の宿業ですが、その後でお経をあげるなどの回向(えこう)をして、成仏させてやらねばならない、これが武士の心得でした。「鵺」は、これを教える演目でした。
これは仏教的な信仰の問題だけではないでしょう。殺した相手が成仏できるよう祈る時には、相手の生前の人生に思いを馳せ、その死を悲しむ両親や妻や子供がいただろう、と思いやります。自分は、そういう人間の「いのち」を奪ったのだと、自省する瞬間を持つのです。それは、今後の無益な殺生は可能な限り避けようとする「武士の情け」につながります。
こういう物語によって、武士は「殺人マシーン」になることを防げるのです。先の大戦で、武士道精神を受け継ぐ旧日本軍が、敵兵に対しても戦いの後に供養を欠かさなかったのは、この鵺の物語が武士の心得となっていたからにほかならない、とねずさんは指摘します。
■4.「鉢木(はちのき)」に学ぶ「私」と「公」の分別
ねずさんは、別の節で、御恩と奉公の関係を説いた「鉢木(はちのき)」という能の演目も紹介しています。
鎌倉時代の中頃、一人の旅の僧が、上野国(こうづけのくに、群馬県)で吹雪に降り込められ、貧しい一軒屋に宿をお借りしたいと頼み込みます。隙間風の吹くあばら屋ですが、家の主人・佐野源左衛門(げんざえもん)は、大切にしていた梅・桜・松の三本の鉢木を火にくべて、旅の僧をもてなします。
旅の僧は、源左衛門の名を尋ねますが、「いやいや名乗るほどのものではありませぬ」と言いつつも、実は親族に領地を横領されて零落し、今はこのような暮らしと、身の上を語ります。「それでも、もし鎌倉で事あれば、私は誰よりも先に駆けつけるつもりでいます」と覚悟を明かします。
それからしばらくして、鎌倉の執権・北条時頼(ときより)は、関東全域の武士に招集をかけます。源左衛門は、みすぼらしい出で立ちながらも、鎌倉に駆けつけます。源左衛門が鎌倉に着くと、時頼の前に呼び出されます。現れた時頼は以前、家に泊めた旅の僧でした。
時頼は、言葉通りに鎌倉に駆けつけた源左衛門を称賛し、横領された土地の回復を約束し、さらに3本の鉢の木の礼に梅、桜、松にちなんだ三カ所の庄を与えたのです。
この物語が教えているのは、主君への忠義の深い意味です。まず、源左衛門が親族に領地を横領されて零落の身になりながらも、そのために戦いを起こすようなことをしていないことです。そこで戦いを起こしたら、それこそ「私」の利益のために武力を用いる弱肉強食の世になってしまいます。
しかし、将軍の招集には誰よりも先に駆けつけようとします。将軍は天下の平穏を守るのが仕事ですから、その招集に応えることは「公」の使命です。この物語から武士たちは、自らの武力を「私」のために使ってはならない、それはあくまでも「公」のためのものである、ということを学んだことでしょう。
■5.信長が桶狭間への出陣の前に舞った「敦盛(あつもり)」
能の声楽部分を謡曲(ようきょく)と言います。謡曲で有名なのが織田信長が好んで舞った「敦盛(あつもり)」の一節です。
人間(にんげん)五十年、化天(げてん)のうちを比ぶれば、夢幻(ゆめまぼろし)の如くなり 一度(ひとたび)生(しょう)を享(う)け、滅(めっ)せぬもののあるべきか
「人間」とは「人間界」、「下天」は、仏教で教える別世界の一つで、一昼夜は人間界の50年の長さ、それが500年続く寿命を住人は持つ、とされています。その世界に比べれば、人間界の50年など一日にしかあたらない夢幻のようなもので、ひとたび生命を受けても滅びないものなどあろうか、という意味です。
今川義元の大軍の尾張侵攻を聞いて、信長はまずこの一節を謡い舞い、出陣を告げる陣貝を吹かせて、立ったまま湯漬けを食した後、鎧をまとって出陣する、という有名な場面です。
尾張織田家はもともと天皇直属の弾正台(だんじょうだい)に属す家柄、これは政府高官の不正を正す役目を授けられていました。将軍家の分家の分家に過ぎない今川が強大な武力を頼んで、勝手に京に上って将軍職や太政大臣の地位を狙うことなど、阻止すべき責任があったのです。
しかし、それまでの信長は「大うつけ(馬鹿者)と呼ばれ、「信長様の時代になったら織田家もおしまい」と言われていました。家督を継いでも、まるで殿様としての自覚のない信長を諫めるために、宿老の平手政秀(ひらて・まさひで)が自害までしました。
■6.「敦盛」に込められた信長の覚悟
そんな「うつけ者」だった信長が、ここで弾正忠の家柄に目覚め、今川と戦うことを決意するのです。ねずさんは、こう語ります。
「人間五十年、下天の内をくらぶれば……」と唄う「敦盛」は、「男子たるもの、たとえ敵わぬ相手、負けるとわかっている相手であっても、戦うべきときには戦わねばならぬ、どうせ人生、長く生きても五十年。夢や幻のようなものなのだから、せめて一太刀、真実の刃を残して死のうではないか」という意味の謡曲です。この歌と舞が行われている間に、家臣一同は信長の心を見ます。
ようやく我らが大将が、弾正の血に目覚めてくれた。
ようやく我らが大将が、本物の男になってくれた。
ようやく我らか大将が、我らの本物の大将になってくれた。
こうして家臣一同、決死の覚悟の集団となります。ただ命令されて付いてきているだけの兵と、死を覚悟の一団では、その戦力差は歴然です。そんな家臣を引き連れて、信長は桶狭間で昼休み中の今川義元を急襲して、倒します。[158]
この一場面は、その後の武士の生き方にも多大な示唆を与えました。潔く散る事を覚悟してでも戦うべき時は戦う、という生き方が貴いということを、武士たちは学んだのです。
■7.「太平記読み」が広めた
江戸時代には講釈師による「太平記読み」も流行(はや)りました。「太平記」に登場する楠木正成(くすのき・まさしげ)は忠臣として後醍醐天皇の為に尽くし、最後は負けると分かっていながら、足利の大軍と6時間も死力を尽くして戦い続け、ついには弟の正季(まさすえ)と差し違えます。この時に正成は、弟に最期の存念を聞きます。
正季からからと打ち笑ひて、「ただ七生までも同じ人間に生まれて、朝敵をほろぼさばやとこそ存じ候へ」と申しければ、正成よにも心よげなる気色(けしき)にて、「罪業深き悪念なれども、我も左様に思ふなり。いざさらば、同じく生を替へて、この本懐を遂げん」と契って、兄弟ともに差し違へて、、、(『太平記』)[JOG(1147)]
「罪業深き悪念」とは、死んで極楽浄土などに行くのではなく、「救いなどいらない。何度でも、この迷いの世界に生まれ変わり、この世を乱す者どもを討ち滅ぼそう」という「執念」です。
自分自身の成仏など「私」のこと、真の武士は天下国家と民の安寧のために、何度でも生まれ変わって、皇室にお仕え申そう、という覚悟が語られています。江戸時代の庶民は、こういう物語を楽しみながら、人として生きる道を学んだのでしょう。
■8.「物語」への共感こそ、最高の人間教育
江戸時代中期には「太平記読み」と同様に、民衆に大きな影響を与えた「忠臣蔵」が登場します。幕府の不当な裁定で自刃した主君のために、忠臣四十七士が苦難を乗り越えて、敵を討ち、本懐を遂げた後で一同、切腹するという物語は、日本人に、正義のためには命も捧げる、という武士道を教えました。
振り返ってみると、「熊野」「鵺」「鉢木」「敦盛」「太平記」「忠臣蔵」は、能、講釈、歌舞伎などの様式の違いこそあれ、すべて登場人物の具体的な生き方を語った「物語」です。
現代の最先端の脳科学は、人間の脳にはミラーニューロンがあって、人は他者の心情を理解し、共感するメカニズムを明らかにしています。それによって四書五経のような抽象的な徳目よりも、物語の登場人物の心情に共感し、そこから学ぶことの方が大きく、かつ永続することが分かっています。
そういえば、明治以降の「修身」の教育も、教育勅語の徳目を子どもにも共感できる幾多の「物語」を通じて語っています[JOG(758)]。我々の先人たちは、もう何百年も前から、この真理に気がついており、様々な「物語」を通じて、庶民全般の生き方のレベルを引き上げていたのです。この先人の知恵を、知識の詰め込みばかりさせられている現代の子供たちの健全な成長のために活用したいものです。
(文責 伊勢雅臣)
















