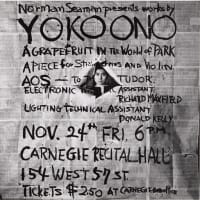1985年に新潮社から出た文庫本の短編集「あほうがらす」の中の一篇、「男色武士道」は、その終いに語られる部分によって、印象に、そして記憶に残る一篇になっているように思う。今、老いて死を迎えようとしている老武士千本九郎が、「この品を、わしが遺体と共に、土へ埋めよ」と長年彼に仕え、齢も七十を超える家来の者に、言う。その裃の切れはしで包んだものの中身は、「書状のきれはし」にすぎないということであるし、それを書いた相手とは、10代の終わりを最後に会ってはいないという間柄。だがそこには秘されている、とりわけ死を迎えようとしている彼には特別な訳がある、というのがこのものがたりにあるわけなのだが、感じるのは、こういう作品を考えた池波正太郎という作家その人への興味もあるということ。男色に触れてこのような時代小説を書けた人というのが、他に思い浮かばない。そういうことでは、山本周五郎のような作家に、一つ位は記憶に残る時代小説の男色作品を残してもらいたかったようにも、思える。そうしたセンスとは縁なさそうなタイプであったのは、残念。

「あほうがらす」の中の短編に触れて書いてみたくなったこの機会、「池波正太郎短編全集」の「上・下」に収められた彼の他の作品もあれこれ読んでみることになって、男色ということに限っても思わぬ作品のあることを知った。自分を仇討ちとして狙っている相手とは知らずに、その若者の布団の中で男色行為に及ぼうとした中年剣術師範が、その全く無防備な状況ゆえに仇を討たれて命を失うという、「波紋」のような作品。「大石内蔵助」という作品では、息子の大石主税が京の陰間茶屋の幸之助という色子と性の初体験をする事を知る内蔵助は父親になるわけだが、それも当時のこととしては普通に違和感なく受け入れられる行為でもあったという一面を教える。その主税と幸之助の出会い、その関係模様、運命について書かれているのが、「あほうがらす」の中にもある一篇「元禄色子」ということになるのだが、池波は性行為初体験の主税、リードする幸之助の関係模様も彼ならではのという、男女に変わらぬ描写ですすめていく。
読んでいて、例えばその作品「大石内蔵助」など、初出がどういう雑誌に書かれたものなのか考えたくなるほどに、40代の内蔵助はどこまでも色好み、女と言えば目がないという好き者として、描かれている。比丘尼宿と呼ばれる娼家で関係を持つ、尼らしく頭を丸めた少女は16歳である。二人のとりあわせに思ったりなどする、作者の嗜好。内蔵助は5尺一寸(154センチほど)と書かれているが、池波は、こんなふうに書く。
『内蔵助の小太りで色白な体躯や、鳩のように小さくて愛くるしい光をたたえた両眼や,かたちのよいふくらみをみせた唇から発せられるやさしい声音やらに、つよく、こころをひかれたらしい。』
これは、他の女とのことの部分に書かれている内蔵助なのだが、何か池波が自身魅せられたい対象として描こうとしているような、そういう小太りタイプが実は性的にも男色的に好きなのではないかと、思わせるほど。「愛くるしい光」などの表現はちょっと、40を過ぎた男にするには過剰。というような具合に、奔放と言えば奔放な池波の内蔵助表現なのだが、討ち入りの吉良邸における最後の部分では、「妻の大きく肉づいた下腹の、その臍下から陰所のふくらみにかけて、女性(にょしょう)にしては濃密に過ぎる陰毛のしげりを、内蔵助は、なつかしく脳裏にえがいていた。」、などのことがくるほどに、性との結びつきを離さない。女も男も、その感覚をもって作品の中で追う。というのが、独特な表現、言葉遣いに感じられる。

「あほうがらす」には、「火消しの殿」という作品も入っていて、この殿は大石内蔵助の主君、浅野内匠頭長矩である。内匠頭は火事災害に対する対応意識の高かった城主でもあったということなのであるが、この殿はまた男色好み、色子好みで小姓たちはその性欲満足のために、奉仕の欠かせない存在。新たに小姓に取り上げられた美少年沢口久馬も、同じように殿の欲望に応えることを求められる。ところが、僅か以前に城への出仕を仲介してくれた側用人の妾宅の女に誘惑されて、既に女の肉体の味を知ってしまっている久馬は、例え殿の求めであれ、男同士の行為ということに嫌悪感を覚える。耐えられないで、拒む。それでも殿の長矩は、久馬が未経験故に戸惑っているものと解し、待つのも一興かと、時間をかけて欲情を遂げるのも良しとして、強要は控える。だが何度か、拒むことがつづいた後、久馬は耐えがたさに、城を逃げ出してしまう。その後に、江戸城、松の廊下でのことが起き、即日処断をくだされ、内匠頭は切腹をさせられてしまうということが起き、赤穂浪士の討ち入りとつづくわけなのだが、久馬の眼を通して見た内匠頭に池波正太郎は、視点を持っていくことを狙って書いたもののようで、男色好み側からすればこの視点はちょっと苦い。
美形ながら、男色を嫌悪すべきものと感じる男子、久馬を見せることには、かなりの不自然さ、無理があるように思う。浪人の父と子の二人家族。城に迎えられて将来も見えてきたこの機会、自分の性指向に合わないというだけで、「殿の為ならば如何なることも厭わず」の心もなく、寵愛対象として選ばれながら、その仕えるべき主君を拒むというのは、この時代のこととして不可解。これでは、こうしたフィクションの中にせよ、色子好みの一面を嫌悪されるような形で晒す破目になった内匠頭が、可哀そうにも思える。というようなことが出てくるくらいに、池波正太郎は性指向をともかく前面に出し、下半身のことを後のことにはしたくない性感覚派と思われるほど、色のことには執着する、それを感じさせる作品があれこれ存在するというのがどこからくるのかな、という興味は覚える。討ち入りの最中に、妻の下腹、陰部に向けての肉体部分を懐かしく大石内蔵助に回想させる、ユニークすぎるそうした性に粘りつ着く感性。

そうして、最初に触れた「男色武士道」のことなのだが、ここにはなにか心の美しさを感じさせるものがある。心にとどまる宝のような記憶のあること、それは何ものにも代えがたいのではないか、と思わせてくれる。生涯というものの中での、究極の得難いもの、とも思えるような宝。 登場するのは、ここでも殿の小姓で寵童の噂のある15歳の細身の美少年鷲見左門。そしてその男色、断金の間柄、太くたくましい19歳の千本九郎。事の発端は、徒士組の若者佐藤勘助がすれちがいさま「尻奉公」の言葉を、左門に投げつけたことによる。殿の寵愛を受けているのは事実ながら、男色行為があるのは事実ではない。その侮辱は、左門には耐えがたい。実のところ、勘助は左門に欲望を抱いていて、以前呼び出して強引に接吻などに及び、抵抗されてそのさいに唇に傷を負ったりなどしている。そうしたことへの腹いせなどもあっての、尻奉公云々のいやがらせの言葉なのである。左門は、そのことを、既に元服していながら小姓として殿が離さないために束ねとしてとどまる千本九郎に話す。九郎は、聞き捨てならないと言う。殿をも愚弄する言葉。武士として主君とと自身へのその侮辱は晴らさなければいけないと、左門を説得する。
だが、主君が気遣う程に体力もなさそうな左門に、屈強な勘助と一対一で勝負ができるわけがない。初めから結果は目に見えている。自分には討てないと九郎の膝に突っ伏す左門に、「断金のちかいをたてたるおぬしの恥は、そのまま、おれの恥じゃ」と九郎は、助太刀のことを言う。その夜、九郎の指図通りに殿や病身の父親への手紙をしたため、討ち果たした後にしばらく身をひそめるための金を九郎から受けた左門が、佐藤勘助を誘い出す。勘助は無論、果し合いのために左門がやってきたなどとは夢にも、思わない。戸外に出ると、なよなよとした風の左門に欲情を覚え、さあ行こうと左門の手をとる。その瞬間の、左門の抜き打ち。勘助は激怒する。斬り合いになれば、左門が敵う相手ではない。刀を飛ばされる。そこで、潜んでいた千本九郎が飛び出して助太刀に入り、勘助を討ち果たす。そして、左門は九郎の指図通りに、そのまま姿を消してしまう。
その夜を最後に、彼らは生涯、二度と会っていない。事件は左門に名誉を与え、召し抱えたいという大名家や名のある幕臣が出てくる。千本九郎の方は、主君が突然病死して、後継ぎがいなかったため、所領を幕府に没収されたことなどあり、浪人の身に。今や、大名に召し抱えられている左門は千本九郎を気遣い、知り得た彼の寄宿先に手紙などするのだが、それに九郎は応えない。左門が事件の真実を話したことにより、是非九郎を召し抱えたいという大名が現われる。時に、九郎は22歳。その彼は、如何に事件について問われようとも、毅然と、一徹に、それは左門ひとりの力で成したもので、自分は一切関わっていない、と返す。大名の取り寄せた左門の証文を見せられても、左門は気が狂ったのであろうと、否定する。 鷲見左門は延宝7年に54歳で病没したとある。6人の子を持った。その死後3年を経た天和2年の夏に千本九郎が61歳で病没。「それがしがご奉公は一代かぎり」と、彼は妻も子も持たなかった。その死に臨んでは、左門との思い出の品を、自分の遺体と共に土に埋めよと遺言する。なにか資料でもあって彼らの没年も知られているような書き方がされているけれども、他の池波作品で日付さえ入っている場合なども見て、あくまでもフィクションでのもの、と思われる感が強い。