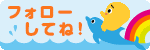☆人物紹介はこちらから→★
【前回まではこちら】
ラヴィリティア王国の空に突如姿を現した敵国ガレマール帝国の飛空艇は何者にも阻まれることなくラヴィリティアの大地へと降り立った。城に激突しなかっただけでも幸いだったが、この船に何かあればラヴィリティア王国はおろか、エオルゼアに存在する連合国等への影響は避けられないほどガレマール帝国との諍いは激化していた。そんな折に前触れもなくやってきたガレマールからの使者はためらうことなくラヴィリティア王宮へと足を踏み入れたのだった。王族の間から慌てて避難してきたこのラヴィリティア王国次期国王である王太子オーク・ラヴィリティアと第三王女のハンナ・ラヴィリティアは、オークの立太子 "宣告" をされた『玉座の謁見広間』までその身を下がらせていた。だがそこに粗雑に扉を開いてやってきたのは多くのガレマール帝国兵を従えた紅蓮色の甲冑を身に纏う無骨な騎士だった。厳しい顔付きをしながらオークは肩を抱いたままのハンナ王女の体を、自分の体に引き寄せ護るようにしてガレマール帝国騎士に声を上げた
「…何用か、ガレマールの使者殿」
「これはこれは。ラヴィリティア王国王太子オーク・ラヴィリティア様とお見受けする。本日はそこに御わす第三王女のハンナ・ラヴィリティア様をお迎えにあがりました」
「迎えとは…?」
「そこにご一緒の“総帥”から話を聞いていらっしゃいませんでしたか。我がガレマール帝国はハンナ王女の“外遊”として、王女様が何時いらっしゃるのかと再三ご連絡申し上げていたんですがね、なぁ、ハーロックさんよ」
「! …ガレマールの使者よ、それは何度も断っていた筈だ。ハンナは第一王女だ、おいそれと他国へは出向かない。それがラヴィリティアの答えだ」
「先程言いましたがハンナ様は第三王女であらせられる。第一王女でもなく、女王にもなられない。本来なら王太子と王妃セットでご招待したいところだったんですがね、こちらにも事情がありまして。お詫びに直接ハンナ様を迎えに来たという訳です」
「…」
(ハンナが第三王女だと知られている…全てお見通しか)
ガレマール帝国騎士の突然崩れた口調に違和感を覚えざるを得ずも、そこで初めてラヴィリティア国“総帥”と呼ばれるハーロック卿が押し黙った。つい先日王太子になったオークは自分の偽りの婚約者ハンナ王女の、ガレマール帝国外遊と称した拝謁行為の件はこれまで誰にも聞かされてはいない。胸に抱くハンナ王女からも戸惑いの色が伺える。恐らく総帥ハーロック卿が上手く取りなしてくれていたのだろうとオークは悟った。口を噤んでしまったハーロック卿を鼻で軽く笑い一瞥して、その騎士の男は今度はオークに言葉を向けた
「オーク殿下、結婚の儀を迎える自分の婚約者と離れたくない気持ちはお察ししますが、ご結婚されてからではなかなかガレマールにも足を運びにくくなるでしょう。ほンの僅かの間ですよ、王太子殿」
「!」
オークにそう口上しながらガレマール騎士は紅蓮色の兜をやっと剥いだ。額にはガレマール帝国人である証のビンディのようなもの『第三の目』が刻まれ、大帝国には似つかわしくない軽薄めいた金短髪をオールバックにした中年の男性の顔が現れたのだった。その男が続ける
「ガレマール帝国への付き添いは私、ネロ・トル・スカエウァがご一緒します。ガレマール帝国軍第十四軍団の幕僚長のこの私が。」
「…十四軍団、か」
ネロと名乗った男の噂はラヴィリティアにも流れてきていた。確かにガレマール帝国軍第十四軍団幕僚長の名前であった。オーク達が想像していたよりもずっと若い、それだけ有能なのだろう。その有能さ故に華々しい昇進を遂げ現在の十四軍団長に、今の地位に引き上げられたとの噂だった。この幕僚がラヴィリティアに直接足を運んだということは、ガレマール帝国が本気でハンナ王女を連れ出しにきたという残酷な出来事だった。やっとの思いで口を開いたのは、さっきから黙り込んでしまっていたハーロック卿だった
「とにかくハンナ王女がそちらに出向くことはない、ガレマールの騎士よ」
「困ったお人だな、ハーロック総帥。それは貴方の判断だけで決めることではないでしょう?貴方がそういうふうに頑なだからこうして王太子と王女に直接お話に来たンじゃないですか、どうですかお二人とも。今この最も最適なタイミングで、ガレマール帝国に足を運んで頂けますよね?」
幕僚ネロの言葉に王太子オークは奥歯を噛み締め肩を抱いたままの、ハンナ王女の肩を強く握り直してガレマール帝国使者の彼にこう言った
「ハンナ王女は行かせられない。行くならこの俺だ」
「オーク…っ!」
「ハンナ、大丈夫だ。絶対ガレマールに行かせない」
「やれやれ…王太子もそこの総帥のように頭が硬いようだ。そんンな態度ではこの先いち官僚としてやっていけませんよ?」
そうガレマール帝国幕僚長の彼は、両手を上げてオークを小馬鹿にするよう諌めた。かと思うと、幕僚ネロの雰囲気ががらりと豹変する。彼が口を開いた
「ここであまり押し問答はしていられない。頑なな保護者達は排除して王女様をエスコートすることになってしまいそうだ」
ネロがその言葉を口にした途端、後ろにか控えていたガレマール帝国兵達が腰に携えていた剣の柄に手を置いた。それに合わせてオーク達を護って取り囲んでいたラヴィリティア国王近衛部隊も剣の柄に手を当てた。ラヴィリティア国とガレマール帝国の、まさに一触即発のそのとき強く声を上げたのは当の本人ハンナ王女だった
「皆、控えよ!ガレマールの使者達もだ!私がガレマールに行こう。それでよいな?ネロ幕僚長殿」
「ハンナ…っ!」
「これはこれはハンナ王女、ご英断で。お前達、早合点だ。手を下ろせ」
剣の柄に手を当てていたガレマール帝国兵が一斉に姿勢を正す。それを見届けたオークの近衛隊長、ベルナンド・オクスフォードが近衛兵達を強く制した。ハンナ王女の発言に強く異を唱えたのはオークだった
「ハンナ、何言ってるんだっ絶対行かせないぞ!」
「今ここで闘ったら無意味に血が流れるだけだ、オーク」
「ハンナ…っ」
覚悟を決めたハンナ王女は、ガレマール帝国に今出向かなければこの場で多くの血が流れるとオークに目線だけを送り彼を説得した。オークの腕の中でハンナ王女が凛としてネロ幕僚長に告げる
「しばし夫と離れる。別れの時間は貰えるな」
「いいでしょう、だけどこの場でお願いしますよ。あまり時間もありませンので。」
「わかった」
「ハンナ、ダメだっ!!」
「オーク…」
王女の彼女を必死に止めるオークに、ハンナ王女は自身の腕をオークの首に巻き付かせた。小声でオークに耳打ちする
「オーク、私がガレマール帝国に行って時間を稼ぐ。その間に準備を整えてガレマールに来てくれ。なに、大丈夫だ、手段は強引だがあくまで国賓。無碍には扱われない。私は王族だ、いつでも覚悟は出来できていた。最近名を連ねたオーク、お前が行く必要はない。いつかこうなったのだ、城を頼む」
これはガレマール帝国の、ラヴィリティアへの完全なる人質要求行為だった。成すすべもない事態に、オークはハンナ王女の指示に従わざるを得なかった。彼女が行かなければ今この場で両国の戦の火蓋が切られる。自分の首に腕を回したハンナ王女の細い腰を抱いてオークは彼女を力いっぱい抱きしめて囁いた
「ハンナ、本当にすまない…っ、絶対に迎えに行く。だから、だから何があっても絶対に諦めないでくれ」
「わかっている、心配するなオーク」
しばらくそうして抱き合っていると、時を見計らうかのようにネロ幕僚長が言葉でふたりを遮った
「もうよろしいですか?お二人とも。ハンナ王女は丁重にお預かりしますよ、お約束します」
「わかった、行こうネロ殿」
「ハンナ…」
「行ってくる、オーク」
ハンナ王女はそう言い残して二度と振り向く事なく、ネロ幕僚長付きの小隊長達に付き添われ玉座の謁見広間を後にした。その後を追うようにオークとハーロック卿が飛空艇の見送りに出ようと広間の廊下へ出た時、後ろをゆっくり歩くネロに声をかけられた
「そういえばオーク殿下。先程ハンナ王女の御前でしたからお聞きしませんンでしたが、もう側室はお決めになられましたか?ハンナ王女とご婚約前、婚姻を結んだ者が居たようですが。確か、農民の娘だとか」
「…」
ネロ幕僚長の問いにオークの歩が止まった。オークはネロを振り返らない、ネロの問いかけにすかさず口を挟んだのは他でもないハーロック卿だった
「あれは王太子即位前の事で、王太子の身分を隠す為に“私が”行わせたものだ。その者には言い含んである、謝礼金も十分に支払った。王太子の威厳に関わる事だ、口を謹んで貰いたいガレマールの使者よ」
「私はオーク殿下に伺っているンですが?ハーロック殿」
「…思い出せない」

オークはしつこく質問を重ねる帝国幕僚長ネロに呟いた
「もう、よく思い出せない」
「…そうですか、わかりましたよ。オーク殿下」
オークはネロと一切目を合わせず、ぽつりとそう言い残してラヴィリティア城の長い廊下を進み始めた。もう思い出せないと、オークの今の心境を表すかのように本当の妻クゥクゥ・マリアージュの笑顔が彼の頭の中をぼんやりと掠めた。幸か不幸か、オークのその力ない言葉にネロは納得したようでそれ以上の追求は以降なかったのだった。
その日の夜、オークがリーダーを務めていた冒険者クランBecome someone(ビカム・サムワン)のグリダニアの冒険者居住区の詰所に、情報屋のウォルステッドという男がはラヴィリティア情報を掴んでオークの本当の妻、クゥクゥ・マリアージュに報告に来ていた。窓口の現リーダー女黒魔道士オクーベルが彼に対応した
「ウォルステッド、今日は何の情報だ?」
「はい、オクベル姐さん達に良い知らせと悪い知らせを持ってきました。良い知らせのほうからです、まずオークさんの婚約式が白紙に戻りました」
「!」
「なんだって?どういうことだウォルステッド」
「昼間ラヴィリティア国に突然ガレマール帝国の特使がやってきたそうです。その件で今ラヴィリティアは大慌てで、結婚話は一旦無くなったようです姐さん」
「結婚話が無くなったことは良かったが、なんでそんなことに…普通逆じゃないか?帝国がいきなり攻め込んできたら結婚の話は押し進めるだろうに」
「はい、そこです。なんでも“外遊”という名目で第三王女ハンナ様の身柄を拘束して自国に連れ帰ったようです。これが悪い報せです」
「なんだって…!?」
「そんなのぜんぜんいい知らせじゃない!!」
「! クゥ…」
「ウォルステッドさん、ごめんなさい…」
ウォルステッドに声を荒げたのは他でもないクゥだった。いくらハンナ王女が自分の夫オークの婚約者候補だったとしても憎んでるわけじゃない。きっと今でもオークの役に立つよう振る舞ってくれて居るのだろう。ハンナ王女のそのオークへの献身的な姿に、クゥは自分の力の無さを痛感したのだった。未だにラヴィリティア国からクゥへのヒーラー離職要請は解けない。オークの結婚話はうやむやのまま、小国の刻は残酷に進む。その成す術ない事態にクゥはだんだんと冒険者としての牙を削がれていくような気がしたのだったー。
(次回に続く)
↓読者登録をすれば更新されたら続きが読める!
ぽちっとクリックしてね♪
↓他の旅ブログを見る↓
☆X(※旧ツイッター)

☆インスタグラム
☆ブログランキングに参加中!↓↓