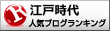まとめ読みサイトに『義公黄門仁徳録』「八幡知らず」を追加しました!
まとめ読みサイトに『義公黄門仁徳録』「八幡知らず」を追加しました!
一段目でページの切り替え、二段目でオリジナル・翻字・原文・現代語訳の画像に切り替えることができます。
これまでに紹介した作品の中で、サイトでまとめて欲しい作品がありましたら、リクエストしただけるとありがたいです。
今のところ、まだリクエストが少ないので、お応えできる確率が高いですw
解説付きで、オリジナル・翻字・原文・現代語訳を一度に切り替えて簡単に見れるようなサイトは、たぶんほぼ無かったと思うので、ぜひ、訪問、拡散、よろしくお願いしますヾ(๑╹◡╹)ノ"
せっかくなので、こちらにも、現代語訳の一気読みを載せますので、よろしければご覧くださいませヾ(๑╹◡╹)ノ"
---------------------------------
『義公黄門仁徳録《ぎこうこうもんじんとくろく》』巻二十七「下総国八幡宮藪を八幡知らずと申す事」
[江戸中後期成立か。呑産通人(呑産道人)作]
国書データベース:国文学研究資料館
---------------------------------
『義公黄門仁徳録《ぎこうこうもんじんとくろく》』巻二十七
こうして義公様[徳川光圀の諡号《しごう》(死後に付けられる尊称)]は、鐘ヶ淵《かねがふち》[東京都墨田区]に 沈んでいる釣鐘をお引き上げなさろうとしたのですが、龍神が釣鐘を引き上げられるのを 残念に思ったのか、とうとう引き上げるために釣鐘に結んでいた毛綱《けづな》まで切ってしまったので、釣鐘は引き上げず、そのまま放っておくことにし、江戸のお屋敷へ お帰りになりました。
それからまた、水戸西山へお帰りになられる際、 真間《まま》鴻《こう》の台[千葉県市川市]の辺りをお通りになって、市川までお越しになりました。 下総国八幡《しもうさのくにやわた》[千葉県市川市]にお入りになり、ここでしばらくご休憩なさいました。
この辺り一帯は人家もほとんどなく、山の中腹に八幡宮の社殿があって、 そこから左右一面に竹藪が生い茂り、ここを「八幡《やわた》の八幡《やわた》知らず」と言いました。
「八幡の八幡知らず」の由来はというと、昔、鎌倉時代に、諸国行脚《しょこくあんぎゃ》をする釈《しゃく》の浄念《じょうねん》という僧がいました。
浄念は元は大和国添上郡春日郷《やまとのくにそうのかみごおりかすがのさと》[奈良県]の生まれで、幼い時から仏道を志《こころざ》し、十八歳の時に剃髪《ていはつ》して、諸国の霊場を巡礼し、三十一歳の時に、この八幡《やわた》に来ました。
八幡宮《はちまんぐう》を伏し拝み、その頃は全く道らしい道もなく、あっちかなこっちかなと、浄念は竹藪の間を、鉦《かね》を打ち鳴らして、通り抜けようとしました。
わずか半道《はんみち》[約2キロ]ぐらいの竹藪の中を十五日もの間、浄念はあちこち歩き回り、やっと十六日目に今の行徳《ぎょうとく》と八幡の間の坂道に出ました。
この浄念は元々世捨て人[俗世間との関係を断った人]だったので、全くこれを苦にせず、十五日の間、全く食料もないのに、ただ鉦を打ち鳴らし、足の赴《おもむ》くまま歩いたのでした。
ところが、振り返ると、結局、竹藪の中の見える所からここまで、わずか直径二丁余り[約220メートル]の道のりだったので、さすがの浄念も驚き、見渡せば、竹藪の広い幅でも、わずか半道《はんみち》[約2キロ]ぐらいで、せいぜい目の届く範囲でした。
また、狭い幅は直径三丁[約330メートル]に足りないぐらいの、小さな竹藪だったのです。
「どうやっても半日以上はかかるはずがないのに、そもそも十五日もかかったのは、どういうことだ」
と、浄念は初めて異変に気づき、恐怖で体中の毛が逆立ったのでした。
とりわけ、夜中になっても、たとえ世間が闇夜であったとしても、藪の中は明るく、昼間のようでした。
しかし、夜の八《や》つ頃[午前二時頃]と思われる時になると、真っ暗闇になり、全く足元もわかりません。
しばらくして一時《いっとき》[二時間]程も経つと、また昼間のように明るくなります。
なので、この浄念は、その真っ暗闇になる時に、夜が来たと確認しながら、ただひたすら仏の名を唱えて歩き続け、このように元の場所に出たのでした。
これはとてもヘンテコな事だと思い、その辺りにあった家に立ち寄って、事の一部始終を語ると、家の主人は、
「それは、まあ、あなた様は命拾いをなされました。
昔からこの藪に入った者で、再び生きて帰った者はいません。
また、この藪に入った者で、再び藪から出ることができた者もいません。
なるほど、近頃、どこからともなく、鉦《かね》の音が聞こえたのですが、さては、あなた様でしたか。
およそ十五日ほど、鉦の鳴る音が止まなかったので、この辺りの者は不気味に思っていたのです」
と言いました。
浄念もとても驚き、
「まさしく、私が命拾いをしたのは、仏の力によるものである」
と、ますます、信心の思いを深くし、とうとう浄念はその名を天下に広く知られる僧になったのでした。
そして、その後、「ここは、『八幡の八幡知らず』である」と名付けたのでした。
さて、義公様はこのことを思い出しになられ、お側近くに仕える家臣たちに、
「この辺りは、あの八幡知らずという所である。
ワシはこの八幡知らずに入って、その奥がどうなっているか見定めたいと思う。
お前たちは、ここに留まって、ワシが帰るのを待っていなさい」
とおっしゃいました。
家臣たちはあっけにとられて、みんな目と目を見合わせて、しばらくご返答を申す者もいなかったのですが、松平主膳《まつだいらしゅぜん》と林田舎人《はやしだとねり》が、口をそろえて、
「なるほど、君《きみ》[黄門様]がおっしゃることは、ごもっともでございます。
しかしながら、昔から人の入る事を禁じていた所へ、大切なお体でお入りになられ、もしものことがあったとしたら、我々は、お屋敷の方へ申し上げる言葉もありません。
ひとまず、お入りになるのはお止め下さいませ。
どうしても、この奥を見定めになられたいとお思いでしたら、建久《けんきゅう》[正しくは建仁《けんにん》。鎌倉時代]に仁田忠常《にったただつね》が、将軍[源頼家]の命によって、富士の人穴《ひとあな》に入った例もありますので、どうぞ我々に仰せ付けください。
たとえ、忠常にはかなわないとしても、君のご威光を頭に戴き、この藪の奥を必ず見定めると、我々は胸の内で決めております」
と何度も申し上げました。
しかし、義公様は、全く納得なさらず、
「そなたたちが申す事は、家来の身としては、当然のことである。
だが、昔から人が入る事を許さない場所へ、大事な家臣を遣わすわけにはいかない。
あの仁田忠常は、入るのが禁止されている富士の人穴へ、将軍の仰せによって、命を掛けて入り、とうとうを命を落としてしまったが、このようなことがあってはならない。
惜しくも大事な武士を、無駄なことで落命させたのは、将軍の過失である。
なので、ワシは家臣を召し連れず、従三位中納言《じゅさんみちゅうなごん》の威光で、たとえ化け物であっても、いとも簡単に正体を暴いてみせよう。
なにしろここも日本の中である。天下の副大将軍のワシが、今この藪の奥を見定めることを、誰もとがめることなどできぬ。
惜しくも家臣を失うより、ワシが直々に藪に入り、化け物に会ったならば説得して、もし、化け物が説得に応じなかったら、ここを焼き尽くし、怪しい物を取り払おう。
天下において、正法《しょうぼう》[仏教の正しい教え]に、不思議があるはずがない」
と、おっしゃって、全くご家臣の説得に応じようとしなかったので、ご家臣たちは誰もがあきれはてて、全くお言葉を返す者もいませんでした。
こういうわけで、義公様は着物の裾《すそ》を高く端折《はしょ》り、大小の刀の柄袋をお取りになって、たいそう静かに藪の中にお入りになりました。
お側にお仕えするご家臣たちは、誰もが義公様の後についていこうとしましたが、義公様は厳しくお叱りになったので、誰もどうしようもなく、その場に控《ひか》えるのでした。
それから義公様は、だんだん藪の奥深くにお入りになり、ご家臣たちは義公様のお後ろ姿を見守っていました。
すると、一町余り[約110メートル]ほどお入りになられるまでは、義公様の後ろ姿が見えたのですが、それからは全くお姿が見えなくなってしまいました。
ご家臣たちは皆、「どうなされたのだ」と、気が気でなく、義公様の言いつけを守り、その場に控えてはいたものの、
「たとえ、お𠮟りを受けても、このまま放っておくわけにはいかない。
我々は義公様の後を追って、ご様子を見届けなければ、家臣としての道が立たない」
と皆で話し合い、全員が「その通り」と同意して、藪の中に入りました。
しかし、巡り巡って、元の場所に戻ってきてしまいました。
「これはどうしたことだ」と、また、藪の中に入りましたが、巡り巡って、元の場所に戻ってきてしまいました。
これが四回続いたので、ご家臣たちは皆、目と目を見合わせ、呆然《ぼうぜん》とするばかりでした。
ご家臣たちは、
「どうしようもないので、このまま義公様のお帰りを待つしかない」
と拳を握りしめて悔しがり、藪を睨みつけて控えるしかありませんでした。
こうして、義公様は、段々藪の中を奥深くお入りになり、四、五丁[約五〇〇メートル]ほどお進みになったところで、大きな池が道を塞《ふさ》いで、全くどこにも進めなくなってしまいました。
仕方ないので、しばらくその場にお佇《たたず》みになられ、「どうしたものか」とお思いになられていると、この池の水が次第に向こうの方へ引いて行くので、これに付いて行って少しずつお進みになられると、とうとう池の水は一滴もなくなり、残らずどこに行ったか分からなくなりました。
しかし、義公様は少しも動揺なさらず、先にお進みになられましたが、急に空全体が暗くなって、たった今まで昼間だったのが、真っ暗闇になりました。
全く物が何色なのかも分からなくなりましたが、義公様は、物事に動じない元々のご性分なので、お足がおもむくままに、お進みなりました。
すると、暗くてはっきりとは分からないのですが、直径が一丈ぐらい[約3メートル]あると思われる洞穴のような穴がありました。
世の中の普通の人なら、これを恐れて引き返すのでしょうが、義公様は恐れず、おどおどもせず、その穴の中にお入りになりました。
義公様は、一間《いっけん》ぐらい[約2メートル]進んだと思われる所で、深さが三、四丈ぐらい[約10メートル]あると思われる、穴の底に落ちてしまわれました。
しばらく、気を失っていらっしゃいましたが、二時《ふたとき》ぐらい[約4時間]経ったと思われる頃、やっとお気づきになられて、お心の中で、
「さてさて、これは深い洞穴である。
その上、闇夜なので、全く物が何色かすら分からず、これはとても困ったものだ。
しかしながら、ここまで来たにもかかわらず、諦めてそのまま引き返し、この奥を見届けないなどということは、決してあってはならない。
たとえ化け物の仕業であっても、従三位《じゅさんみ》の官位の威光で通行すれば、恐れる事はなにもない」
と一人でつぶやきになり、お足がおもむくままに、少しずつお進みになると、だいたい十町余り[約1キロ]もお歩きになった所で、穴の中は進める道がどこにもなくなってしまいました。
そういうわけで、義公様は、しばらく岩に腰をお掛けになって、お休みになりました。
八方をご覧になると、左の方に杉がたくさん生い茂り、木の間から、見えるか見えないぐらいかすかに、灯明が確認できました。
「まさしく、ここが八幡知らずの化け物の棲《す》み家だろう」
と義公様はお思いになり、杉の茂みをあちらこちらとお歩きになりました。
ここからは、全く道と言うものが無く、蔓草《つるくさ》に手をおかけになられたり、木の根をよじ登りになられたり、冷たい水の流れをお渡りになられたりしました。
熊笹《くまざさ》が何重にも生い茂るので、足をお痛めになり、実に苦しい思いをなされ、やっとのことで少し広い所にお出になりました。
前方を見ると、古びた社《やしろ》がありました。
鳥居は朽ちて笠木[上部に渡した横木]も傾き、屋根は荒れ果てて草が生い茂り、たいそうひっそりと静まり返り、いかにも年を経た様子に見えました。
何の社という標《しるし》も無く、社殿の中にかすかに灯明が掲げられていました。
この灯明は先ほど、木の間からかすかに確認したものでしょう。
こうして、義公様は荒れて朽ちた社殿に草鞋《わらじ》のままお上りになり、よくよくご覧になると、「正八幡《しょうはちまん》」と記した、いかにも古びた、文字がやっとのことで読める額がありました。
八幡神は源氏の守り神なので[徳川家は源氏の流れという]、ここで義公様は社殿にひざまづかれ、しばらく拝まれました。
義公様が横をご覧になると、人の死体が山のように積み上げられていました。
中にはまだ生々しい死体、白骨となった死体などがたくさんあり、手足を引き抜かれたような死体、首の無い死体もありました。
その臭いことといったら、たとえようがありませんでした。
義公様もその臭いがとてつもないので、鼻を覆《おお》いになられてあちこちをご覧になると、女子の死体ばかりが積み重なっている所もありました。
また、正面の社殿の前には、長さがだいたい一尺二、三寸ぐらい[約35~40センチ]あると思われる剣が飾られ、「征夷将軍万代不易《せいいしょうぐんばんだいふえき》[征夷大将軍の威光は永遠に続く]」という八文字が書かれた大きな額がかけられ、左右には供えられてからそれほど時間が経っていないように見えるお供え物がありました。
義公様は、「あまりにも不思議だ」とお思いになったので、供えられた餅を手にお取りになってお調べになると、柔らかくてたった今、供えられたようでした。
義公様はますます不思議にお思いになり、社殿の扉が開きかかっていたので、容赦なく引き開けになられると、中には白髪の老人が目を閉じてお経を唱えていました。
義公様は声をおかけになり、
「お前は何者だ。
こんな所で一人、何をしておるのだ。
きっと化け物に違いない。
天下に住む者は全て、時の将軍のご威光に従い、その恩恵を得ているというのに、誰の目も届かないこんな洞穴の奥に住居を構えるとは、一体、どういうことだ。
今の天下の副将軍、水戸従三位《じゅさんみ》、前《さき》の中納言光圀《みつくに》がここへ来たというのに、社殿で一人眼を閉じているとは、ワシに対して無礼な奴だ。
さあ、まずすぐに姓名を名乗るのだ。
ここにある死骸の境遇もきっと知っているだろう。
一つ一つこの黄門に語り聞かせるのだ。
承知しないのなら、刀でバッサリと斬って命を絶ってやろう。
さあ、返答なされ」
とおっしゃい、刀の柄《つか》に手をおかけになりました。
例の老人は、少しも動じず、お経を読み終わり、しばらくしてから目を開き、
「黄門よ、そんなに気性を荒くなさるな。
最初からお前がここに来ることは、とっくに知っておった。
ここは元々、天でも地でもなく、中有《ちゅうう》[死んでから次の生を受けるまでの間]でもなく、世界[人や生物が住む全ての時間(過去・現在・未来)と空間(東西南北上下)]でもない。
ここは空空寂寂《くうくうじゃくじゃく》の世界[実体がなく思慮分別を超えた世界]と言って、「如来一切《によらいいっさい》、自在神力《じざいじんりき》[如来(仏)の全ての自由自在な神力を、私(釈迦)はこの経で説く]、如我昔所願《にょがしゃくしょがん》、今者已満足《こんじゃいまんぞく》[人々を私(釈迦)と同じ境地に至らしめるという昔の願いは、今はもう満足に叶った]」と法華経の一節にあるように、「我不愛身命《がふあいしんみょう》、天下太平《てんかたいへい》」を祈る[命を惜しまず、平和を祈る]場所である。
よって、この場所を「無上道《むじょうどう》」[最高の悟り]と言う。生きている者で、この場所に来ることは難しい。
ただ、この場所に来たいと思うなら、法華経の功徳《くどく》の力に頼るしかない。
ああ、お前は天下の賢人[徳のある人]であるから、ここに来れた。
ワシはまさしく天帝[最高神]に、人々の善悪を報告する者である。
ここを住み家として、毎日のように天に上る事、八百六十三回。
これ以上ワシを怪しいと思うのなら、たとえ黄門であろうとも、ワシの力をはっきりと思い知らせてやろう。
早くこの場所を立ち去るのだ」
と言いながら、両手を伸ばして義公様を捕まえ、目の位置より高く持ち上げました。
義公様も持ち上げられながら、刀をお抜きになり、「無礼な奴め!」とおっしゃいながら、切り付けになると、老人は義公様を持ち上げたまま投げつけました。
すると、そのまま義公様は元の藪の中にお立ちになっていました。
風の音だけがこだまのように残り、時間もそれほど経ってはいないようでした。
四方を見渡しになられましたが、ただ一面の藪で、少しも変ったことはありませんでした。
ここで初めて義公様はハッとお気づきになられて、
「この藪は八百万《やおよろず》の神[多くの神々]がお住みになる、神の森である。
以降、人の出入りは完全禁制にしなければ」
とお思いになり、藪の外にお出になりました。
御家臣の面々も、とてもお喜びになりました。
義公様のお顔の色が、青ざめてらっしゃったので、御家臣の面々は、すぐに薬を調達し、ご気分をお尋ねになると、義公様は、「全く問題ない」とおっしゃったので、御家臣の面々は安心しました。
それから、ここに立ち入り禁制の高札を立てられ、
「なるほど、八幡《やわた》に住んでいても、この藪の中がどうなっているか、誰も知らなかったので、まさしくここは『八幡知らず』という名がピッタリだな」
とおっしゃられ、西山[茨城県常陸太田市。光圀が隠居生活をした場所]にお帰りになりました。
『義公黄門仁徳録』巻二十七終
![]()
---------------------------------
 この蚊の目玉が目に入らぬか!
この蚊の目玉が目に入らぬか!![]() ヾ(๑╹◡╹)ノ"
ヾ(๑╹◡╹)ノ" 目に入るだろうけど、入れたくないよ
目に入るだろうけど、入れたくないよ![]() ヾ(๑╹◡╹)ノ"
ヾ(๑╹◡╹)ノ"
---------------------------------
※諸事情により、このアカウントで、はてなブックマークに伺うことができなくなりました。ご了承ください。
---------------------------------
 ランキング参加してます、よろしくね♪
ランキング参加してます、よろしくね♪
---------------------------------
 姉妹ブログもよろしくね♪ヾ(๑╹◡╹)ノ"
姉妹ブログもよろしくね♪ヾ(๑╹◡╹)ノ"
myougirl.hatenablog.com
kihimikeheme.hatenablog.com
---------------------------------
三つ目のLINEスタンプ、不好評発売中!
store.line.me
---------------------------------
◆北見花芽のほしい物リストです♪
5月3日は北見花芽の誕生日ヾ(๑╹◡╹)ノ"
◆拍手で応援していただけたら嬉しいです♪
(はてなIDをお持ちでない方でも押せますし、コメントもできます)
---------------------------------
---------------------------------