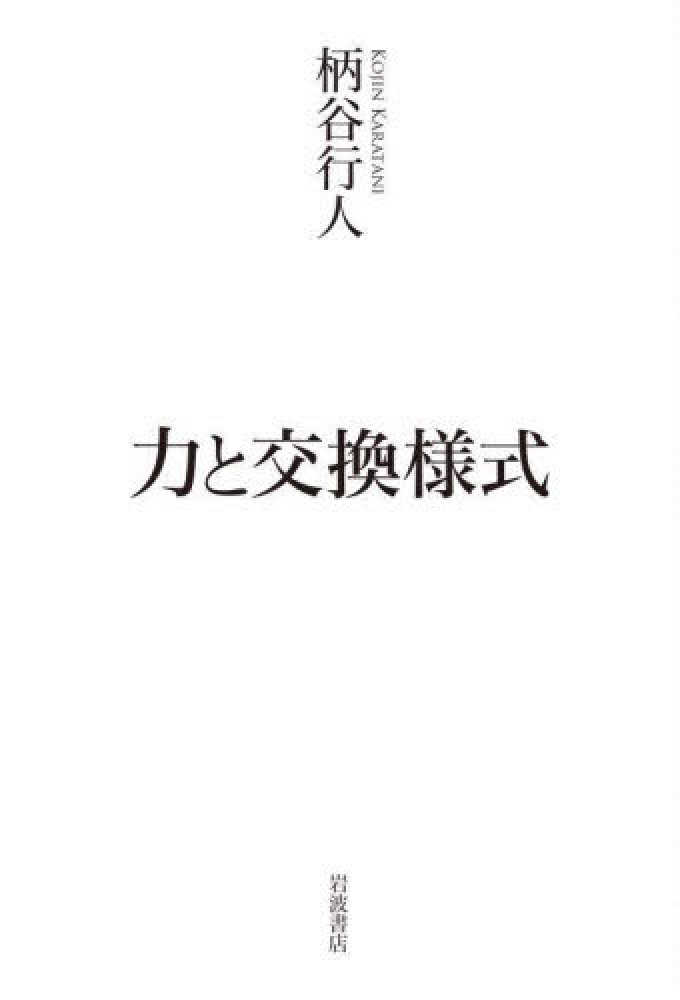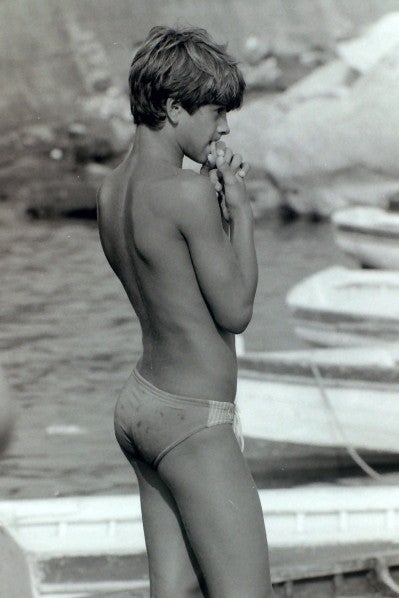レビ人への神判。 モーセとアロンの祭司権に異議を唱えたコラ,ダタン,
アビラムとその一族は、生きながら冥府(ゲヘナ)に落とされた。〔民数記16〕
【21】 ワルター・ベンヤミン――
「神話的暴力」と「神的暴力」
法治国家の法措定的暴力と法維持的暴力――これらの「管理された」飼いならされた暴力の根底にも、「神話的な暴力」が、そのおどろおどろしい姿をかいま見せています。この「神話的な暴力」に対してベンヤミンが持ち出すのは、「神的な暴力」です。こうして、
神話―権力―「法の措定」―国家法―処罰 という系列の傍らに、
神―正義―「法の脱措定(解体)」―災禍―贖罪 という別系列が想定されます。
ギリシャ神話に淵源をもつ「神話的な暴力」に対して、「神的な暴力」の範例は『旧約聖書』に求められます。しかし、荒野彷徨時代のユダヤ人〔「イスラエルの民」〕が経験した・この神判の伝説は、ギリシャ神話よりはるかに難しく理解しがたい内容なのです。
『直接的暴力の神話的宣言は、それが、もっとも深いところではすべての法的暴力と同じものであることを示しており、法的暴力の漠とした問題性を、その歴史的機能の腐敗性として明確にする。したがって、その〔ギトン註――法的暴力の歴史的腐敗の〕根絶(Vernichtung)が課題となる。この課題こそまさに、神話的暴力に停止(Einhalt)を命じうるような・純粋な直接的暴力はないものだろうか、という問いを、最終審においていまいちど提起するものである。
すべての領域で神話に神が対立するように、神話的暴力に神的暴力が対立する。しかも、その対立は、あらゆる点に表われる。神話的暴力が法措定的であるとすれば、神的暴力は法破壊的(rechtsvernichtend)である。前者が境界を設定するなら、後者は限度なく破壊する。神話的暴力が罪を負うと同時に贖 あがな う(sühnend)のにたいし、神的暴力は罪を祓い清める(entsühnend)。前者が脅迫的なら、後者は衝撃的で、前者が流血的なら、後者は無血的やりかたで致命的結果をもたらす。
〔ギトン註――神話的暴力の典型である〕ニオベ伝説にたいして、後者〔神的暴力――ギトン註〕の暴力の実例となるのは、コラの徒党への神の裁き〔『旧約聖書』民数記16章――ギトン註〕であろう。神の裁きは、特権者であるレヴィ人 びと たちを襲うが、予告なく彼らを襲う。脅迫も無く、かつ衝撃的であり、〔ギトン註――特権者を〕絶滅する(Vernichtung)までとどまることがない。しかしながら、この裁きは、まさに絶滅することにおいて罪を取り去って(entsühnend)もいるのだ。この暴力の無血的性格と滅罪的性格とのあいだの深い連関は、見まがいようがない。というのは、血とは、肉体の生命(das bloße Leben たんなる生命)の象徴だからだ。法的暴力の解消(Auflösung)は、いまや〔…〕肉体的な自然的生命の負罪へも遡及する。その負罪は、罪なく不運な生者(der Lebende)を、贖罪の手にゆだねる;贖罪は、彼の負った罪を《贖う》。――罪ある者を滅罪するとは言っても、罪からではなく、法からである。というのは、肉体の生命が終るのと同時に、生者に対する法の支配も止むからだ。神話的な暴力は、たんなる生命(das bloße Leben)に対する血の暴力であり、暴力自身のための暴力である。神的暴力は、全生命に対する純粋な暴力であり、生き生きと生きる者(der Lebendige)のために振るわれる。前者は犠牲を要求し、後者は犠牲を受け入れる(nimmt ... an)。』
ベンヤミン,野村修・訳「暴力批判論」, in:ders.『暴力批判論・他10篇』,1994,岩波文庫,pp.58-60.
コラと 250人の「選ばれた司」が結集し、モーセのリーダーシップに抗議する。
【22】 ワルター・ベンヤミン――
『民数記』「コラの反逆」
『民数記』16章に記された伝説は、「コラの反逆」などと呼ばれています。
イスラエルの民は、モーセに導かれて、奴隷的境遇におかれていたエジプトを脱出し、先祖が暮らしていた「カナン」の地をめざして砂漠と荒野をさまようのですが、このモーセという人は、ユダヤ人ではなかったという説もあるほどで〔エジプト王族の私生児説など〕、かならずしもイスラエルの民に信頼されていません。
エジプト脱出の時からモーセを補佐していたアロン〔口下手なモーセに代ってファラオと交渉するなど〕は、「レヴィ人 びと」というイスラエルの祭司の家系のひとりで、荒野彷徨の時代には、アロンの一族が最高位に立って、ヤハヴェ神の祭祀をつかさどります。
レヴィ人のなかで、アロンの一族だけが祭祀職を独占しています。コラもまたレヴィ人のひとりなのですが、アロンの第3子の監督のもとで「契約の箱」〔神が「十戒」を刻んだ石板が入っている〕を運搬するなどの下働きをさせられていました。儀式を取り行なったり、神に捧げものをしたりといった祭司の仕事は、アロン一族以外の者には許されなかったのです。神と直接対話する能力は、モーセとアロンだけが持っていました。
そこで、コラがモーセとアロンに不満を抱くのは自然な成り行きで、あるときコラの仲間たちは、「アロン一族の祭祀職独占は不当だ」と、モーセに集団で抗議します。
『彼らは集まって、モーセとアロンとに逆らって言った、「あなたがたは、分を越えています。全会衆は、ことごとく聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、どうしてあなたがたは、主の会衆の上に立つのですか」』〔民数記16:3〕
コラに加勢したのが、ダタンとアビラムで、彼らは、「豊かな別天地カナンに連れてゆくとモーセに言われてエジプトを出たが、何十年たっても砂漠をさまようだけだ。エジプトのほうがまだ良かった。これでは約束が違う」と言って抗議します。しかしこれは、イスラエルの民全体が抱いていた不満で、ダタンとアビラムは、たまたまコラのテントのすぐ隣にテントを設けていたので、不満分子の代表となったにすぎません。そして、「イスラエルの……会衆のうちから選ばれて司 つかさ となった・名のある人びと」250人がコラとともに抗議しました。〔16:2〕
モーセは「ひれ伏して」神のお告げを受けると、あす、神みずから「聖なる者」(祭司)を選ばれるであろう、と、抗議の人びとに告げます。
「コラの徒党」と向かい合うモーセ,アロン。
しかし、250人の「つかさ」とコラは、「会見の幕屋」〔ヤハヴェ神の礼拝所〕の入口に集まり、モーセ,アロンとともに、そこに立ちます。コラは、モーセとアロンを人数で圧倒しようと、さらにおおぜいの会衆を集結させます。モーセはダタンとアビラムを呼びにやりますが、ダタンとアビラムは、モーセには従えないと言って出頭を拒否しました。〔16:12-14〕
「会見の幕屋」の入口に集まった会衆を、「主の栄光」〔神罰や奇跡が起こる予兆〕が包みます。神は、「わたしは、この会衆をただちに滅ぼすであろう」とモーセとアロンに告げますが、モーセがひれ伏して取りなしたので、それは断念し、コラ,ダタン,アビラムとその一族を、彼らのテントごと、地下の冥府に落とします。
『彼らと、彼らに属するものは、皆生きながら冥府に下り、地はその上を閉じふさいで、彼らは会衆のうちから、断ち滅ぼされた。』〔民数記16:33〕
つづいて、「主のもとから〔幕屋から?〕火が出て」、250人の「つかさ」を焼き滅ぼしました。
翌日、2万人以上の「イスラエルの会衆」がモーセとアロンのもとに集まって、「あなたがたは主の民を刹した」と言って抗議します。すると、「会見の幕屋」を雲がおおい、「主の栄光」が現れて、「わたしはただちに彼らを滅ぼす」という主の声をモーセは聞きます。同時に、抗議の会衆は「疫病」で次々に倒れていきます。モーセはアロンに、会衆のなかで薫香を焚 た いて、彼らの罪の「あがない」をするよう命じます。アロンが「薫香をたいて、民のために罪のあがないをし、すでに死んだ者と、なお生きている者との間に立つと、疫病はやんだ。この疫病によって死んだ者は一万四千七百人であった。」〔民数記16:47-49〕
こうして、冥府に落とされたコラ,ダタン,アビラム一族数十人、焼き滅ぼされたイスラエルの「つかさ」250人、翌日の抗議衆のうち 1万4700人、合計 1万5000人が犠牲となった。
そのうえでヤハヴェ神は、前日に予告したとおり、アロンの枯れ枝の杖から芽を出させる奇跡を起こして、アロンを祭司に選ぶ決定を改めて示したのです。〔民数記17:1-8〕
以上が、「コラの反逆」伝説の筋書きですが、ここに描かれた神判と神罰は衝撃的なものです。
天幕の入口に出てきたダタンとアビラムの子供たちまでが、地割れによって冥府に落とされます。神の判定を受けようと集まった 250人の長老たちは、全員が焼き尽くされます。抗議の群衆のうち、ランダムに 1万4700人が疫病で死亡します。↑上でベンヤミンが言うように、彼らは「罪なく不運な」犠牲者なのです。
しかし、このように理不尽なものであればこそ、「神的な暴力」は「法」を措定しない、むしろそれを破壊する力をもつのです。
爆発して噴煙を上げる福島第一原発3号機(2011年3月14日)
=福島中央テレビ提供=読売新聞オンライン
「神的な暴力」の例として、現代の私たちにも理解しやすいのは、自然災害ではないでしょうか?「3・11」は、科学万能を誤信した人間に対する天の警告だった、という言い方も可能なのかもしれません。しかし、そこで犠牲となったのは、「罪なく不運」としか言いようのない人びとです。日本じゅうの原発を同等の災害が襲えば、おそらく国家も「法」も、それらの法措定的・維持的「暴力」も、すべてが亡び去ることでしょう。
しかし、そうやって何もかも破壊されて亡びることが「正義」なのか?!
この点は、↑上の引用文でベンヤミンが、
『肉体的な自然的生命〔…〕の負罪は、罪なく不運な生者(der Lebende)を、贖罪の手にゆだねる;贖罪は、彼の負った罪を《贖う》。〔…〕神的暴力は、全生命に対する純粋な暴力であり、生き生きと生きる者(der Lebendige)のために振るわれる。前者〔神話的暴力〕は犠牲を要求し、後者〔神的暴力〕は犠牲を受け入れる。』
と言っていることに関係します。この「犠牲」とか「贖罪(償 つぐな い)」というのが、非キリスト教圏の私たちには、たいへん解りにくい。
【23】 『新約聖書』で考えてみる
例を替えてみましょう。『新約聖書』で「贖罪」の代表例といえば、イエスの処刑、キリストの「十字架上のタヒ」による「贖い」でしょう。イエスは、「十字架上のタヒ」によって全人類の罪を贖ったとされます。
ところが、そのイエスは、十字架の上で、
「エリ エリ レマ サバフタニ」(わが神、わが神、なぜ私を見捨てたのですか)
と叫んだのです〔マタイ27:46〕。つまり、十字架の上で人としてタヒぬことを、イエスは予想していなかった。全能の神と一体であるはずの自分が、みじめな一人の人間として苦しみ、息絶えるとは。。。。「十字架上のタヒ」という「神の暴力」は、イエスにとっても予想外で衝撃的なことだったのです。
神から見離された衝撃は、イエスに、何を考えさせたでしょうか? 「正義」とはいったい何なのか? 自分が今まで考えていた「正義」は、はたして「正義」だったのか? そういう限界的な疑いではなかったでしょうか?
「神的暴力」つまり「贖罪」ということを、倫理・心理の言葉に翻訳すると、そういうことになるのではないでしょうか? つまり、「神的暴力」は、「法」とその「暴力」をいったん壊滅させて、「法」以前の「正義」を返りみる機会を人間に与えるのです。
ローザ・ルクセンブルクとカール・リープクネヒトを追悼する人びと
【24】 ローザ・ルクセンブルク――
「スパルタクス団の蜂起」
ーーさらに、 ベンヤミンが、「神的暴力は犠牲を受け入れる」と述べている点について、考えてみましょう。「神的暴力」の場合、「贖罪」は神が要求するのではなく、人間の側からなされるのです。
『民数記』でも、モーセとアロンは、神が全会衆に「絶滅」的な暴力を下そうとするたびに、ひれ伏して祈ったり、薫香を焚いたりして、人びとの罪をあがない、犠牲の範囲を可能な限り小さくしようとしました。
ここで参照したいのは、第1次大戦後の「ドイツ革命」――ベンヤミンが『暴力批判論』を書く直前――のなかで起きた「スパルタクス団の蜂起」と呼ばれている事件です。
『1918年11月3日のキール軍港での水平反乱を機に、革命が起こり、同月9日にドイツ社民党(SPD)のシャイデマンは「ドイツ共和国」の成立を、他方、〔ギトン註――「スパルタクス団」の〕カール・リープクネヒトは「ドイツ社会主義共和国」の成立を宣言する。翌10日に皇帝ヴィルヘルム2世がオランダに亡命。シャイデマン〔…〕ら社民党主流派は、〔…〕評議会 レーテ 勢力〔ロシアの「ソヴィエト」にあたる労働者執権組織――ギトン註〕の封じ込めに着手する。〔…〕
〔ギトン註――「スパルタクス団」の〕ローザ・ルクセンブルクは〔1919年〕1月15日、カール・リープクネヒトとともに虐刹される。〔…〕社民党主流派が、これに「冷ややかに満足した」ことは事実である。この刹害につづいて、国民議会選挙阻止を訴える共産党(KPD)勢力が武力で制圧される。』
市野川容孝「暴力批判試論」 in:『現代思想』33巻12号,2005年11月,青土社,p.225.
ローザ・ルクセンブルクは、大戦中、反戦・平和運動をする恐れがあったことから、保安処分として収監され、各地の監獄を転々とたらい回しにされていました。終戦とともに 18年11月10日釈放され、「スパルタクス団」の一員として同年12月末の「ドイツ共産党」創設に加わっています。
しかし、ローザは、共産党内の多数派だった議会主義否定路線には同調せず、SPD政権が行なう国民議会選挙についても、ボイコットするのでなく、それを批判する見地からも候補を立てて闘うべきだと主張したのです。
最終的に彼女の主張は、共産党内で支持を得られませんでした。が、ローザは、「革命」後の社会主義国家においても、言論・出版の自由と議会政治は必須の要素であり、社会主義党の官僚独裁によって社会主義を建設することはできないとして、レーニン,トロツキーとボルシェヴィキ派を批判したのです。
『文字通り血なまぐさいこうした情勢の中で、1919年1月19日に国民議会選挙が実施され、〔ギトン註――社民党主流の〕エーベルトが大統領に、シャイデマンが首相となる。同年8月11日にはワイマール憲法が採択される。
〔…〕若きベンヤミンは『暴力批判論』を、こうした動向をつぶさに見つめながら書いたのである。』
a.a.O.
ドイツ革命: 1918年9月9日、ベルリン、ウンター・デン・リンデン通り
をデモする人びと。Foto: Deutsches Bundesarchiv.
Bild 183-18594-0045 / CC-BY-SA 3.0.
1919年1月5日にベルリンで起きた大規模なデモは、自然発生的な労働者蜂起に発展し、ベルリン各地の公共施設が評議会 レーテ 勢力に占拠されました。翌5日には一部企業で労働者がゼネストに入ります。
この蜂起は自然発生的なもので、「スパルタクス団」も当初はそれに反対し、ローザ・ルクセンブルクは蜂起勢を激しく非難して中止を呼びかけたほどでした。ところが、エーベルトの SPD政府が「フライコール」を送って武力鎮圧を始めると、ローザら「スパルタクス団」は一転して蜂起側に加わり、武力抵抗を開始したのです。
「フライコール」は、大戦に従軍したドイツ帝国軍将兵からなる義勇軍で、SPD政府のもとで、レーテ勢力と共産主義者を憎悪し、その鎮圧の役割を買って出た部隊です。
さらに、これと並行して、奇妙な現象が始まりました。蜂起勢は、施設の占拠と工場ストライキを越える行動に出ることはなく、かえって潮が退くように解散を始めたのです。結果として、この蜂起は、「フライコール」による武力攻撃と、それに対抗する「スパルタクス団」の戦いという様相を呈してきました。こうして、蜂起は最初から「スパルタクス団」が起こしたように誤解され、「スパルタクス団の蜂起」と呼ばれるようになったのです。
はじめは爆発的に立ち上がった民衆が、緒戦の成果を見ただけで、たちまち醒めたように武器を捨てて家に帰ってしまうという現象は、覚えておられるでしょうか。「ドイツ農民戦争」でもしばしば見られた事態でした。いつでも帰る「故郷(ハイマート)」がある――というのが、ドイツの民衆の心性の特質なのかもしれません。
1月15日、ローザとリープクネヒトは数百人の同志とともに逮捕され、「フライコール」部隊員らによって惨刹され、遺体は川に捨てられました。(⇒ wiki「ローザ・ルクセンブルク」)
つまり、武装蜂起は自然発生的なものだったのに、マスコミはそれを「スパルタクス団の蜂起」として報じ、世人もそう誤解した。ところが、形勢が変って鎮圧側が優勢になり、蜂起勢が危機に瀕すると、ローザらはあえて、その誤解と “冤罪” とを受け入れ、“罪” を引き受けて、生命を投げうって抵抗しました。つまり、もっとも不利な局面で矢面に立ち、犠牲を引き受け、みずからの生命をもって「革命」を贖ったのです。
Hans Thoma: "Faun im Wald".
【25】 ワルター・ベンヤミン――
「正義」を開く「神的暴力」の贖い
『ベンヤミンは『暴力批判論』において、法を措定する暴力〔…〕維持する暴力〔…〕に、「神的暴力」なるものを対置し、それは「法を否定する」と述べた。
神的暴力、あるいは根源的な暴力〔たとえば「正当防衛」――ギトン註〕は、生命を肯定するために、より正確には新しい形で肯定するために、〔…〕既存の「法」〔…〕を否定するだろう。それは事実だ。ならば、その否定は、「法」そのもの〔…〕の否定を、つまりは純粋な無法状態、無権利状態の出来を意味するのか。そうではない。
神的暴力は、「正義」を否定するのではなく、それを(新たに)設定するのである。さらに、それは「法」を全否定するわけではない。そうではなく、〔…〕「権力」によって常にすでに措定されている法――すなわち法律――から私たちを解放しつつ、正義とは何か、またそれに照らしたときのあるべき法/権利とは何かという問いを、私たちにたえず再開させるのである。〔…〕それは、法/権利の否定とは微妙に、しかし決定的に異なることだ。
神的暴力は、神話的暴力によって措定された既存の法秩序を否定しながら、その外部に、正義と法/権利の新たな可能性を開く。しかし、その〔…〕いまだなき正義と法/権利に至る道筋は〔…〕既存の法秩序の内側から、「実在するもの」から紡ぎ出されなければならないのである。言い換えるなら、正義に至る道は常に、法の内破によってしか与えられないのである。〔…〕
正義とは、私たちが求めていくもの、そしてその希求は終りのないものだ。完全に現実化されることがないから、正義を求めたりしない、というのはまちがっている。ちょうど、もう正義に至っているので、あとはその体制を強化すべく適切に武装することのみだと信じているのと同じくらい、それはまちがっている。〔ジュディス・バトラー,竹村和子・訳「自分の生と名に、いかに最後に応えるか」, in:『現代思想』2004年12月,pp.80-84.〕』
市野川容孝「暴力批判試論」 in:『現代思想』33巻12号,2005年11月,青土社,pp.223-224,236.
ベンヤミンの多義的な言い方を透視して読むならば、「神的な暴力」が開く可能性とは、既存の「法」と「暴力」の秩序をいったん否定し、そこから「法」を救出し新たに蘇らせることです。「正義」は、既存の法秩序の外側に、できあがった架空のものとして、どこかから与えられるわけではない。それは、どこまでも現実の法秩序の「解体」と「再生」の繰り返しによって築かれてゆくほかはない。ベンヤミンの議論が導く先は、そのように言い換えることができるでしょう。
しかし、それにしても、「神的な暴力」が「生命を肯定するために〔…〕既存の法を否定する」とは、どういうことでしょうか?
『この神的な暴力は、宗教上の伝承によってのみ存在を証されるわけではない。むしろ、現代生活においても、少なくともある聖化された宣言において見られるものである。完成された形の教育的な暴力として法の外に立つものは、その現象形態の一つである。これら〔ギトン註――現代における・神的暴力の現象形態〕は、神自らが奇跡として行なうかどうかではなく、無血的・衝撃的・滅罪的な・刑の執行という・かの諸契機〔「神的暴力」の特徴――ギトン註〕によって、究極的には、いかなる法措定も無いことによって、定義されるのである。
そのかぎりで、この暴力を破壊的(vernichtend)と呼ぶこともできるかもしれない;しかし、神的暴力が破壊的であるのは、ただ相対的に、財産、権利、生命、及びその種のものにかんしてである。絶対的に生き生きと生きる者(der Lebendige)の心(Seele たましい)にかんして破壊的であることは、決してないのである。』
野村修・訳「暴力批判論」, in:『暴力批判論・他10篇』,岩波文庫,p.60.
「法の外に立つ・完成された形の教育的な暴力」が何を指すのかは、よくわかりません。学校教育のようなものではないことは、たしかでしょう。人びとに厳しい教訓を与える自然災害かもしれないし、世界大戦や暴動,革命のようなものかもしれません。
【26】 ローザ・ルクセンブルク――
「何物にも妨げられぬ自由」が「正義」を生む
『存在(Dasein)は、正義をそなえた存在よりも尊い、という命題は、そこで云う存在が、たんなる生命以上のものを意味しないなら、〔…〕誤りであり下劣である。けれども、この命題は、有無を言わさぬ真理をも含んでいる。もし、存在(生命、と言うほうがよい)が、〔…〕「人間」という揺るぎない集合態(Aggregatzustand)※を意味するのであれば。もし、この命題が、正義をそなえた人間がまだ存在しないこと(絶対に:単にまだ、である)よりも、人間そのものが存在しないことのほうが、より忌まわしい、と言おうとするのであれば。』
「暴力批判論」, in:『暴力批判論・他10篇』,岩波文庫,p.62.
註※「集合態,凝集態 Aggregatzustand」: この語は通常は物質の三相(固体,液体,気体)を意味するが、ここでは、各個ばらばらな個人ではなく、社会という凝集態を形づくっている人間たちということ。
『正義があって、その後に人間が存在するのではない。そうではなく、人間から正義が生成するのである。〔…〕あくまで人間から出発して、正義をその後に紡ぎ出さなければならないのである。あるいは、正義から始めて人間を選別してはならないのであり、まず人間を、すべての人間を存在せしめた上で、そこから正義を作り上げなければならないのである。すべての人間を存在せしめる、すべての人間を「生き生きとした者 der Lebendige」にする、つまり、すべての人間に生命の息吹を与えるという意味において、〔…〕「生命の尊さ」という命題は、〔…〕「有無を言わさぬ真理」を有するのである。』
市野川容孝「法/権利の救出――ベンヤミン再読」 in:『現代思想』34巻7号,2006年6月,青土社,p.133.
これを別の言い方でいえば、カントが『永久平和のために』で述べているような、「自分とは異なる法/権利を有する他者を承認し、受け入れるという意味でのリベラリズムである。」
『「生命の尊さという命題」に、右の意味で正しさを認める際に、ベンヤミンは一つの条件を絶対不可欠のものとして付けている。すなわち、正義をそなえた人間は「単にまだ存在しないだけ」なのであって、正義とそれをそなえた人間は、やがて必ず到来する、到来することができるという信念である。〔…〕正義への信念こそが、個々に断片化され、互いに隔絶した生命を、再び相互に繋ぎとめる要 かなめ にほかならないからである。〔…〕
ベンヤミンが正義と人間の関係を、人間がまず存在すべきなのであって、正義はその後に紡ぎ出されるという形で定式化するとき、〔…〕彼が導入しているのは、人間の複数性、より正確には法/権利について異なる考えをもつ人間の複数性を承認するリベラリズムであり、この導入は、神的暴力の第1の課題である、法/権利の脱措定の遂行と同義である。
しかし他方には、法/権利の救出という第2の課題がある〔…〕――ローザ・ルクセンブルクが提示したものにほかならないが――異なる考えをもつ人の自由を認めつつ、その他者に反射させながら、自らを正し、また他者を正しながら、一つの共有されるべき正義を希求し続けるものである。これを、積極的で力強いリベラリズムと呼ぶことにしよう。ベンヤミンが、神的暴力の中に導入するリベラリズムは、後者である。』
市野川容孝「法/権利の救出――ベンヤミン再読」 in:『現代思想』34巻7号,2006年6月,青土社,pp.133-134.
そこで、ローザ・ルクセンブルクからも引用しておきましょう:
『自由は、つねに、思想を異にする者の自由である。それは、「正義」への狂信のゆえではなく、政治的自由がわれわれを教え、われわれを正し、われわれを浄める力、それがすべてこの本質にかかっているゆえであって、万一、「自由」が私有財産になれば、その働きは失われるのだ。〔…〕
なにものにも妨げられることなく泡立つ生命のみが、何千もの新しい形式や即興を思いつかせ、創造的な力を維持しながら、あらゆる失策を自力で正していくのである。制限された自由しかない国家の公共生活は、民主主義を締め出すことで、すべての精神的な豊かさや進歩の、生き生きとした源泉を断ち切ってしまう〔…〕全人民大衆がそれ〔国家の公共生活――ギトン註〕に参加せねばならない。そうでなかったら、社会主義は1ダースのインテリによって上から命令され、強制されることになるであろう。
レーニンとトロツキーは、万人の選挙によって生まれる代表機関=議会ではなく、ソヴィエト〔労農評議会。公選制を欠く民主集中制の機関――ギトン註〕が労働者大衆の唯一真実の代表機関であると称している。けれども、〔…〕万人による選挙、なにものにも妨げられぬ出版および集会の自由、自由な論争、そういうものがなければ、あらゆる公共的制度における生活は亡び、偽りの生活になり、官僚制だけが制度の活動的要素として残ることになる。〔…〕20~30人の政党指導者〔…〕じっさいにはそのなかの1ダースばかりの卓越した人たちが指導して、労働者のエリートは、時おり会議に召集されて、指導者の演説に拍手を送り、提出された決議に満場一致で賛成することになる。要するに、派閥政治になる。〔…〕こういう状態は、暗殺とか人質の射殺とか、公共生活の野蛮化を生まないではいないだろう。』
清水幾太郎・訳『ロシア革命論』 in:『ローザ・ルクセンブルク選集』4,1969,現代思潮新社,pp.256-258. [一部、市野川訳による]
レーニンは、「官僚制」を「民主主義」に優越させ、議会を否定して「ソヴィエト」による集権体制を築き上げました。しかしローザは、これに対して、いっさいの制限を廃した自由な言論、選挙と議会を通じた大衆の自由な政治活動なくしては、積極的な「力強いリベラリズム」は発揮されず、いかなる失策も偏見も正されない寡頭支配の迷路に陥ってしまうと警告しているのです。
ひと握りの指導者たちが、これが「正義」だと決めて、選ばれた忠誠分子を通じて全大衆に信奉させる。このような体制は「正義」とは程遠い。欲望本位の神話的「法的」暴力の支配する野蛮な世界でしかないのです。ローザの具体的叙述は、ソ連「社会主義」体制のその後の事態を正確に予言していて、恐ろしくなるほどです。
『暴力批判論は、暴力の歴史の哲学である。この歴史の・「哲学」であるのは、暴力の〔ギトン註――歴史的〕結末(Ausgang)という理念のみが、そのときどきの暴力的な事実にたいする批判的・弁別的・かつ決定的な態度を可能にするからだ。〔…〕
法維持の暴力は、かならずその持続の過程で、敵対する対抗暴力を抑圧することを通じて、自己が代表する法措定の(rechtsetzend)暴力をも、間接的に自ら弱めてしまう。このことは、あらたな暴力、または、まえに抑圧された暴力が、従来の法措定の暴力に打ち勝ち、新たな法を創設し、それがまた新たな没落へと向かう時まで、つづく。神話的な・法の諸形態に縛られたこの循環を打破する時にこそ、すなわち、法を、それと依存しあう諸暴力もろともに脱措定(Entsetzung)する時に、つまり国家暴力を脱措定する時に、新しい歴史時代が創建されるのだ。
もしも今すでに、神話の支配があちこちで破れてきているのだとすれば、かの新しきもの〔「法と諸暴力」の脱措定後の世界――ギトン註〕は、それほど・想像もできないほどの彼方に遠ざかっているわけではない。法にさからう言葉というものが、ことごとく疲れ切って自滅してしまうほど遙かな遠方ではない、と言えるのだ。とはいえ、もしも〔ギトン註――その「脱措定」後の〕法の彼岸においてさえ、暴力というものが、純粋な直接的なものとしてその存在を保証されるのだとしたら、そこから証明されるのは、革命的暴力は可能だということ、また、いかにして可能かということ、そして、純粋な暴力の最高の顕現は、人間たちによってどんな名で〔ギトン註――その至高性を〕裏づけられるべきか(zu belegen)、ということである。
とはいえ、いつ、具体的なケース(Fall)において、純粋な暴力〔神的暴力――ギトン註〕が実現されたか、見定めることは、人間にとってすぐにできることではないし、すぐにしなければならないわけでもない。なぜなら、それとしてはっきりと認識できるのは、神的な暴力ではなく、神話的な暴力だけだからだ。神的な暴力は、比較を絶する作用をおこなった場合にかぎって、例外的に認識されうる。それというのも、〔ギトン註――神的な〕暴力の滅罪的な力は、人間の眼には隠されているからである。
純粋な神的暴力の前には、神話が法と野合して産んだ(bastardierte)あらゆる永遠の諸形態が、あらためて随意の用に供されている。神的暴力は、真の戦争の形で現れることもできるし、まったく同様に、犯罪者〔安倍晋三のような――ギトン註〕に対する大衆の・神の裁きにおいて現れることもできる。しかし、斥 しりぞ けられるべきは、すべての神話的暴力であり、法を措定する暴力である:それは、取り仕切る(shaltend)暴力と云ってもよい。斥けられるべきはまた、法措定的暴力に仕える・法維持的な・管理された暴力である。〔ギトン註――この2つとは対照的に、〕神的暴力は、聖なる執行の宝剣であり証印であって、けっして手段などではなく、それは〔ギトン註――自然法則の支配と同様の〕治 しろしめ す(waltend)暴力と呼ばれるべきものである。』
「暴力批判論」, in:『暴力批判論・他10篇』,岩波文庫,pp.63-65.
これが↑、ベンヤミンのこの論文の結論部分ですが、なお読み取りがたい不可解な部分も残るかと思います。
しかし、ベンヤミンに関してはここで区切りとし、次回は柄谷氏に戻って、ブロッホとフロイトの精神分析との関係を論じます。
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!