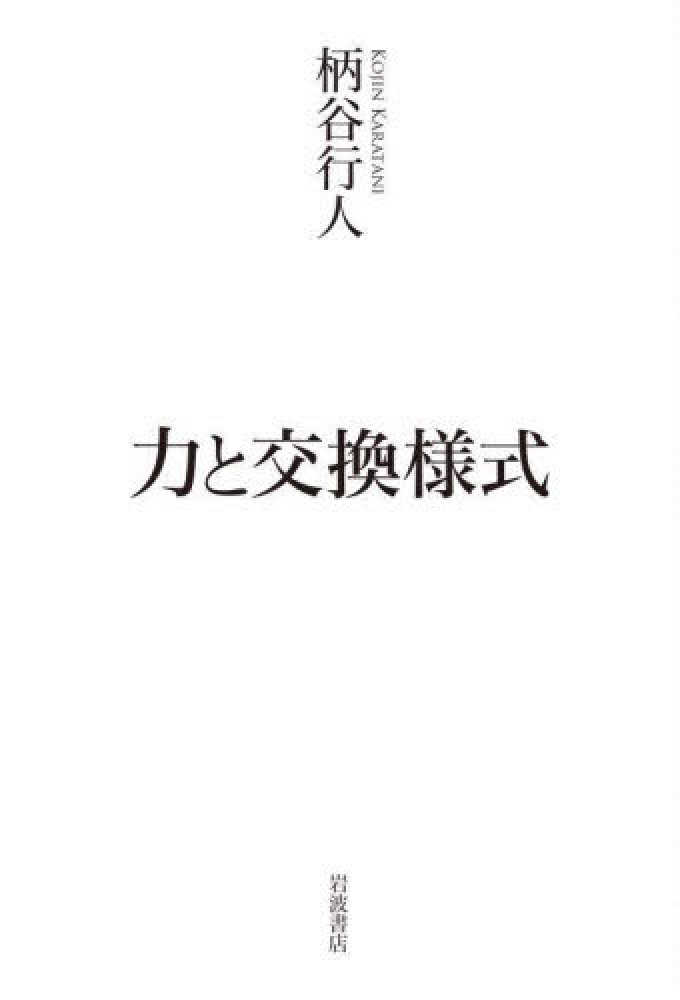仏西国境のスペイン側ポルボウにあるワルター・ベンヤミンの墓石。
1940年、ベンヤミンは、ヨーロッパのユダヤ人迫害から逃れてアメリカに
渡ろうとしたが、スペインへの不法越境に成功した直後、この地で
自タヒした。遺体は共同墓地で失踪しており、他刹説もある。
【17】 ブロッホとベンヤミン
『ブロッホがマルクス主義(史的唯物論)とキリスト教神学を結びつけたことは確かである。彼は次のように述べた。《無神論者のみがよきキリスト教徒たりうる。キリスト教徒のみがよき無神論者たりうる》〔竹内豊治・他訳『キリスト教の中の無神論』,上巻,1975,法政大学出版局.〕彼がめざしたのは、マルクス主義の刷新であった。〔…〕
実際、神学者ユルゲン・モルトマンが『希望の神学』〔1964年〕』で『いう「希望の神学」とは、神が「約束」した「神の国」という未来を信じ、そこへと向かう信仰である。このような希望によって生かされている者だけが、「変革」をもたらしうる。〔…〕それは内面のみでなく、具体的にこの世界の変革と創造に向けられる。
しかし、ブロッホはこのように、事実上「神学」を考慮に入れながらも、そこには向かわなかった。あくまで「希望」を、社会主義あるいは無神論の上で考えたのである。とはいえ、彼が言わんとすることは曖昧(両義的)なままにとどまった。
その点では、ブロッホと親しかったベンヤミンについても、同様のことが言えるだろう。
たとえば彼は、『暴力批判論』〔1921年〕で、「神話的暴力」と「神的暴力」を区別して、つぎのように述べた。《非難されるべきものは、いっさいの神話的暴力、法措定の――支配の、といってもよい――暴力である》〔野村修・訳,岩波文庫,p.64.〕このような区別は、ジョルジュ・ソレルが『暴力論』〔1908年〕で、国家による力を force とし、それに対抗する力を violence と呼んだことに基いている。ベンヤミンの場合、神話的暴力が force であり、神的暴力は violence である。彼はいう。神話的暴力からの解放は、神的暴力なしにはありない。そうすると、国家や資本は「神話的暴力」であり、共産主義は「神話的暴力」である、ということになる。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,pp.383-384.
ベンヤミンの『暴力批判論』について、柄谷さんの説明はたいへんわかりやすいのですが、キルケゴールの場合、ブロッホの場合と同様に、それはあくまでも説明のための図式です。「彼はいう。神話的暴力〔国家による力 force〕からの解放は、神的暴力〔国家に対抗する力 violence〕なしにはありない。」と聞くと、そうか、ベンヤミンは暴力革命を絶賛してるんだな。レーニン万歳! ってわけだ、などと誤解する人が出てくるかもしれませんね。
もちろん、そんなことはありません。それでは『暴力批判論』にはならないからです。暴力を国家が行使するか、誰かが国家に対して行使するか、その向きだけで質的違いが生じる――などというのは、むかし新左翼過激派が言いふらしたアホ論理にすぎない。誰が使おうと、暴力は暴力だ。――ベンヤミンもまた、この基本的な常識観念に立脚しています。
それでは、「暴力」のなかから、質的に違う2つのものを、どのようにして区別するのか?‥‥
この論文を書いた 1921年、ベンヤミンは 29歳でした。その前々年に、《ドイツ革命》が鎮圧されています。前に出した↓この写真をもう一度見ておきましょう。
ドイツ革命(第1次大戦後) 共産主義者を処刑するドイツ共和国軍
この写真の右側にいる兵士が行使している「法」を執行する「暴力」と、左側の少年が、おそらく例えば政府庁舎を占拠するさいに振るっただろう「法」に刃向かう「暴力」と、どこが違うのか? ‥誰が? という点を除外しても区別できるような質の違いが、両者の間にないだろうか? ‥単に強い、弱い、といった物理的なことでなく、社会的な、あるいは人間社会の成り立ちにかかわるような大きな種別が、そこに見出せないだろうか?
若きベンヤミンが、この論文で追究したのは、そのことだったのです。
【18】 ベンヤミン『暴力批判論』
↑上で柄谷さんが引用している箇所は、ベンヤミンの論文のおしまいのほうにあるのですが、その前後を広く切り取って見てみると、「支配」という訳語の適切さをふくめて、大きな疑問にとらえられます。「神話的暴力」対「神的暴力」という種別の意味も、前者が「国家による暴力」で、後者が「それに対抗する暴力」であるというような・単純なことではないように思えてきます。
たとえば、ベンヤミンが「神的暴力」の典型として例示している『旧約聖書・民数記』の「コラの反逆」の箇所〔民数記16章〕を見ても、イスラエルの会衆の上に立つ・モーセとアロンに対してコラたちが反逆したので、ヤハヴェ神が罰を下してコラの一族を亡ぼした、という筋書きなのです。「神的暴力」は国家に叛逆する暴力だ、などという単純なことは、とうてい言えません。むしろ逆に見えます。
もうひとつ、大きな問題は、この論文の日本語訳として現在入手しうるものが、野村修氏訳1種類しかなく、その適切さが疑われることです。野村氏の訳が悪いというのではありません。それしかないことが問題なのです。
ベンヤミンの文章は、多義的なドイツ語で書かれていることがしばしば指摘されます。同じ文章が、いくつかの意味に取れることが珍しくない。ベンヤミン自身が、多義的に書くことを意識して書いているように思われるのです。市野川容孝氏によれば、ベンヤミンの論文は、多義的な筋のそれぞれが対等の旋律をなす「フーガ」のようなものです(市野川容孝「[暴力批判論]のフーガ」 in:『ベンヤミン 救済とアクチュアリティ』,2006,河出書房新社,pp.168-171.)。
しかし、ベンヤミンのそのような多義性は、通常は意識されず、ベンヤミンといえば、徹底したアナーキズムとして読まれることが多いと言えます。この論文も、国家の暴力、法の暴力を全否定する見地で読まれているようで、野村訳も、そのような見地を前面に出しています。いきおい、これは翻訳なのか、それとも訳者の主張なのか、と疑わざるをえない箇所も散見するのです。
『『暴力批判論』というテクストは、対位法に支えられたフーガのようなもので、そこでは複数の旋律が独自性を保ちつつ、互いに重なり合って響いている。どの旋律も、確かに一貫性を有している。「法/権利」の「否定」や「廃止」という視点だけで、このテクストを読み貫くこともできるだろう。しかし、それは旋律の一つにすぎず、それだけではテクストが奏でる旋律の全体を聞き落とすことになる。法/権利の新たな可能性の模索、法/権利の救出というポジティヴな旋律を重ね合わせるべきなのだ。〔…〕
私が『暴力批判論』において、あらためて問題にしたいのは、議会制民主主義なのだ。これを(法/権利と同様)単に破壊するのがベンヤミンの考えなのか。私はそうは思わない。〔…〕
議会主義の否定が新たな「神話」を生み、そこからファシズムという暴力が誕生する。その現場をベンヤミンは目撃した。「神的」暴力をそこから救出するためには、議会制民主主義そのものを救出する必要があったのだと私は思う。』
市野川容孝「[暴力批判論]のフーガ」 in:『ベンヤミン 救済とアクチュアリティ』,2006,河出書房新社,pp.169-171.
そういうわけで、前節で見た柄谷氏の紹介も、野村氏の訳も、うのみにしないで、まずは『暴力批判論』――幸いに、長い論文ではありません――を最初から読んでいきたいと思います。
なお、このような次第ですから、以下での『暴力批判論』の訳文は、私なりに原書を参照して、かなり手を入れています。
Max Liebermann "The Jewish Quarter in Amsterdam" 1906.
National Gallery of Art
【19】 国家の「暴力」――
「法措定的」暴力と「法維持的」暴力
『暴力批判論の課題は、暴力と、法および正義との関係を描くことだ、と言ってよいだろう。』
ベンヤミン,野村修・訳「暴力批判論」, in:ders.『暴力批判論・他10篇』,1994,岩波文庫,p.29.
国家――すくなくとも近代の国家は、「法」による支配を統治の原理とする一方、「法」の支配を実効化する手段として、軍隊、警察、刑吏などの「暴力」装置を備えています。しかし、近代国家の「暴力」は、つねに「法」の忠実な執行者なのかというと、これには大きな疑問が付きまといます。「暴力」は、それが振るわれることによって「敵」の圧服に成功したときには、新たな「法」を定立しているのではないか? むしろ、国家がそれまで目的としてきた「法」とは無関係に、新たな「法」の定立を目的として「暴力」が現出する場合もあるのではないか? 大きくは戦争やクーデター、小さい出来事としては、警察の恣意的な規制や逮捕が、例として浮かびます。
ともあれ、近代国家の「暴力」が実効性あるものとなるためには、国家による「暴力」の独占が必須の条件となります。国家の「暴力」が最大の効果を発揮するためには、私人の「暴力」は徹底して禁止されなければならない。私人にたいする「暴力」の禁止が徹底すればするほど、国家による「暴力」の行使は最小限ですむようになり、法秩序の平和的維持が可能になる。いちおうは、そう考えられます。前近代社会では許されていた「報復」「仇討ち」「決闘」などの暴力が徹底して禁圧されたのも、そうした理想に基くものだったとされます。
そうすると、近代国家が私人から「暴力」を奪い取り、「暴力」を独占するのは、平和な社会の維持、自由・平等をめざす国家の政策実現といった・「法」の掲げる理想的な目的のための手段である。いわば必要悪である。そう言えるでしょうか? ベンヤミンはこれに大きな疑問符を投げかけます:
『個々人』を排除して『暴力を独占しようとする・法の利害関心は、法の目的を護ろうとする意図からではなく、むしろ、法そのものを護ろうとする意図から説明される。法の手中にはない暴力は、それが追求するかもしれぬ目的によってではなく、法の外にあること自体によって、法にとって脅威なのである。
こういった推測は、つぎのことを考えれば、もっと劇的な説得力をもつのではないか。〔ギトン註――歴史上の〕「大」犯罪者の人物像は、彼の目的が反感を惹き起した場合でも、しばしば民衆の秘かな讃嘆を呼んできた。そうした讃嘆は、彼の行為に対してではなく、行為が証拠立てる暴力〔「法」の暴力支配を嘲うほどの「法」外の暴力があったという事実――ギトン註〕に対してこそ可能なのである。その場合、現行の法が個々人のあらゆる行動領域から奪い去ろうとしている暴力が、おどろおどろしくも現実に登場し、法に反逆する・大衆の共感を、ひそかにそそるのである。』
ベンヤミン「暴力批判論」, in:『暴力批判論・他10篇』,p.35.
日本の歴史を振り返っても、「平将門」という人がいます。彼は、「石川五右衛門」や「鼠小僧治郎吉」のような義賊ではありません。自分の親族と次々に戦って刹害しただけでなく、その際には敵の支配下にある民を容赦なく刹戮し、家々を焼き払い、田畑を蹂躙して荒廃させました。「将門の乱」のせいで、その後1世紀以上にわたって東国の地は荒れ果てたと言われるほどです。
にもかかわらず、将門を讃える伝説や民衆説話は数多く、関東には将門を祀る多くの神社があります。これはひとえに、将門が天皇を中心とする「法」秩序の外に権力を打ち立てたことによります。他の有力者と違って、彼は朝廷から位階を与えられたことがなく、にもかかわらず天皇と並ぶ「新皇」を自ら名乗って支配したのです。
Walter Benjamin und der "Angelus Novus" von Paul Klee (1920).
『今次の戦争〔第1次世界大戦――ギトン註〕で、軍事暴力に対する批判が、暴力一般に対する情熱的な批判の出発点となった。それは一方では、もはや暴力は、素朴に行使も受忍もされないことを教えた。が、そのとき暴力は、法を措定するものとしてのみ批判の対象となったのではなかった。むしろ、暴力は、もうひとつの機能〔法維持的機能――ギトン註〕においてこそより破壊的であると断罪されたのだ。
ミリタリズム〔軍国主義――ギトン註〕は、一般兵役義務〔国民皆兵――ギトン註〕を通じてはじめて形成されえたのであるが、暴力の機能の二重性〔法措定的機能と法維持的機能――ギトン註〕こそ、まさにミリタリズムにおいて特徴的な』暴力の性質『なのである。ミリタリズムとは、国家の〔ギトン註――追求する〕目的のための手段として、暴力を全面的に使用することの強制である※。この・暴力使用の強制〔たとえば、徴兵された兵士に武器を使用させること――ギトン註〕は、さいきん、暴力の使用そのものと同等の、いやそれ以上の力点をおいて断罪された。そこでは暴力は、その単純な・自然目的の使用〔酔っぱらいの喧嘩のような――ギトン註〕とはまったく異なる機能を発揮する。〔ギトン註――国家による〕暴力の強制は、法的諸目的のための手段として暴力を使用することに存する。というのは、市民たちを法律――この場合は一般兵役法――の下に服従させることもまた、ひとつの法目的だからである。かの・法の第1の機能を法措定的と呼ぶならば、この第2の機能は、法維持的と呼んでよい。
兵役義務は、法維持的機能の〔…〕1適用ケースなのだから、これに対する真に有効な批判は、〔…〕あらゆる法的暴力に対する批判、すなわち、合法的ないし執行的暴力に対する批判であるほかない。それ以下のプログラムでは遂行できないのである。その批判は、〔…〕子供っぽいアナーキズムを唱えるのでもないかぎり、人格に対する強制はすべて拒否する、「気に入ることは、してよいことだ」などと宣言すれば、批判したことになるわけではないのである。』
ベンヤミン「暴力批判論」, in:『暴力批判論・他10篇』,pp.40-41.
註※「ミリタリズム」: 「軍国主義」とは、軍事力の強化が国民生活の中で最高の地位を占め、政治・経済・文化・教育などすべての生活領域をこれに従属させようとする思想や社会体制(デジタル大辞泉)
国家の「暴力」の第1の機能は、「法」を「措定(setzen)」すること(法措定的 rechtsetzende 機能)です。国家が暴力を振るうと、国家の支配を受ける人びとは、そういうこと(暴力で罰せられた民の行為)は、してはいけないんだな、と感得します。こうして不文法や慣習ができ、全体としての国家の「法」が成立します。
近代国家は、最初にいきなり暴力を振るって感得させるのではなく、成文法を公布して予告したうえで、違反があれば「暴力」を発動するという方式をとります。しかし、その場合でも、すでにそれ以前から、国家の「法」に反すれば「暴力」が発動されたことを人びとが知っているからこそ、つまり、「暴力」じたいに法を措定する機能があるからこそ、成文法という紙っぺらの公布が強制力をもつのです。
これに対して、国家の「暴力」には、すでに成立している「法」(法秩序)を維持する機能(法維持的機能)もあります。たとえば警察,検察,裁判所といった司法機関は、「法維持的機能」を専門にしているように見えます。でもそれはタテマエにすぎません。裁判所は、しばしば「判例法」という法を定立します。警察は、――とくにベンヤミンの時代のドイツや日本の警察は――法律に規定のないことでも、独自に市民に命令を発して規制することがあります。のみならず、個々の警官が、法律を無視しておこなう「暴力」も、それが批判されず繰り返されるならば、市民はそれに従うようになり、ここに新たな「法」が措定されます。
近代国家は、「法措定的暴力」と「法維持的暴力」の分離をタテマエとしていますが、じっさいには、それらはしばしば混用されます。ベンヤミンは、そこに大きな問題があると言うのです。
ベンヤミン『一方通行路』の表紙
他方、ベンヤミンの見るところでは、「軍国主義」の特性は、「国民が、暴力をふるうことを強制される」ことにあります。近代「法」と「法の支配」体制の要めは、国民から一切の暴力を奪い去って、国家が暴力を独占することにありました。この「暴力の奪取」と「暴力行使の強要」は、一見すると矛盾するかのようですが、後者は前者の歴史的発展なのです。というより、「暴力行使の強要」に発展してはじめて、近代「法」体制の暴力支配は完成するのです。
豊臣秀吉の「刀狩り」や徳川幕藩体制のようなものは、農・工・商の民から兵役を奪い、暴力を純然と禁止するがゆえに、近代国家ではありません。
『個々の法律(Gesetze)や法的慣習を保護しているものは、じじつ法(Recht)の権力(Macht)であって、この権力は、ただひとつの運命(Schicksal)だけがあること〔…〕を、その実質としている(darin besteht)のだ。法維持的暴力は、脅迫的な暴力であって、しかもその脅迫は、〔…〕警告の意味をもたない。〔…〕警告には確実性が付随するはずであるが、確実性は、脅迫とは矛盾するし、確実な法律などありえないからだ。
法律には、法律の腕を逃れる希望があるが、法律は、それによっていよいよ、運命と同様に〔不確実であり、その結果――ギトン註〕脅迫的であることを露わにする。犯罪者が法律に引っかかるかどうかは、運命しだいなのだ。〔…〕暴力が、運命の冠をかぶった暴力が、法の根源だとすれば、暴力が生死をこえて法秩序のなかに姿を表す最高の形態〔ギトン註――である死刑執行〕において、法秩序の根源が代表的に実体化し、そこに怖るべきすがたを顕わしているのだ、との推論は、的はずれなものではない。〔…〕じじつ、死刑の意義は、法への違反を罰することではなく、新たな法を打ち立てることにある。というのも、生死をこえる暴力の実行によって、法はみずからを、ほかのどんな法執行にもまして強化するからだ。しかし、まさにそこ〔死刑という最高の法的暴力――ギトン註〕にこそ、〔…〕法における何か腐ったものが感じられる。運命が、そのような執行において、固有の尊厳をまとって顕現するような諸関係が、』
ベンヤミン「暴力批判論」, in:『暴力批判論・他10篇』,pp.42-43.
ベンヤミンの云う「運命」とは、ギリシャ悲劇で「英雄」や「人間」たちを襲う神々の「神話的暴力」です。それが、国家の「法的暴力」の起源だと彼は考えるのです。神々は、これこれのことをしてはいけない、などという法律を公布したりはしません。人間が気に入らないことをすれば、いきなり「暴力」を行使して処罰を下します。しかし、その結果として、そういうことをしてはいけないのだ、ということが「神話」という形で子孫たちに伝えられ、ひとつの「法」が形成されます。
これが、「神話的暴力」による「法の措定」であり、国家の「法的暴力」の起源です。しかし、ベンヤミンによれば、こうして国家の「法」体制が成立し、「暴力」は「法」のしくみのなかで機能するようになった後も、「神話的暴力」は潜在的に存続するのです。国家の「暴力」には、「神話的暴力」の・無定形な・おどろおどろしい性質が付きまといます。それは、現代国家にまで尾を曳いています。
ジャック=ルイ・ダヴィド「ニオベの子供たちを襲うアポロンとアルテミス」1772
『この2種類の暴力〔法措定的暴力と法維持的暴力――ギトン註〕は、死刑におけるよりももっと不自然に結合して、いわばオバケめいた混合態となって、近代国家の別の1制度である警察のなかに現存している。警察はたしかに、法的諸目的のための暴力(処分権を持つ)だが、同時に、広範囲にわたって法的目的を自ら設定する権限(命令権)を持っている。こういう官庁の非道さは、〔…〕この官庁の中では法措定的機能と法維持的機能の分離が無くされていることから来ている。〔…〕警察の暴力は法を措定する、――じっさい、警察の特質的機能は、法律の公布ではなく、法的効力をもつ・ありとあらゆる命令の発布(Erlaß)であるが、――それでも、それは法の措定である。なぜなら、警察暴力は、それら〔ギトン註――法の〕諸目的を、自分の意のままにしているからだ。警察暴力の〔ギトン註――追求する〕目的は、他の法〔機関、国家機関――ギトン註〕のそれと常に一致しているとか、すくなくとも結合している、などといった見解は、まったくの大嘘である。そうではなくて、警察の定める「法」〔などという本来あってはならない存在――ギトン註〕が根底において指し示しているのは、国家が、〔…〕なんとしてでも達成したいと望む自らの経験的諸目的〔ギトン註――の実現〕を、もはや法秩序によっては保証しえなくなっているということなのである。
それゆえに警察は、「保安のため」と称して、明瞭な法的局面が存在しない無数のケースに介入する。』具体的には:『法の諸目的と関係が無いとはいえないなどと称して、市民生活のすみずみまで命令によって規制する・粗暴なやり方で、市民を煩 わずら わし、付きまとい、あるいは、とことん監視する。』つまり、警察の暴力というものは、一定の時と所をふまえた「法」のような・はっきりした実体をもたないがゆえに、批判が困難なのである。『警察の暴力の無定形さは、警察制度そのものと同様であって、警察とは、文明国家の生活の・どこにでも顔を出すオバケのような・どうにも把えがたい現象なのである。〔…〕警察の精神は、かつて絶対君主制において〔…〕支配者の暴力を代表していた時には、今日ほど破壊的ではなかった。民主制の諸国家においては、警察の存在は〔…〕考える限りで最も歪んだ暴力の証示となっている。これは、誤認されえないことである。』
ベンヤミン「暴力批判論」, in:『暴力批判論・他10篇』,pp.43-45.
「ニオベの泣き岩」 スピル山、トルコ。 ギリシャ神話でニオベが姿を
変えられたとされる岩。古代ギリシャ時代からニオベの岩とされてきた。
【20】 国家「暴力」の起源と「抵抗権」の根拠
――「神話的暴力」と「神的暴力」
ここでベンヤミンは、国家の「暴力」の起源と本質を尋ねてギリシャ神話にさかのぼります。ベンヤミンが「神話的暴力」の典型的表現と見るのは、「ニオベ伝説」です。
ニオベは、リュディア王タンタロスと、巨人アトラスの娘ディオネの間に生まれた半神半人の女性で、テーバイ王アンピオンと結婚して多くの子宝に恵まれました。ニオベは、レト女神の前で、子が多いことを自慢しただけでなく、レトの子であるアポロン神とアルテミス女神の姿をばかにして、自分の子供たちのほうが優れていると吹聴しました。
怒ったレト女神は、アポロンとアルテミスに命じて、ニオベの子供たちを皆刹しにさせた。ニオベは嘆き悲しんで故郷のリュディア(現・トルコ西部)に帰ったが、なお悲しみに耐えられず、シピュロス山でみずから神々に願って石に変えられた。石になっても、彼女は涙を流しつづけた。――という話です。
この・ニオベに下された劫罰によって、神々を侮辱してはならないという「法」が定立され、それを人びとに記憶させるために、神々はニオベを岩にして、永遠の標石として打ち建てたのです。
『神話的な暴力は、その原型的な形態においては、神々のたんなる宣言である。その目的の手段ではなく、その意志の表明でさえなくて、まず第一にその〔ギトン註――神々の〕存在の宣言である。ニオベ伝説は、これの顕著な一例をふくんでいる。たしかにアポロンとアルテミスの行為は、ただの処罰に見えるかもしれないが、彼らの暴力は、ある既成の法の違反を罰しているというより、ひとつの法を設定しているのだ。ニオベの不遜が禍 わざわい を招くのは、それが法に違反しているからではなく、運命に対して闘争を挑んだからである。〔ギトン註――神々は、人間から喧嘩を売られた以上、〕その闘争において運命は勝たなければならないし、勝利によって初めてひとつの法が明るみに出されるのだ。〔…〕
暴力は、不確定で曖昧な運命の領域からニオベにふりかかる。この暴力は、ほんらい破壊的ではない。それはニオベの子らに血みどろのタヒをもたらすが、母の生命には手を触れない。ただし、〔ギトン註――神々は、〕この生命を、子らの最期によってさらに罪深くなった者、黙して永遠に罪を負う者として、〔ギトン註――ニオベを〕人間と神々とのあいだの境界標として残すのだ。
もし、神話的宣言としてのこの直接的な暴力が、法措定の暴力の最近親だと、いや、同一物だと証明されるならば、問題は〔…〕法措定の暴力へ跳ね返る。同時に、このつながりは、あらゆる場合に法的暴力の根底に存する運命というものへ、より多くの光を投げかけ、法的暴力の批判を大幅に進展させる〔…〕。
なるほど法の措定は、法として設定するものを目的とし、暴力を手段として、自らの目的の実現に努める。しかし、その目的とされたものが法として設定された瞬間に、法措定は暴力を解雇するどころか、いよいよもって厳密な意味で〔…〕法措定的暴力にしてしまう。〔ギトン註――というのは、〕法措定は、必然的・内的に暴力と結びついた目的を、法として、権力(Macht)の名のもとに設定するのだからである。法の措定(Rechtsetzung)とは権力の設置(Machtsetzung)であり、そのかぎりで、暴力を直接的に宣言する儀式である。正義は、あらゆる神的な目的設定の原理であるが、権力は、あらゆる神話的な法措定の原理である。
この後者の原理は、国家法に適用されて、重大きわまる結果を生んでいる。』
ベンヤミン「暴力批判論」, in:『暴力批判論・他10篇』,pp.55-57.
ここでベンヤミンが俎上にのぼらせているのは、「神話的暴力」と「神的暴力」、「法」と「正義」の関係です。私たちは、「法」は「正義」に叶うものでなければならないと思っています。国家の「暴力」は、「法」を通じて「正義」とつながるものであればこそ正当化される……――
しかし、現実の人類の歴史は、けっしてそのようなものではなかったことを、私たちはベンヤミンとともに見てきました。国家の「法的」暴力の起源は「神話的暴力」であり、自らは何物にも制約されない(「正義」にも制約されない)神々が、人間たちに、分をわきまえた振る舞いを教え込むために行使されるものでした。国家の「法」と「暴力」には、どこまでも神話的な「力」が刻印されているのであって、その核心にあるものは「正義」などではない、とベンヤミンは看破して言うのです。
このような「国家の暴力」「神話的な暴力」に対して、人間は、黙って従うことしかできないのでしょうか?
そこで「神話的な暴力」に対してベンヤミンが持ち出すのは、「神的な暴力」です。ギリシャ神話と拮抗しうるような文明の遺産を探し求めたときに、私たちなら仏教や中国の古代思想に眼が行くでしょう(柄谷氏は、ブッダのほか諸子百家の「墨子」に注目しています)。が、ユダヤ人であるベンヤミンは、『旧約聖書』の古代ヘブライズムにそれを求めたのです。
神話―権力―「法の措定」―国家法―処罰 という系列の傍らに、
神―正義―「法の脱措定(解体)」―災禍―贖罪 という別系列が想定されます。
こうしていよいよ、この論文の結論部分に近づいてきたのですが、残念ながら字数の制約のために、ここで次回に送らなければなりません。
次回は一気に、ベンヤミンの「暴力批判」の結論に突入することとなります。
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!