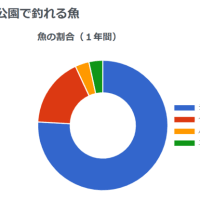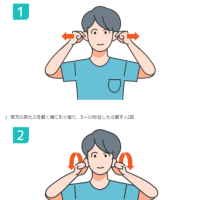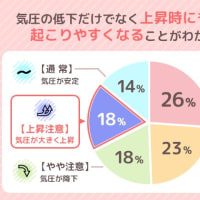Why Did China Banish Its Chief ‘Wolf Warrior’?
<新型コロナの中国起源説や新疆ウイグルの人権問題などで率先して諸外国に噛み付いてきた「戦狼外交」の顔が裏方に回された意味は>
中国の強硬な「戦狼外交」の顔として知られてきた趙立堅が、中国外務省の副報道局長から、隣国との国境画定や海洋問題の管理を行う国境海洋事務局に異動したことが明らかになった。
新部署でも報道官時代と同じ副局長のポストに就くことになるが、表舞台からは姿を消すことになる。
趙がツイッター上で存在感を確立し、大きな注目を集めるようになったのは、在パキスタン中国大使館勤務時代(2015~2019年)だった。
当初のツイートは主にパキスタン国民に向けたもので、地元の文化を称えたり、中国・パキスタン経済回廊における中国の役割を擁護したりする内容だった。
ツイッター名を「ムハンマド趙立堅」に変えたことまである(中国の外交官が地元色の強い名前を名乗るのは珍しいことではない)。
彼の姿勢はパキスタン国民の間で共感を呼んだが、2017年4月に新疆ウイグル自治区で、ウイグル文化の弾圧の一環としてイスラム風の名前の使用が禁じられ、趙も「ムハンマド」の使用を撤回し、かえって裏目に出ることになった。
2017年までには、ツイッター上での反米姿勢が趙のより大きな特徴となり、その強硬な外交スタイルから(2017年に公開された好戦的かつ愛国主義な映画のタイトルにちなんで)「戦狼」外交官と呼ばれるようになった。
彼のツイートの多くは、新疆ウイグル自治区での中国政府の残虐行為についての否定や反論で、これが評価されて2019年には名誉ある報道官のポストに昇進した。彼に触発されて、その外交スタイルを真似る者も多くいた。
〇オーストラリアをフェイク写真でディスる
2009年〜2013年にかけて米ワシントンに赴任していた頃の趙と仕事をしたアメリカの外交官たちは、当時の趙は控えめな若手外交官だったと記憶している。
趙はその後の数年間で大きな変化を遂げたことになる。
その好戦的な外交姿勢がピークに達したのが、2020年11月。
新型コロナウイルスのパンデミックの起源をめぐってオーストラリアと中国の対立が激化していたとき、趙はオーストラリアの兵士がアフガニスタンの子どもを殺しているように見える合成写真をツイッターに投稿。
国際社会の怒りを買ったが、中国国内では支持を集めた。
中国では2020年に入ってから、新型コロナのパンデミックの原因は、米メリーランド州にある米陸軍の医学研究施設「フォート・デトリック」の実験室から流出したとする陰謀説が広まったが、趙はこの陰謀説を先頭に立って拡散した。
彼の好戦的かつ被害妄想的な外交スタイルは、国際社会からの孤立を深める中国の姿勢に合致しているようだった。
例えば、中国政府は2021年3月、新疆ウイグル自治区での人権侵害を理由に西側諸国が中国当局者に制裁を科したのに対抗して、EUの政治家などに報復制裁を導入し、これが原因で中国とEUの貿易協定の批准が凍結されている。
趙はナショナリストからの支持を得ていた一方で、中国のインターネット上では厳しく批判されていた。
彼がお高くとまっていると不満を抱いていた者もおり、新型コロナウイルスの感染拡大により多くの国民が外出を厳しく制限されていた頃に、趙の妻が(中国版ツイッターとされる)微博にマスクをしていない自身の写真を投稿した時には大きな騒ぎになった。
また最近では中国の指導部の中に、「戦狼外交」が中国の国際的なイメージに悪影響を及ぼしていると考える者が出てきているようだ。
中国が態度を改めようとしているのだと関係各国(とりわけアメリカ)に確信させるための取り組みも行われている。
その一因は、アメリカが本気で(米中の経済を引き離す)デカップリングを仕掛けたことによる衝撃と、ゼロコロナ政策が中国経済にもたらした打撃にある。それを踏まえると、中国は今後、比較的穏健な人物を次期駐米大使に任命する可能性が高いだろう。
しかしながら、この外交的なシフトだけが原因で、趙が外務省報道官の座を追われたのかどうかは分かっていない。
国外追放されたジャーナリストの王志安が先月指摘したように、趙は2022年11月にゼロコロナ政策に反対する抗議デモについての記者会見の中で言葉に詰まり、資料の紙をせわしなくめくり、しどろもどろの答えをした失態もあった。
〇欧州は騙せてもアメリカは無理
中国による強硬な外交スタイルの軌道修正が、実際の政策の変化のあらわれなのかどうかも不明だ。
たとえば中国はウクライナ問題について、戦闘に否定的な考えを示唆しつつも、戦闘が始まった当初から基本的にロシア寄りの姿勢を変えていない。
中国が再び優れたビジネスパートナーとして戻ってきたと、それを切実に望んでいるヨーロッパ諸国を納得させることは簡単かもしれない。
だがアメリカは中国を戦略上の大きな敵と考えているため、納得させるのは難しいだろう。
それに中国の国内メディアは、反米姿勢を貫いている。
中国の当局者たちは、アメリカの当局者が容易に中国のテレビを視聴し、中国の新聞を読むことができるのを忘れているようだ。
中国が再び優れたビジネスパートナーとして戻ってきたと、それを切実に望んでいるヨーロッパ諸国を納得させることは簡単かもしれない。
From Foreign Policy Magazine
From Foreign Policy Magazine