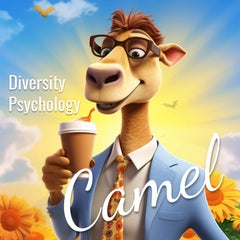こんにちは、らくだです。
インサイヘッドで
心のしくみを学んで、
心が育つプロセス
心が育つ理想的な状態
心を育てるためにはどうすればいいのか
こんなことを学ぼうという
シリーズの7回目。
今回も
作中の表現から
心の構造の解説です。
今回は
シンプルに
無意識について。
作中だと、
この崖の下が
無意識の領域として描かれていますが、
この
底が見えないほどの
深い谷。
無意識は
「無」の意識というくらいなので、
自分では認識できない
意識なわけです。
なので、
底が見えないというのは
見えない=認識できない
という表現にも通じるわけです。
でも、
ここまでなら、
一般の人のレベルでも
まぐれでも描けるのですが、
さすがディズニー
この谷
絶望するほど深さのある谷なのですが、
底の部分もしっかり描いていて、
無意識の谷の底には、
忘れた記憶の玉が
山のように転がってるんです。
ここが素晴らしい。
ちなみに、
人の脳には
「忘れる」という忘却機能が備わっています。
これは、
言われなくても、
誰でも経験的にわかることですが、
「我々の脳は無限の量の情報を保存するようにはできていません」
神経学者のジョー・ツィエン(ジョージア・リージェンツ大学)
脳の解読研究を指揮する専門家も明言しているとおり、
記憶の保持には
一定の容量(キャパ)があるからなんですね。
忘却ができないと
脳のキャパオーバーが起きて
早死にするとも言われています。
ただ、
この忘却の「忘れる」という意味
実は
忘れるとは、
消えるということではないんです。
忘却 ≠ 消失
記憶にアクセスするのが
ものすごく難しくて
思い出しにくくなっているだけで
失っているわけではないんです。
だから、
無意識の谷の下に
記憶の玉が
山のように転がってるわけなんです。
実によく描かれている。
細部にわたる
プロ意識に、
脱帽です。
素晴らしい。
ちなみに、
無意識はよく
こんな氷山として表現されることがあり、
私たち認識できている
意識とは
無数の無意識の上に成り立つものとされています。
そして、
NLP(神経言語プログラミング)的には、
意識と無意識のパワーバランスは、
1:18000(約2万)と言われ、
圧倒的に
無意識のほうが
脳の機能や
私たちの判断に
強力な影響力をもちます。
なので、
認識できる意識の量も
こうしてみるとものすごく多いですが、
この無数の感じの
圧倒的な量の感じ。
これもまた
とても納得な表現でもあるわけなんです。
まとめると
この無意識の記憶の表現からいえることは
私たちには、
自分では思い出すことのできない
強力な影響力をもつ
無意識が
想像を絶する量
自分のなかに眠っています。
人の脳が
全体の10パーセント程度しか
使われていないという
理屈の一端には
こういったものもわるわけです。
ということは、
もし
自分の無意識を
自分でコントロールできれば、
ものすごい力を発揮できるようになることが
わかるでしょうか?
心理学における20世紀最大の発見は
「無意識」といわれています。
今後は、
一般の人でも
心理学のなかでも
この無意識という部分の活用が
どんどん盛んになっていくでしょう。
そして、
この無意識の領域になる
ノウハウのひとつが
まさに
9つの才能タイプ
(自分の気質)にあたる部分でもあるんです。
僕は自分の人生において
心理学の知識に
さまざまな助けをもらいましたが、
特に
この無意識の領域の
9つの才能タイプの知識で
これまでと比べ物にならないほど
いろいろなものがクリアになり、
人生が救われました。
こうした経験を
少しでも多くの人に
届けるために、
これからも発信していきます。
今回は以上!
インサイドヘッドの解説は
まだまだ続きます!