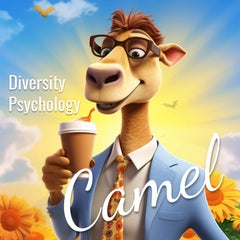こんにちは、らくだです。
インサイヘッドで
心のしくみを学んで、
心が育つプロセス
心が育つ理想的な状態
心を育てるためにはどうすればいいのか
こんなことを学ぼうという
シリーズの6回目。
今回は、
作中にでてくる
イマジナリー・フレンド
ビンボンの解説のつづきです。
前回
イマジナリー・フレンドは
自分自身を保つためのサポート機能
自分の望む成長モデルとしての効果
自分の心を癒す効果
こんな役割を果たしてる
という解説をしました。
今回は、
この
イマジナリー・フレンドを
さらに深く解説していきます。
この
イマジナリーフレンド
別の表現をするなら、
幼いころに体験する
現実世界では
ありえない、
自分の空想
ファンタジー
そして、
作中の表現でなぞるなら
この
空想・ファンタジーは
自分の人生における
困難を突破する力になったり、
生きることをさらに強くする
こんな要素になりえるんです。
人は
大人になればなるほど、
これまでの経験や教育から
理論的に考えるようになり、
ある種の
固定概念や常識というものを
しっかり学習します。
(社会を育るために仕方ないんだけど)
すると、
この固定概念や常識によって
自分の限界を勝手につくってしまい、
人は
自分の本来持っている力を
発揮することに
制限をかけてしまうんです。
「他の人もそうだったんだから、自分にはどうせ無理・・・」とか
「大勢がそうなんだから、ふつうに考えてありえない・・・」など。
すると、
特に
仕事などにおいても
(商品開発、人材育成、マネジメント・・・)
何かアイデアを出そうとしたときも
常識にとらわれたり
すでにあるもににとらわれ過ぎて
人並のことは考えられても
そこから
何か突き抜けるアイデアを出すのは
非常に難しくなります。
自分らしさを発揮して
直面している課題や
変化していく時代に合わせて
これまで以上の
さらなる新しい自分で
今を切り開いていくことが
めちゃめちゃ難しくなるんです。
自分に制限をかけてしまうために・・・。
何かチャレンジをするにしても、
創造性をもって取り組むことを恐れ、
仲間からのアイデアで
「おぉ!いいね!」
と思えるソリューションが
なかなか生まれない・・・。
上司の立場だと
こんな経験
けっこうあるんじゃないでしょうか。
当たり前や常識にとらわれて
自分に制限をかける人の特徴は、
理論的に考えすぎて
頭のなかだけで
シュミレーションを完結させ
それ以上の
思考も行動もやめてしまう・・・。
これ
非常にもったいない。
僕も人のこと言えませんが。
そこで、
その突破口となるのが、
空想
ファンタジー
なんです。
現実世界では、
実際にやってみないとわからないことが
山ほどあります。
思いもよらない結果や
思いもよらない化学反応で
想像を超えることなんてザラにある。
現実は理論を超える
でも、
こうした行動の原動力につなげるには、
思考を柔軟に楽しめて
常識にとらわれず
発想を広げて思考できる
「自由度」が必要。
そうした
常に革新的な発想へと
アクセスできるよう
思考の自由度を広げてくれるものが、
空想
ファンタジー
なんです。
ありえないを
楽しむ経験が
ありえないを
生み出せるわけです。
なので、
作中でも
ヨロコビが無意識の谷に落ちて
選択肢がなく
どう考えても
絶望的な状況になったときにも、
最終的に
現状を打開し、
救ってくれるような
強力な後押しをしてくれたのが、
ビンボン
(イマジナリー・フレンド)
という
空想
ファンタジー
だったわけです。
だから、
幼少期に
空想や
ファンタジーに触れるのって
めちゃくちゃ重要なの、
わかります?
だから、
売れている絵本や
素晴らしいといわれる絵本には、
こうした
ファンタジー要素が
多分に含まれているんです。
本来
こんなデカいかぶなんて、ないし
犬と猫とねずみが手伝ってくれるなんて、
ありえません。
動物の兄弟が、森のなかまと
めちゃくちゃおいしそうな料理をつくるなんて、
ありえませんし、
家に鬼が落ちてきて、
オジイの頭に、おへそがくっつくなんて
ありえません。
信号機に、
3色以外の色が登場するなんて
常識にとらわれてたら
思いつかないわけです。
幼少期に
ファンタジーに触れ
ファンタジーの経験を蓄積できることが
人の人生のお守りになるくらい
重要で、
それが
いかに昔から大切にされてきたのが
分かると思います。
なので、
結論、
幼少期の時ほど、
子どもの
創造性を育むために
思考の自由度を育むために、
空想
ファンタジーを
ぜひ大切にしていきましょう。
ということになるわけです。
そうすると
クリスマスのサンタや
節分の鬼も、
ひとつの
ファンタジー。
なので、
怖がらせたりすることは
必要ありませんが
ぜひ、安心しながら、
心も通うような
なるべく
リアルなファンタジーの体験を
大切にしてもらえたらと思います。
今回は、
ここまで!
解説は
まだまだ続きます!