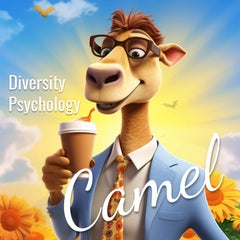こんにちは、らくだです。
インサイヘッドで
心のしくみを学んで、
心が育つプロセス
心が育つ理想的な状態
心を育てるためにはどうすればいいのか
こんなことを学ぼうという
シリーズの10回目。
今回は、
抽象概念のトンネル(エリア)の
補足解説です。
前回で、
抽象概念のトンネルのなかで
なにが起こっていて
それがどんな意味なのかを
解説しましたが、
もう一つ
このトンネルの存在が
私たちの
脳の中で
どんな構造として
位置づけられているのかを表す表現があるので
それをご紹介します。
それがこれです。
記憶に玉が保管されてる台地に
大地を分けへ立つ
塀ように
トンネルが存在しています。
これ、
どういうことかというと、
簡単にいうなら、
概念(抽象)の枠によって
記憶(体験)が
整理されている状態なんです。
私たちの記憶や体験は、
本来、
それが一つずつ
短編的に記憶されています。
それが
記憶の玉だったとしたら
単に記憶しているだけだと
以下のように
記憶が
バラバラに
置かれている状態です。
でも、
これだと、
いろんな記憶が
バラバラに置かれすぎて
思い出したり
知識として
思い出して活用するときに
とても探しにくい
だから
ここで、
概念という枠組みができることで
記憶は
おおまかな概念ごとに
整理されます。
そうすると
過去の記憶や経験から
思い出そうとするとき
アクセスしやすくなるんです。
たとえば
私たちも
自分の家を思い出してもらえたら
もっとわかると思うんですが、
どの家庭にも
キッチンには調理用品があったり
風呂場にはお風呂用品があります。
これが
調理用品が
置き場が定まってなく
玄関とか
2階とかにあると
必要なときアクセスしにくいですよね。
お風呂用品が
キッチンにあったり
子ども部屋にあったりすると
アクセスしにくいわけです。
なので、
私たちも自然と
道具は
それぞれのジャンルで、
整理して
片付けてるわけです。
なので、
脳のなかでも
それが行われてると
思ってください。
ありがたいことに
脳は
発達するにつれて
概念という
枠組み(壁や塀のような仕切り)を作ることで
私たち自身が
記憶や経験を活用しやすいように
整理してくれているんです。
その描写が
これなんです。
ちなみに、
整理されている
ということは、
アクセスしやすいのは
お伝えしたとおりてますが、
忘れた記憶は、
ちゃんと
無意識の谷で
地面に
バラバラにちらかっているというのも
実は
すごく筋が通ってるわけなんです。
この一貫性!
本当にすばらしい。
まさしく
プロの仕事だなと思うんです。
(地味にすごくないですかこれ。)
ここまでは、
映画の描写からみた
構造の話ですが、
ここからさらに補足で
人の発達的な観点から
さらに深い理解をお伝えします。
それはなにかというと
人の脳は、
ひとつひとつの記憶が
抽象概念という
枠組みで整理されている
といいました。
だから
高度な思考や分析
理解ができるわけですが、
この概念形成が
もっとも活発になるのが、
5~6歳
そして、
小学校以降になると、
様々な教科・科目を通して
いろんな概念の
つながりや関係性を学び
知識や理解がさらに整理され、
概念が
体系化されます。
ということは、
そもそも、
この黄色い記憶(体験)があるからこそ
概念が作られ、
概念が
体系化されることになるとすると・・・
つまり、
記憶の玉(体験)がないと、
概念が作られず、
そして
後々の
概念の体系化が
しっかりできなくなるんです。
この順番、
理解できるでしょうか?
ずばり、
幼少期(0~6歳)までは、
勉強以上に、
いろいろな記憶に残る
体験が
どれくらいできているか、
これが
人(子ども)の成長にとって
めちゃくちゃ重要になるんです。
専門用語でいうなら、
この記憶(体験)のことを
素地(そじ)といいます。
この素地を
どれくらいストックできるかで、
どれくらい多くの概念を形成し
概念が整理されていくほど
この世界が面白く理解できるようになる、
勉強が面白くなるわけなんです。
じゃあ、
どうすればいいのか。
だから、
、
子どもの
好きなことを通して
いろいろな体験をしましょう!
っていうことになるんですね。
習い事や
勉強もいいですが、
子どもの興味関心や
好きなことを通して
さまざまな体験をぜひしましょう!
これ、
子どもの興味関心がなぜ重要かというと、
大人が勧めたり
強制させるものよりも、
自分が好きで楽しいという感覚が伴う方が、
記憶に残りやすい!
ぜひ、
大人のエゴではなく、
子どもの興味関心からの
多くの体験で
子ども達の頭の中を
大きく伸ばしていってあげましょう!
今回はここまで!