海を望む丘にある小さなカフェ"Ciel bleu "。そこで織りなされる小さな物語と小さなミステリー。
前回までのあらすじ→前編をお読みください。
☆☆☆
「わかりました。奥様が口をきかなくなってしまった原因がわかりました!」
興奮のあまり思わず大きな声を出してしまった。驚いた老紳士はコーヒーをこぼしそうになる。
「すみません。ごめんなさい。お召し物は大丈夫ですか」
「ああ、大丈夫ですよ」ほら、このとおりとわたしに微笑んでみせる。
「良かった。今、コーヒーを新しいものにお取り替えします」
「いや。いい。大丈夫だから。ありがとう。それより早く貴女の答えを聞きたい」
ヒントはコーヒーに添えたミルクだ。しかしそんなことよりも先に、老紳士の期待に満ちた眼差しに応えるべきだろう。
「昨晩のメニューは何でしたか」
「ああ、そういえばそれはまだお話していなかった。それでも貴女は真相を突き止めたと?」
「ええ。どのようなメニューでも同じ答えに行き着くので」
「ほお。それはまるでベイカー街の住人のセリフのようですね。では、このワトソンに真相を教えてくれたまえ、きみ」
ベイカー街?ワトソン・・・ああ、わかった。イギリスのコナン・ドイルが産んだ稀代の名探偵のことね。それにしても洒落た言い方をする。思わず笑ってしまった。
「ふふふ。シャーロック・ホームズがお好きなんですね」
「はい。著作は全部読みましたよ。まだ若い頃ですが、ロンドン滞在中にベイカー街へ何度も足を運んだものです。貴女も推理ものがお好きなのかな」
好きかと聞かれたら、どうなんだろうと思う。小説は読む。でも推理小説が特に好きというものでもない。だから、ええまあと曖昧な返事をした。
「それで、奥様がお作りになったお料理は何でしたか」
「カレーです。欧風の、夏野菜のカレーと言っていたな。ナスとかの今が旬の野菜がたくさん入った」
そっちかあ。けっこう庶民的なんだ。まるで英国貴族のようなこの方の佇まいからコース料理を連想したのだけど、また予想が外れたよ。でも、まあいい。
「サイドメニューはありましたか」
「ああ、ええ、サラダがあったな。レタスにトマトにマッシュドポテトに・・・」
とても美味しそうだ。聞いているだけでよだれが出そう。だがしかし、よだれをこぼしている場合ではない。
「テーブルの上にはお料理以外に何がありましたか?」
「えっ?何って言われても」
「調味料の類はいかがですか?」
そこで老紳士は、はっと虚をつかれた顔になった。
「塩、コショウ、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、もしも和食ならば醤油、七味唐辛子、山椒とか、そんなエトセトラです」
「ああ・・・」
「奥様のお料理に手をつける前に、それらの調味料をお使いになっていらっしゃいませんか?」
「うう、うむ。言われてみれば確かに」
「昨夜のカレーには何の調味料をお使いになりました?」
「ええと、ブラックペッパーと塩と、ソースを少々」
「ソースも!?食べる前にですよ?」
「・・・食べる前に」申しわけなさそうな小さな声の老紳士。どうやらご自分で気がついたらしい。
そんなにてんこ盛りの調味料をぶっかけてしまったら味が変わってしまう。しかもソースまで。
ソースはトマトをはじめいくつもの野菜類を原料に、そこに塩と酢、香辛料を加えて作る。そのような最強の調味料を、奥様が丹精込めた手料理に、しかも味見する前にかけてしまったら、奥様でなくても怒るだろう。
「前に妻から言われたことがある。そんなにかけたら身体に悪いですよとね」
「やっぱり和食の時は醤油ですか」
「そう。醤油と時は塩も。若い頃から僕ははっきりした味付けが好きでね。妻が作ってくれる料理は美味しいのだが何だか味が薄いと感じてもいたから」
男性に多いタイプだ。濃い目の味を好む男性は多い。若い頃はそれでもいいかもしれない。しかし加齢と共に健康上のリスクが増え、若い頃のツケが回ってくるようになる。
「お料理は、その料理を食べてくれる人のことを思いながら作るんです。長年一緒に暮らしていらっしゃるご夫婦なら尚さらだと思う。奥様はご主人の健康を考え、塩分調整をして美味しいと言ってもらえるものを作っていた。それなのに・・・」
「それなのに僕は妻のその思いを、たとえ無意識にせよ、いつも踏みにじっていた。そういうことか。なるほど」
わたしは黙ってうなずいた。冷めてしまったコーヒーを下げ、淹れたばかりの三杯目の夏ブレンドをそこに置く。
「これは?」
「サービスです。ところで大変失礼ですが、お客様は本当にこの夏ブレンドを美味しいと感じますか?」
「ああ、うん」
「はっきりおっしゃっていただいて結構ですから。いかがですか」
「それなら、はっきり言おう。昨日までのプレンドの方が美味しいと感じた」
やっぽりそうだ。そうだと思っていた。その理由もわかる。
「なんだか薄らぼけた味だ、そう思われたのでは?」
「何もそこまで酷い言い方をしなくても」苦笑いを浮かべ、老紳士は、まあ当たっていると認めた。
「では、今度はミルクを入れないで召し上がってみてください」
「うん?ミルクを?」
「そうです。ブラックで一口。騙されたと思って」
その言い方がおかしかったらしい。老紳士は笑いながらカップを持ち上げ、夏ブレンドを口に含んだ。ワインテイストをするように口の中で転がす。
「いかがでしょう」
「甘い。甘みがあって軽いのだが奥が深い。繊細でもある」
「昨日までのブレンドはマンデリン主体のどっしりした味わいなんです。だからミルクにも合うし味の個性がミルクと重複しない」
ミルクを入れるとコーヒーの味が甘くまろやかになる。だからどっしりした味の豆には合う。しかし。
「今日からお出しするプレンドは、夏ですから爽やかに軽く甘みのある豆をセレクトしました。だからミルクを入れると味がボケてしまうのです」
「僕はコーヒーを飲む際にはいつもミルクを入れている。それはただの習慣で・・・ああ!そうか!貴女は僕のその習慣から妻が機嫌を損ねた原因に思い至った。そうなんだね!」
「ええ。そうです」
「素晴らしい。なるほど。やはり貴女は名探偵ですよ」
褒められても手放しで喜べない。反省すべき点もある。
「わたしからお客様へ、夏ブレンドはミルクは合わないと申し上げるべきでした」
「うむ。しかし」
「しかしそんな差し出がましいことを言うのもどうかと。それに」
「それに?」
「お客様は当店の常連様です。ですからどこかで甘えていたのかもしれません」
いらっしゃるお客様の嗜好はさまざま。わたしはプロなのだからその嗜好を考えるべきだった。老紳士にそう言ったところ「僕はそうは思わないな」と微笑んだ。
「客の嗜好に寄り添うことも、無論、大切だと思う。しかし店の味、個性、そこでしか味わえないもの。それが一番大切なのではないかな」
「・・・ええ。そうですね」
「僕は貴女が淹れてくれるコーヒーが美味しいからこうして通っている。とはいえ、出されたコーヒーすべてに味見もせずにミルクを入れてしまう習慣は改めるべきであると、貴女から教えてもらった。この歳で目から鱗が落ちた気分ですよ。ありがとう」
「そんな・・・恐縮です。わたしこそありがとうございます」
立ち上がった老紳士が優雅にお辞儀をした。わたしも慌てて頭を下げる。
「さて、さっそく妻に謝らねば。また来ます。今日のお礼はその時に」
「えっ!お礼なんていりません」
「いやいや。それでは僕の気がすまない」
「いえいえ。本当にいりません。こうしてここでコーヒーを楽しんでいただけるだけで十分です」
老紳士はそうですかと残念そうな表情になった。
緑色のジャガーが夏の眩しい陽光が降り注ぐ坂道を下ってゆくのを、お店の窓越しに見送る。きっと奥様は機嫌を直すはずだ。良かった良かった。
カップを片付けていたら、カランという音。今日、二人目のお客様だ。
「いらっしゃいませ!」
〜Fin〜
☆他サイトと同時掲載です。
© 2021 ciel-bleu

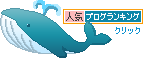

0 件のコメント:
コメントを投稿