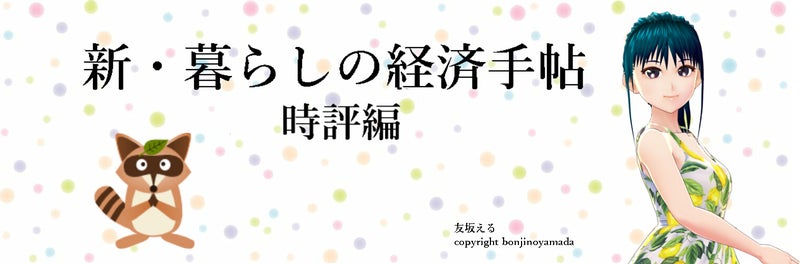2025年初投稿となります。昨年の衆議院選挙で国民民主党の玉木雄一郎代表らが掲げていた「年収103万円の壁」引き上げの意義とその実現可能性について少し遅ればせながら取り上げます。石破政権になってからますます緊縮色を強め、有権者から見放されかけつつある自民・公明与党に対し、国民民主党は恒久的な減税策を打ち出し有権者からの支持と議席を拡大しました。元名古屋市長で減税を訴えてきた河村たかし氏が立候補した日本保守党も好調でした。なるべく国民からの税徴収を抑え、政官による過剰な介入をしない小さな政府主義的政策は保守リベラルの王道といえるもので、それが勤労者たちの支持を集めたのでしょう。
いわゆる「年収103万円の壁」というものは基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)を合計した額であり、勤労者の年収がそれを超えると課税対象となってしまいます。夫に扶養されている主婦が配偶者控除を受けられるようパートタイム労働の収入が103万円を超えないよう働き控えをするといった行動をとっていたりしました。現在働き手不足といわれている中で労働供給に制約を与えていたことになります。
また基礎控除と給与所得控除は元々人々が最低限生きていくために必要な所得については税を課さないという考えのもとでつくられたものです。日本においてはアベノミクスが成果を出せるようになるまで30年以上という異常なデフレ不況下にこれまで置かれていたのですが、コロナウィルスによるパンデミックが収束した後にインフレ基調の経済状況に転じました。となってくると生活に最低限必要な所得が高くなっていきます。パート・アルバイト労働者の賃上げも進みました。となってくると103万円の控除額は低すぎるということになってきます。インフレになってきますと所得税や消費税などの税収も増えてきますが、それは税の取り過ぎといえます。玉木雄一郎代表はその問題を突いたのです。
それに対し減税、とくに恒久的なものを嫌う財務省やそれに靡く政治家、マスコミは国民民主党の各減税案潰しを始めだしました。国民民主党は基礎控除+給与所得控除を178万円に引き上げることを求めていますが、政府与党や財務省側はそれをやるとなると7.6兆円の税収減になると言い出しました。村上誠一郎総務大臣や総務省が全国の都道府県知事らに年収の壁の上限引き上げを行うと地方税が大きく減少するから反対するようにといったことを趣旨とする「要望書」を提出するといった行動をとっていたとも伝えられます。
しかしながら官僚や政治家たちがいう「7.6兆円の税収減」というものは減税による景気刺激とそれがもたらす税収増の効果を見込まない・認めないために出てきた数字です。役人たちの多くは名目GDPが1%増えたとき、税収がどの程度増加するかを表す税収弾性値を慢性的デフレ不況時代のときのまま「1.1」と低いまま計算しているために税収増効果を低く見積もってしまっているのです。現在日本はデフレからインフレ時代に転換したため、実際の税収弾性値は「2~3」になっています。その証拠に2024年は3.8兆円上振れて過去最高の税収。2023年が2.5兆円、2022年が5.9兆円も上振れました。
財務省をはじめとする官僚は経済成長や持続的なインフレで税収を伸ばしていくという発想ができなくなっています。バブル景気崩壊前までの大蔵省官僚はまだ経済活性化による税収増という発想を持っていた人がいたといわれますが、慢性的なデフレ不況が当然化してしまった1990年代以降の財務省官僚たちはそれを信じなくなってしまいました。増税するしか税収を伸ばす方法はないと思い込むのです。日銀についても景気や雇用を統治する責任を放棄してしまいます。(中央銀行無能論)筆者はバブル崩壊からアベノミクス始動までの日銀の金融政策失敗が、社会保険料も含めた税収の伸び悩みと過度な財政政策への依存を高めることにつながったと考えます。
「減税をやるにも日本の国家財政がますます悪化してしまうのではないか」と恐れる人たちが今もなお絶えないのですが、このブログで何度か説明してきましたとおり、日本の国家財政は思われているほど悪い状況ではありません。よく日本国政府の負債が1300兆円近くに達しているとかいわれますが、それは政府のバランスシートの負債側の額だけであり、資産側を無視したものです。
高橋洋一氏動画
別の方の説明も視てみましょう。
岡崎良介×永濱利廣【『インフレで103万円の壁は越えらえる』基礎控除引き上げの財源ねん出|世界でアップデート財政政策論】<世の中の誤解を正す シリーズ>(番組見逃し配信)2024年11月23日配信
永濱利廣さんは「日本で財政の指標としてプライマリーバランス(基礎的財政収支)が注目されるが、世界標準的には政府債務残高/GDP比」であるとして、そのグラフを用意されました。
これを見ると緑線の純債務がパンデミック下の2020年で高くなったものの、それを過ぎてからはぐんぐん下がっていっています。赤い粗債務もそういう動きです。それと入れ替わるように金融資産の残高が上昇しているのです。
インフレで所得税・法人税・消費税の税収が上昇し、さらに円安で膨らんだ外貨建て資産価値の上昇などで政府金融資産が殖えたことが貢献しました。上の高橋洋一さんの解説と併せてみると、その意味がわかってきます。
ストックだけではなくフローの方も確認してみましょう。
そのときよく使われるのはこうしたグラフで、政府の一般会計歳出額(青線)と歳入額(赤線)の推移を示したものです。
しかしながら財務省などが示してくる一般会計歳出額と歳入額の計上方法に問題があります。それは歳出の中に債務償還費と利払い費の両方を組み入れてしまっており、これは日本だけが行っていることです。他国は利払い費のみです。債務償還費は満期となった国債の元本を投資者に返還する費用ですが、現在その多くを日銀が保有しています。満期となった国債は新たな国債を政府が発行して借り換えしますが、政府と日銀の場合は日銀に対し現金ではなく国債をあげています。この借り換えした国債の額が債務償還費として計上され、実際より政府の財政赤字が高くなってしまいます。
さらに歳入についても為替相場に介入した際のキャピタルゲインなどといった税外収入が含まれておらず、低く見積られています。
ここで森永康平さんと会田卓司さんの対談記事を紹介しますが、会田さんは一般会計の「歳入」に税外収入を足し、「歳出」から償還費を引いた財政状況の推移のグラフを提示されています。
やはりパンデミックが拡散期だった2020年は歳出が突出していますが、状況が落ち着いてだんだんと下がってきています。歳入の方はじわじわ伸びています。ワニの口は閉じてきています。
こうしてみると国民民主党の減税策は決して荒唐無稽なものではないことがわかってきます。その一方で減税に消極的で防衛増税などをも仕込もうとする自民党や公明党の不埒さが目に付いてきます。この両党や立憲民主党はどんどん国家社会主義に傾倒していく一方です。
関連記事
血祭謙之介@それ行け!カープ(左党) さんのブログ記事
質問者2さんの記事
「新・暮らしの経済手帖」は国内外の経済情勢や政治の動きに関する論評を書いた「新・暮らしの経済」~時評編~も設置しています。
画像をクリックすると時評編ブログが開きます。
サイト管理人 凡人オヤマダ ツイッター https://twitter.com/aindanet

:quality(50)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/WWG7XC7IMVFUHFD6DSQK43OZKU.jpg)