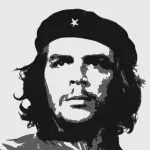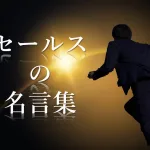社会人であれば、会社の研修会などで「報告・連絡・相談」というフレーズを一度ぐらい聞いたことがあると思います。
しかし新入社員など経験が浅い人、報連相に馴染みがない人にとっては「どこまで報連相すればいいのか?」という疑問が残るのも事実です。
そこで今回は、ビジネスパーソンが把握しておきたい報告・連絡・相談というテーマにフォーカスして解説してみたいと思います。
目次 [非表示]
ホウレンソウ(報連相)とは?
「ビジネスのホウレンソウとは何か?」を聞かれて答えられない人は少ないでしょう。
今や、それくらいビジネスの基本的な言葉となっている「報・連・相」ですが、「自分はきちんとできている!」と胸を張って言える人は、果たしてどれほどいるのでしょうか?
ご存知の通り、ビジネスにおける「ホウレンソウ」とは、「報告」「連絡」「相談」の頭文字をつなげた略語になります。
山種証券(現在のSMBC日興証券)の社長であった山崎富治さんが、社内で「ほうれんそう運動」を始めたことがきっかけだと言われており、山崎富治氏は、ベストセラーとなった自身の著書、『ほうれんそうが会社を強くする:報告・連絡・相談の経営学』の中で、温かい人間関係を作って、下からの意見を吸い上げ、みんなが働きやすい環境を作るための手段として「ほうれんそうの法則」を思いついたと記しています。

このことからも、「ホウレンソウ」の本質とは、単に上司と部下が情報共有をするための合言葉ではなく、上司と部下の垣根を超えて情報のやり取りができるような風通しの良い職場環境を作るための方法であることが理解できますよね。
この有名なホウレンソウ(報連相)も、最近では「もう古い!」と言われることがあり、「かく・れん・ぼう(確認、連絡、報告のこと)」などの新しい略語が使われている職場もあるようです。
報告と共有の違いとは?
「ホウレンソウは単なる情報共有とは違う」と前述しましたが、それでは情報を「報告」することと「共有」することは、どう違うのでしょうか?
まず報告とは、「上司・先輩・作業の依頼者等に経過や結果を伝えること」を言います。
つまり情報の方向性としては、「後輩→先輩」「部下→上司」という、下から上への流れになります。
一方、「共有」とは、情報の流れが「下から上へ」という一方向に限られず、「上から下へ」という流れを含む「双方向」の情報のやり取りを意味しています。
これは先ほど解説した「ホウレンソウ」の本質に近い考え方と言えそうです。
さて、先輩や上司から「仕事の状況を報告しなさい!」と言われたら、実際どこまで報告すれば良いのでしょうか?
上司は報告の抜けを防ぐために、「仕事に関係することは何でも報告しなさい!」と言うかもしれません。
しかし、「自分はきちんと仕事をしていたが、先輩は営業の途中でサボっていた…」というような告げ口は、果たして報告と言えるのでしょうか?
それでは、告げ口と報告の違いは何なのでしょう。
「報告」は、先にも述べた通り「上司・先輩・作業の依頼者等に経過や結果を伝えること」なので、「作業がどこまで進んでいるか?」という客観的事実を伝えればOKということになります。
一方、「告げ口」は「特定の個人の評価を下げるような情報伝達」なので、仕事の進捗状況の報告とは無関係と言えるでしょう。
なので、報告を求められた場合には「自分の仕事の進捗状況だけを報告するのが正解」ということになります。
以上を踏まえて、過不足のない”上手な報告”を心掛けましょう!

報連相(ほうれんそう)は仕事を管理する
「どこまで伝えればいいか分からないから報連相(ほうれんそう)は苦手」という人は多いかもしれません。
しかし、ビジネスパーソンは「報連相」を徹底することで、自分自身の身を守ることにもなるのだと心得ましょう。
ここでは、そうなる理由を解説していきたいと思います。
仕事には一人で取り組むタスクもあれば、チームで協力して行うものもあります。
しかし、一見すると一人で取り組んでいるように見える仕事でも、大抵は大きな仕事の一部だったりします。
したがって、自分一人の仕事のミスが、仕事全体に悪影響してしまったり、報告を怠ったせいで仕事がうまく回らないケースも起こり得るのです。
だからこそ、自分の仕事の進捗状況を”まとめ役”である上司に報告することが必要となるのです。
全てを報告しておけば、後から「どうして言わなかったんだ!」と責められることはありませんし、もし予定通りにいかないような問題が生じた場合にも、全体が把握できていれば微調整して、達成までの見通しを示すこともできます。
つまり、プロジェクトを管理する管理者(上司)の立場になって考えれば理解しやすいと思います。
自分が管理者の立場になった場合、一番評価を下げることは「プロジェクトの管理ができなかったこと」になります。
なので、誰が何パーセント進捗していて、どこで問題が発生している、ということを全て把握しておきたいのです。
問題というのは、把握さえできていれば対処のしようがありますが、把握できていないと全く対処できませんし、後から挽回するのが難しくなるケースもあります。
大切なことは、自分に都合の悪い事実を隠そうとするのではなく、客観的にありのままを報告・連絡し、どうすれば良いかを相談することなのです。
このようなロジックを理解できていたとしても、「なかなか部下が報連相してくれない…」と悩んでいる上司はたくさんいるので、そんな時にはぜひ下の名著を読んでみてください。

報告・連絡・相談ができない人
「報告・連絡・相談」は自分の身を守るために必要なことですが、いくら「ホウレンソウ」の必要性を説いても、できない人やしない人が一定数存在します。
それではなぜ「ホウレンソウ」をしない人が出てくるのでしょうか?
それにはいくつか理由がありますので、ここで解説していきたいと思います。
①「ホウレンソウ」の必要性を感じていない
きちんと報告・連絡・相談をしない人は「自分に与えられた仕事を淡々とこなせばそれで良い…」と思っているのかもしれません。
このような発想の人はサラリーマンとしては優秀かもしれませんが、組織の癌(ガン)になり得るので注意が必要です。
このような考えになってしまうのは、仕事の全体像が見えていないことが原因だと考えられます。
個人の仕事は、あくまでも全体の仕事の一部であると説明すれば、「ホウレンソウ」の重要性が理解できるかもしれません。
➁上司に話しかけづらい
このパターンは非常に厄介だと思います。
上司という仕事はただ管理すれば良いというわけではなく、時には叱咤する場面も出てきます。
なので、「常に優しい上司を演じる」というわけにはいかないのです。
とはいえ「怖い上司(=話しかけづらい)」という印象を持たれることはマイナスでしかありません。
そのような雰囲気を醸し出している上司の側にも問題があります。
また、部下の中には社会人としての経験不足、コミュニケーション障害、あるいは何らかの病気等が隠れている場合も考えられます。
どちらにしてもこのようなケースで報告・連絡・相談が歩留まりすることは、後々のトラブルに繋がりかねません。
「部下がホウレンソウしてくれない…」という問題が出た際には、チーム力が足りない可能性もあるので早めに対処することをお勧めします。

➂注意や指導、叱責を受けるのが怖い
これも、先ほどと同様の原因が考えられます。
さらに前段にも書きましたが、「何を報告すれば良いかわからない」というビジネスパーソンもいます。
ホウレンソウを徹底するためには、「各自の仕事の進捗状況を決まった曜日に全体報告する」などのルール作りが必要かもしれません。
「いつ、だれが、どこで、なぜ、どのように、どうした」の5W1Hの形式で報告し合うようにすれば、報告内容の抜けもなくなるでしょう。
そして、「きちんとホウレンソウしてくれれば、怒ることはしない!」と宣言してしまうのもアリだと思います。
例えば「問題が発生してから1時間以内に報告すれば報連相ポイントを付与する」みたいな制度を作るのもおすすめです。
これが意図していることは、「報連相するのは良いことなのだ!」と社員に理解してもらうことです。
そもそも報告連絡相談することをネガティブに捉えている人が多いので、
- 報連相するのは良いこと
- 報連相するのは仕事の一環
と啓蒙していく必要があるかもしれません。
このような意識改革をしていくと、徐々に報連相が浸透していくと思います。
マネージャー(管理者)の仕事とは「自然に報連相できる仕組みを創ること」だと思うので、そのあたりは抜かりなく実施していきましょう。

報連相はコミュニケーション手段
ここまで、ホウレンソウの必要性とコツ、ホウレンソウ徹底のためのルール作りや工夫などについて解説してきました。
ホウレンソウはそもそも、会社内で温かい人間関係を作り、下からの意見を吸い上げ、みんなが働きやすい環境を作るための手段として考え出された方法です。
その本来の意味からすると、会社内で良い人間関係が作られていて十分なコミュニケーションが図られていれば、ホウレンソウを強調したり、強要する必要はないでしょう。
ホウレンソウの大半は、雑談のついでに報告できる程度の内容だと思います。
であるとすれば、ホウレンソウを怠る部下がいるのは、「部下の意識が低いから」でなく、「職場で気軽な雑談もできない雰囲気にしている上司(=会社)のせい」なのかもしれません。
そのようなケースでは、社内のコミュニケーションがスムーズに取れていないから、「ホウレンソウ」が必要になっているのです。
今やビジネスの基本として習慣化しており、会社の新人研修などでも当たり前のように教育されている「ホウレンソウ」という仕組み。
そのあり方を今一度見つめ直して、「ホウレンソウ」の本当の意味を考え直してみる必要がありそうです。