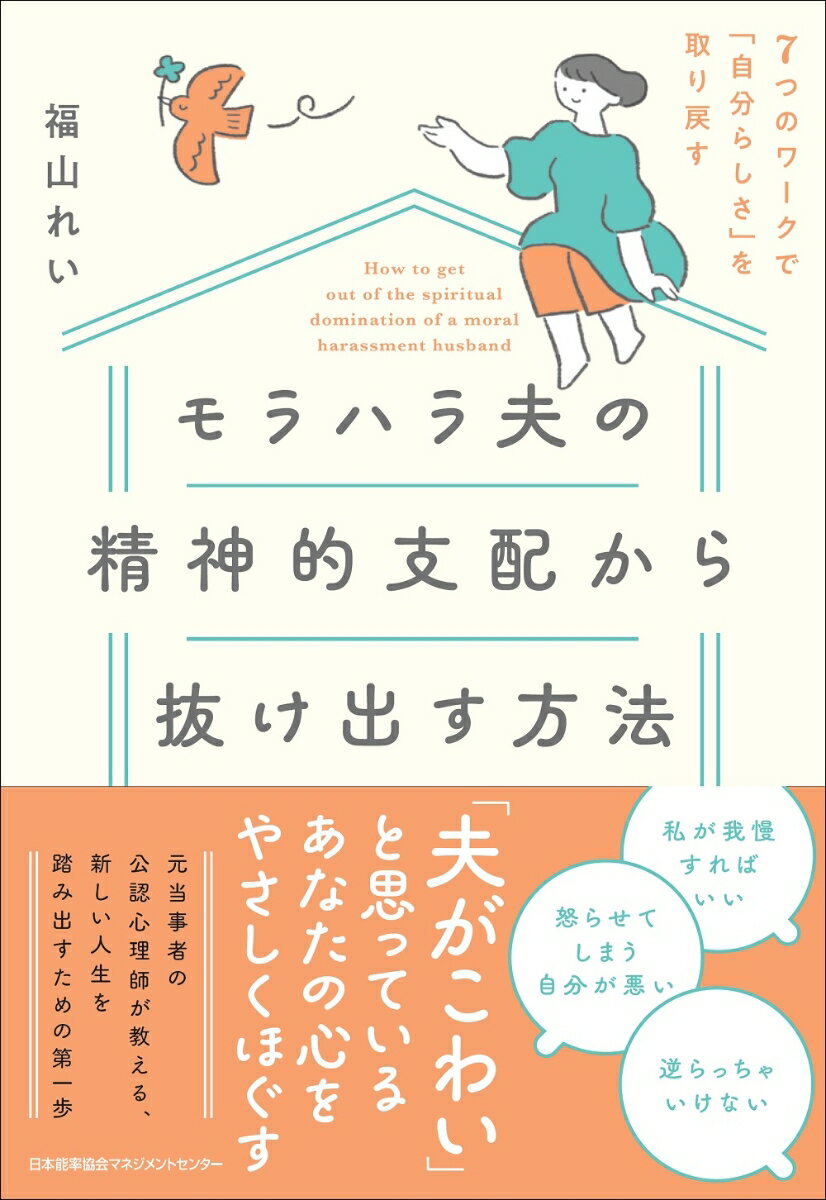マネハラ旦那の真実

マネハラとは、家庭内で金銭を使った支配や嫌がらせを行う行為のことを指します。被害者を経済的に依存させることで逃げ場を奪い、加害者の意のままに操ろうとする特徴があります。基本的にマネハラ旦那=モラハラ夫です。モラハラ(モラルハラスメント)やDV(ドメスティック・バイオレンス)の一環として行われることが多く、被害者に対して多大な心理的・経済的負担を与えます。
【目次を開く】スポンサーリンク
マネハラ(マネーハラスメント)とは?
マネハラとは、家族間のDVやモラハラに伴うマネハラは、金銭を利用して相手を支配・コントロールする行為です。被害者の自由を奪い、生活に必要なお金や経済的な選択肢を制限することで、被害者を加害者の意のままに操ろうとする目的があります。マネハラ(マネーハラスメント)は和製英語で、英語ではEconomic Abuse(経済的虐待)と呼ばれます。よく見られるマネハラ行為の具体例を以下に示します。
-
経済的な翼を奪う
被害者が就職やパートをすることを禁止し、収入源を断つことで経済的に依存させます。さらに、被害者にわずかなお小遣いしか渡さないことで、自由な選択肢を奪います。 -
経済的制限
家計をすべて加害者がコントロールし、被害者に十分な生活費を与えない。また、必要な支出をすべて加害者の許可制にし、子供の教育費や医療費さえも制限します。さらに、加害者が許可なく過度の浪費を繰り返すことで、被害者が自由に使えるお金を意図的に減らします。 -
監視と無駄遣いの強調
被害者の消費を監視し、「無駄遣いをしている」と非難することで罪悪感を植え付けます。購入したものをチェックし、不必要だと責めるなどの方法で行動を制限します。 -
借金の強要
被害者の名義を使って借金をさせ、返済を強要します。 -
収入の搾取
被害者が稼いだお金を取り上げ、自分のために使います。 -
経済的な脅迫
「お金が足りない」と不安を煽り、離婚や別居を防ごうとします。さらに、「お金がない」「貯金が減る」などの言葉で被害者に罪悪感を持たせ、心理的に追い詰めます。
これらの行為が行われることで、被害者は経済的な自由を奪われ、加害者の支配下に置かれる状態に陥ります。
マネハラ旦那に特徴的なマネハラ行為

マネハラ旦那が最も特徴的に示す行動の一つが「経済的な翼を奪う」ことです。この行動は、マネハラ妻にはほとんど見られない独特の特徴です。具体的には、被害者の就職やパートタイムの仕事を禁止し、収入源を断ち、経済的に加害者に依存せざるを得なくなる状況を作り出します。
一方で、マネハラ妻は夫の稼ぐ力を直接制限するのではなく、稼いだお金を浪費することで結果的に経済的な自由を奪う場合が一般的です。例えば、高額な買い物や過剰な浪費を繰り返し、夫が自由に使えるお金を減らすことで、間接的に経済的な支配を行います。このような特徴を踏まえると、「経済的な翼を奪う」という行為は、マネハラ旦那に特有の直接的な行動であり、妻の稼ぐ力を断つ形で行われます。
これ以外の行為、例えば経済的制限、監視、収入の搾取などは、マネハラ旦那とマネハラ妻の双方に共通して見られる手法です。ただし、稀に「マネハラ妻型の特徴」を示すマネハラ旦那も存在します。つまり、自分は働かず、家事もせず、妻に働かせて寄生する形のマネハラ旦那です。
興味深いことに、夫の稼ぐ力を断つ形のマネハラを行う女性はほとんど見られません。この点は、マネハラ行動の男女差を理解する上で重要な視点となります。
マネハラ旦那の手口
「経済的な翼を奪う」手口は、以下のパターンが多いです。:
-
「家庭に入ってほしい」と要求する
妻が働きに出ることを制限し、家庭に専念するよう求めることで、経済的な自由を奪います。 -
「育児に専念してほしい」と強制する
子供のためを理由に、妻のキャリアを諦めさせ、専業主婦としての役割に閉じ込めることで、経済的な依存を強います。一見すると家族を思いやる行動のように見えるため、被害者自身も当初はその意図を見抜きにくいのが特徴です。その後、妻が仕事に復帰しようとする際にも、さまざまな理由を持ち出して妨害するケースが多く見られます。
これらの行動は一見、家族のための配慮のように見えますが、裏には被害者を支配下に置く意図が隠されていることが多いです。

モラハラ夫は必ずマネハラもする!
マネハラは、モラハラの一環として行われるケースがほとんどです。「DVモラハラにはほぼ100%の可能性でマネハラが伴う」と研究結果を発表したアメリカの研究者もいます。モラハラ夫は、心理的支配と経済的支配を巧みに組み合わせて被害者を従わせることを目的としています。そのため、マネハラが単独で発生することは極めて稀であり、常にモラハラとセットで行われる傾向があります。

さらに、モラハラの根底には、自己愛性人格障害や境界性人格障害といった心理的要因が深く関わっています。これらの人格障害は、加害者が被害者を支配しようとする根本的な動機となり、マネハラやモラハラの行動パターンを形成しています。
マネハラ旦那=モラハラ夫=人格障害
マネハラ妻=モラハラ妻=人格障害
この原則を理解することが重要です。つまり、マネハラは人格障害を原因としたモラハラ(ハラスメント)の一部として行われています。男女でその行動に違いが見られるのは、モラハラ(人格障害)夫が相手を支配することに執着するのに対し、モラハラ(人格障害)妻は相手から搾取し、利用することに執着するためです。
マネハラ旦那の心理と動機

マネハラを行う旦那の心理や動機には以下のような要因が挙げられます:
-
支配欲
被害者を完全に自分の支配下に置きたいという強い欲求は、加害者にとって大きな動機となります。これは、自分が相手より優位に立つことで得られる安心感や、支配することそのものによる満足感に根ざしています。さらに、経済的に被害者を自分に依存させることで、被害者が自立する機会を奪い、自分から離れることを防ぐ狙いも含まれています。このような行動は、被害者の自由と選択肢を制限し、心理的にも拘束することで、加害者の支配欲を満たす重要な手段となっています。
-
上下人間関係による支配
人格障害者は人間関係を上下の力関係として捉え、自分を常に上の立場に置くことで精神的な安定を図ります。特に、経済的な自由を奪うことで被害者を自分に依存させ、「自分が上で相手が下」という関係性を確立し、優越感を得ようとする心理が働きます。このような心理から、優れたキャリアを持つ妻や高収入の妻の仕事を辞めさせるケースも少なくありません。妻が持つ社会的地位や収入は、加害者にとって脅威と映るため、それを奪い取ることで自らの優位性を保とうとします。また、そのような「優秀な妻を専業主婦にできるほど優れた夫だ」と他者にアピールしたり、自分自身がそのイメージに酔いしれる心理も働いています。
-
嫉妬心
人格障害者の特徴の一つに、不貞への傾向があります。この傾向が裏返しとなり、強い嫉妬心を引き起こします。例えば、妻が働きに出ることで、「自分と同じように不貞に走るのではないか」と過剰な疑念を抱き、それを理由に妻の行動を厳しく制限することがあります。このような心理が結果として、妻の経済的な自由を奪い、依存状態に追い込む動機となります。直接的にはお金との関連性が薄いように見えますが、この嫉妬心は経済的支配の手段を強化する重要な要因となっています。
-
損得勘定
人格障害者は極端な損得勘定に基づいて生活しています。自分が稼いだお金を妻が使うことに対して強い不満を抱き、それを「損をした」と感じます。その結果、妻には厳しい制限を課し、必要以上に管理する一方で、自分の支出には制限を設けず、自由に使おうとする行動が見られます。このような行為は、加害者が自身の利益を最優先する心理の表れです。
マネハラ旦那か倹約家か?

DVやモラハラは、被害者が逃げにくいタイミング、例えば出産やマイホームの購入といった重要なイベントの際に苛烈さを増す傾向があります。「経済的な翼を奪う」行為は、結婚の初期に行われることが多く、後になってみれば、これがDVやモラハラの最初の兆候だったと気付くケースが少なくありません。
マネハラ行為と単なる倹約家の行動は、一見すると似ているため見分けが難しい場合があります。倹約家の場合、家計の安定や将来のための貯蓄を目的としており、支配やコントロールを意図していません。これに対して、マネハラ旦那は被害者を自分に依存させ、自由を奪うために経済的な制約を利用します。
さらに「家庭に入って欲しい」「育児に専念して欲しい」は家庭の安定やパートナーへの配慮を装うこともあり、被害者自身が状況の本質を理解しにくい場合があります。しかし、「経済的な翼を奪う」行為が行われた後、次のような兆候が見られる場合、それはモラハラの一環としてのマネハラである可能性が高いといえます。
-
働いていないことを責める
マネハラ旦那は、妻の仕事や収入を自ら制限しておきながら、後になってそれを攻撃材料にします。例えば、「働いていないくせに」「家計に何も貢献していない」「稼いできてから口を開け」といった非難の言葉で、被害者に罪悪感を抱かせるのです。被害者である妻は「夫が希望したから仕事を辞めたのに、なぜ今になって責められるのか」と混乱し、精神的なダメージを受けます。このような状況は、議論が堂々巡りとなる人格障害者特有のパターンに見られるものです。
私の経験では、このような議論の堂々巡り感を覚えるのは、酷い人格障害者のみです。具体的には、モラ元妻や、職場にいる酷いナルシシストの行動に共通しています。
-
自分は浪費

妻に過度の節約を強いる一方で、マネハラ旦那自身が浪費をする場合は危険信号です。倹約家であれば、自身がまず節約を実践するはずです。また、倹約家はそもそも妻の仕事を制限することが少ないため、このような矛盾した行動は、支配を目的としたマネハラ特有のパターンといえます。 -
DVモラハラが始まる
これは説明するまでもなく、「経済的な翼を奪う」行為がモラハラの一環であることを示しています。経済的な支配が確立されると、そこから更なるDVやモラハラが激化する可能性が高まります。
-
度重なる不貞
DVやモラハラといった直接的な攻撃性を示さない場合でも、妻を家庭に閉じ込めたまま、自身は不貞行為を繰り返すケースがあります。このような行動は、「カバートナルシシスト」と呼ばれるタイプの自己愛性人格障害者に特徴的です。このタイプは、不貞が発覚した際には一時的に謝罪したり、妻の機嫌を取ろうとする素振りを見せることがあります。しかし、根本的な行動は変わらず、同じ行為を繰り返す傾向があります。さらに、一旦離婚に至った場合、片親疎外や虚偽DVといった非常に悪質な加害行動に発展することも少なくありません。このような行動パターンは、表面上は穏やかに見える一方で、内在する悪性度が高く、被害者に深刻な精神的・社会的な影響を及ぼします。
マネハラは家庭裁判所でDVモラハラ被害者が不利になる大きな要因
家庭裁判所では、DVやモラハラ被害者に対して公平な判断を下すべき場ですが、実際には被害者が不利な状況に陥ることがあります。その大きな要因の一つがマネハラです。DVやモラハラにはほぼ確実にマネハラが伴い、加害者は意図的に被害者の経済力を奪うことで支配を強化します。結果として、被害者は法的手続きに必要な弁護士費用や裁判費用を捻出できず、適切に反論できないまま不利な判決を受けるケースが多発しています。
さらに、加害者が家計や資産の管理を独占している場合、被害者はこれらの詳細な情報にアクセスできず、資産分配が公平に行われているかを確認する手段を失います。また、加害者が巧妙に虚偽を織り交ぜて自身を被害者として装う場合、被害者の訴えが信用されにくくなるリスクもあります。
マネハラ旦那への対処法
マネハラは、モラハラの一環として行われるため、加害者の人格障害の程度によって、適切な対策は異なります。以下の方法を参考に、状況や相手の人格特性に応じた対応を検討してください。特に、マネハラが家庭裁判所で被害者を不利な状況に追い込む大きな要因であることを踏まえると、早期の対処が被害者の立場を守る上で非常に重要です。ただし、そもそもマネハラは被害者が逃げるのを防ぐために意図的に行われているため、解決は容易ではない場合が多いです。
真正面から伝える
人格障害がまだ軽度の場合は、問題を真正面から指摘し、修正を試みることが重要です。人格障害は加齢とともに悪化しやすく、入籍や結婚式、出産といった被害者が逃げにくいタイミングで顕著になる傾向があります。婚姻初期の段階であれば、まだ会話が通じる可能性があります。被害者が知っておくべきことは、時間の経過とともに状況が悪化する可能性が高いということです。この記事の情報を参考にマネハラがモラハラの一環である可能性を察知した段階で、早期に対処することをおすすめします。
避難する・距離をとる
人格障害が悪化し、修復が困難な場合、実家や友人など頼れる人がいるなら、マネハラ・モラハラ旦那と距離をとることです。そこから、経済的自立を図ります。もし、あなたが稼ぎ頭で、旦那がマネハラ妻型の搾取系のマネハラをしている場合も避難します。無職のマネハラ旦那は婚費を請求してくる可能性があるので、そこから収入を上げる努力が必要です。
秘密口座の開設
収入を安全に管理できる口座を開設し、秘密裏にお金を貯めておくことが有効です。経済的な翼を奪われ、家計を完全に管理され、妻の支出を細かくチェックするマネハラ旦那の場合は、これは簡単ではありません。一例ですが、買い物をした後で、一部の商品を返却し、そのお金を貯め続けて避難に成功した被害妻がいます。冷静に柔軟に対策を考えましょう。
マネハラ旦那の真実まとめ
マネハラ旦那の問題は、経済的な支配を通じて被害者の自由と選択肢を奪い、精神的にも拘束することにあります。モラハラやDVとセットで行われることが多く、その根底には自己愛性や境界性人格障害、支配欲、嫉妬心、さらには極端な損得勘定などの心理的要因が潜んでいるケースが少なくありません。これらの行動は一見、家庭や配偶者を思いやる配慮のように見える場合もありますが、実際には被害者を経済的・心理的に依存状態に追い込むための巧妙な手段です。
特に「経済的な翼を奪う」という手口は、被害者が自立する力を削ぎ、結果として逃げ場を失わせる非常に危険な行為です。さらに、家庭裁判所など法的な場面でも、経済的に不利な状況にある被害者が正当な主張を展開しにくくなるため、被害を深刻化させる要因にもなっています。加害者はこれらの状況を利用して自分の優位性を確保し、支配関係を固定化する傾向があります。
このような問題を解決するためには、被害者がマネハラの兆候を早期に見極め、適切な対策を講じることが重要です。例えば、秘密口座の開設や経済的な自立を図るための準備など、小さな一歩から始めることができます。また、被害者がこの問題を孤独に抱え込まず、周囲の支援を借りることが不可欠です。最終的には、マネハラを含むモラハラの問題を広く理解し、社会全体で防止と解決に向けた取り組みを進める必要があります。
関連記事