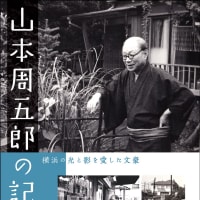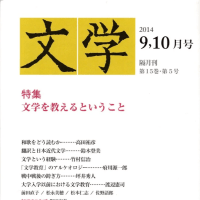「歌」が生み出されるとき、いわゆる「メロ先」か「詞先」かは別として、曲に詞が付き、詞に曲が付けられる。詞は文学、曲は音楽であるが、ともにその世界には「情感」が込められ流れている。だが、それが聴衆をまず動かすのは、音楽の方であろう。前奏が始まり音楽の世界に誘われたその後で、詞が歌われ言葉が表現する世界が眼前に浮かんでくる。だがそれ以上に音楽は感情に直接働きかけるので、情感を伝えるうえで優っている。言葉の方はいったん耳に届いたあとで、その情景や意味するところを想像しなければならないので、詞の世界に込められた情感に心が向くのは遅れてしまう。このタイムラグを超えて歌曲としての感動(=詞と曲の一体化)が生まれるとしたら、それはひとえに作品世界を聴き手に伝える歌い手の「歌」にある。音楽とともに詞の世界を表現する言葉が歌い手自身に内在する場合に限り、音声を伴う音楽ではなく「歌」になる。このことは本稿⑻で『城ヶ島の雨』を取り上げた際にも触れた。
「歌い手自身に内在する言葉」は、あらゆる声楽家にとって重要な問題である。歌曲には音楽とともに詞の世界があり、言葉の内実まで深く表現しなければならない。それを軽視することは「歌」をないがしろにすることにつながるからだ。
 さて、「聴き手の心を打つ歌とは」「詞と歌い手と聴き手の関係とは」を考えるには大衆音楽から入ると理解が早いだろう。庶民の喜怒哀楽を音楽に乗せて語りかけるという面で、詞の世界の表現がメロディ以上に重要なエレメントになることは疑いない。
さて、「聴き手の心を打つ歌とは」「詞と歌い手と聴き手の関係とは」を考えるには大衆音楽から入ると理解が早いだろう。庶民の喜怒哀楽を音楽に乗せて語りかけるという面で、詞の世界の表現がメロディ以上に重要なエレメントになることは疑いない。 例えば、シャンソン。
パリのコンセルヴァトワールに留学していた若き日の作曲家・黛敏郎が『とてもいい歌だから、ぜひ歌ったら』と譜面を送ってきた「愛の讃歌」(1950年・詞:エディット・ピアフ、曲:マルグリット・モノー)。受け取ったのは後に「日本のシャンソンの女王」と称される越路吹雪。当時は宝塚歌劇団を退団後、東宝専属の女優となってミュージカルに出演、また歌手としてシャンソンや映画音楽のカヴァーで活躍していた頃だった。1952(昭和27)年、帰国した黛敏郎が音楽監督を務める日劇のショー「巴里の歌」で越路は初めてこの「愛の讃歌」を歌う。黛がピアノを弾きながら原詩の訳を伝える。それを聞きながら「日本語詞」を書きあげたのは岩谷時子。越路が歌劇団にいた15歳から宝塚出版部に勤めていた親友だった。
翌1953年春。“舞台で歌うこと”を何よりも愛し、新しい自分を切り開きたい情熱は越路をパリへと向かわせる。ところが、エディット・ピアフのステージを生で聴いた衝撃は大きかった。本物の歌と自分との乖離に打ちのめされ、日記に書きつける。『…ピアフを二度聴く。語ることなし。私は悲しい。夜、一人でなく。悲しい、寂しい、私には何もない。私は負けた。…』

しかし、パリ行から戻ると、失意のどん底から越路は立ち上がる。「“私の”歌」を生み出していく。それを支えたのは、越路とともに宝塚を退社し東宝に所属していた岩谷時子である。越路のマネージャーを無給で担いながら、訳詞・作詞家として世に出ていた。岩谷はピアフが歌う原詩とは全く異なる翻案を試み、越路のための「愛の讃歌」を作詞した。音楽(曲)は全く同じでも、そこに付けられた詞(言葉)によって全く異なる世界が生み出され新しい命が吹き込まれる魔法。「エディット・ピアフのシャンソン」に言葉を失った越路吹雪が親友の書き上げた詞によって「自分自身のシャンソン」を歌い出すことになる。
ピアフの書いた原詩と岩谷時子が書いた「愛の讃歌」を比較するとき、外国人と日本人・人生体験の違いがあぶり出される。そのあたりから考えていきたいと思う。