塾なしで偏差値39から立命館大学に一年で合格した僕の体験談について【番外編】

皆さんこんにちは! 立命館大学2回生、塾講師経験のあるタイジュです!
今回は『塾なしで偏差値39から立命館大学に一年で合格した僕の体験談について【番外編】』を書かせていただこうと思います!
こちらの記事は今回の記事は『塾なしで偏差値39から立命館大学に一年で合格した僕の体験談について②』の記事の続きとなっています。そのためそちらをお先にご覧になってからこちらの記事を読むようにしてください。
いきなりですが、皆さんは受験期のスランプを経験したことはありますでしょうか?
受験生にとってスランプとは受験における一番大きな壁であり、ここを乗り越えることが出来るかどうかが受験の合否を左右するキーポイントとなっています。
受験生の中にはスランプを抜け出せず受験を諦める人や、志望校のレベルを下げる人などがとても多く見られます。
しかしこのようなことで受験を諦めてしまったり、志望校を下げてしまうというのはとても勿体ないように感じます。
今回は僕のスランプ期の体験談を通して、もし皆さんがこのような状況に陥ってしまったときにどのように対処するべきかということについてお話しさせて頂こうと思います。
そのため今回の記事は9月から11月にかけての僕のスランプ期のお話を中心に解説させていただきますので、若干今までの記事とはテイストが違うようなものになっていますのでよろしくお願いします。
【スランプ期】
僕のスランプ期の始まりは9月の頭ごろで、スランプに陥った大きなキッカケは初めて過去問を解いた時のことでした。
当時は第一志望が具体的には決まっておらず、とりあえず関関同立を目指していたため関西大学の過去問に挑戦してみました。

結論から申し上げますと、テストの出来は最悪でした。
英語は4割5分、国語4割、日本史6割ほどでした。
「えっ、普通にやばない?」
先ほども書かせていただいたのですが、当時の僕は勉強以外に費やすような時間は睡眠以外なく、その睡眠でさえも5時間ほどでそれ以外はすべて勉強に捧げていました。
それにも関わらずこの結果だったので、自分には勉強の才能がないと失望してしまいました。最初から自分自身が不器用な人間であるということはわかっていたものの、実際にこのようにして数字で出たときはとてもショックでした。
とはいっても今までの勉強してきたことをこの一瞬で棒に振るわけにはいかず、一か月ほどいろいろな勉強法を試してみました。しかし、どれほど改善策をとっても自分の成績をうまく上げることが出来ず、関関同立に合格できる希望が全く見えませんでした。
その結果、今までたまっていたストレスが爆発して勉強を全然しなくなりました。
そうとはいっても現役で学校には通っていたので受験や勉強の話が耳に入ってきます。
一時期はそんな環境でさえ嫌すぎて親に黙って学校をさぼって家でゲームをしたり、友達と遊んだりしていました。

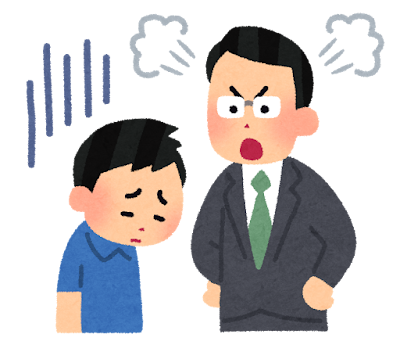
まあもちろん先生に怒られたりもしましたが、何を言われても無視していました(笑)
ただ、そのような状況下でどれだけ友達と遊んでも、ゲームをしていてもやはり自分の頭の片隅には常に勉強しないといけないという思いがあり、勉強をしていない自分にとても罪悪感を感じていました。
その結果、1か月くらいで全く勉強をしないという最悪の状況からは抜け出せたものの
それからは受験動画ばかりを見たり、勉強のやり方や体験談を読むことに時間のほとんどを使ってしまうようになりました。
そんな中でいろんな勉強動画を見ていると、一つの気になったアドバイスがありました。
それは「大学ごとで入試の傾向は違うため、自分に合う入試傾向の大学を探せ」というようなものでした。
それはつまり、それぞれの大学によって重要視されている力が違うため自分の得意分野を活かせる大学を受験をしたほうが良いということ。
英語に関して言えば、関西大学が長文読解能力に力を入れているのに対して、立命館大学では長文読解能力・文法・語彙など満遍ない知識が必要とされています。
このような入試傾向を基に自分自身の得意分野が活かされやすい大学を見つけることで得点率を大幅に上げることが出来ます。
僕の場合は今までの勉強法からも関西大学より立命館大学の入試傾向の方が向いていることは明らかでした。
実際に僕が関西大学の入試問題を解いていた時は平均で5割5分ほどだったのに対し、立命館初回得点率は7割程度でした。
正直これほど同じレベルの大学で得点率が変わるとは思っておらず、とても驚きました。
それと同時に自分が勉強してきたことは力になっていたと感じることが出来たことで勉強に対するモチベーションが戻り、うまくスランプ期を脱することが出来ました。

これは塾講師をしていても感じることなのですが、最近の入試では関西大学に落ちて、同志社大学に合格しているような生徒をよくに見かけます。
この生徒たちが一概に受験問題の傾向がその生徒たちに合っていたということは出来ませんが、少なからずそのような影響はあると思います。
このようなことからも色んな大学の過去問をやってみて自分に合った入試傾向の大学を探すというのはとても効果的な受験戦略だと思います。
もし現在、第一志望で絶対にここに行きたいという大学が無いのであればこのような方法を是非参考にしていただければと思います。
以上が僕のスランプ期を乗り越えることが出来た対処法でした。
【この記事を書いたもう一つの目的】(重要)
実は僕がこのスランプ期におけるお話だけで記事を書こうと思ったのは、皆さんにスランプ期における僕の対処法を知ってもらって、ご自身のスランプ期に活かしてもらいたいということだけが目的ではありません。
現在スランプに陥っている人やこれから先にスランプに陥ってしまった人に向けて、この体験談を読むことで同じような気持ちの人たちが受験勉強しているという事実を知ってもらいたいと思いました。
簡潔に言えば、
あなただけがしんどい思いをしているわけではないということです。
昨年僕の生徒の中で通信高校に通っていて、中学校からの勉強スタートというような子がいました。
その生徒は毎日12時間以上は勉強していて、僕が宿題とは別で出していた追加の課題も完ぺきにこなしていました。毎回の小テストでも9割以上の得点率を常にキープしてすごく勉強熱心な子でした。
ですが第一志望が近畿大学だったこともあり、11月ごろから近畿大学の過去問を初めても思うように点数が上がらず、塾に来ては毎回「自分は自頭が悪いから成績が上がらない」と言い始めるようになりました。
その時期は全く勉強に身が入らず、僕が出した課題の半分以下もやっていないような状況が長く続いていました。
ですがその時に僕自身のスランプの体験談を話したことで、成績が上がらない時期があるのは自分だけでないということを理解し、もう一度勉強を頑張ってみたいと思ってくれました。
そしてスランプを何とか乗り越え、最後まで自分を信じ抜いて勉強をし続けたことで最終的には後期日程で近畿大学に合格することが出来ました。
誰しもが受験にスランプがあるということは聞いたことがある話だと思いますが、実際に自分がそのような状況に陥ってしまったときには冷静に物事を見ることが出来ず、自分だけが成績が上がっていないと考えがちです。
しかし実際はそうではなく、スランプは誰にでも起こり得るものでたくさんの受験生がそのような壁にぶちあっています。
スランプをどのように対処するかどうかが受験の合否にとても大きく関わってくるため僕は皆さんにこの事実を知ってもらうことで、モチベーションを維持していただき、うまくスランプ期を乗り越えていただきたいと思いました。
それこそが記事を書かせていただいたもう一つの理由です。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
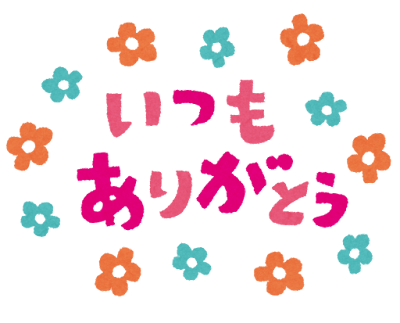
この記事を書くのに合計で17時間くらいは費やしていますが、文才が全くないため、何言ってるかわからないと感じる部分が多々あると思います。(笑)
その点に関しては本当に申し訳ございませんm(__)m
ですが少しでも皆さんがこの記事を読んで、励みや元気になっていただければとても嬉しいです!
次の投稿は『塾なしで偏差値39から立命館大学に一年で合格した僕の体験談について③』についてです。9月から11月ごろの勉強法・進捗・模試結果について書こうと思っていますのでよかったらまた是非見てみてください!
もし、このようなスランプをだれにも相談できず困っているのであればtwitterなどにメッセージを飛ばしてください!(笑)
「誰やねん、おせっかいや」って感じるとは思うのですが…
本当に怪しい感じの人とかではないので安心してください!(笑)
Twitter: @gakusyuuouen39
ブログランキングに参加しております。
よろしければポチっとお願いします!
塾なしで偏差値39から立命館大学に一年で合格した僕の体験談について②

こんにちは!現在立命館大学2回生、塾講師経験のあるタイジュです!
今回は『塾なしで偏差値39から立命館大学に一年で合格した僕の体験談について②』について書かせていただこう思います。
こちらの記事は『塾なしで偏差値39から立命館大学に一年で合格した僕の体験談について①』の記事の続きとなっております。そのためそちらをお先にご覧になってからこちらの記事を読むようにしてください。
今回の内容は主に春休み明けごろの4月から10月まで受験勉強中期におけるの僕の勉強量・勉強法・進捗・成績などについてを記述していこうと思います。
4月~7月(高校三年生)
この頃は受験勉強初期と比べて勉強自体にやる気が出てきていて、毎日長時間勉強する習慣が出来ていたため勉強に対して苦に思うようなことが無くなりました。
参考書
- 英語:東大英単語鉄壁、英語長文ハイパートレーニング2、センター過去問、スタディサプリ英文法ハイレベル
- 日本史:Z会入試に出る一問一答、金谷の「なぜ」と「流れ」が分かる本
- 現代文:現代文キーワード読解、田村のやさしく語る現代文
- 古文:古文上達基礎編、望月光の古文教室・古典文法編
*以前の速読英単語・熟語・ゴロゴに関しては模試直前に復習する程度なのでこちらの主な参考書一覧には載せておりません
参考書進捗【4月~7月】
【英語】
【日本史】
- Z会一問一答:室町くらい?(模試に合わせて進捗をとっていました)
- 金谷の「なぜ」と「流れ」が分かる本:室町
【現代文】
- キーワード読解 :1/3程度
- 田村のやさしく語る現代文:完了
【古文】
- 古文上達基礎編:1/3程度
- 望月光の古典文法:完了
模試結果【6月】

前回の2月に受けた進研模試のマークテストと比べて偏差値が上がりました!


この時は英語と日本史を重点的に勉強していたので、成績が上がっていることが分かって少しホッとしていました。
英語に関してはこの模試を受ける前に二つほど大きな問題があり、その問題をうまく対処することが出来ていたので成績は上がっているだろうなと感じていました。
一つ目の問題は英文法についてだったのですが、それは前回の『塾なしで偏差値39から立命館大学に一年で合格した僕の体験談について①』の方に載せさせていただいておりますので興味があれば読んでいただければと思います。
二つ目の問題については後ほど勉強法の解説の際に説明させていただきます。
日本史に関しては勉強時間に成績が上がりやすいものだと思っていたためこの模試に向けて3教科の中で一番勉強しました。春休みなどは毎日6時間くらい日本史に時間を割いていたので努力が数字に表れてとてもうれしかったです。
いやあそれにしても国語ひどすぎですよね…(笑)

自分の中で国語は感覚的要素がとても強い科目だと思っていたのでこの時まで古文単語以外は全く手を付けていませんでした。
この偏差値見た僕はさすがにやばいなと感じ、この時から国語の勉強を開始しました。
勉強法【4~7月】
【英語】
僕は英単語と英文法の基礎的な部分に関してはほぼ理解できていたのでとりあえず一度センター試験の過去問を解いてみようと思いました。
解いてみると
「え??まったく時間足りなくない??」
自分が間違えてタイマーを短くしてしまっていたんだろうと思い、もう一度解いてみました。

「やっぱりまちがってない…」
そのときはもう絶望でしかなかったです(笑)
私はこの時に初めてセンター試験に速読が必要であることを知り、焦って速読を習得するための方法をインターネットで調べまくりました。
そこで見つけた教材が…
「英語長文ハイパートレーニング2」です!
本当にこの参考書は買ってよかったと今でも思えるほど効果があった参考書でした。
また僕が一冊どれかをおススメできるとすれば間違いなくこの参考書を選びます!
理由としてはスラッシュリーディング用のページとCDが付いているため速読力を養うのにうってつけの教材だったからです。
また、全ての英文に丁寧な解説が書かれており、SVOCを一文一文に振ってくれているため初学者がとても勉強しやすいような構成になっていました。
では僕が実際に行っていたこちらの参考書の勉強方法を解説します。
①時間を測って問題を解く。
②間違えた問題を解説を見ながら英文解釈をする。(SVOCを振る)
③しっかりと英文解釈した後に日本語と照らし合わせて文の全体のテーマをくみ取る
④スラッシュリーディング用のページで付属のCDを使いながらシャドーイングを行う
僕はこの方法を実践したことでセンター試験で必要な速読力が身につけることができ、英語のセンター過去問の点数が102→150点まで一気に上がりました!!
次にここでの注意点について解説します
ここでの注意点としては
④のシャドーイングをする前に必ず②・③でわからない部分をなくしておいて下さい。
②・③の行程の中で使われている文法や英文構造が理解できていなければ、④のシャドーイングをやっていても英語の処理スピードは上がらないため結果として速読力は身につきません。
なのでゆっくりでもいいので一つ一つのわからない部分をしっかりと解決していってください。
もう一つの注意点としては
シャドーイングを行っている途中に文節ごとでいいので日本語を頭に浮かべるようにしてください。
シャドーイング中に日本語を頭で想像しながら練習することによって英語と日本語が頭の中で同時翻訳 されるようになり、結果として英文を読んだときに英語のままで理解できるようになります。
以上が僕の4月から7月にかけての英語の勉強法でした。
【日本史】
日本史に関しては以前の記事でも説明していましたが流れのわかる教材と一問一答を関連づけながら覚えていくことが非常に重要となっています。
そのため僕は日本史の歴史の流れを理解するための教材として金谷の「なぜ」と「流れ」が分かる本を使っていました。
こちらの参考書を使うメリットとしては歴史上における重要な出来事一つ一つを
かみ砕いて説明してくれているため、歴史の大枠の流れを初学者でも理解できるように設計されていることです。
なのでもし、日本史の勉強をしたいけど何から手をつけていいかわからないと悩んでいる方は一度チェックしてみてもいいかもしれません
では僕が実際に行っていたこの参考書の使い方を説明します。
この参考書は重要な出来事をまとめた年表がそれぞれ時代ごとに作られています。そのため、世紀ごとで重要な出来事を19世紀ぐらいまで一つづつ抜きだし、自分で表を作って覚えれるようにしていました。
例えば、1世紀であれば「漢書地理誌」が作られた。3世紀であれば「魏志倭人伝」が作られたなど。
このようにして19世紀ごろまでの自分なりの世紀年表を作り、日本史の大まかな流れを簡単に覚えられるようにしていました。
これをすることによって、「流れを順番で並び替えなさい」などの年表問題が出てきた時でも世紀ごとの出来事を基準に「〇世紀の出来事より前に起こったのか?それとも後に起こったのか?」と考えることができるようになります。
*出来事を選ぶ際に前後の出来事と結びつけられないような出来事を選んでしまうとこのような知識の応用が利かなくなるので注意してください。
【国語】
国語に関してはこれといった成績を飛躍的に伸ばすことの出来た方法がなく、この記事を読んでいる皆様にお勧めできるようなものがないため大変申し訳ありませんが今回は割愛させていただきます…(笑)
本当に申し訳ございません!!
ですが、この『塾なしで偏差値39から立命館大学に一年で合格した僕の体験談について』を全て書き終えた後もしかしたら国語のみを取り上げて記事を書くかもしれません。
その時には成績を上げれるような方法についての記事ではなく、僕の入試における国語での失敗談となどについてのお話になるかもしれませんが…(笑)
次は『塾なしで偏差値39から立命館大学に一年で合格した僕の体験談について③』についての記事を書かせていただこうと思います。
今までの記事の中心内容が勉強法・参考書・進捗・成績推移だったのに対して、次はこれらも書きつつ、僕のスランプ期のお話などもさせていただこうかなと思っています。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました!!
受験勉強などについてわからないことなどがあればいつでも相談にのらせていただきますのでtwitterなどでのメッセージお待ちしています!
Twitter: @gakusyuuouen39
また、人気ブログランキングなどにも参加させていただいておりますのでよろしければポチっとお願いします!
塾なしで偏差値39から立命館大学に一年で合格した僕の体験談について①

初めまして! 現在、立命館大学2回生のたいじゅと申します。
なにか新しいことをしたいなぁと感じ、あっという間に大学2回生になりました…
そんな僕ですが二年前は受験生で毎日10時間以上勉強していたんです。
受験期には、授業の一番前の席で英語の時間中に古文の教科書を開いて勉強していたほど猛勉強していました。
ですがその度に先生には教科書を取られて怒られていました(笑)
現在では塾講師などもやっており、両方の立場から見た今だからこそ受験生に伝えられる部分もたくさんあるのかなぁと感じております。
今回はそんな僕の受験体験談について書かせていただこうと思います。
少しでも受験生の役に立てれば嬉しいです。
【まず初めに】
僕は偏差値55くらいの平凡な高校に通っていたごく普通の高校生でした。
色んな事を一気にできるような器用な人間ではなく、どちらかといえば不器用な人間です。定期テストなどもクラス40人中30位くらいでした。
二年生の終わりに受けた進研模試では偏差値39という類まれなるバカさを発揮しています(笑)
資料を探したんですが、一番最初に受けた2年の11月の模試が見当たらなかったので勉強初めて2ヵ月目の高校2年の2月の成績を公開します。

ひどすぎませんか?これ勉強初めて2か月ですよ。
え、元々志望校早稲田だったの?と感じたと思います。
そうです。バカだったので早稲田に行って高校に伝説作ってやるぞなんて本気で考えていました。まあ結果的には受けてすらないのですが(笑)
今では笑い話になっていますが、当時は毎日10時間くらい勉強したにも関わらず、この点数だったのでメチャクチャへこみました。進研模試は比較的簡単とされている模試なので「河合模試受けたら偏差値もっと低いんだろうなぁ」なんて考えていました。
【勉強開始~3カ月まで】
僕は高校2年生の1月1日から勉強を始めようと自分で決めていたので、それまでは毎日のように友達と遊んでいました。昔から崖っぷちに立たされないとやらないようなタイプの人間なんです。
例を挙げると中学の夏休みの宿題を最終日に徹夜で終わらせるみたいな(笑)
画面の前の皆さんの中にも「うわーわかる!!」そう思っていただける方が多くいらっしゃると思います……たぶん(笑)
まあそんな感じで推薦枠も取れるわけもないので、仕方なく一月一日から僕の受験生活がスタートしました。
最初の3か月間に関しては英語と日本史を集中的に勉強し、国語は古文の単語のみ。
参考書(高校2年・1~3月)
- 英語:NEXT STAGE英文法、速読英単語、速読英熟語、東大英単語鉄壁
- 日本史:Z会入試に出る一問一答
- 古文:古文単語ゴロゴ
参考書進捗
- NEXT STAGE英文法:1周(復習込み)
- 速読英単語、英熟語:終了
- 鉄壁:3分の1ほど
- 日本史一問一答:鎌倉時代くらいまで
- 古文単語ゴロゴ プレミアム:終了
勉強方法
- 英単語、熟語: 毎日200単語(約10セクション)、熟語100個ほど。
僕が速読英単語・熟語を使っていた大きな理由ははなんといっても長文読解を練習しながら単語学習ができるという点です。
長文のテーマも面白いものが多く、ディズニーのトピックなども使われているため長文読解が苦手な方でも楽しく単語勉強をすることが出来ます。
また、僕の場合は別売りのCDを購入して長文をシャドーイングしながら単語勉強していたので単語勉強しながらリスニング力も高めることを意識していました。
僕の基本的な単語勉強法は前日の復習などを行いながら毎日200語づつ覚えて、とりあえず単語帳を一周する。
2週目でも毎日200語チェックし、覚えていなかった単語の左にチェックをつけ、毎日復習するようにしていました。
また、学校に行く途中や休憩時間などのスキマ時間はCDを聞きながら前日の覚えた単語復習していました。
単語の勉強はいかにして復習の時間効率上げるかという点が非常に重要になってきます。
僕は初めのころ、単語を覚えても次見た時にはすぐに忘れてしまっていてもう一度覚え直すというような無駄な作業を何回も繰り返していました。
しかしこれでは大幅な時間ロスになってしまい、本来割くことの出来るはずだった勉強時間を英単語勉強に当てなければいけない状況に陥ってしまいます。
このような状況にならないためにはできるだけ最短日数で英単語帳一冊を覚えてしまい、あとは記憶が抜けないように毎日復習します。
これを意識しながら実践したことで僕の場合は2週間で単語帳を一周し、また毎日復習していたこともあって、単語勉強を始めて3週間時点で毎日の200単語チェックが10分で終わるようになりました。
結果として、他の教科に割くことが出来る時間が増え勉強効率が飛躍的に向上しました!
単語は長期間かけて覚えるよりも、短期間で覚えて復習時間を短くするほうがより効率的に時間を使うことが出来るため皆さんにもぜひ試していただきたいです!
このような理由から僕は速読英単語が終わってから比較的に時間があったため、
二冊目の英単語帳として鉄壁を使っていました。
この英単語帳は以前水上さんが東大王で紹介していて一気に人気が出た商品です。
この単語帳の大きなメリットは記憶に刺さる、気になるイラストです。
単語ごとに頭に残るイラストが描かれており、このイラストが頭に強い印象を残し、記憶定着の手助けしてくれます。
この教材は東大生用だと思われがちですが関関同立、MARCH以上を受ける方で2冊目を考えている方であればぜひともお勧めします!
- NEXT STAGE英文法: 毎日100問と前日の復習
英文法は毎日100問文法問題を解き、前日の復習も100問行うようにしていました。
英文法を勉強する際に一番注意していた点は、暗記ではなく理解をするということです。
僕自身、NEXT STAGE英文法をやっていた際に理解できないようなものがあると、家で勉強していてすぐに人に聞けない環境だったこともあり、わからないまま放置していることが多々ありました。
そのため理解が出来ていない点がとても多く、4月目以降に学校での英文法対策の問題をやっているとき全然問題が解けなく落ち込んだ経験があります。
そして、「勉強しているのに…」自分の気持ちとは反対に、英語の成績が伸びないスランプに陥ってしまいました。
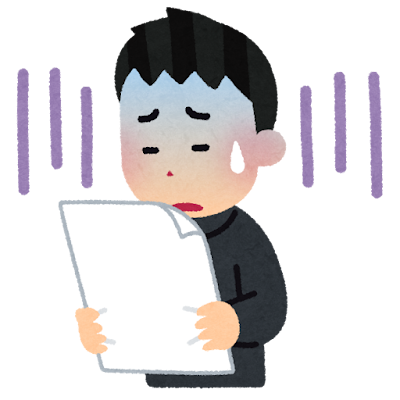
この日々がとてもきつかった印象が強いので、皆さんには絶対にこのようなことになってほしくないと思っています。
このような状況にならないためにも文法を理解することがとても重要です。
当時、僕は成績が上がらず塾に行こうか迷いましたができるだけ受験費用は抑さえたいと考えていたので、藁にもすがるような思いでスタディサプリに入会し、英文法の授業を受講しました。

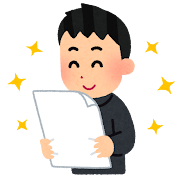
本当に驚きました。英文法を「なぜそうなるのか?」というような観点から一つ一つ丁寧に教えていただけるので、すぐに英文法を理解することができました。
自分のやる気次第では英文法コースを2週間ほどで終わらせることが出来ます。
そのような経験から、塾講師をやりながら自分の持つ生徒にはいつもこそっとスタディサプリをおすすめしています。
多分ばれたら塾長には怒られますが…(笑)
塾講師の中でもトップレベルの方々が授業を提供しているにもかかわらず、1990円で5教科18科目の授業を受けられるというあり得ないサービス。
「やる気はあるし、勉強はしているけど成績が伸びない…」
そんな方々にはとてもおすすめ出来ます。
2週間の無料体験なども行っているので
興味があれば下の概要欄をクリックしてみて下さい!
- Z会入試に出る一問一答 :毎日10ページ
最初のころの僕は日本史の勉強に関しては一問一答をやりこめば難関大学でも合格できると思っていました。
もし皆さんがこのやり方でやっているのであれば今すぐ変えてください!
「ではなぜ一問一答だけではだめなのか?」それは、
大学側は受験者が本当にその問題の意味を理解しているかどうかを確認したいため、様々な問題提起の仕方で本質的に問題を理解していない受験者を振るい落とそうとするためです。
これはとても重要です。近年の受験では一問一答だけまる覚えの受験者は産近甲龍・日東駒専でも合格点に到達しないほど受験問題のレベルが上がっています。
そのため、日本史の一問一答と流れを理解できるような参考書を組み合わせて関連付けながら覚えていく必要があります。
僕はその流れについて理解するためにスタディサプリを使って勉強していました。
日本史トップレベルの講座を受講しながら一問一答を解いていたことで立命館大学の入試では日本史で93パーセントをとることが出来ました。
- 古文単語ゴロゴプレミアム:毎日100単語
ゴロゴに関してはひたすら毎日作業のように覚えていました。
ゴロゴを使う利点としては語呂で覚えることができるので記憶の定着がとても速いです。そのため復習頻度も減り、最初の一か月以降はテスト前に復習する以外使う必要がありませんでした。
今回は大学受験初期の僕の勉強法解説と進捗とそれを踏まえた受験生の気を付ける注意点について書かせていただきました。
次は受験の中盤期における僕の勉強法解説と6月ごろの模試結果などについて投稿しようと考えています。
この記事が少しでも面白い、役に立ったという方はフォローいただけるとメチャクチャうれしいです!!
また受験勉強などで困ったことがあればいつでも相談乗りますのでtwitterの方にいつでもメッセージください!
ブログランキングに参加しております。
よろしければポチっとお願いします!


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e052219.76afc4ee.1e05221a.3a99030e/?me_id=1213310&item_id=19504088&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2287%2F9784865312287.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e052219.76afc4ee.1e05221a.3a99030e/?me_id=1213310&item_id=19924895&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4112%2F9784046044112.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e052219.76afc4ee.1e05221a.3a99030e/?me_id=1213310&item_id=17191992&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1203%2F9784342431203.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e052219.76afc4ee.1e05221a.3a99030e/?me_id=1213310&item_id=18371985&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1372%2F9784865311372.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e052219.76afc4ee.1e05221a.3a99030e/?me_id=1213310&item_id=19987225&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2325%2F9784907422325.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)