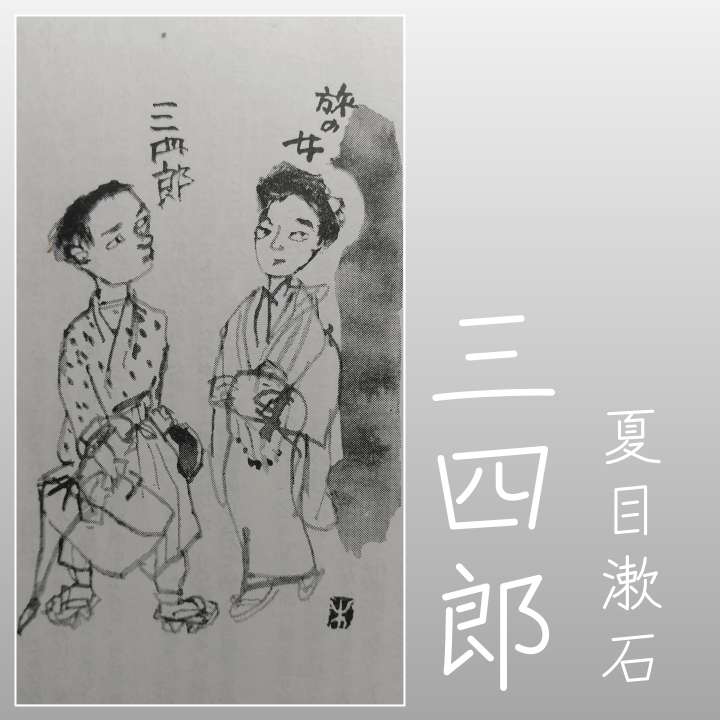例の女が入り口から、「ちいと流しましょうか」と聞いた。三四郎は大きな声で、「いえたくさんです」と断った。しかし女は出ていかない。かえってはいって来た。そうして帯を解き出した。三四郎といっしょに湯を使う気とみえる。別に恥ずかしい様子も見えない。
「三四郎」p.13 夏目漱石 著 1909年5月
女は腰を曲めた。三四郎は知らぬ人に礼をされて驚いたというよりも、むしろ礼のしかたの巧みなのに驚いた。腰から上が、風に乗る紙のようにふわりと前に落ちた。しかも早い。それで、ある角度まで来て苦もなくはっきりととまった。むろん習って覚えたものではない。
同 p.70
上は三四郎が上京する道中で出会った九州の女と東京で出会った女の所作を描写した部分の引用である。並べるとその差は尚のこと歴然としている。この場面に限らず、例えば美禰子の「きれいな歯」や着物、振る舞い等を通して田舎と都会、近代化の前と後の差が窺い知れる。
...長い廊下のはずれが四角に切れて、ぱっと明るく、表の緑が映る上り口に、池の女が立っている。...(略)...振り返った女の眼に応じて、四角の中に、現れたものもなければ、...
同 p.68
上京してきた三四郎の眼に東京が如何様に映ったのか垣間見える場面だ。四角と三四郎に言わしめる程廊下の輪郭線は四角かったようだ。クルジジャノフスキィの小説などを読むとこのような描写が出てくるが、おそらく産業革命によって当時周囲の景色が一変したのではないかと思う。廊下の輪郭はまさに四角な四角となり、その変化、異様さは、特徴的なもの、特筆に値するものとなったのだろう。またほかの観点でも野々宮から木々と建物(ビルジング)の配置の巧さについて講釈を受け自分と野々宮の鑑賞力の差に気づく場面があったりと、この比較は常に意識的に描かれている。この差は物体や所作のみには留まらない。人の性質についても描かれている。5人で菊人形を見に行く場面でそれはとりわけ判り易く描かれている。乞食と迷子がその場面では出てくる。乞食は恵んでもらえず、迷子は助けてもらえない。三四郎以外の都会の4人は同情なくただの振る舞いの一つとして批評する。この4人の行為を可能たらしめるものは何かというと、おそらく人が多すぎる、つまりその場所が都会であるということであろう。人が多くいすぎることは、自分でない誰かがやってくれるだろうという考えを人に抱かせ、自分が関わることによって負う責任を逃れるために、それを言い訳として使わせるようだ。私自身、その微妙な居心地の悪さを抱いた記憶がいくつか思い当たる。この同情の欠落はこの小説中で何度か取り挙げられている。
今上で当時の建物観について言及したが、広田先生の口を通した建築のアナクロニズムについての言及もある。アナクロニズムというのは時代錯誤という意味だが、ここから日本人の感覚全般に論を展開し、日本人の時代感覚について言及される。日本人には自分が長い歴史の中のどような時代を生きているのかという自覚がないと丸山真男の「日本の思想」で述べられている。思想というものが、作り出されては忘れられ、忘れられてはまたゼロからつくられる、という歴史を辿ってきたそうだ。思索の塵は日本では積もらないらしい。したがってこの歴史が小林秀雄に「歴史とは思い出すことだ」と言わしめたのだ、と書かれている。この「三四郎」ではそこまでの考察は無いにしろ、洋行経験のある漱石の眼には日本のこの性質 ― 「ものわかりのよさ」と前に挙げた書では表現されている ― が異様なものとして映ったのだろう。
ところでこの小説中では女人が2人出てくる。よし子と美禰子である。彼女らは双方ノラ的だと評されつつも、それぞれ異なる価値観を代表している。まずよし子は旧式に近い。兄に甘え大きく依存している。言うことはノラ的かもしれないが、立場は完全に旧式になっている。一方美禰子は近代化以後の価値観に近く、働いているか否かははっきり書かれていないが、自分の預金通帳を持っているところを見ると、ある程度兄から独立していると言える。そして三四郎は後者の美禰子に惚れる。
三四郎は田舎から上京して来たとはいえ、九州の女に「あなたはよっぽど度胸のない方ですね」と言われてしまうところを見ると、ドが付くほどの田舎かではなさそうだ。また彼のものの見方をみてみると、中立的に、理性的に理屈でものを考えることができるとみえる。田舎、つまり旧式に近いは近いが、どちらかといえば中間的な存在と言える。ただし三四郎はこの二つの世界のはざまで揺れている。冒頭などでは広田先生のような意見を持った人間をも包摂している新しい世界に期待を抱いているように感ぜられるが、与次郎の斡旋に奔走するのを見ているときには辟易しているようにも感ぜられる。
こう見ると三四郎と美禰子が惹かれあうのは納得がいく。互いに似た立ち位置にいるからだ。しかし二人は結ばれない。最後に美禰子はよし子と美禰子双方に縁談を持ち掛けていた男と結婚し、去ってゆく。この結末は、美禰子が旧式の価値観を持つ男と結婚したことを表しているようにも読める。美術館で画工の原口に美禰子が褒められるということに、美禰子本人よりも喜ぶという振る舞いが新旧どちらを示すものなのか私には分からない。自分の所有する女が褒められたという感覚で喜んだのか、はたまた美禰子と自分を同等の人間として捉え、ただ自分の妻が褒められたという意味で喜んだのか。ただ言えることは、この男はよし子と美禰子双方に縁談を持ち込むという、「不思議な」ことをする男だという点だ。これはそのまま受け取ればどちらでもよかったという意味ととるのが自然だろう。さすれば前者、旧式の、女性を自分と同等の人間とは見ない価値観を持っている、もしくはただ既婚という事実、世帯持ちという事実を得ることが目的であったのいずれかということだろう。これは下で挙げる与次郎の美禰子についての科白にはそぐわない。
その科白は、美禰子に惚れた三四郎が与次郎に言われる「二十歳前後の同じ年の男女を二人並べてみろ。女のほうが万事上手だあね」という科白に続く、長い与次郎の女性観についての科白の中で述べらている。ここで何度も登場する「偉い」という語は多義的に使われているように感ぜられるが、なかなかこの科白は意味深長だと思う。ここで示される男女観は、当時としてはそこそこ新しかったのではないかと思われる。また「吾輩は猫である」よりも漱石自身の結婚観、価値観も変化したようだ。個人主義を見直した感がある。
この小説の最後の語は「迷羊(ストレイシープ)」だ。この語は、三四郎が美禰子が描かれた水彩画の題名として然るべきと思っている語だと推測できる。また菊人形を見に行った帰りに二人きりになった時、美禰子が呟いた語でもある。またそれらに上に挙げた二人の立場と心情を加えて考えると、つまり、三四郎と美禰子は迷羊(ストレイシープ)なのだろう。だがもう一人、漱石自身も迷羊だったのではないだろうか。近代化の前と後、そのはざまで揺れていたのは小説中の人物だけでなく、彼らと同じそのはざまの時代を生きた漱石自身でもあったのだろう。明治の空に浮かぶ雲は、やはり大理石(マーブル)のようだったのだろう。
少しここまでの話からは逸れるが、「とらわれちゃいけませんよ」という科白が小説中二度登場する。広田先生との最初の邂逅で一回、運動会の後与次郎とその友人とすれ違った時、その友人の口からもう一回。この文章は受動態になっているから、無論主語はそれを聞いていた三四郎であろう。では、英語でいうbyのつくる前置詞句の目的語は何なのだろうか。前後の文脈から考えて、一度目は「日本は今後発展する」という当時大きかったと思われる世論、二度目は三四郎の美禰子に対する無根拠な疑念、つまるところ疑念を挟むことなく信じ込んでしまっている考え、といったものだろう。この「とらわれちゃいけませんよ」というのは、「どんなことでも疑ってかかって、本当のところを知らなければなりませんよ」ということだ。事実と風説・推測を明確に捉え分け、事実のみ基づいて考えを組み立てなければならないということだ。三四郎曰く、物事を考えもなく無根拠に信じ続けるのは「卑怯」なのだ。これはなかなか耳の痛い漱石先生のご叱咤だと私は受け取った。当てはまる人も多いのではなかろうか。今日あっちにもこっちにもテキトウな主張が氾濫しているが、私ももっと口を慎まねばなるまい。
小説中、三四郎は自分の見える世界を3つに分類する。第一の世界は近代化以前の日本。第二の世界は近代化以後の日本、つまり東京。第三の世界は第二の世界の女たちである。ここまで主に第一と第二の世界を比較して論じてきたが、最後にこの第三の世界、三四郎の目に映った第三の世界について一言だけ書きたい。この第三の世界というものは、上に挙げた「二十歳前後の同じ年の男女を二人並べてみろ。女のほうが万事上手だあね」という与次郎の科白が要約するように、第一第二のそれとは別の次元のものだと思われる。三四郎の振る舞いや心情にも、随所に美禰子やよし子の振る舞いに対して恐れ入ったり感心したりしているのがみられるところからすると、漱石自身の考えであったとも考えられる。そして私は、この世界の描写に感心した。描写というと視覚的な感が強いから、むしろ手触りを書き表したといった方がよいかもしれない。菊人形を見た後の帰り道で偶然美禰子の息を顔のすぐ近くに感じる一瞬の描き方の巧さ、金を貸してからの美禰子の振る舞いの巧さには感服した。説明を排し、短い句の会話だけであるのに、なんとなく頬が薄赤くなっているような二人の心情が非常に感じられる。二人の間にある判然とはしないながらも確かにある薄赤い空気、この手触りが伝わってくるのだ。これらは中でもとても好きな場面だ。
この「三四郎」では、ある程度理性的な人物を通して社会を観察し考察するというやり方は「吾輩は猫である」と同じだが、茶目っ気が抜けて淡々とした文体に変わっている。また確かに上で述べたように迷いのある、過渡的な小説である。この小説は、「迷い」を書に書き取ったという意味で、日本という国の中に存在することに意味がある。そしてまた、それだからこそといえる趣がある。小説に限らず過渡的な作品というのはあるが、その作家が確立したスタイルで書いた作品では出し得ない、あったかもしれない作風、またその作家の横顔なんかが垣間見えて妙に心に残ったりする。これもそんな作品と言えると思う。私はこの作品が好きだ。