
こんにちは。RIYOです。
今回はこちらの作品です。
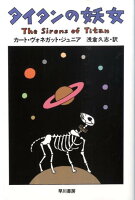
第一次世界大戦争は、アメリカ経済へ大きな潤いを与えました。ロシア、フランス、イギリスによる三国協商からアメリカに向けて、戦時中は軍需物資を、戦後はその復興に必要な物資が求められ、戦争被害の少なかったアメリカの国益を増やし、国家成長を促していました。その後、復興が落ち着き始めるとアメリカの経済は再び停滞を見せ始めます。より多くの需要に応えようと生産規模を拡大したさまざまな工場の生産量は、滞り始めた需要と見合わなくなり、経済成長を維持し続けることが困難な状況になりました。しかし、局地的に勢いをつけた経済成長は、アメリカの株式市場を暴走させていきます。実態として国益は停滞していながらも株価は上昇を続けるという状況で、国民は幻の好景気に身を委ねていきました。こうして膨らんだバブルの泡は1929年に崩壊し、アメリカ株式市場発の世界恐慌が起こります。この不況からアメリカ経済を復活させるために、フランクリン・ルーズベルトは「ニューディール政策」を打ち出しました。これは、ケインズ経済学に基づいた対策で、前大統領ハーバード・フーヴァーが国家として「為すがまま」に経済を放置した姿勢とは対照的に、国家が積極的に公共事業や社会保障を経済的に支援するというものでした。バブルの崩壊は多くの倒産と失業を生み、国民の生活は不安定となり、各々が資産を少しでも守ろうと財布の紐を固く締め、アメリカ経済は全く回らなくなっていました。その国民へ金銭的な支援を国が行い、経済を活性化させ、失業者の雇用を促して、国民の有効需要(物を欲して買う)を引き出そうとしました。このような試みで一定の効果を見せたニューディール政策でしたが、実施期間の短さも原因となって充分な経済回復には至りませんでした。
世界恐慌が各国の経済を混迷させたことで、それぞれの国が「自国の経済を守ろう」と他国との取引を縮小させていきます。他国の通貨の「信用性」を失ってきていたこともあり、多くの経済大国は「自国通貨に基づいた取引」のみを行うように、植民地との貿易だけに絞り始めました。この「ブロック経済」と呼ばれる取引政策は、為替に左右される不安もなく、経済を自国領で回すことができるため、少なくとも資本が他国へと流れることはありません。しかし、このような経済大国以外の、或いは多くの植民地を確保していない国家は、恐慌からの脱却は困難となり、ブロック経済によって安定している国々に対して「不満」を抱きます。このような不満を抱いた国々と言えば、独自通貨の日本、第一次世界大戦争の敗戦国とされた植民地のないドイツ、社会主義運動によりストライキが頻発して経済が困窮したイタリアなどが挙げられますが、これらは全て国内でファシズムを推し進めていた国でした。このファシズム国家が「他国の資源を奪おう」と考えることは当時の理念では自然に導き出される答えでもあり、三国は互いの状況と理念を理解し合い、のちに「日独伊三国同盟」として結びつきます。こうして第二次世界大戦争の下地が敷かれました。
カート・ヴォネガット・ジュニアは、アメリカの第二次世界大戦争参戦に合わせて徴兵されます。斥候として駆り出された彼は、結果的にドイツ軍に捕えられて捕虜となりました。ドイツ軍の殲滅に躍起となるイギリスは、美と信仰の都ドレスデンへ大規模空爆を与えました。イギリス空軍は、ツヴィンガー宮殿、聖母教会(フラウエン教会)、ドレスデン美術館など、美しく伝統のある建物や街そのものを、国民とともに、そして捕虜とともに、恐ろしい絨毯爆撃を浴びせました。つまり、ヴォネガットはアメリカ軍でありながら、連合国軍に銃撃を浴びせられたのでした。このときに受けた不条理による精神の傷は、彼を生涯、苦しめ続けました。
一九四五年二月十三日、ドレスデンでは約十三万五千の人間が殺された。イギリス空爆隊によって、ひと晩のうちに。とことん無意味で、不必要な破壊だった。
カート・ヴォネガット『国のない男』
本作『タイタンの妖女』は、ヴォネガットが二番目に発表した長篇小説です。この作品は、個々の登場人物を具に追うという手法ではなく、作品全体を眺めながら描く活劇「スペース・オペラ」と一般に呼ばれる手法で語られます。作中では現実と遠くかけ離れた世界が描かれ、その紡ぎ方はファンタジー的であるとも言えます。土台は当然ながらサイエンス・フィクションとして存在していますが、そこにはヴォネガット独自の理論や理屈で構築された出来事が多く、ファンタジーの色が強く出ていることから、本作をどのようにカテゴライズするべきかという争論がいまだに絶えません。ただ、間違いなく言えることは、本作に込められた皮肉を諷刺的に描き、その手法としてサイエンス・フィクションの世界をヴォネガットが選択しているということです。
ここに込められた批判は、ルーズベルトのニューディール政策、株式市場への固執と崩壊、信仰の非絶対性、歴史と運命の関連否定などであり、非常に重い主題が含まれていますが、それでいて本作にはどこか軽快な空気を醸し出すユーモアがいたるところに存在し、読み手は悲惨な状況を目にしながらも笑みをこぼしてしまうという場面が随所にあります。
ニューイングランドの貴族であるウィンストン・ナイルズ・ラムファードは、愛犬カザックとともに私有している宇宙船での航行中に、「時間等曲率漏斗」(クロノ・シンクラスティック・インファンディブラム)と呼ばれる時空間異常現象へと突入しました。これにより一人と一匹は、太陽とオリオン座の恒星ペテルギウス(冬の大三角など)の間を「波動現象」として螺旋のなかに存在することになりました。この螺旋上で時空間が合致した際に、彼らは「実体化」します。彼らはさまざまな時空間で同時的に散らばって存在し、螺旋上の時空間に合わせて実体化と非実体化を繰り返しています。地球での周期は五十九日ごとであり、その都度、短時間での実体化で彼らは地球に滞在します。ラムファードは自身の実体化時期に合わせて、アメリカ国内において最も裕福な人物マラカイ・コンスタントを招待します。コンスタントは傲慢で好色な人物であり、さほどの努力もなく父親譲りの強運でのみ富を豊かにしてきました。そのような彼に対し、ラムファードは自身の置かれた螺旋波動としての存在と、その存在ながらの未来予測(実質的な未来経験によるもの)をコンスタントに提示します。この時より、コンスタントは「受難者」としての運命を歩むことになります。
ラムファードは、コンスタントが長大な宇宙の旅に向かい、全く違う境遇ながらも幸福な生活を得ることができると予言します。莫大な富によって数多の欲望を満たしてきた、また、これからも満たすであろう生活以上に魅力的な人生があるものかと、コンスタントはこの予言を否定します。しかしラムファードは、そのように進むものだと運命の確定を明言しました。そして、宇宙を広く駆け回る運命、具体的に言えば、火星、水星、地球、土星の衛星と辿る旅を、コンスタントが行うと確定的に伝えます。予言を信用できないコンスタントはラムファードとの会合を終えますが、直後に今までの強運が嘘のように効力がなくなり、資産を失い、無一文の生活に陥りました。そして運命の歯車が動き出すように、コンスタントはラムファードの言葉通りに火星へと向かいます。ここから火星による地球への侵略戦争、水星での音楽的共鳴を伴う上司との遭難、受難者としての地球への帰還、そして土星の最も大きな衛星タイタンでのラムファードとの再会という、広大なスペース・オペラが繰り広げられます。
火星軍は、記憶を取り除かれて洗脳された地球人たちで構成されています。コンスタントもやはり、記憶を失います。ラムファードが首謀となって、貧困、絶望、不幸などにより地球での生活で苦しむ人々へ甘言を用いて誘い出し、火星に送って洗脳兵士に仕立てていきます。この火星軍による地球侵略戦争は、人権を無視した大きな犠牲の上に成り立つ「狂言」であり、ラムファードの描くひとつの脚本でした。しかし、コンスタントは地球へとは向かいません。彼はボアズという上司とともに、水星へと打ち上げられます。そこには水晶のように輝く岩盤に囲まれた、清澄な世界が広がっていました。ハーモニウムという菱形の凧のような形をした生物が生息し、彼らは「ボクハココニイル」「キミガソコニイテヨカッタ」という意思疎通のみを行い、振動を生命の熱量へ変換させて生活しています。ボアズが持ち込んだ音楽に多大の幸福を覚えたハーモニウムたちは、彼に信頼と好意を抱き、彼もまたそれに応えるように離れがたくなります。食糧は何度も人生を送ることができるほど持ち合わせていたため、これをコンスタントと分け合い、ボアズは水星に残ってコンスタントは再び宇宙船へと乗り込みます。大きな戦力差によって火星軍を殲滅させた地球へと辿り着いたコンスタントは、戦争後にラムファードによって広く地球に布教された「徹底的に無関心な神の教会」という宗教の「予言された受難者」として降り立ちます。熱狂的に迎えられたコンスタントは、ラムファードと三度目の出会いを果たします。英雄的な扱いを受けて迎えられたコンスタントに対し、ラムファードは辛辣な告白を行います。コンスタントが記憶を失う前の生き方、つまり傲慢で好色な大富豪の生活を糾弾し、信者たちが「憎悪すべき受難者」であると示します。そして、土星の最も大きな衛星タイタンへと「星流し」にされました。到着したタイタンには、途轍もなく文明の進化したトラルファマドール星からの使者サロという意思を持った機械が存在していました。思考や感情を持ち合わせるサロは、ラムファードと旧知の仲で、時間等曲率漏斗によって変在する彼の良き理解者でもありました。そして、ラムファードの描いた人権を無視した戯画の真の意図が、その地で読者に明かされます。
サイエンス・フィクションという手法は、社会や世界に対する諷刺を見せるためによく使用される手法ですが、ヴォネガットの意図はその点に固執していません。科学的な論拠は構築されておらず「この世界ではこうだ」といった示し方がなされます。このような要素が強いことで、本作はファンタジーが色濃く見せられ、読者はどこかしら寓話的な印象を受けます。ラムファードが起こす事件や行為は非道そのものであるにもかかわらず、ユーモアによって悲惨さが軽減されています。そしてこのラムファードの結末も、神の如く振る舞った行為そのものに皮肉を与えるように迎えられ、作品全体に通底するシニックな思想によって導かれます。ラムファードとその思想は、ヴォネガットの言葉通りに「ルーズベルトとニューディール政策」が戯画的に用いられていますが、そこに信仰という精神性の利用が合わさり、全体主義的な世界を構築させています。しかしながら、ここに「神性」が見られるわけではなく、ラムファード自身が「神」として存在しようとする意識が働いているわけであり、実に人工的で滑稽な世界を見せています。だからこそ、ラムファードは真実を受け入れられないまま、絶望したうえでこの世界での結末を迎えます。また、対比的に機械のサロが絶対的な力の恩恵を受けていることが、ラムファードが描いた戯画を否定するように皮肉をもって描かれています。
また、コンスタントとその父親が聖書を用いて株式市場で成功するという点も、信仰に対して、或いは神という存在に対して否定的に描かれています。信仰心の無い者が神聖な聖書を俗的に利用するという描写は、そこに資本主義の、いわばブロック経済のように経済的自己本位性を強調させており、ヴォネガットによる第二次世界大戦争を引き起こした原因的追求を垣間見ることができます。
本作における登場人物は、誰もが自分の立場や状況を選択したわけではなく、世界や社会の「見えない力によって促されるように」その位置に辿り着き、その場を懸命に生きるということしかできません。偶然や状況、神の如き力や他者の気紛れといったものからの影響を受けながら、誰もが自分の意思をもって行動している認識があります。しかしながら、世界や社会の「見えないような圧力」に促され、真の意味での自由意思は持ち得ていないと、ヴォネガットは訴えます。人間は、このような抗うことのできない世界から、「意思の解放」によって本質的な自由を得ることができます。水星で滞在し続けることを選択したボアズ、受難者として地球を追放されたコンスタントは、「大いなる何ものかの力」から解放され、真の自由意思を獲得することができました。そして心の求める辿り着くべき場所は、その人間の本質的な自由意思を得られる環境が整っている場所であり、言い換えれば、本質的な自由意思を得られる状態を維持できる場所であると言えます。これはつまり、心の辿り着くべき場所は、「場所」ではなく「自由意思を得られる状態」であると言えます。
おれたちはそれだけ長いあいだかかってやっと気づいたんだよ。人生の目的は、どこのだれがそれを操っているにしろ、手近にいて愛されるのを待っているだれかを愛することだ、と。
自分の置かれた立場や状況において、個人の行動によって世界や社会を変化させることは到底出来うるものではありません。しかし、自身の「自由意思」を尊重し続け、心の辿り着くべき「状態」へと導くことは可能であると言えます。そして、心が最も欲するもの、大切であると感じるもの、無くてはならないものとして、「愛」が挙げられます。ヴォネガットは、どのような「大いなる力」が働こうとも、自由意思を保ち、心の辿り着くべき「状態」を維持させるものこそが「愛」であり、自身の自由意思を尊重することが、人間の最も目指すべき生き方であると提示しています。その生き方は、コンスタントという受難者が宇宙を駆け巡って体現した事実であり、その結末がヴォネガットによって救済されていることからも、読者は裏付けとして読み取ることができます。
物語や定められた理論の理解が、やや困難に感じられる場面も多くありますが、さほど深く理解をせずとも「そういうものだ」という理解で読み進めることをお勧めいたします。カート・ヴォネガット・ジュニア『タイタンの妖女』、ファンタジーのようなサイエンス・フィクション作品、未読の方はぜひ、読んでみてください。
では。