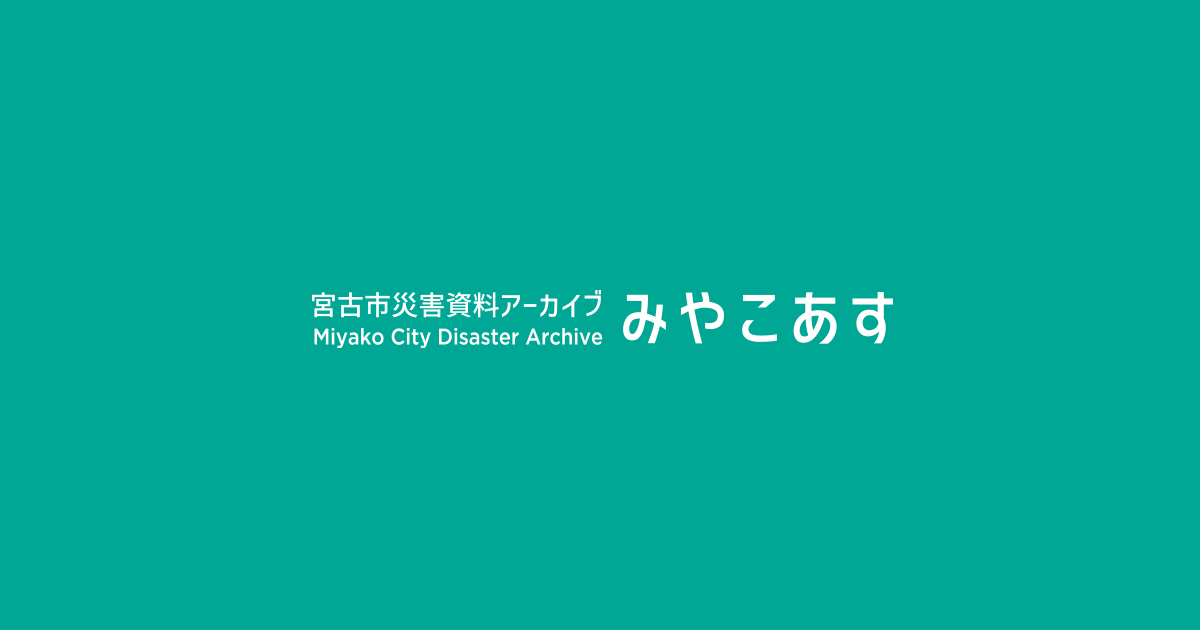森林や草地などの地表は通常、
落ち葉や草で覆われているので、
豪雨の時でも雨水はほとんど地中に浸透し、
地表流は発生しません。
しかし、
地表に落ち葉や草がないと
森林であっても地表流が発生します。
なぜでしょうか?
これは、
雨が直接土の表面をたたく(雨滴侵食)と、
跳びはねた細かい土粒子が
土の表面の隙間を塞いで、
下図のように水を通しにくい薄膜
(雨撃層あるいはクラスト)をつくります。
雨撃層を作るのは山火事だけとは限らない。
雨が直接土に打撃を与えるようにふりつければ
そのまま表層泥流になりやすい。
理科の記述系の学校では
以下のようなメカニズムが
出題される可能性がある
しかし、森林の管理状況によっては、
土壌の浸透能が低下する場合があります。
たとえば、過度な森林利用により
ハゲ山になった場合、
または人工林の手入れ(間伐)遅れや
高密度化したシカの採食影響によって
下層植生が衰退し
地表面の被覆が乏しくなった場合です。
地表面の被覆がないと、
降雨時の雨滴の衝撃により
土壌の孔隙が目詰まりし、
雨水が浸透しにくくなり地表流が発生します。
このように、
降った雨が土壌に浸透せずに
地表流のまま河川に流れ込むと、
“時間をかけてゆっくり流出する”という
森林の水源かん養機能は発揮されません。
というわけで、森が失われるだけでなく、
下層植生が失われるだけでも、
洪水や土砂崩れの危険性は高まるのだ。
このことをぜひ押さえておいてほしい。
どうしても森林資源というと、
立ってる高層木のことを考えがちだが
実は森の植生でいうと、
下層植生の方が防災上は重要な意味を持つ。
マント群落やソデ群落も合わせて覚えておこう
特に
つる性植物に落ち葉が絡んだものが
マント群落であり、
日差しや風を防ぎ、
森林内の温度と湿度を一定に保つ役割がある。
ソデ群落とは森林周辺に生える
低木または下草である。
草なんだ
大船渡火災の時系列
大船渡山林火災の原因
直接のきっかけは不明。
野焼きという情報もあるが、
ちょっと怪しい。
ただ火災が広がった理由ははっきりしてる
乾燥・強風注意報が出てる。
つまり、フェーン現象。
国外、国内で被害が多発する要因として、
温暖化が指摘されています。
温暖化による異常少雨や干ばつで、
空気や地面が乾燥し、
発火や延焼の危険性が高まっています。
特に山林の落ち葉が積もって燃えやすい冬から春にリスクが高まると考えます。
今回の大船渡市の火災発生日には乾燥注意報が出ていました。
今年の冬は、太平洋側の空気が乾燥して、
起こりやすい気象条件になったと思われます。
また、高温で乾燥したフェーン現象の風が吹くことも一因として考えられます。
風が強くなればなるほど、火災は一気に広がります。
また、風向は突然変わることがありますので、
消火するにも予測がたてにくいのでないかとも推測します。
このように、気候変動によって、
降水量が少なく、着火しやすくなる「乾燥」と、
燃え広がりの原因となる「強風」という気象条件が、
林野火災の被害を頻発・拡大しているのだと改めて感じています。