王妃の物語が完成してから、季節は瞬く間に過ぎていった。新しい年を迎え、母の1周忌も無事に終わり、僕の中で母に対して抱えていた様々な想いは徐々に薄れていった。母の事を考える時間は減り、家族の間でも話題になる事は少なくなっていった。故人というものはこうして忘れられていくものなのだろう、そう実感していた。

母の介護をしていた頃に比べると、僕が自由に使える時間は格段に増えていたが、新たな物語を書こうという気には全くなれなかった。物語を書き切った事で、僕を駆り立てていた何かは消え、最後に残っていた燃えかすのような想いも、母の死とともに完全に消滅してしまっていたからだ。
それからの日々を僕はなるべく家族と過ごす時間に充てるようにした。週末には家族でドライブや小旅行に出かけたり、夜更かしして颯太とゲームを楽しんだりした。そして美穂と颯太がどう感じていたかは解らないが、二人に物語を話したことで、家族の絆のようなものがより深まったように感じられていた。
ちょうど1周忌が終わった頃、年に数回ある研修のため、再び市ヶ谷にある本社まで行く機会があった。いつものように研修後の飲み会を早々に抜け出して帰る途中に、昨年、通りがかった旅行代理店の前でふと足が止まった。ショーウインドウには以前にあったカウアイ島にあるシュロの木の広告はすでになく、韓国や東南アジアの市場の広告に様変わりしていた。ひょっとしたらまたアリゼに会えるのではないかとしばらくショーウインドウをのぞき込んでいたが、何かが起こりそうな気配は全く感じられなかったので、諦めて市ヶ谷の駅まで歩き埼玉方面へと向かう地下鉄に乗った。
地下鉄の中は暖房が効き過ぎていたせいか、ついウトウトして眠り込んでしまった。目を覚ましたときには、なぜか車内の電灯が全て消灯していた。車両は止まっており、瞬時に停電ではないかと思ったが、それにしては何のアナウンスも無いのが不可解だったし、何よりも他の乗客のいる気配が無かった事が理解できなかった。ひょっとしたら、これは夢の中なのではないかと、手のひらで頬を何回か叩いてみたが軽い痛みがあったので、おそらくそうではないと思った。
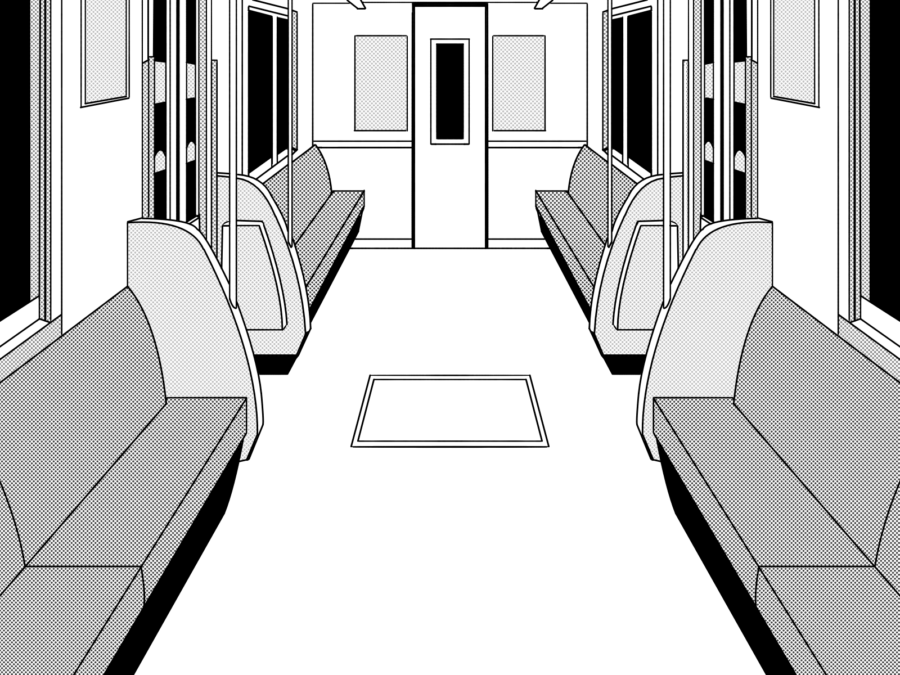
通常ならパニック状態になるところだが、僕は自分でも驚くほど冷静にその状況を受け入れていた。それは直感的に、またあの時と同じ事が起こったんだ、そう思ったからだ。やがてヒタヒタという足音が聞こえ、誰かが僕の方に近づいてくる気配がした。やってきたのは思った通り、僕の古い友人だった。
「やぁシュン、久しぶりだね、元気だったかい?。」
アリゼはいつもの軽い口調で僕に話しかけてきた。薄明かりの中、アリゼの顔の輪郭だけがうっすらと見えた。
「アリゼ、また会えて嬉しいよ。ここはまた時空の間とやらなのかい?」
「まぁ、そんなところだ。以前は僕が君を僕達の世界に招待したけど、今回は僕が君の世界までやって来た。」「ところで何でこんなに暗いんだ?君の顔がよく見えない。」
「悪いけど今はこれが精一杯なんだ。でもこれはそもそも君のせいなんだぜ。」
アリゼの苦笑いしている顔が自然と頭に浮かんできた。
「僕のせいって?どういう意味だ?」
僕は驚いて尋ねたが、アリゼはその問いには答えなかった。
「僕はもう君に会うつもりはなかったんだ。それでも今日ここに来たのは、どうしても君にお礼が言いたかったからだ。」
「お礼って?」
「僕の願いを聞いてくれただろ。母様を悪者にしないで最後にはみんな救済してくれた。そして大切な【お国】の復興まで…。感謝の言葉も無い。本当にありがとう。」
アリゼが感極まり、深々と頭を下げているのを感じた。
「それはお互い様だよ。君のおかげで僕もようやく重い足枷がとれたんだ。」「ところで、あれから美穂さんや颯太と話はできたのかい?」
「美穂には物語を最後まで話したよ。結末にはとても満足して喜んでいた。君の母様というより僕の母の事を考えていたんだろうけどね。颯太には、君に会った時の事を話そうと思っていたんだけど、まだそのタイミングがなくて話ができていないけど。」
「そうか、美穂さんと話が出来て良かった。これで君たちの家族の間にあった溝のようなものも徐々に埋まってくるだろう。でも颯太にはもう話をしない方がいいかもしれないな。プロムスも言っていたように、子供は時間の流れ方が僕達とは全く違うんだ。もう颯太の関心はきっと別の所に向いているよ。」「そんなものかな。ちょっと寂しい気もするけど。」
「そんなものさ。颯太から聞きたいって言ってくれば話は別だけどね。」
「僕も君の事はもう忘れた方が良いのかな?」
「そうかもしれない。でも実際に君は僕の事を忘れかけていたんじゃ無いか?」
アリゼが突然、思いがけないことを言ったので僕は動揺した。暖房の切れた車内の気温は徐々に低下していたが、僕は寒さを堪えながらアリゼの問いに答えた。「そんな事はない。僕は君にずっと会いたいと思っていたんだ。」
「そう言ってくれるのは嬉しいが、物語が完結してから、君の僕達に対する関心は明らかに薄まってきている。僕がこういう形でしか、君に会えなくなったのもそのためだよ。」
僕はその言葉を否定できなかった。母の事を忘れていくのと同時に、物語に対する関心も薄れてつつあったのは事実だったからだ。
「アリゼ、そうかもしれないけど、君は今でも僕にとってかけがいのない友達だ。」
「シュン、君は勘違いをしている。僕は君の中の一部にすぎない。僕は君で君は僕なんだ。友達じゃない。」
「それは解っているつもりだ。でも、君は実際にこうして僕に会いに来てくれているじゃないか。僕自身とは異なる存在として。」
僕がそういうとアリゼは静かに首を振った。話をしているうちに、暗闇に目が慣れてきたのだろうか。アリゼの仕草が徐々に見えるようになってきていた。
「僕は君のイリュージョンでしかないんだよ。君が思い描かなければ僕の存在も消える。」「アリゼ、君に聞きたいことがあったんだ。確かに僕は美穂や颯太とも以前より親密になれたと思う。これも全て君達のおかげだ。でも同時に僕の中にあった核のようなものも消えてしまった気がするんだ。それは僕の足枷でもあったけど、僕が何か行動を起すための原動力でもあり、物事を受け入れるための物差しのようなものでもあった事に気がついたんだよ。だからこれから何を基準にしてどうやって生きていったいいか解らなくなっているんだ。」
僕はアリゼに自分でも思っていなかったような問いかけをしていた。これはおそらく僕の心の奥底に眠っていた根源的なもので、美穂や颯太、マサ兄にも話せないものだった。アリゼは僕の言葉を聞いて淡々と話した。
「いいかい、これから先は僕が君にアドバイスできることはない。でも君はもう前に進んでいるじゃないか、無意識のうちにね。僕達の事を忘れかけているのがその証拠だ。」
「アリゼ、そんな事は無い。僕はまだ途方もなく複雑な迷路の中にいる。君達は永遠に生きられるけど、僕達は違う。僕の母さんを見ただろ?いつか骨と皮だけになって自分が誰かも解らなくなって死んでしまう。やがて燃やされて、つるつるして無機質な小さな壺の中に収められてしまうんだ。君に僕達の気持ちは解らないだろう。」「シュン、君は生き急ぎ過ぎている。年老いていく事や死に怯えていても、何も考えずにダラダラと生きていたとしても結局、最後は巨大なオーブンで焼かれて小さな蛸壺に入れられるんだ。それでももう君は終わりなのか?そうじゃないだろ?まだ君には出来る事があるはずだ。君自身の想像力を駆使して新たな物語を生み出すことも出来る。何よりも大切な家族を守り、慈しみ、温もりを感じる事ができるじゃないか。限られた時間を愛おしみ、大切にするんだよ。逆に君の物語が完結した事で、僕達の時間は止まってしまった。人工衛星みたいに同じ所をぐるぐると回るしか無い。これがどんな気持ちかわかるか?」
アリゼは珍しく興奮気味にそう語った。暗闇の中でなければ吐く息が白く見えたのではないかと思うほどだった。
「君の気持ちも解らなくもない。以前にも言ったように、君達の世界はとても複雑で争い事が絶えず、常にアップデートされ続けている面倒な世界だ。おとぎ話の世界じゃない。だからもし、生きていくのに疲れたら、僕達と過ごした日々をほんの少しで良いから思い出してみてくれないか。君さえ思い描いてくれれば、僕達はいつだって君の中にいる。それが君の癒やしとなり、生きる原動力になるのならこれ以上の喜びはない。寂しさを紛らすために、退屈しのぎの友達なんか無理に作らなくていいさ。どうやら君はそういうタイプの人間じゃ無さそうだしね。ところでシュン、そろそろ時間切れだ。」「アリゼ、何て言ったらいいか解らないけど、僕は君達に出会えて本当に良かった。様々な物を得て、そして失いもしたけど多くを学べた。物語はもう完結してしまったけど、この心に刻まれたものはずっと忘れない。例え君が僕を忘れてしまったとしても…。」
僕がそう言うと、アリゼはとても微かで優しい笑みを浮べて頷き、残像を残しながらゆっくりとその姿を消した。
アリゼが姿を消すと、突然、車内の灯が付き地下鉄のモーター音と空気を切り裂く音が聞こえた。暗闇に目が慣れてしまっていたせいか、目を開けていることができず瞬時に目を閉じた。それから眩しさなのか別れの余韻のせいなのか解らなかったが、とめどなく涙がこぼれた。これでようやく何かが終わり、そして始まろうとしている、そう感じた。
強い南国の日差しと潮風、シュロの木の下で寝そべって嗅いだ草花と土の香り、談笑するアリゼやルイカやタフラの無邪気な笑顔。僕はすっかり冷え切った体を擦り温めながら、おとぎ話の世界で過ごした温かな時間の事を考えた。そしていつか再び訪れるかもしれない奇跡の時間を思い浮かべた。そう、アリゼの言う通り、僕が思い描きさえすれば、彼らはきっと僕の中で永遠に生き続けるのだろう。
-完-

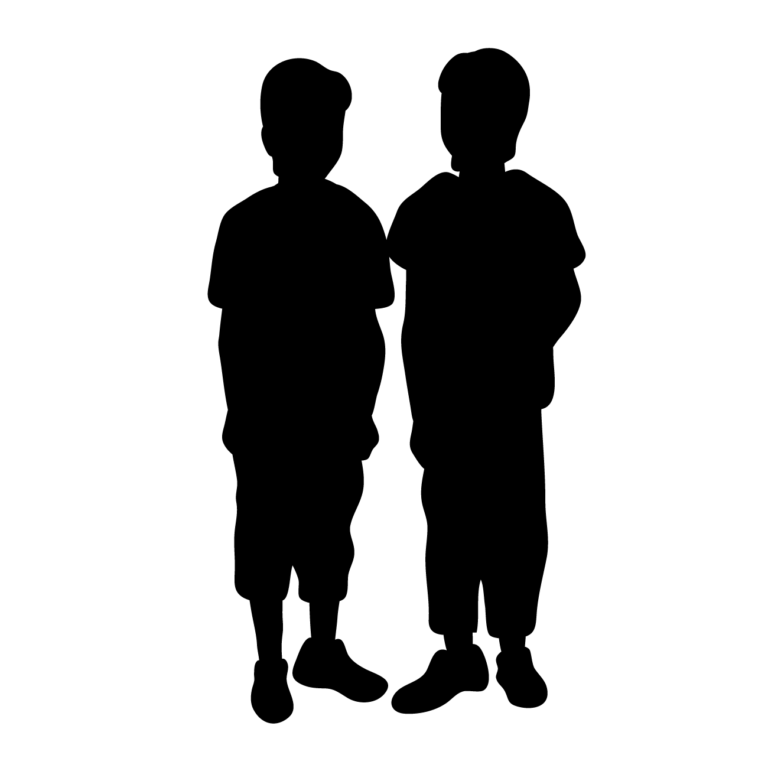
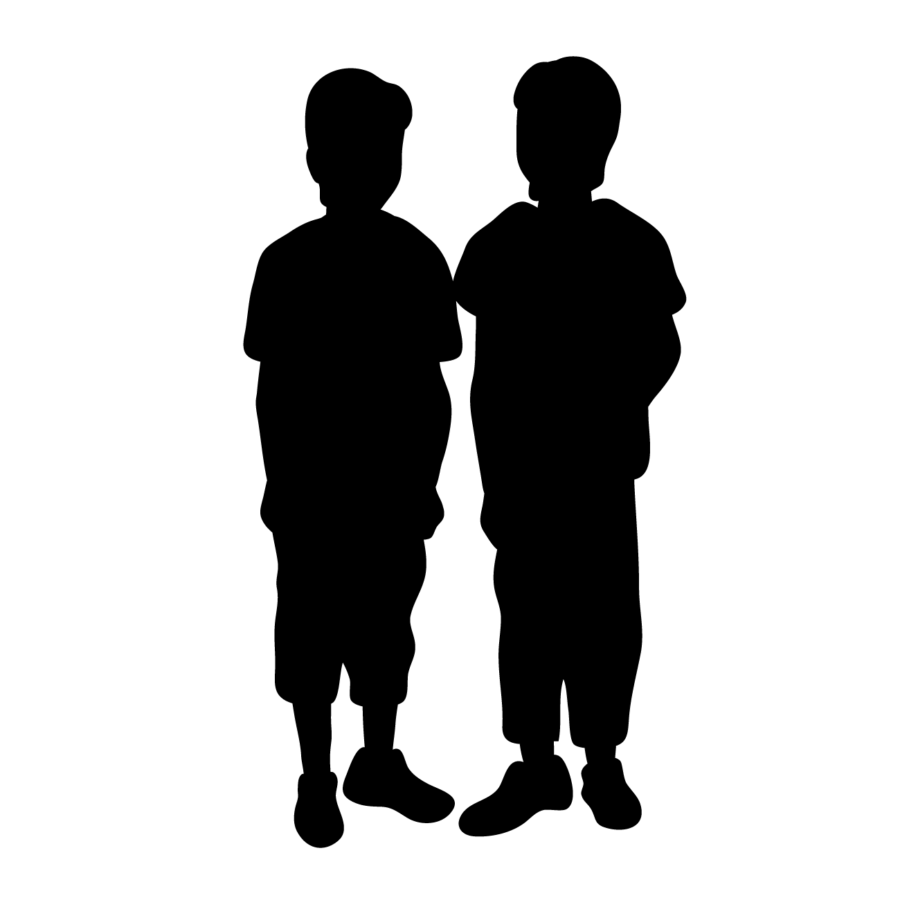


コメント