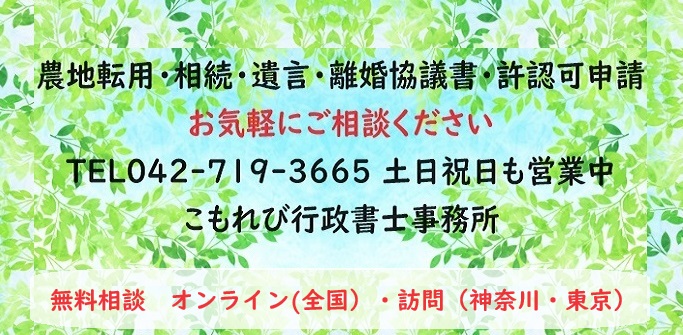農地の農水省の定義は以下のとおりです。
「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。この場合、「耕作」とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいい、「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地等)も含まれる。
上記の中で「耕作しようとすればいつでも耕作できるような」という部分の解釈が市町村によって異なることがあります。
極端な例ですが、A市では「種をまけば芽が出る土壌の状態」を指し、B市では「外見は畑に見えなくても、伐採・草刈りをしてトラクターで耕せばなんとか畑に戻せる可能性がある土地」を指すということがあります。
各自治体の現状に合わせて解釈に幅を持たせているように思いますが、申請者にとってはやっかいです。
解釈の違いから同じ申請書の内容でもA市ではOK、B市ではNGということになりかねません。
申請者にとって極端に不利になる場合は、「平等原則」を持ち出して、「A市ではOKだった。B市の解釈は間違えている、法的根拠を示してください。」と主張することもできます。
どれだけ法律を詳しく知っているか、が肝になります。
お困りの際は、専門の行政書士への相談をお勧めします。