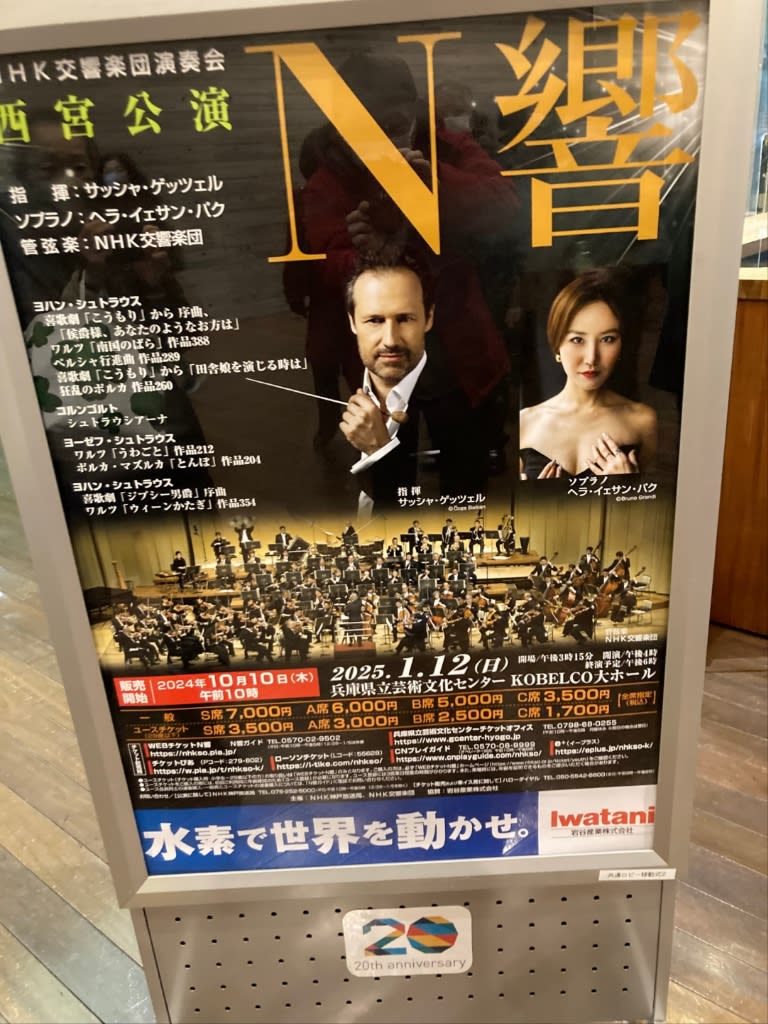チャップリン、およびチャップリンファンにとって、この『モダン・タイムス』は特別な作品です。作品が作られた1936年。すでにテクノロジーは残酷なまでに発達し、映画はセリフ入りのトーキー、となっていました。
チャップリン自身は、トーキーが大嫌いだったようです。
『放浪者チャーリーが喋ると、映画の魔法が消えてしまう』
『英語を喋らない、世界中の子どもたちが、僕のサイレント映画を観てくれるはずだ‼️』
それでも時代の波は抗いようもありません。
サイレント喜劇のチャーリー・チャップリンはこれで最期なのだ、と覚悟していたようです。
そして、古き良きサイレント喜劇の名場面を、懐かしむように、作品の中にはめ込んでいきました。
スケートシーンもその一つですね。
この他にも、エスカレーターのシーン、などがあります。
そしてなにより、映画の終盤。
ついにチャップリンが劇中で歌を披露しました。それがなんと、全くのデタラメ語。無国籍語だったことは有名です。
やがてラストの一本道。挫けそうになるヒロインに、
さあ、元気をだしていこう! 笑顔をつくってごらん!と、勇気づける放浪紳士チャーリー。


チャップリンファンにとっては胸が一杯になる、ラストシーンですね。
フルオーケストラが演奏する『Smaile』の余韻がいつまでもコンサート会場に残っているかのようでした。














 そのあと、オーケストラの皆さんが現れ、観客から大きな拍手が……。
そのあと、オーケストラの皆さんが現れ、観客から大きな拍手が……。

 中に入ると、そこが大ホールの1階となっています。
中に入ると、そこが大ホールの1階となっています。 (上の写真、建物の中。右側に大ホール入口があります)
(上の写真、建物の中。右側に大ホール入口があります)